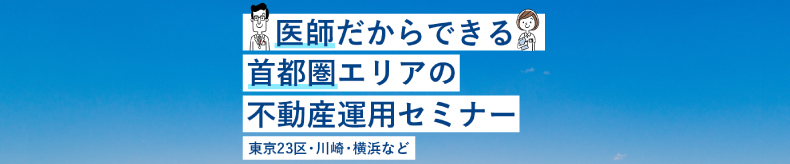少ない資金でも大きな利益を生みだすことができる不動産投資。
利回りを高めるために、中古物件を狙っているという投資家もみられるようになりました。
そこで、投資物件として検討する場合、築年数は関係あるのでしょうか。
ここでは、不動産価格と築年数のバランスや、注目すべき新耐震基準に合致した物件と築年数の関係等に関してまとめました。
また気になる利回りにも触れてまいります。
築年数からみる不動産価格
このところ中古でも品質が良く付帯設備が整っている物件が多く、修繕やリノベーション等を行うことで賃貸物件としても十分に活用できるようになりました。
また、中古物件というだけで不動産価格が安く、不動産投資初心者にとっては「足がかりとなる物件」として選びやすいメリットがあります。
さて、中古物件となると気になるのが「築年数」ではないでしょうか。
投資物件を探す場合、「築15年(注:平成29年8月基準)」前後を目安に不動産購入価格を注視されるのも1つの手です。
この理由は、平成11年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」にあります。
この法律によって新築住宅において、施工会社等に対し10年間の瑕疵担保責任が課されるようになりました。
この法律が施行されて以降に完成している物件については、品質に対する安心感も得られるといった観点から逆算して「築15年」という目安をご紹介しました。
中古物件の場合、築15年を境に築年数に比例し不動産価格も下がっていくと捉えましょう。
ただし、中古マンション・中古一戸建てなど物件の形態が異なれば、そのものの価値が替わります。
中古マンションの場合、築5年を過ぎると価値が下がり、不動産の販売価格も安くなります。
その後しばらく横ばいが続きますが、築15年ほどでさらに価値が下がると考えられています。
そして築21年以上のマンションに関しては下げ止まり状態となり、販売価格が安くなるケースは少ないと考えられます。
地震に対する強度と築年数の関係
築年数が経過した物件であれば、購入価格が安いと捉えることができますが、先に触れた「住宅の品質確保の促進等に関する法律」や、1981年に施行された耐震性に対する新体制基準に基づく造りをしていなければ、リスクを背負うことになります。
特に、首都圏では「首都直下型地震」が懸念されており、高層マンションなど免震構造がなされている住宅でも被害を受けるといったようなシミュレーションは、マスコミが大きく取り上げているためご存知の方も多いことでしょう。
築年数が古い(平成29年8月基準で築35年以上経過している)建物に関しては、1981年に制定された新耐震基準に合致しているかどうかがポイントとなります。
ただし、阪神淡路大震災(1995年)を受けて2000年に耐震基準が改正されています。
2005年には新潟中越地震(2004年)を受けてさらに基準が改正されました。
2011年の東日本大震災というような先にあげた地震の規模を上回る巨大地震にも見舞われています。
これらを踏まえると「1981年新基準」という触れ込みだけではなく、改正後の新耐震基準に見合っている住宅であるか否かをみた方が、賢明であると考えられます。
ただし、いくら地震に対する強度が認められた物件でも、地盤の状態が原因で(地盤沈下・液状化現象など)で建物被害に遭うケースが後を絶ちません。
周辺環境も含め総合的に判断することをおすすめします。
築年数と利回りの関係
不動産投資ですので、購入時には「表面利回り」を検討する必要が生じます。
新築物件であれば、不動産販売価格が高いため利回りが低くなります。
では、中古物件であればどうでしょうか。
築年数だけでみると、築浅物件であれば購入価格も新築物件に近い価格となるため利回りは低めになります。
築年数が古いと、建物価格が下がるため利回りは高くなります。
この築年数に関しても先にあげた「築15年」を境とすると分かりやすいのではないでしょうか。
ただし、購入価格や、売り主側が提示する利回りからみる数字が必ずしも正しいとは言えません。
建物が古ければ家賃を下げる必要が生じ、これによって年間の家賃収入が下がりますので、利回りにも影響するでしょう。
築年数が経過した建物の場合は、購入価格が安いためリフォームやリノベーションにお金を掛けることができます。
それによって、建物の価値を高めることができ家賃も想定された価格よりも上乗せすることができるので、利回りを高めることもできると考えることも可能です。
このように、建物の築年数や販売価格だけで評価することはせず、必ず「将来性」も見据えて判断することが大切です。
築年数が経過している物件は購入価格も安くなります。
しかし、それだけで投資物件として最適だと決定することは、リスクを伴います。
最新の耐震基準を満たした建物であることを確認することと、瑕疵担保責任を建物に反映させ始めた「築15年」を境に検討することはおススメです。
ただし、築年数に振り回されることなく、周辺環境や建物を修繕した時に生まれる価値にも着目することも大切です。
不動産の専門家に相談しながら「収益物件」を見極めていきましょう。