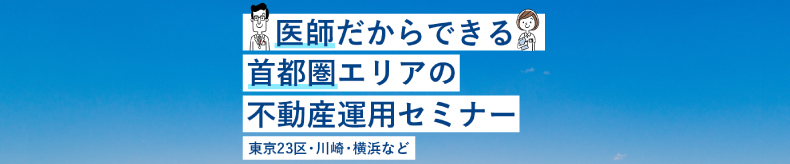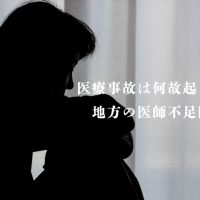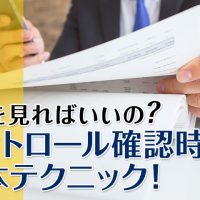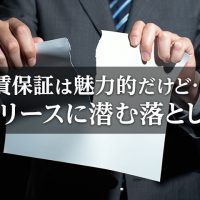勤務医として働いている医師の節税対策を考える際、「不動産投資が最適」と言われます。その理由は「減価償却費を経費として計上できるから」です。この減価償却費とは一体どのようなものなのでしょうか? そこで今回は不動産投資には欠かせない減価償却について、概要や計算方法、注意点などを解説します。
減価償却とは?
 節税をするためには経費を計上する必要があります。なぜなら税金は「売上-経費=利益」の利益の額に応じて一定の税率をかけて計算するため、経費を多くすればするほど、税額を抑えることができるからです。
節税をするためには経費を計上する必要があります。なぜなら税金は「売上-経費=利益」の利益の額に応じて一定の税率をかけて計算するため、経費を多くすればするほど、税額を抑えることができるからです。
通常、経費というと、講演を行うために買った書籍代、書籍を買うために買ったパソコン代金、関係者と連絡を取るための通信費など、「実際に使った費用」が経費になります。単純計算ですが、10万円の報酬(売上)の仕事をするために書籍代や通信費の合計経費が3万円だった場合、7万円が利益になります。
でも、不動産投資は経費の考え方が異なります。ここで登場するのが「減価償却費」です。不動産投資を行う場合、上記の例と同様に物件購入費用や登記費用、リフォーム代などの「実際に使った費用」を経費として計上しますが、さらに減価償却費も経費として計上することができるのです。
減価償却費とは「時間の経過によって建物などの価値が減少するため、減った分を費用として損失計上する金額」のことです。この費用は物件購入費用などと違い、「実際には払っていない費用」のため、言ってみれば“イレギュラーの経費”なのです。医師の中でも勤務医の場合、このように実際には払っていない費用を経費にできるものは不動産投資ぐらいしかないため、「不動産投資が節税対策には最適」と言われているのです。
ただし、減価償却費はあくまでも「価値が減少する」という観点から「建物のみ」に計上することができる経費です。土地に関しては減価償却費が発生しないということも頭の片隅に入れておきましょう。
減価償却費の算出方法
減価償却の対象になる資産のことを「減価償却資産」と呼びます。この資産には使用期間が「法定耐用年数」として法律で定められているので、それに準じて減った価値のぶんの金額を減価償却費として計上することになります。法定耐用年数は建物の構造によって異なり、居住用のRC造は47年、重量鉄骨造は34年、木造は22年です。
減価償却費 = 建物価格 × 償却率
減価償却費は上記の計算式で算出するため、法定耐用年数から償却率を確認する必要があります。償却率は国税庁のサイトでチェックすることが可能です。
たとえば、まずはとても単純化して、2,000万円のRC造の新築マンションを購入したとします。RC造は法定耐用年数が47年なので、上記の表に従って見てみると、償却率は0.022です。そのため、減価償却費として計上できる額は、2,000万円×0.022=44万円になります。
ちなみに、0.022は「定額法償却率」の数値ですが、同じ表には「定率法償却率」があります。建物には定額償却率、建物設備には低率償却率を掛けることになっています。そのため、最初に不動産物件を購入した場合は、土地、建物、建物設備の3つに分けて、計算する必要があります。
中古マンションを購入した場合は、法定耐用年数の途中であれば、「法定耐用年数-(経過年数×0.8)」でその物件の耐用年数を計算します。たとえば、築20年のRC造のマンションであれば、「47-(20×0.8)=31年」になり、31年の償却率で計算することになります。
耐用年数の切れた「築古物件」に注意
 前節の最後で、「法定耐用年数の途中」で購入した中古マンションのケースを出しましたが、「法定耐用年数が終了」した中古マンションの場合、減価償却はどのように行うのでしょうか?
前節の最後で、「法定耐用年数の途中」で購入した中古マンションのケースを出しましたが、「法定耐用年数が終了」した中古マンションの場合、減価償却はどのように行うのでしょうか?
その場合、耐用年数は「法定耐用年数×0.2」で計算することになります。たとえば、法定耐用年数が終了した木造の物件を購入した場合、「22年×0.2=4年(端数は繰り下げ)」なので、減価償却が行えるのは4年間ということになります。
耐用年数が終了した物件は、不動産投資のメリットである減価償却を行える期間が短いというマイナス面があります。冒頭で勤務医として働く医師に節税対策が向いているのはイレギュラーな経費である減価償却を計上できるから、とお伝えしましたが、この場合はその旨味が薄れてしまうというわけです。
さらに、耐用年数が狩猟した物件は、「金融機関からの評価が低い」というマイナス面があります。そのため、必然的に融資が受けづらくなり、結果、自己資金を多く入れなければならなくなる恐れがあります。
不動産投資を行う場合、購入した物件に居住者が入ってくれて、毎月の家賃収入を得るということは投資を成功させるための必須条件ですが、減価償却で経費を計上できないと、毎年利益分が高くなり、支払う税金が増えてしまうかもしれません。こうなると、何のために節税対策を行っているかわかりませんよね。不動産投資を行う際は、「耐用年数」をチェックするようにしましょう。
まとめ
不動産投資の節税に欠かせないのが「減価償却」です。減価償却を行ううえでキーとなるのが物件の「耐用年数」。このことを正しく理解し、物件を選ぶ際には、「どれだけ減価償却とれるか」という視点も欠かさないようにしてください。
不動産運用セミナーTOPはこちら