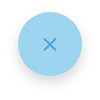Ranking ランキング一覧
-
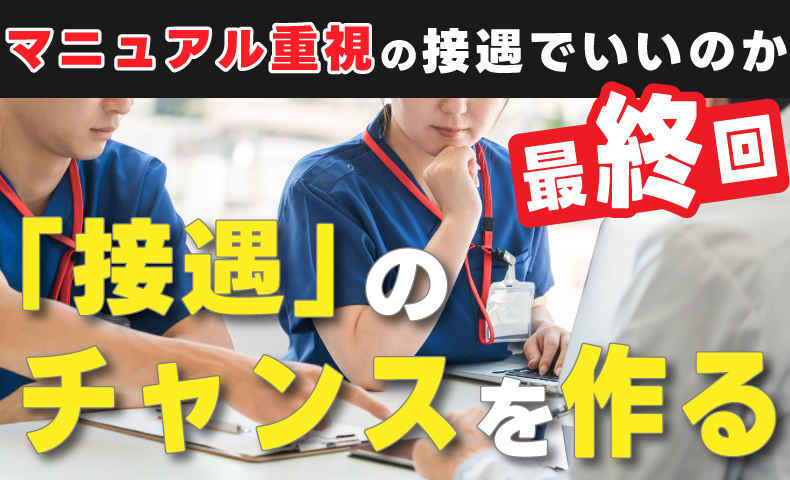
【マニュアル重視の接遇でいいのか 最終回】接遇のチャンスを作る
医療現場における「接遇」とは、安心と信頼を創り出すためのコミュニケーションの1つの形態です。
医療サービスの一環として捉えるのではなく、ホスピタリティに近い「こころの在り方」を示すことが大切です。「接遇」は職員が積極的に患者や家族に働きかけてこそ生まれるものなのです。
-

【マニュアル重視の接遇でいいのか 第3回】「接遇」イコール「受容・承認」
前回(【マニュアル重視の接遇でいいのか 第2回】旧来の方策から脱却を図る)の事例のように、マニュアルレイバー的な対応とは異なる、まさにヒューマンな処し方により、医療側と患者側の心の交流が図られ、患者の方は心温まる思い出として心の中に残り続けます。
このような交流は、患者のみならず医療従事者とっても癒しと安心を実感できる「接遇」のゴールとも言え、やりがいと誇りをはぐくむ鍵となります。
-

【マニュアル重視の接遇でいいのか 第2回】旧来の方策から脱却を図る
マニュアルレイバーとしての接遇向上施策は、医療従事者に「ただでさえ忙しくて余裕がないのに、さらに負担を強いられる」とのマイナスイメージを持たれることが多いことが、次第に明らかになりました。そこで、多くの医療機関で、マニュアルレイバーから、ヒューマンワークへの転換が見直されるようになったのです。
-
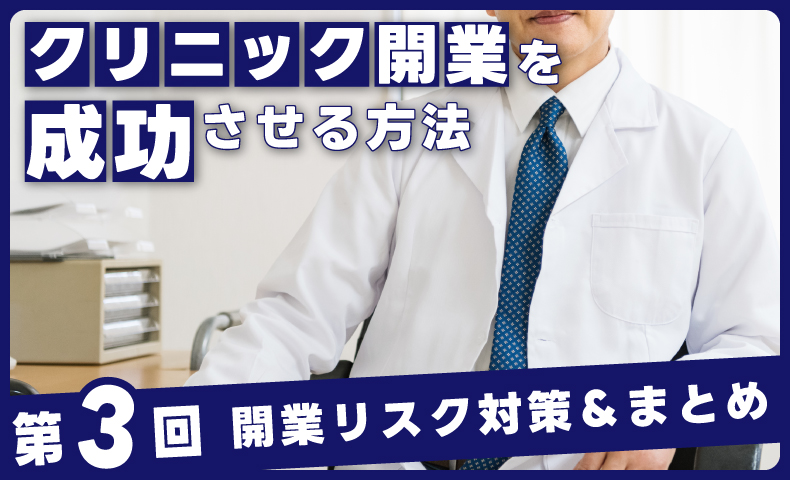
医師がクリニック開業を成功させるには?【第3回】開業リスク対策とまとめ
このコラムでは、「医師の人生をより豊かに」をモットーに、多忙の極みである医師に、少しでも有益なコンテンツを提供しようと日夜考える勤務医ドットコム編集部が監修しています。
今回は最終回、開業リスク対策とメリット・デメリットなどを解説します。
-
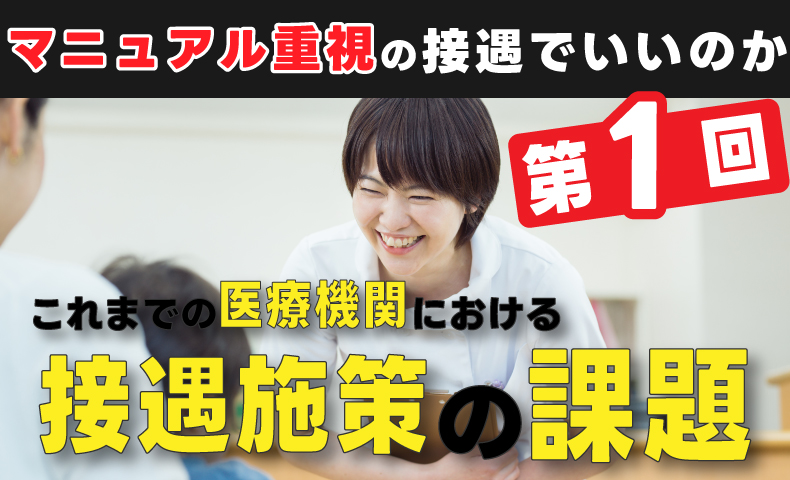
【マニュアル重視の接遇でいいのか 第1回】これまでの医療機関における接遇施策の課題
一時期、マナーのルールを制度化した、マニュアルありきの接遇研修が多くの医療機関でも導入されましたが、現場にそぐわず、いまだ定着するには至らないケースも多いようです。何が問題なのか。どうすれば接遇力を上げ、患者から信頼される医療機関になれるのかを、4回連載で接遇イノベーションともいうべき、これからの「接遇」のあり方について考察します。
-

開業医が年収1億円を目指すためには?特徴や具体的な方法を解説
-

開業医の月収はいくら?勤務医との比較や月収を増やす方法を解説
-

不動産投資とは!?メリットやデメリットから成功するためのポイントを解説
-

医者が知っておきたい不動産投資の仕組みと成功の秘訣とは
-

資産運用とは?始め方や注意点について徹底解説
-
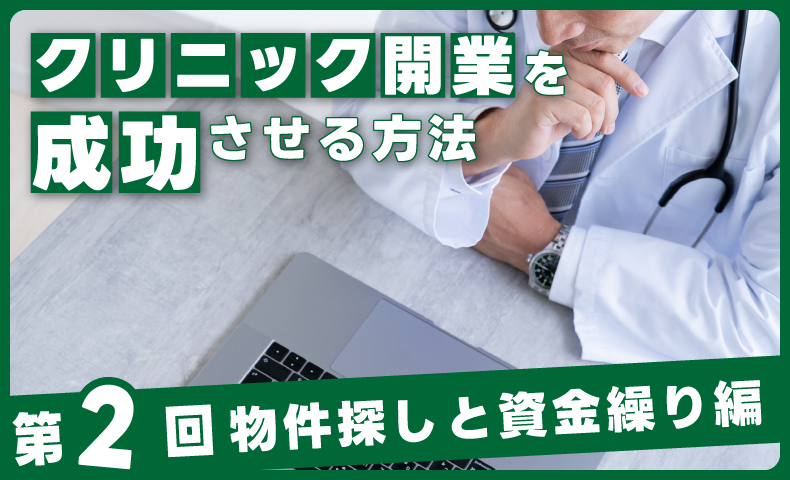
医師がクリニック開業を成功させるには?【第2回】物件探しと資金繰り編
このコラムでは、「医師の人生をより豊かに」をモットーに、多忙の極みである医師に、少しでも有益なコンテンツを提供しようと日夜考える勤務医ドットコム編集部が監修しています。
今回は物件選びから初期費用、資金繰りなどを解説します。
-

株での税金対策と節税術のポイントについて徹底解説!
-

医者が本命彼女にする女性の特徴とは?接し方のポイントも解説
-
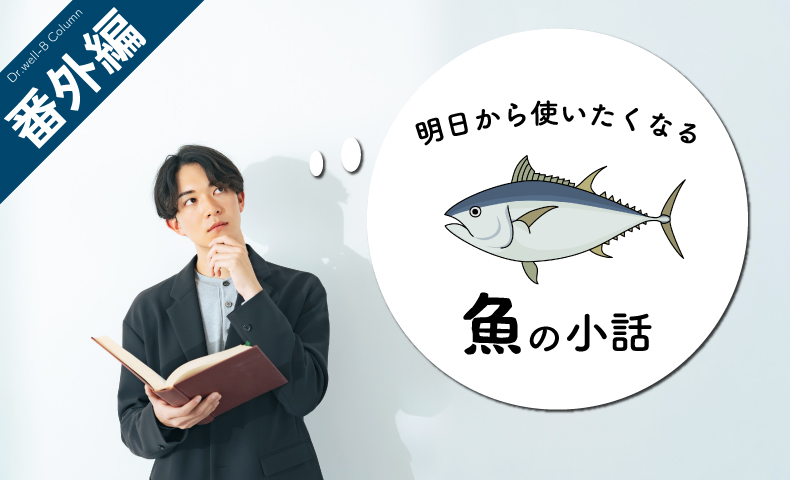
【医師が知っておきたい雑学】明日から使いたくなる魚の小話
突然ですが、皆さん魚を区別するとき、赤身の魚、白身の魚、青魚などの区別をされていることを耳にすると思います。
・この区別はどのようにしているのか?
・何か基準値のようなものがあるのか?
疑問に思いませんか?
本日は医師が知っておきたい、ちょっとした魚の雑学のお話をさせていただきます。
-

医師がクリニック開業を成功させるには?【第1回】地域とコンセプト編
このコラムでは、「医師の人生をより豊かに」をモットーに、多忙の極みである医師に、少しでも有益なコンテンツを提供しようと日夜考える勤務医ドットコム編集部が監修しています。
今回は「開業準備どう進めれば良いのかよくわからない」という方に向けて、開業場所の選び方から、開業にかかる時間やお金のことなどを解説します。
-

資産運用のポートフォリオとは?作り方や年齢別の例について解説!
-

事業投資とは?金融投資との違いや利回りについて徹底解説
-

経費は節税に効果的!必要経費について徹底解説!
-

医師の節税方法・対策のおすすめ12選! 法人・個人などカテゴリー別に解説!
-
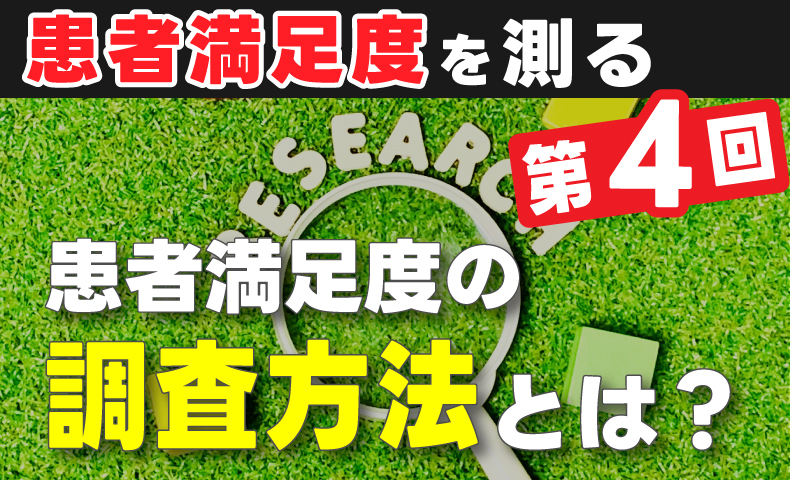
【患者満足度を測る 第4回】患者満足度の調査方法とは
患者満足度を調査することで、既存患者の定着化を図るだけにとどまらず、診療・治療・接遇などの改善に活かしたり、新規患者の獲得につながる施策を検討する上で、非常に重要なデータを得ることが可能となります。
調査のやり方はさまざまですが、最初は外部の機関を使って大掛かりに行うのではなく、自前で簡潔に実施することから始めてみてはいかがでしょうか。
-
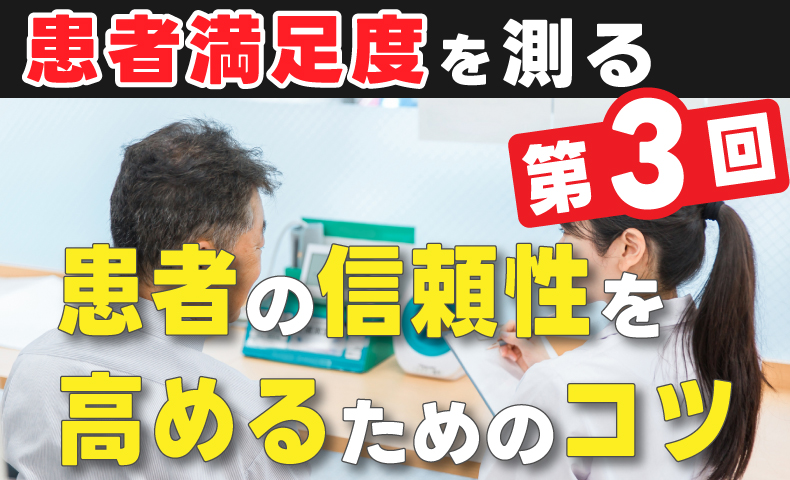
【患者満足度を測る 第3回】患者の信頼性を高めるためのコツ
患者は初回受診に当たって、どのような基準で医療機関を選択するのでしょうか。
診療所を探す場合は、インターネットの情報は場所や診療日、施設概要の確認のためが主目的であり、「家族や知人による紹介・評判」が第1の選択ポイントであろうと考えられます。
それに対し、病院を選ぶ場合では、診療科の有無や診療体制、設備や技術の充実の度合いなどのWebサイトに表記すべき情報が最優先すると思われます。
-

勤務医の平均年収は?年代ごとに徹底解説
-

不動産投資は節税対策に繋がる?メリット・リスクも徹底解説
-

勤務医におすすめの節税対策とは?抑えておくべきポイントも徹底解説!
-

医者が結婚相手に求めるものとは?職業・学歴など
現代の結婚市場では、職業や学歴などが重要な要素となっています。特に医者という職業は、その特性上、結婚相手に対する要求も独特かもしれません。
そこで本記事は、医師という専門職を持つ人々が、結婚相手にどのような特質を求めるのかに焦点を当てています。この記事を通して、医師との結婚に対する理解を深め、より充実した人生を送るための参考となれば幸いです。
-

549名の医師が回答!医師の結婚に関する意識調査
人生の岐路となる「結婚」。
医師の方も大きなターニングポイントとなるのではないでしょうか。
今回、勤務医ドットコムでは医師の結婚に関する意識調査アンケートを実施し、医師の既婚率、男性医師と女性医師の結婚感の違いなどをまとめました。 -
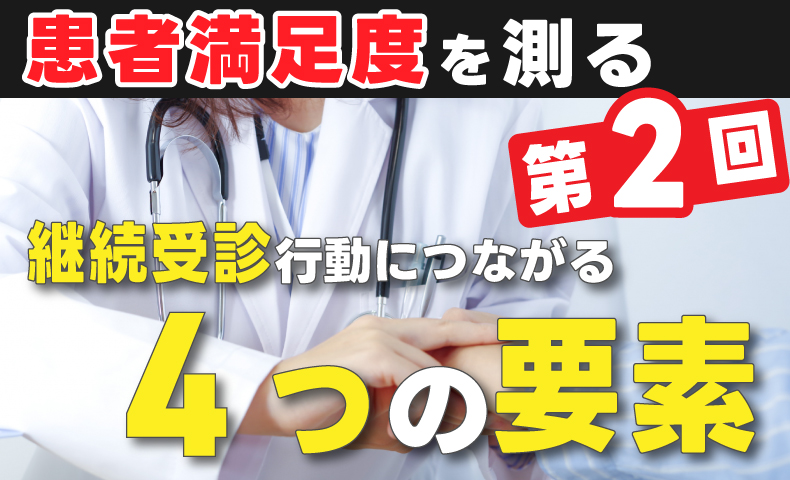
【患者満足度を測る 第2回】継続受診行動につながる4つの要素
一般的な消費市場では、顧客はリピート購買を繰り返しながら固定客になっていきます。
医療においても、患者満足度の向上が継続受診の意向に影響を与えており、慢性疾患の治療のために診療所や病院を繰り返し受診している患者が固定患者となり、他の病気やけがの際にも当該医療機関を選択する意向がいくつかのデータから示されています。
患者満足度は、かかりつけ医としての信頼性を測る基準にもなるのです。
-

医者は年収1億円は可能なのか?平均年収と儲かるポイントについて徹底解説!
-

1,000万円の資産運用方法とは?おすすめの投資と注意点について徹底解説!
「1,000万円をどう運用すればいいのか?」そんな疑問をお持ちのあなたへ。この記事は、そんな悩みを解消するために特化しています。
1,000万円という額は、ただ預けておくだけではもったいないけれど、リスクも避けたいと考える方にとって、適切な運用方法を見つけることは重要です。
この記事では、1,000万円を最大限活用するための方法を詳しく解説します。資産運用の基本から、おすすめの投資先、そして失敗しないための戦略まで、幅広くカバーしています。
-

1億円の資産運用のおすすめ方法!運用利回りや注意点についても徹底解説!
-

医師におすすめの節税方法!不動産投資、法人設立など注意点について解説!
医師は高年収である一方、税金の支払いも多くなる傾向にあります。節税方法を知ることで、今までよりも税金の支払いをおさえ、その分資産増加につながるでしょう。
そこで本記事では、医師の方々に向けた節税方法を具体的かつ効果的に解説しています。不動産投資や会社設立などの節税策を考えている方、これから節税計画を立てようとしている方は、ぜひ最後までご一読ください。
-

勤務医で年収は3,000万可能なのか?稼ぐポイントについて徹底解説!
勤務医をしている方にとって、年収3,000万円という目標は遠い夢のように思えるかもしれません。しかし、この記事では、その夢を現実に変えるための実践的な戦略を徹底解説します。
日々の忙しさのなかで見落としがちな収入アップのチャンス、キャリアアップのための具体的なステップ、さらには勤務医の働き方の最適化についても触れます。
本記事を読むことで、自身のキャリアにおける課題を明確にし、それを乗り越えるための具体的な方法を得られるでしょう。自身の収入とキャリアアップを目指したい方は、ぜひ最後までご一読ください。
-

【患者満足度を測る 第1回】継続的に受診してもらうには
患者による医療の評価を知ること、すなわち患者の主観的感情である「患者満足」の検討は、患者インサイトを探る上で大きな手掛かりとなります。
そして、安定した経営基盤の確立、つまり継続的に受診してもらいロイヤリティを高めてもらうためには、個々の患者の満足度の向上は不可欠の要素です。
-
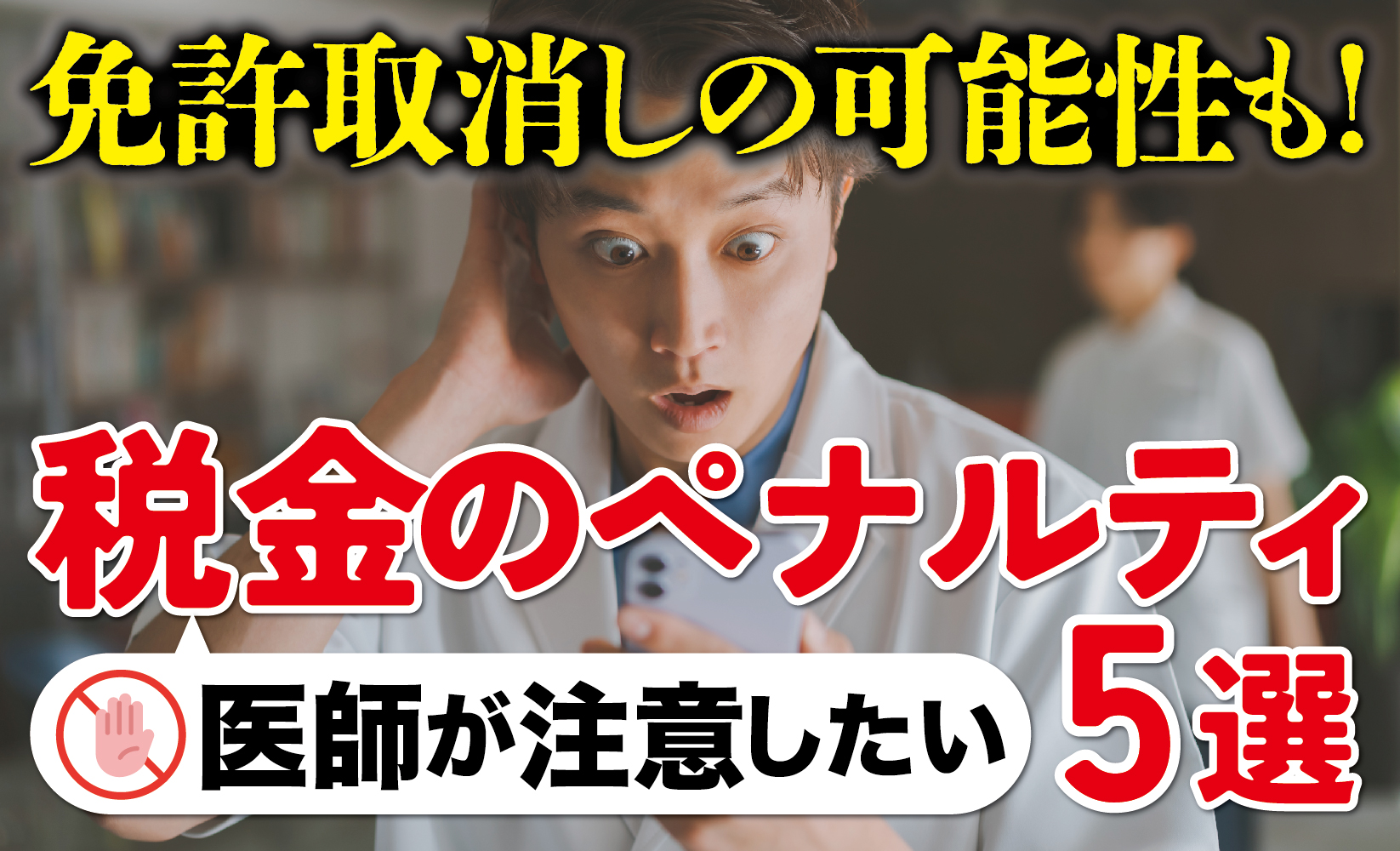
免許取消しの可能性も!医師が注意したい「税金のペナルティ5選」
医師が税法違反を犯した場合、どのような処分が下されるかご存じでしょうか?
意外と知られていませんが、医師の税法違反の行政処分はかなり重く、悪質なケースと判断された場合には免許取消になる可能性があります。
今回は、税金関連で医師が気をつけたいペナルティについてお伝えします。間違っても“うっかり違反”を犯すことがないよう、しっかりチェックしていただきたいです。
-

【チーム医療のマネジメント最終回】不公平を是正する
チーム医療を推進したのは良いが、一部の医療スタッフに負担が集中したり、安全性が損なわれたりするという事案はよく起こることです。
チーム医療とは、「患者さんにとって望ましい医療を実現するために、医療従事者がお互いに対等の立場から連携して活動していくこと」であり、この基本理念は常に意識しなければなりません。 -

【チーム医療のマネジメント第3回】誠実なリーダー4つの姿勢
チーム医療を実践する医療従事者、わけてもその中心的役割を担う医師においては、その行動規範の中心にあるのが「誠実さ」だと考えます。「チーム医療のマネジメント」第3回は、「誠実さ」にスポットを当てました。常に誠実さをもって患者さんや医療スタッフに接していれば、所属する医療機関の評判はしっかりと守られます。
-

【チーム医療のマネジメント第2回】気遣いを示すコミュニケーション
チーム医療の質向上を図るには、他の職種を尊重し、明確な目標に向かってそれぞれの立場から評価をし合い、専門の技術を効率よく提供することが求められます。そのためには、カンファレンス等を充実させることが必須となりますが、その場で医師やスタッフ同士が気遣いを示しながら、互いの仕事の大変さや難題に関心を寄せることが大切です。「チーム医療のマネジメント」講座の2回目は、「気遣いを示す」にポイントを当てました。
-
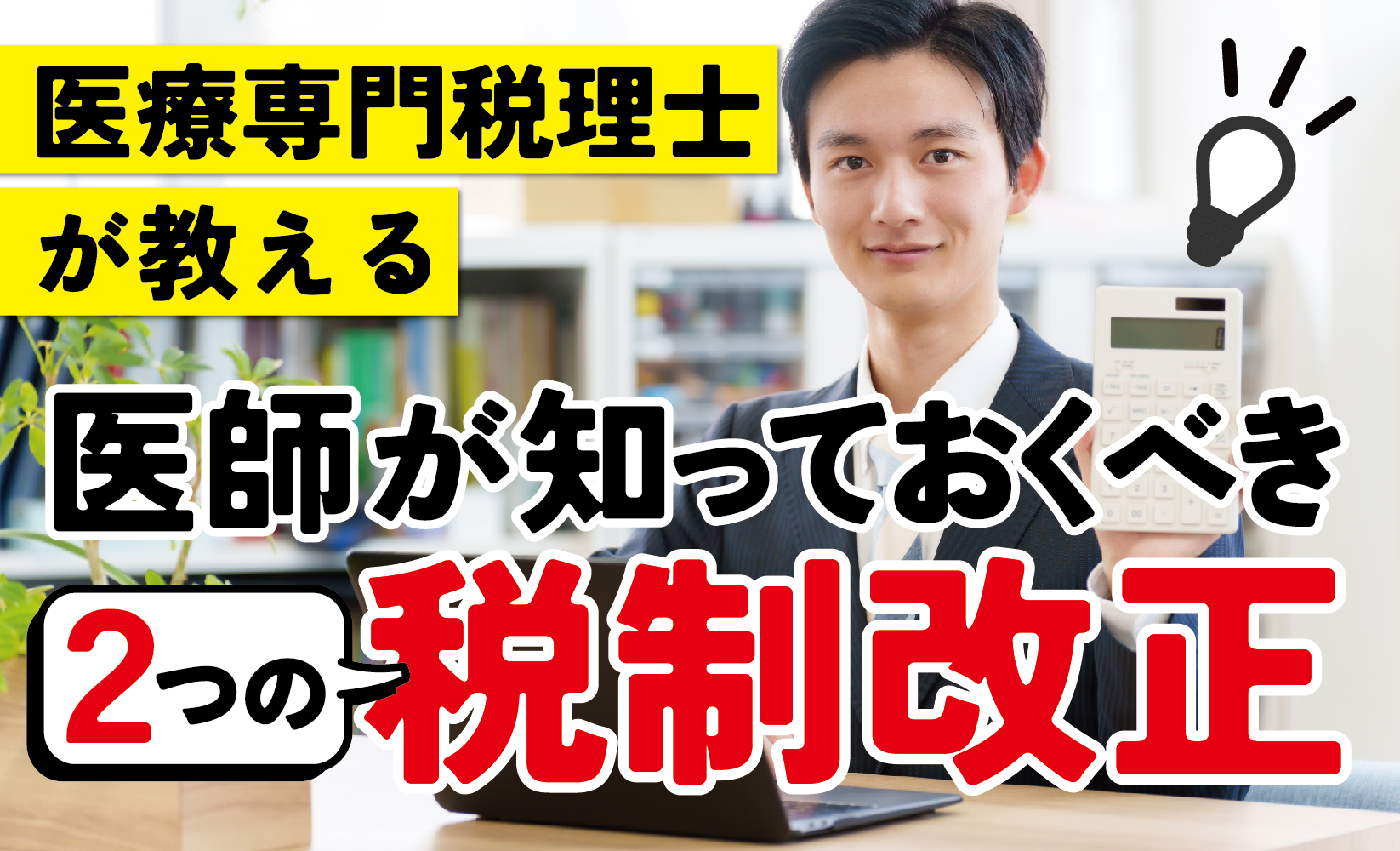
【医療専門税理士が教える】医師が知っておくべき「2つの税制改正」
近年の日本では、収入にかかわらず、個人の納税額は増加の一途をたどっています。特に2019(令和元)年の消費税増税は記憶に新しいでしょう。
加えて高所得者にとっては、本来は国からの恩恵であるはずの制度でさえ、ますます不利なものになっています。
今回は、その代表例である「児童手当制度」と「住宅ローン控除制度」についてお伝えします。 -
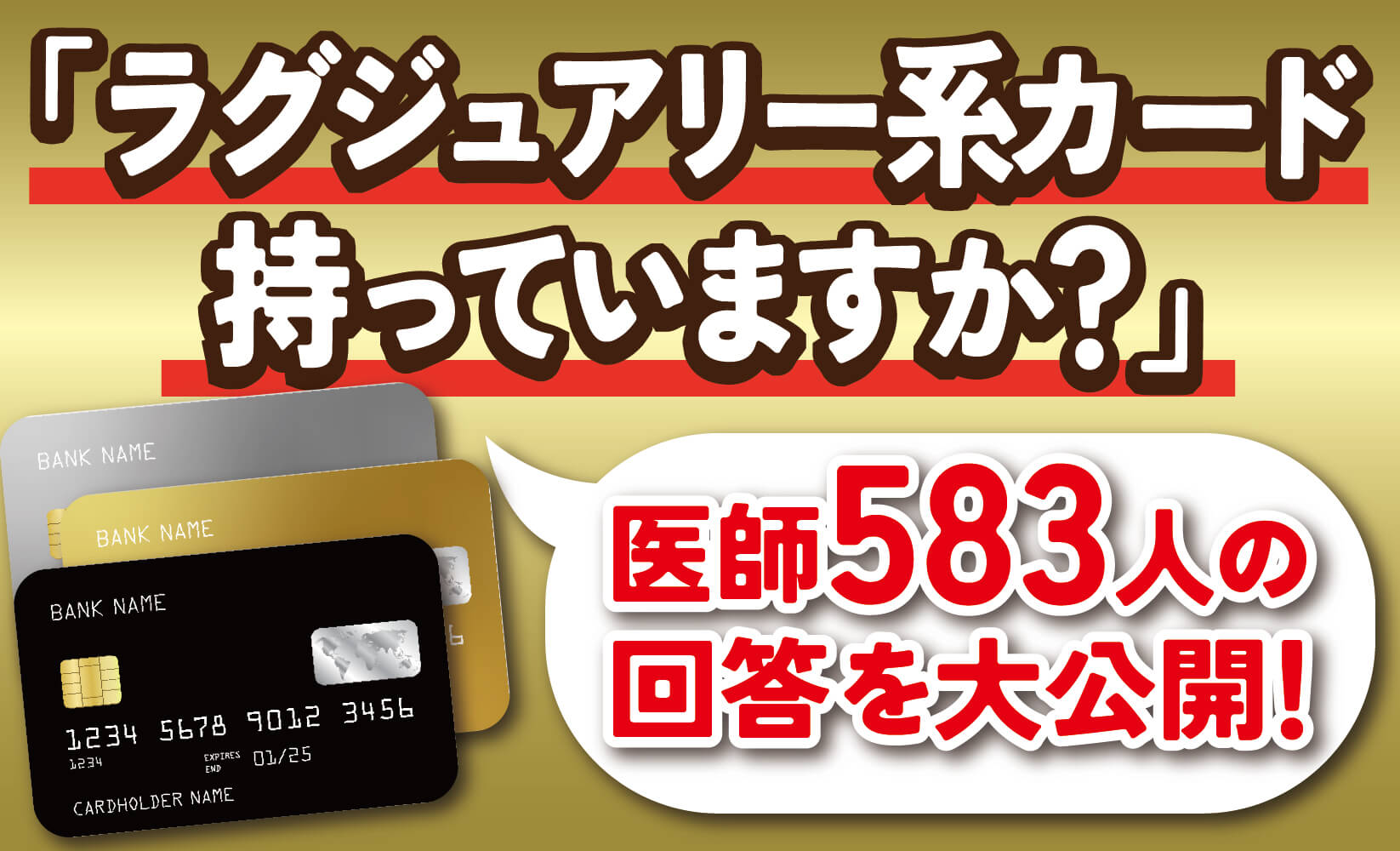
「ラグジュアリー系カード、持っていますか?」医師583人の回答を大公開!
「高年収な職業といえば?」と聞かれると、多くの人は「医師」と答えるでしょう。ゴールドカードやブラックカードを所持し、高価な時計やジュエリーを次々に購入する……というイメージを抱いている人も多いはずです。
そこで勤務医ドットコムでは、医師のクレジットカードに関する意識調査を実施し、ラグジュアリー系カードの所持率や、これまで最も高額だった決済の額、その使い道などを尋ねました。
高年収な医師はどんなクレジットカードを所有し、何にお金を使っているのか。ぜひご覧ください。 -
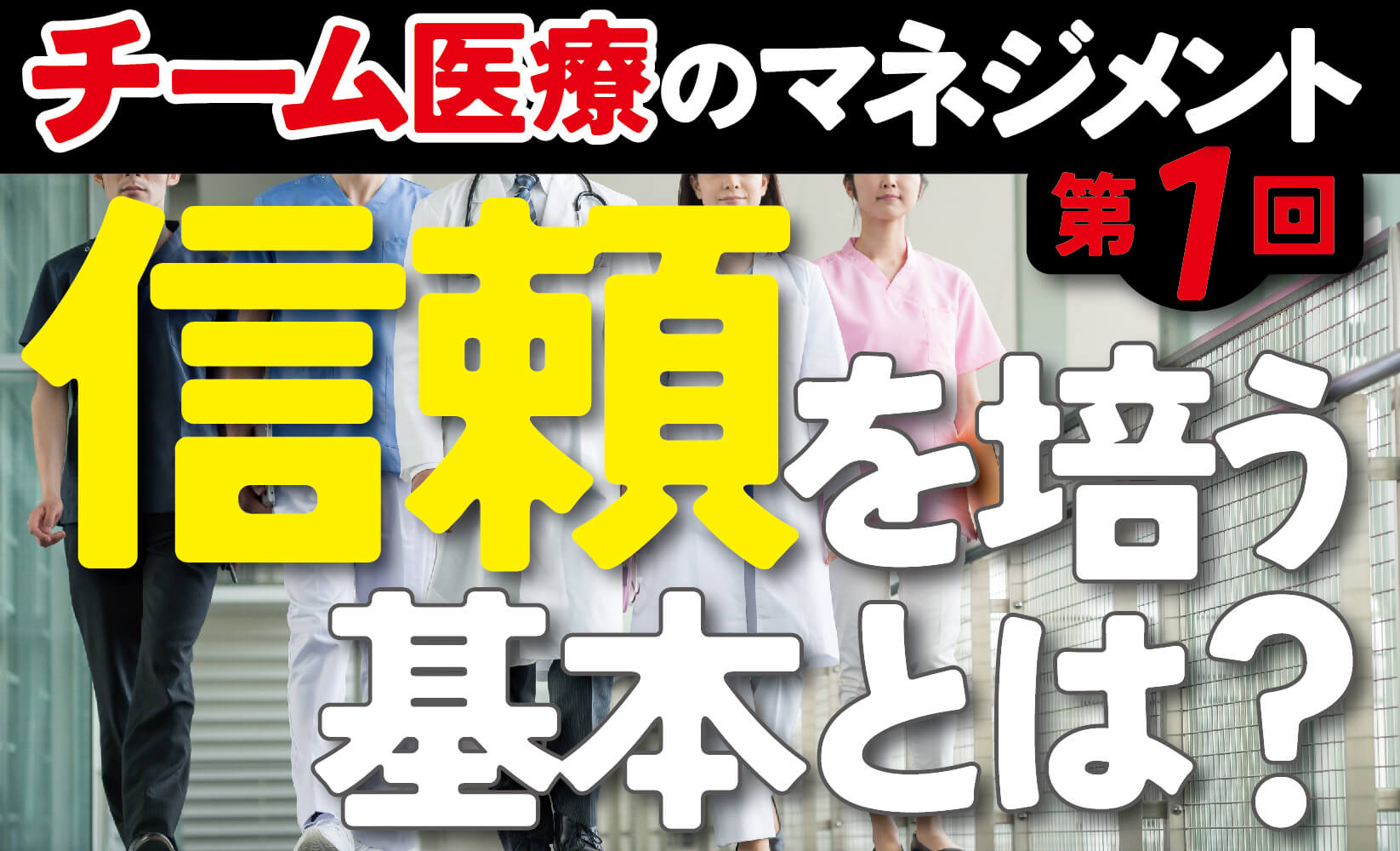
【チーム医療のマネジメント第1回】信頼を培う基本とは?
チーム医療のマネジメントは、リーダーという立場にある医師だけに必要なものではありません。チーム医療を効率よく実践するためには、どんな役割、立場にある人にも、リーダーシップやマネジメント力が求められます。優れたリーダーは、周囲とどのように関わり、どのように物事を推進しているのでしょうか。実践のポイントを4回に分けて紹介します。
-

医師583人が回答「最も人気のクレジットカード」は? その理由も公開!
コロナ禍を経てますます一般的になったキャッシュレス支払い。
「現金はほぼ使わなくなった」「小さな財布に買い替えた」という方も多いのではないでしょうか。
そこで勤務医ドットコムでは、医師のクレジットカードに関する意識調査を実施。高年収職業とされる医師がどんなクレジットカードを何枚持っているのか、なぜそのカードを選んだのかなどについて調査しました。
この記事では、医師のクレジットカード所持枚数やカードのランクについてまとめます。 -
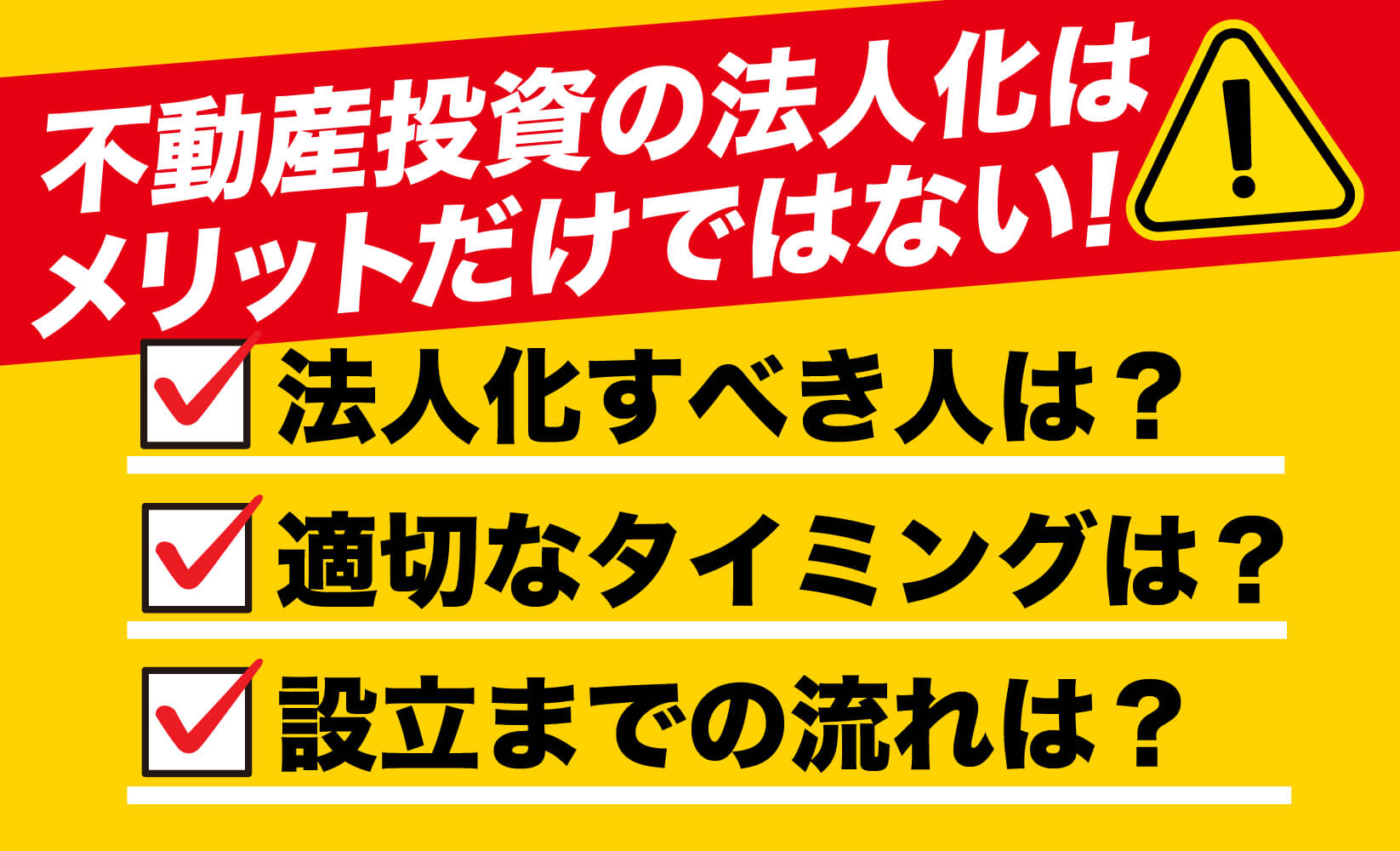
不動産投資の法人化はメリットだけではない! 法人化すべき人、適切なタイミング、設立までの流れは?
不動産投資は節税効果が期待できることから、ある程度年収が増えてきたら、法人化することを推奨されています。今回は、勤務医や開業医が不動産投資を法人化することのメリット、法人化移行へのベストなタイミング、業務開始までの流れについてまとめました。
-
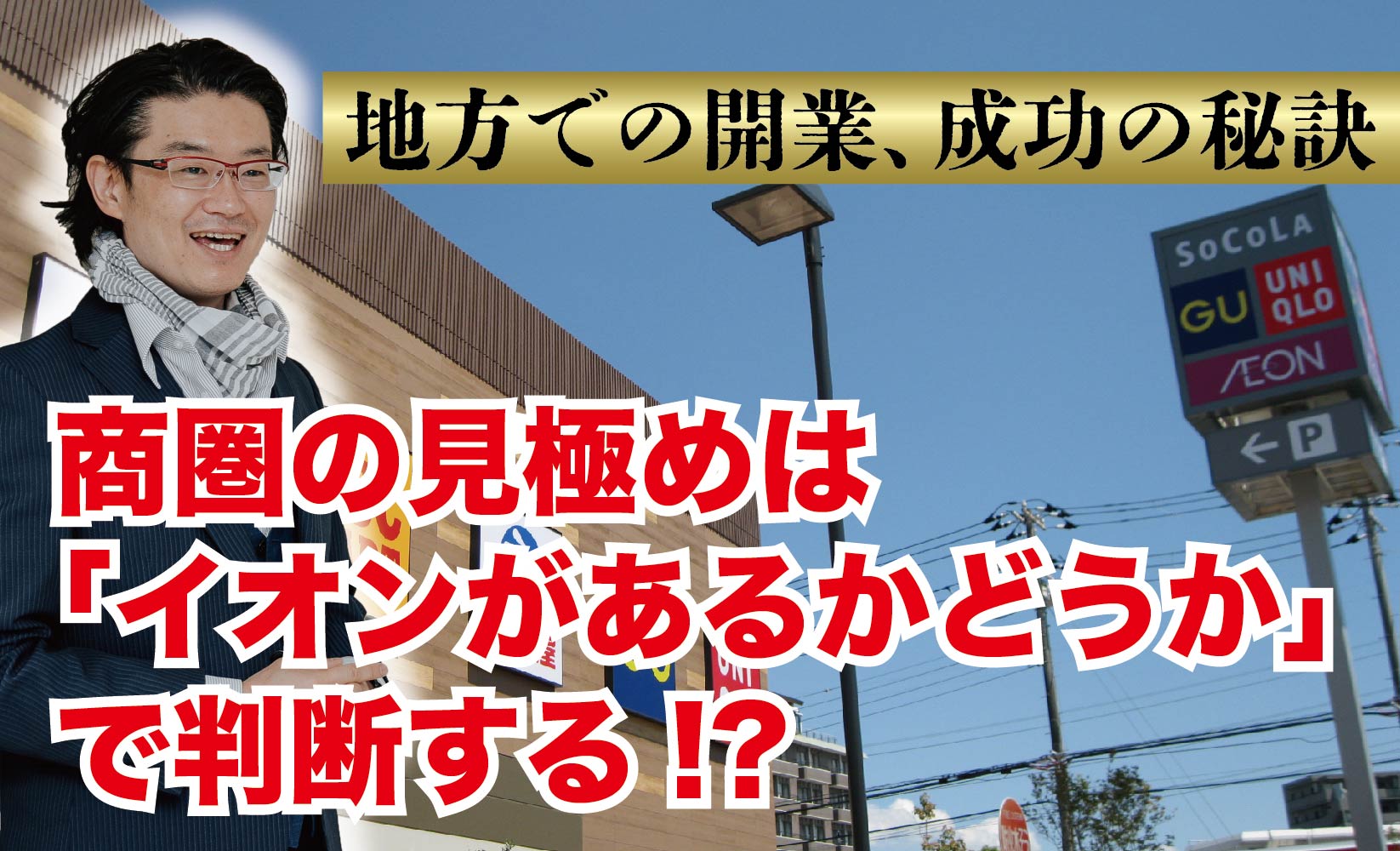
【地方での開業、成功の秘訣】商圏の見極めは「イオンがあるかどうか」で判断する!? 〜1日300人来院のクリニック院長が必勝法を伝授〜
勤務医ドットコムをご覧になっている勤務医の方々のなかにも、「いずれは開業」と目標を持っている方もいらっしゃるかと思います。開業は決断の連続です。決めるべきことはたくさんありますが、なかでも「都心か、地方か、どこで開業するか」は大きなポイントです。
今回は、人口およそ3万人の市にもかかわらず年間4万8000人もの患者が来院する「すずきこどもクリニック」院長であり、“日本一忙しい小児科医”として有名な鈴木幹啓医師に、地方での開業で成功するための必勝法を伺いました。 -
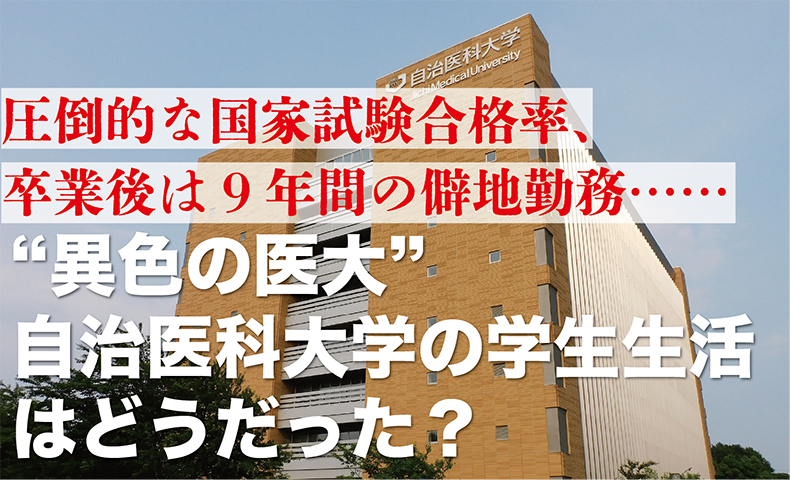
圧倒的な国家試験合格率、卒業後は9年間の僻地勤務……“異色の医大”自治医科大学の学生生活はどうだった?
私は自治医科大学を卒業して、現在は和歌山県で小児科のクリニックを経営しています。自治医科大学は防衛医科大学と並んで“特殊”と言われているようですね。実際に、私が在学していた頃も卒業後も、波瀾万丈で得難い経験を送った日々でした。
今回は、そんな自治医科大学についてお話しします。現在とは異なる部分もあると思いますので、“そんなこともあったんだなぁ”という気持ちで読んでいただければと思います。 -
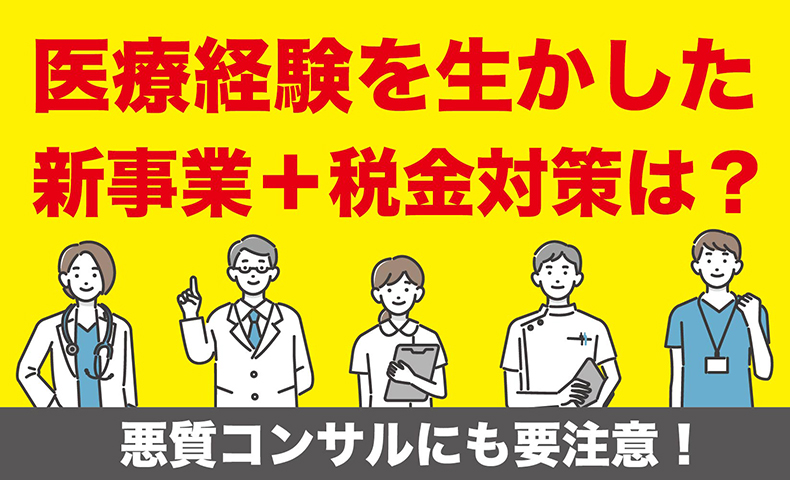
医療経験を生かした新事業+税金対策は? 悪質コンサルにも要注意!
医師のみなさんはどのようして収入をあげていますか? 当直やアルバイトなどで収入を増やす方もいますが、医療経験を生かした新規事業というチャレンジングな選択肢もあり得るでしょう。
今回は医学生時代から事業を興した経験のあるH先生に、また医師でありながら大家業を営むS先生に、事業内容やそれに伴う税金対策などについてお話を伺いました。キャリアアップを考える医師の方はぜひ参考にしてみてくださいね。 -
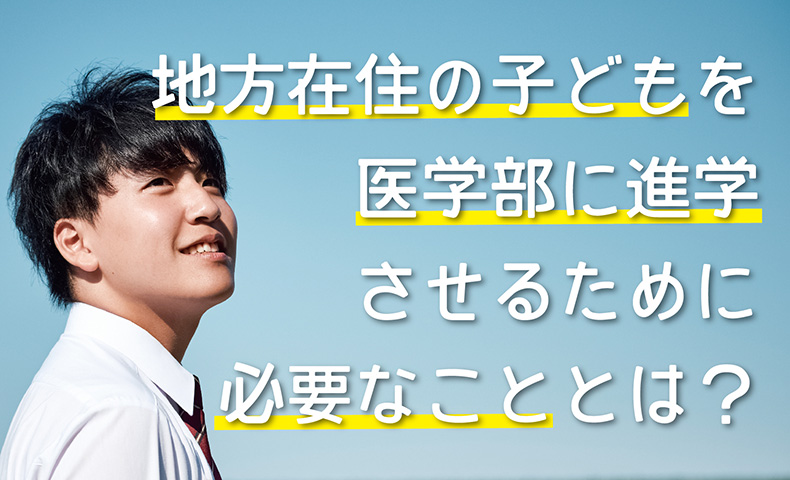
地方在住の子どもを医学部に進学させるためには? 〜都会の子どもと同レベルの教育を受けさせるために、医師である親ができること〜
医学部部生のうち、親が医師である割合は私立大学で約半数、国立大学で約3割といわれています。しかし、医師の子どもであっても、地方在住の場合、「周りに進学校がない」「進学塾もない」「医学部を目指している学生も少ない」という環境の中で、全国の医学部受験生と戦わなくてはいけません。そんなとき、親はどうサポートするのがいいのでしょうか?
今回は、非医師家庭に育った私の体験談をもとに、親としてできることは何かお伝えしたいと思います。 -

産業医や労働衛生コンサルタントへキャリアアップ! 試験や実際の仕事はどんな内容?
医師免許を持っている方であれば、キャリアアップの選択肢の一つとして「産業医」や「労働衛生コンサルタント」への道を考える方もいるでしょう。さまざまな職場での労働衛生を指導したり、そこで働く人たちの健康管理を行ったりするのが主な役割です。コロナ以降特に需要が高まったこともあり、資格取得を目指す医師の方も多いのではないでしょうか。
今回は両資格を持つ医師のS先生に、主に労働衛生コンサルタントの試験に関する話、また現場での体験談などをお伺いしました。 -
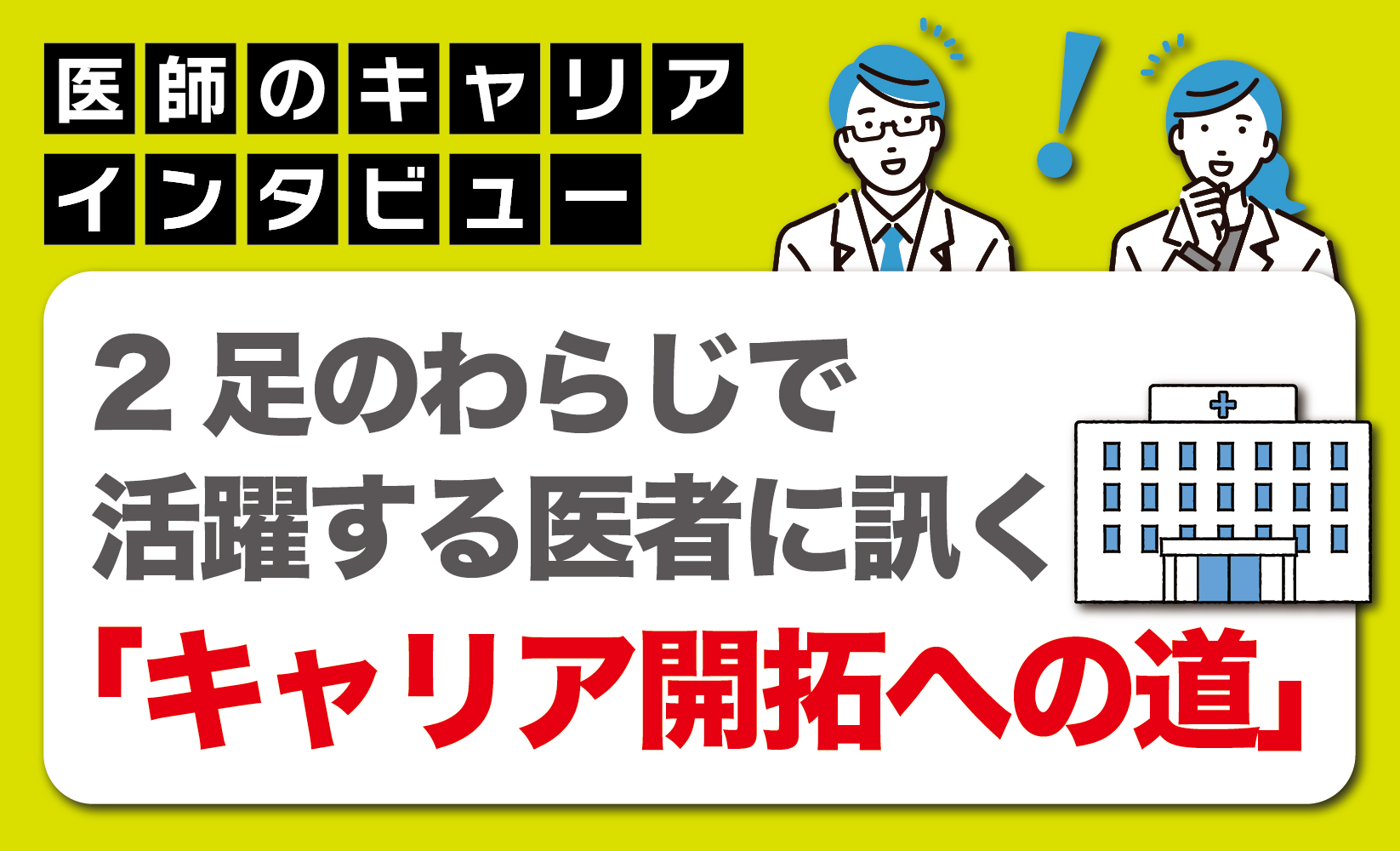
【キャリアインタビュー】専門医と会社経営、2足のわらじで活躍する医者に訊く「キャリア開拓への道」
医者の働き方は勤務医か開業医の2択に括られがちですが、他分野ビジネスでの起業を目指す方は少なくありません。医者の世界に入り、紆余曲折を経て起業した「株式会社カスミトル」の代表・杉下義倫先生に、現在のキャリアを開拓するまでのストーリーを伺いました。
-

やっぱり気になる! 30代勤務医のクルマ・女性・おカネ事情あれこれ
若い勤務医はどんなクルマ選びをしている? 女性とのお付き合い事情は? おカネのことはどう考えている? 関東の某大学病院に勤務する30代前半の整形外科医のスカイ先生に、そんな素朴な疑問に対するあれこれを、リアルに語っていただきました。
-
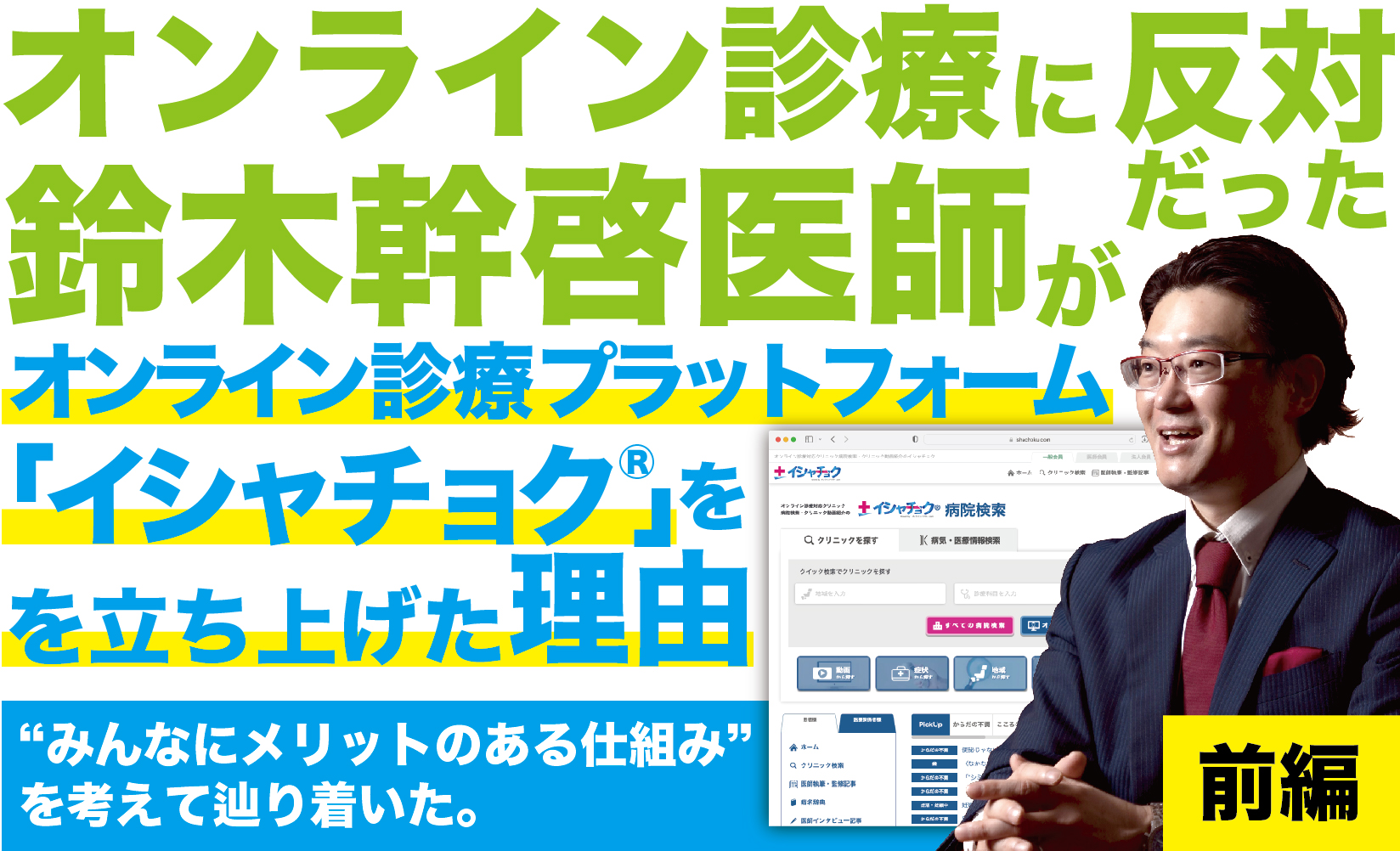
“みんなにメリットのある仕組み”を考えて辿り着いた。オンライン診療に反対だった鈴木幹啓医師がオンライン診療プラットフォーム「イシャチョク®」を立ち上げた理由(前編)
新型コロナウイルス感染拡大を受けて、オンライン診療は大きな進展をみせました。オンライン診療は患者にとってさまざまなメリットがある一方、対面診療よりも報酬点数が低い等の理由で、医師にとってはデメリットとなる場合があります。その定説を覆し、オンライン診療プラットフォームで大成功をおさめたのが鈴木幹啓医師が手がけるサービス「イシャチョク®」です。
今回、勤務医ドットコムでは鈴木幹啓医師の独占インタビューを実施。「イシャチョク®」をローンチするまでのストーリーや、鈴木医師が思い描く“あらゆる人にメリットがあるシステム”とはどのようなものなのか等、貴重なお話を伺いました。 -

“オンライン診療は儲からない”定説をひっくり返す! 開業医と勤務医の収入格差をなくすオンライン診療プラットフォーム「イシャチョク®」を鈴木幹啓医師が立ち上げた理由(後編)
“対面診療よりも報酬点数が低いオンライン診療は儲からない”という定説を覆し、オンライン診療プラットフォームで大成功をおさめた「イシャチョク®」。
今回、勤務医ドットコムではイシャチョク®︎を手がけた鈴木幹啓医師に、独占インタビューを実施。前編に引き続き、貴重なお話を伺いました。 -
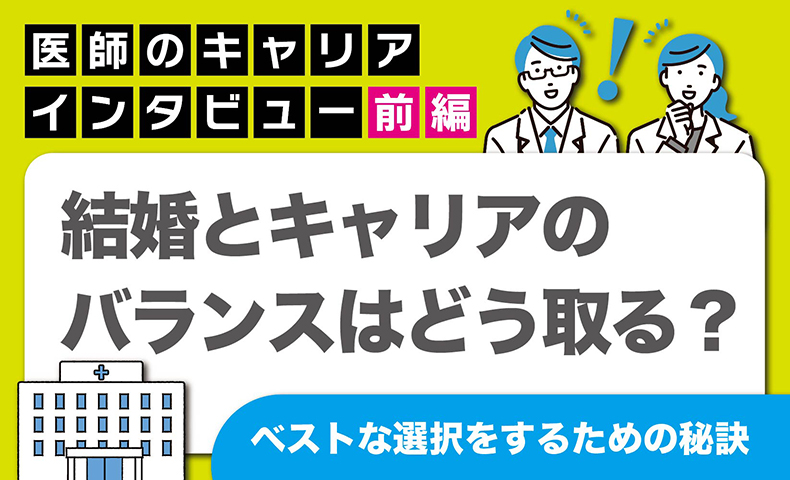
【キャリアインタビュー前編】結婚とキャリアのバランスはどう取る? ベストな選択をするための秘訣
今回登場いただくのは、某県にある大学病院の消化器外科を担当する夜王先生。研修医を経て、消化器系を中心に幅広い治療領域で活躍する夜王先生は、仕事と遊び、そして投資にも全力投球だ。30代に入り、病院で主軸として活躍する独身男性医師の「リアル」を訊いてみた。
-
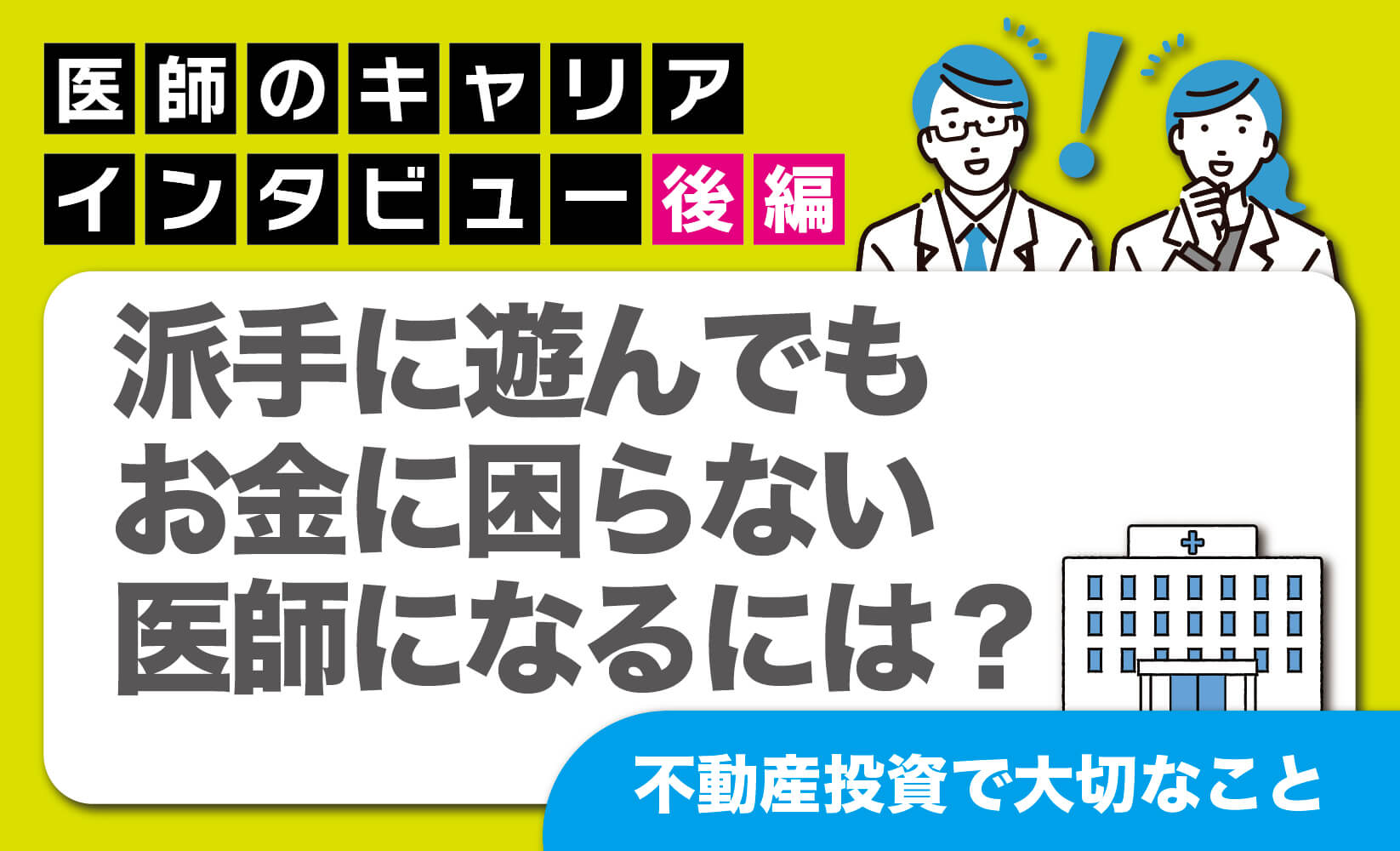
【キャリアインタビュー後編】派手に遊んでもお金に困らない医師になるには?不動産投資で大切なこと
某県にある大学病院の消化器外科を担当する夜王先生のインタビュー第2弾。
30代前半独身で、仕事と遊びを充実させる夜王先生のプライベート、またコロナをきっかけに始めた不動産投資について、医師のお金まわりの「リアル」を訊いてみた。 -
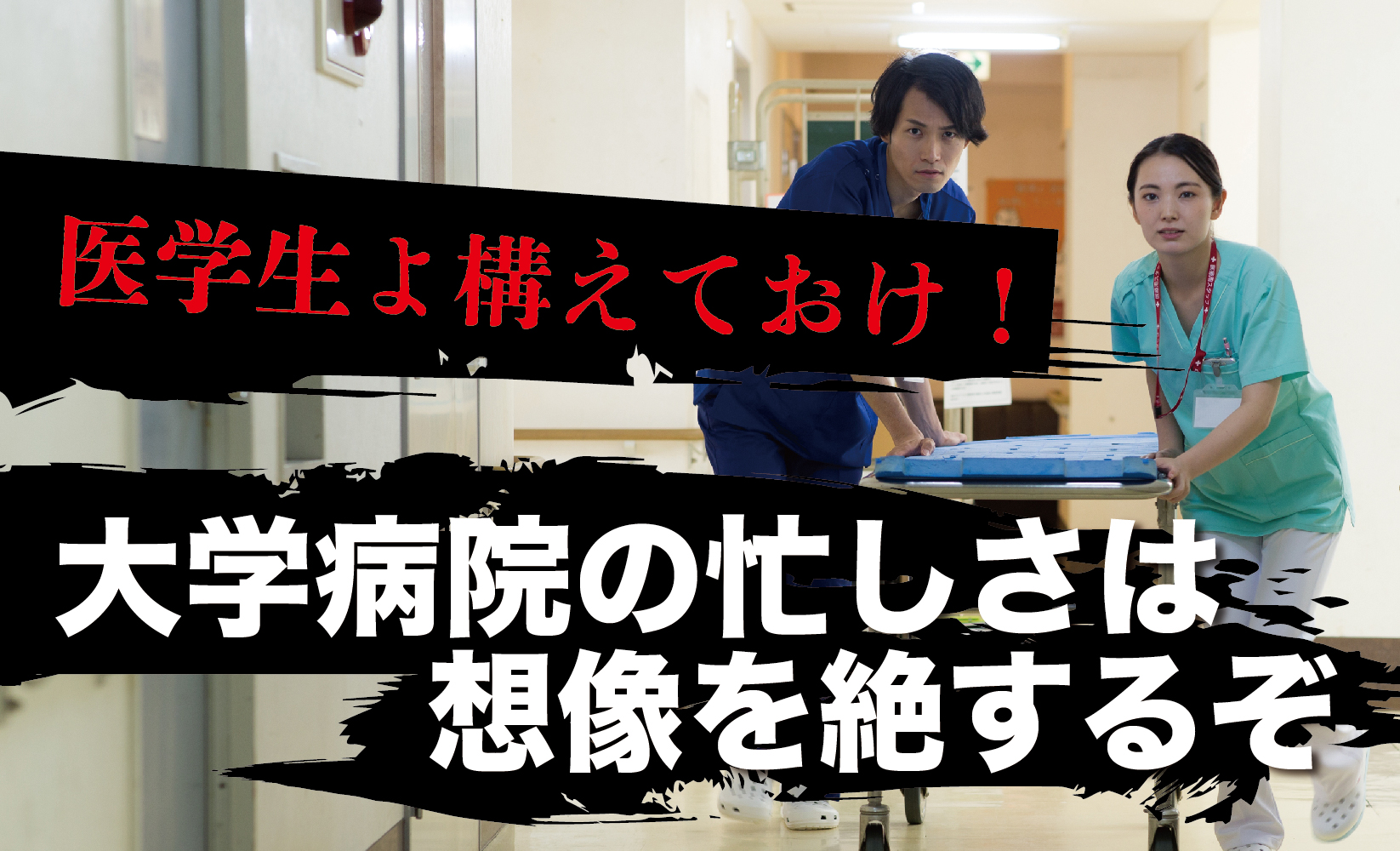
医学生よ構えておけ! 大学病院の忙しさは想像を絶するぞ
医師を目指している医学部生の皆さんは「きっと医師免許を取得したら忙しい日々が待っているんだろうな」と、ほんのり考えているかもしれません。 しかし現実は、想像を何倍も上回る忙しい日々が待っています。通常業務以外のイレギュラーな対応や予想だにしない邪魔が入ることも……。
今回は医師の日々の忙しさについて、現役医師からの助言も含めて解説します。医学部生の皆さん、必読です! -

≪タイアップ≫開業1年で規模拡大も! 在宅医療の“ひとり開業”は可能?
※本記事はマイナビとのコラボレーションです。
日本の高齢化や過疎化に伴い、年々ニーズが高まる「在宅医療」。ニーズの高まりに比例して、在宅医療での開業を希望する医師も増加傾向にあります。
在宅医療で“ひとり開業”は可能なのか、開業するならどのエリアを選ぶべきか……医療求人のプロフェッショナルであるマイナビドクターさんに、在宅医療開業についてうかがいました。(インタビュアー:Dr.マック) -

≪タイアップ≫人柄が最重要! 地方の在宅医療のリアル
※本記事はマイナビとのコラボレーションです。
高齢化の進む日本で注目されている「在宅医療」。
地方の在宅医療の現状とは? 在宅医療にはどのようなスキルや経験が求められる? まずは総合病院に入職して“修業”すべき? など、在宅医療を目指す方にとって気になる質問を、医療の求人のプロフェッショナル、マイナビドクターさんにうかがいました。(インタビュアー:Dr.マック) -

≪タイアップ≫好待遇が最大の理由⁉ 「美容の道」を選ぶ若手医師が増える理由
※本記事はマイナビとのコラボレーションです。
近年増加傾向にある「初期研修を終えてすぐ美容医師になる」というキャリア。
なぜ美容の道を選ぶ若手医師が増えているのでしょうか? 美容医師に必要な資質は? 美容の道を進みたいとき、誰に相談すればいいのでしょうか――美容医師の求人に強みを持つマイナビドクターさんにお話をうかがいました。(インタビュアー:Dr.マック) -
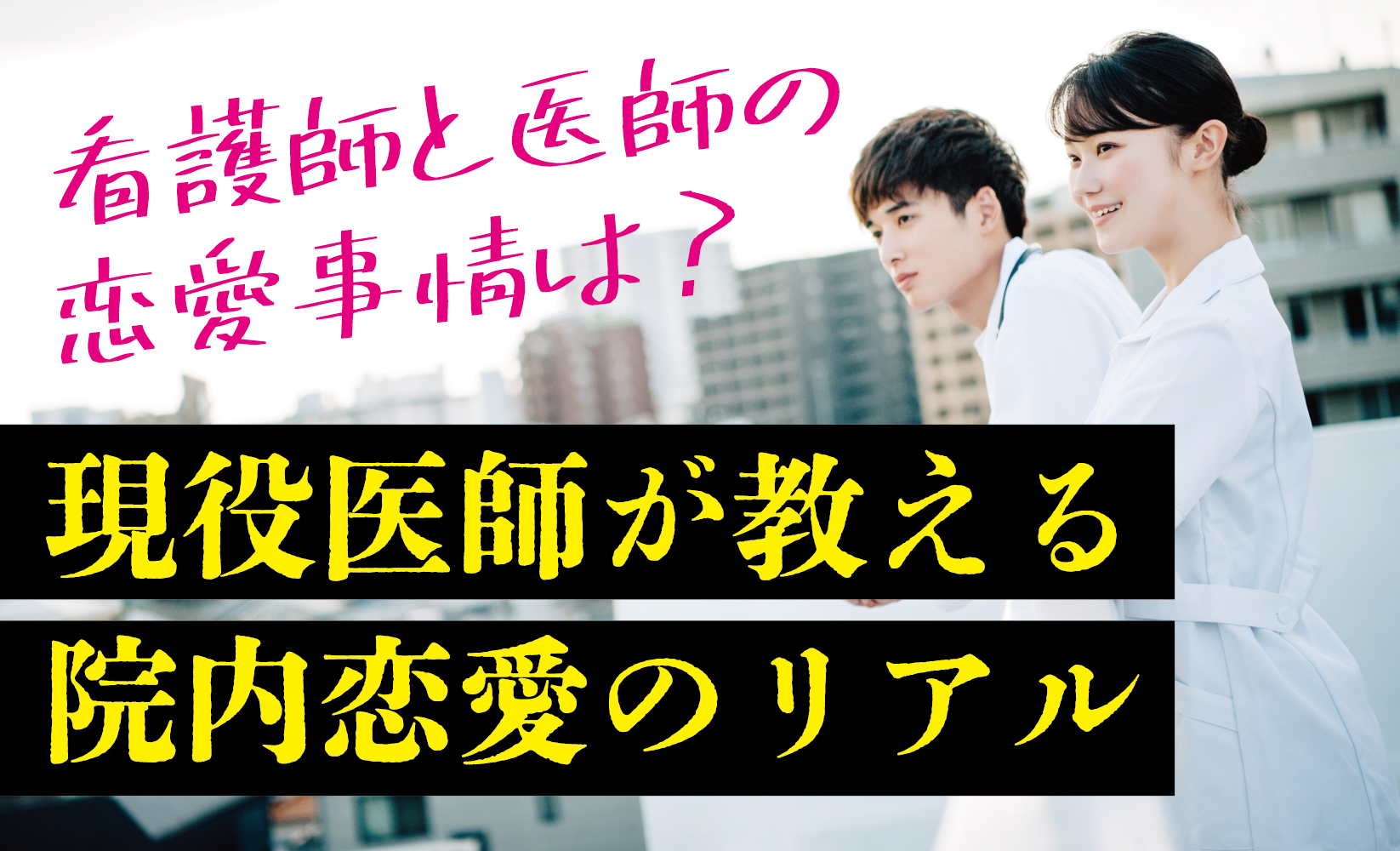
看護師と医師の恋愛事情は? 現役医師が教える院内恋愛のリアル
医師はどのようにして異性と出会うのでしょうか? 多忙を極める職業柄、医師の恋愛で最も多いのはやはり医師と看護師の組み合わせでしょう。
実際に職場が一緒だった看護師と結婚した医師である私から、院内の恋愛事情や結婚後の生活についてご紹介します。 -
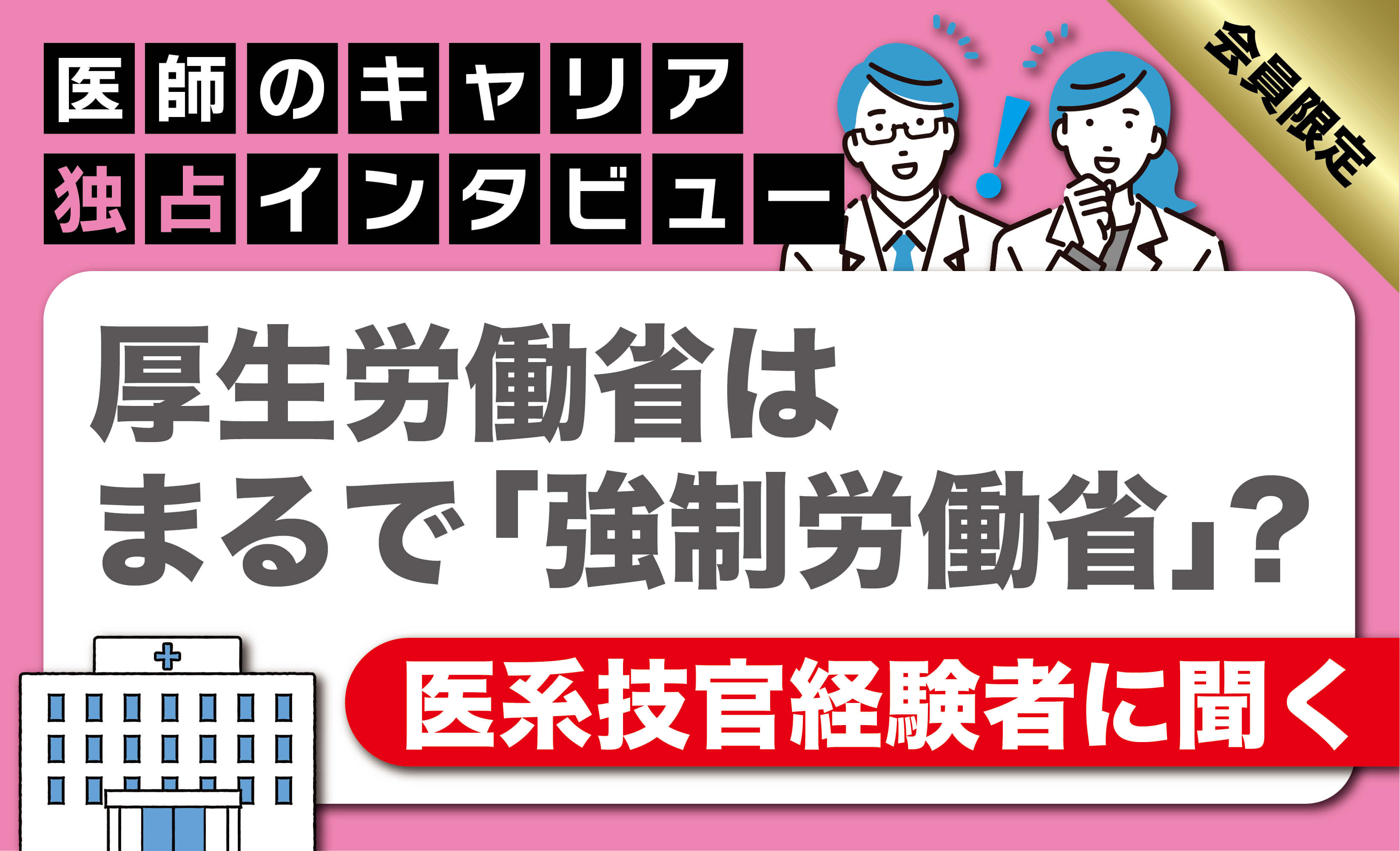
厚生労働省はまるで「強制労働省」? 医系技官経験者に聞く
厚生労働省には「医系技官」と呼ばれる医師免許を必要とするポジションが存在します。採用試験は年2回、6月と11月に実施されますが、卒後年数や年齢の制限はなく、医師免許を保有していれば誰にでもチャンスのある仕事です。とはいえ、その実態はあまり知られていないのも事実。
今回は、過去に医系技官として勤務経験のある先生にお話を伺いました。ご協力いただいたのは、大学病院に10年間勤務したのち、厚生労働省医系技官として1年間従事し、その後フリーランスを経て現在はクリニックを開業されている渡邊譲先生です。 -
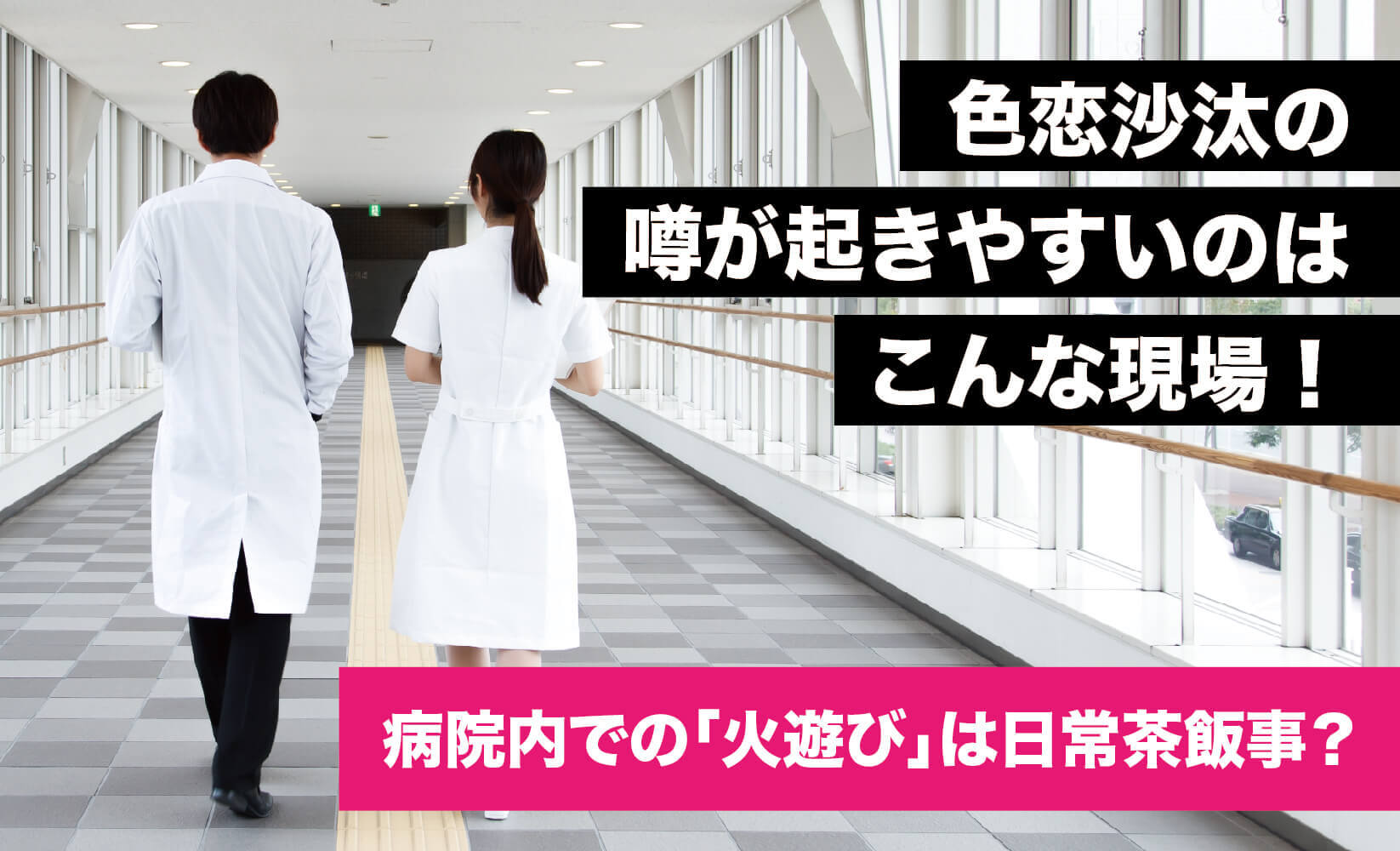
病院内での「火遊び」は日常茶飯事? 色恋沙汰の噂が起きやすいのはこんな現場!
病院内での色恋のドラマは、医師や看護師の間ではよく聞く話です。24時間体制で稼働し、人とのコミュニケーションが多い現場では、自然と恋愛感情が芽生えやすいのかもしれません。院内結婚はよく耳にする話ですが、そこまでシリアスではない「火遊び」も同時に起こりやすいようです。今回は、現役医師のマック先生に職場の恋愛沙汰にまつわる「あるあるパターン」を聞いてみました。
-
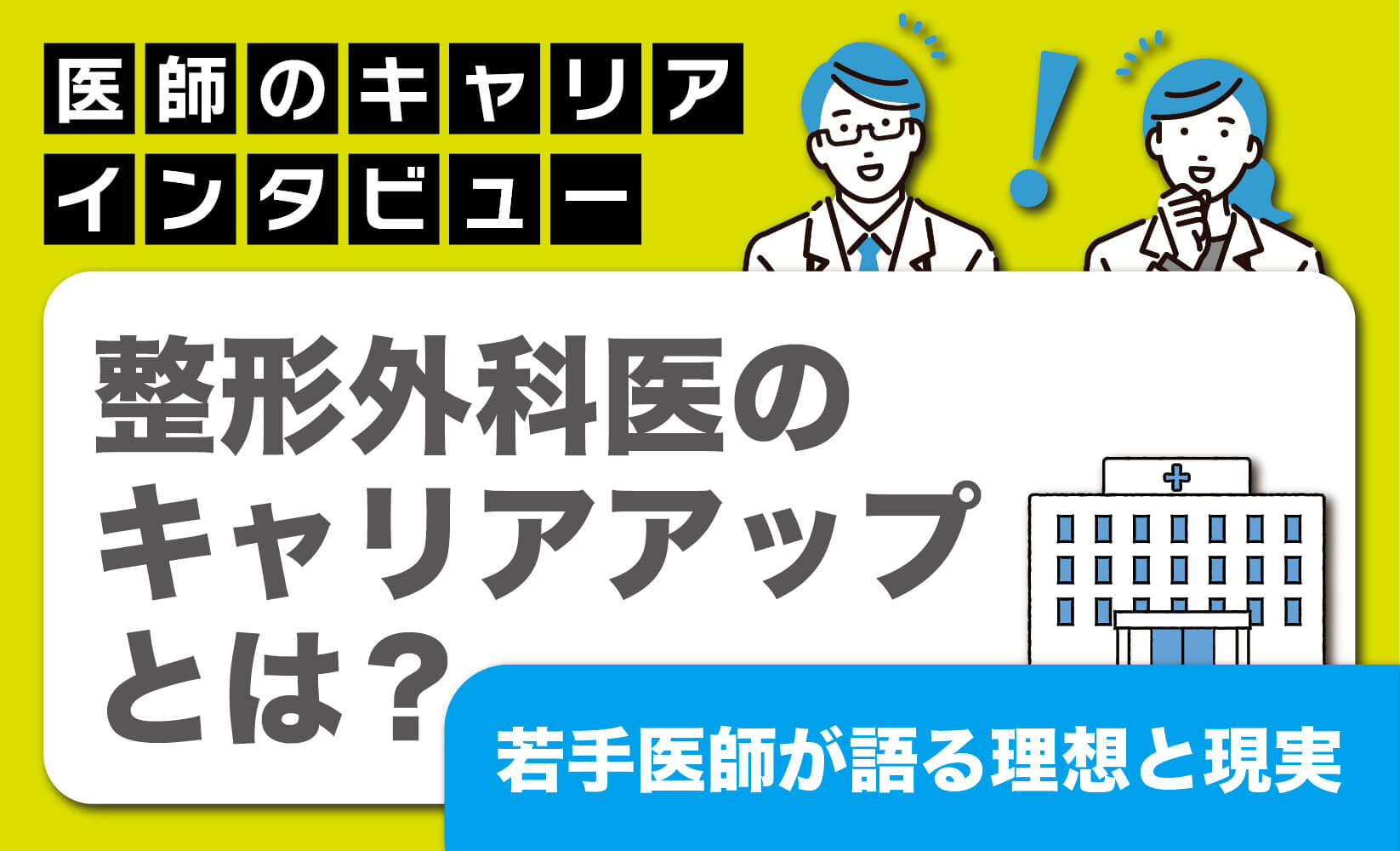
【キャリアインタビュー】若手医師が語る理想と現実・整形外科医のキャリアアップとは?
関東の大学病院で整形外科医として勤務するスカイ先生。これまで歩んできた道筋と、医師として6年目の今、あらためて考える将来のキャリアプランなどについて、お話を伺いました。
-
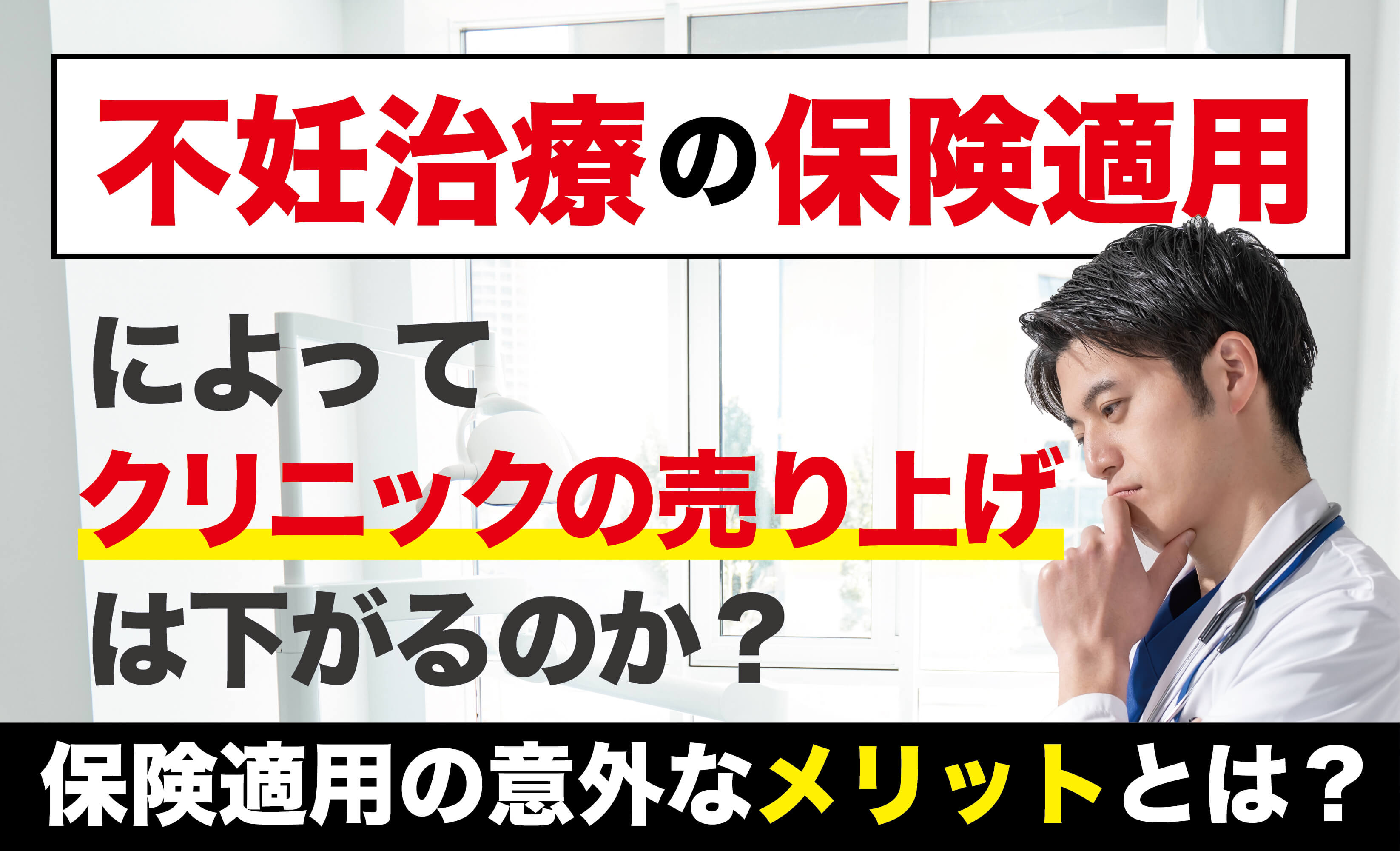
不妊治療の保険適用によってクリニックの売り上げが下がるのか? 保険適用の意外なメリットとは
不妊治療の一部が保険適用になったことは、これまで不妊治療に踏み出せなかった人々にとって嬉しいニュースかと思います。一方で、クリニックにどのような影響を与えるのでしょうか。今回は不妊治療の保険適用がクリニックに与えるメリット・デメリットを紹介します。
-
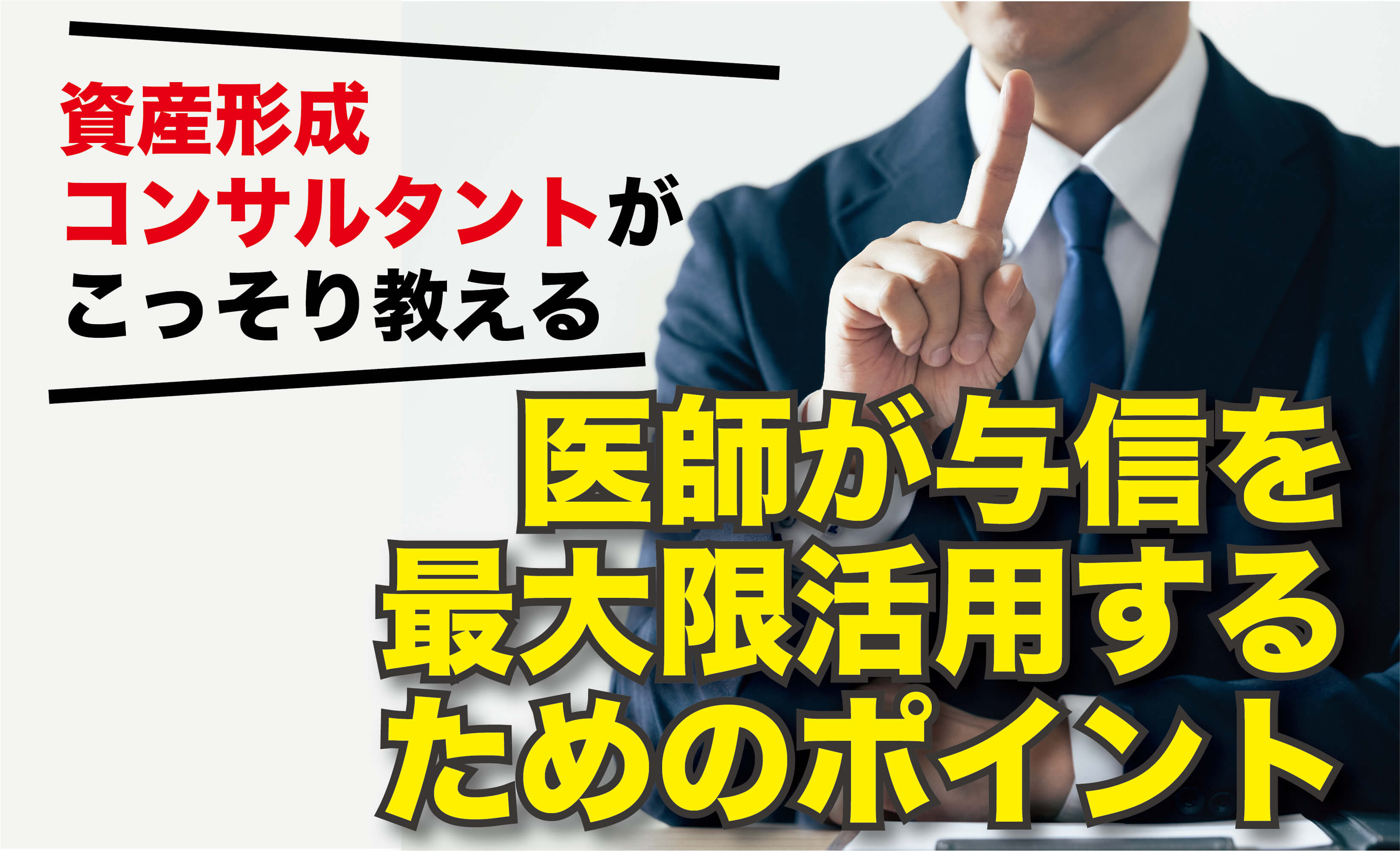
【元銀行員が教える】医師が与信を最大限活用するためのポイント
医師は社会的にも信用のある仕事で、かつ高収入が望める職業です。住宅ローンや開業の際の融資がおりやすいと考えている方も多いかもしれません。しかし実際のところ、「医師だから融資がおりやすい」と一概には言い切れません。今回は医師免許のもつ与信力を最大限に活用し、融資がおりやすくなるためのポイントについて解説します。
-
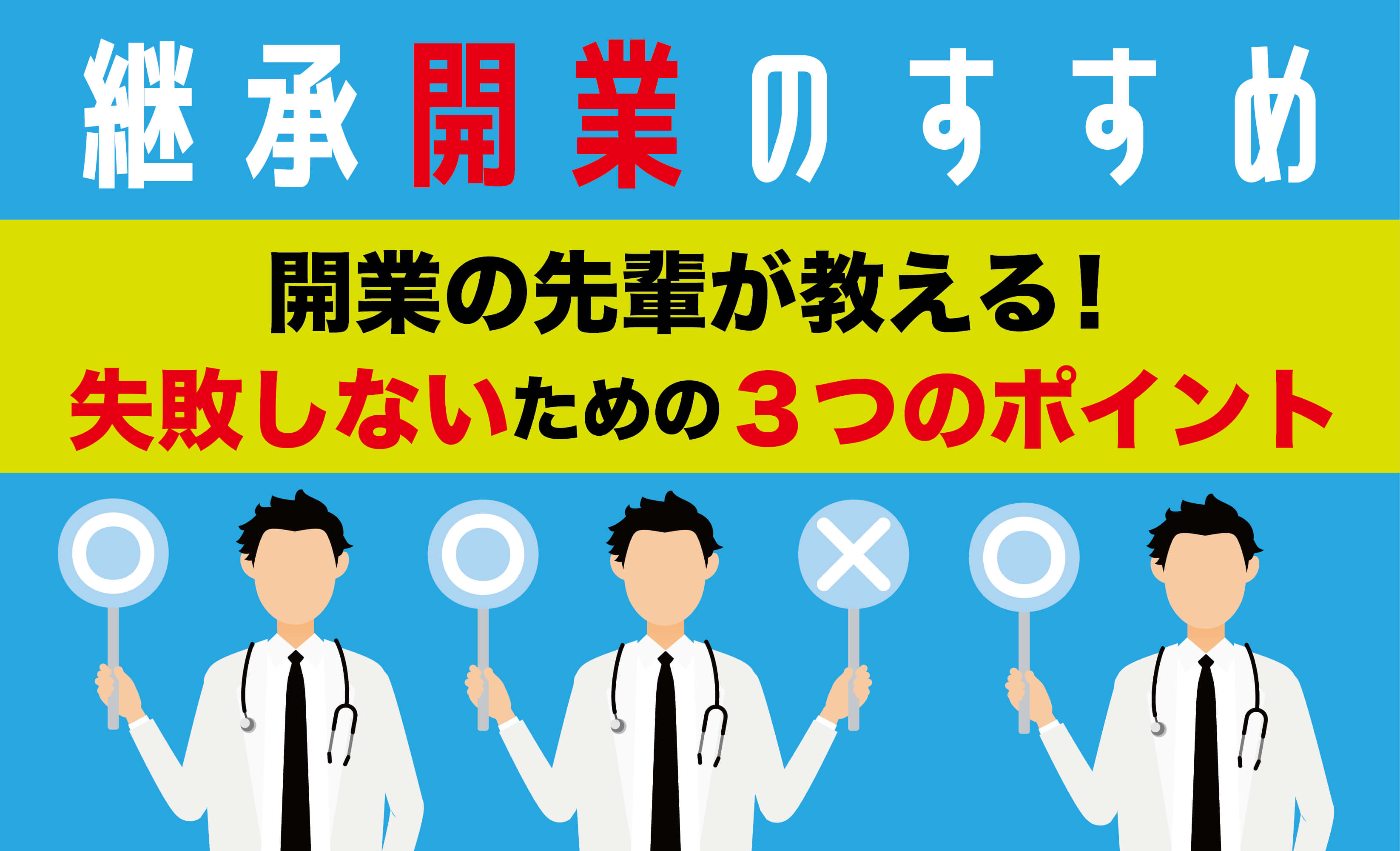
【継承開業のすすめ】開業の先輩が教える、失敗しないための3つのポイント
いつかは開業したいと考えている医師の方は多いと思います。しかし開業にあたっては資金面でのハードル、そして患者さんをゼロから開拓しなければならないなど様々な難しさがあることも事実です。そこで今回は「事業継承での開業」という方法をご紹介します。新規開業よりも多くのメリットがある「事業承継での開業」について、実際に経験し今も順調に経営を続けている立場から、失敗しないためにおさえておきたい3つのポイントを解説します。
-
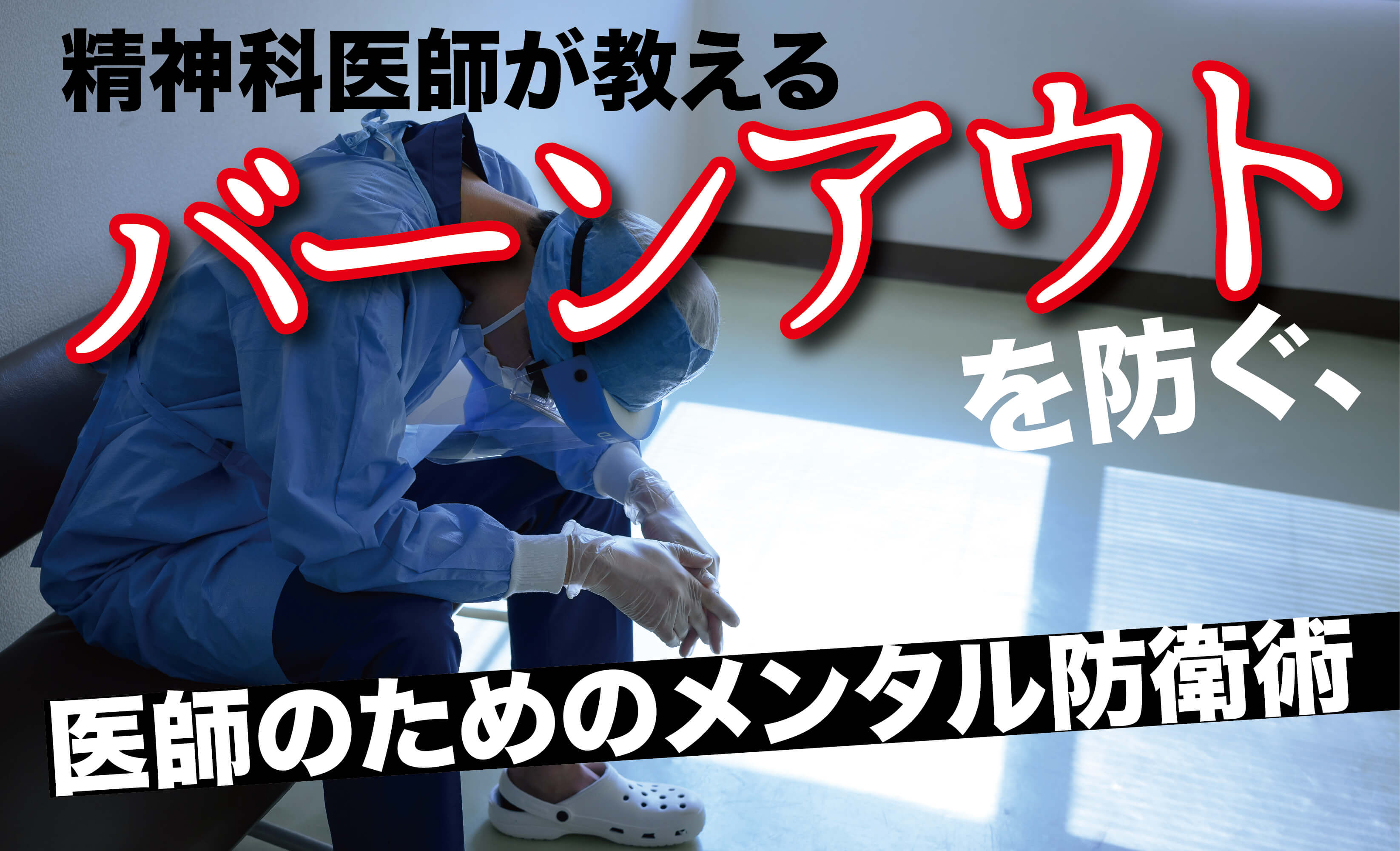
【精神科医師が教える】バーンアウトを防ぐ、医師のためのメンタル防衛術
職務を果たすことが社会貢献に直結する医師は、精神的・体力的にもタフな方も多く、ワーカホリックになりがちな職種でもあります。近年では医師の働き方改革も進みつつありますが、忙しさやストレスからメンタルをやられてしまう方も少なくありません。そこで今回は精神科医の筆者が自分でも実践している「メンタルの保ち方」をご紹介します。
-
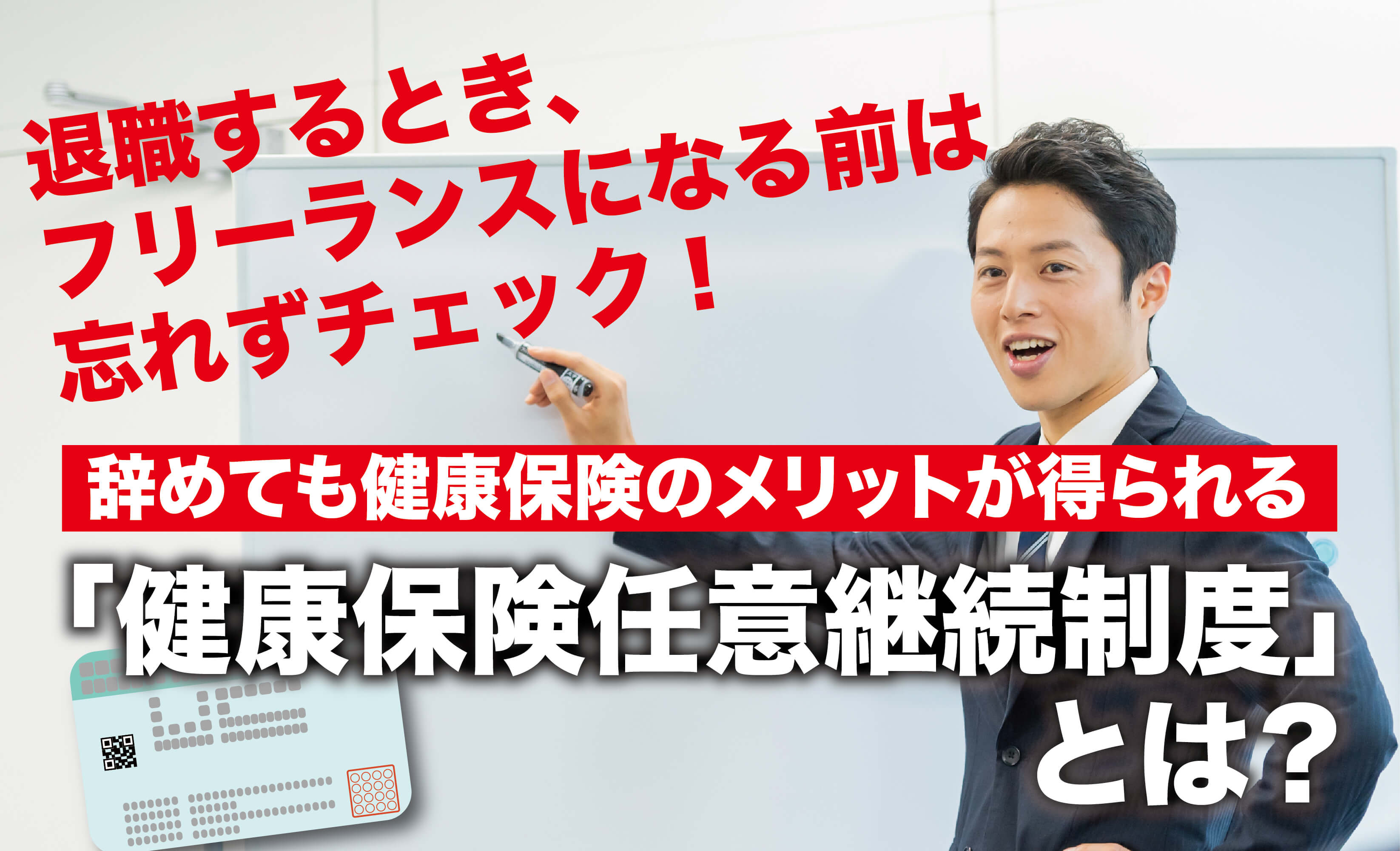
退職するとき、フリーランスになる前は忘れずチェック!辞めても健康保険のメリットが得られる「健康保険任意継続制度」とは?
フリーランス医師にとって、健康保険をどうするか? の問題は避けて通れません。高所得といわれている医師ですが、会社や病院を辞めるとこれまで勤務先が半額負担してくれていた社会保険料が全額負担になるため、しっかり考える必要があります。実は、健康保険には退職後も加入し続けられる「任意継続」という制度があることをご存知でしょうか?
今回は、勤務医を辞めてフリーランス医師になることを考えている方に向けて、健康保険任意継続制度の具体的な内容や、メリット、注意点などを解説します。 -
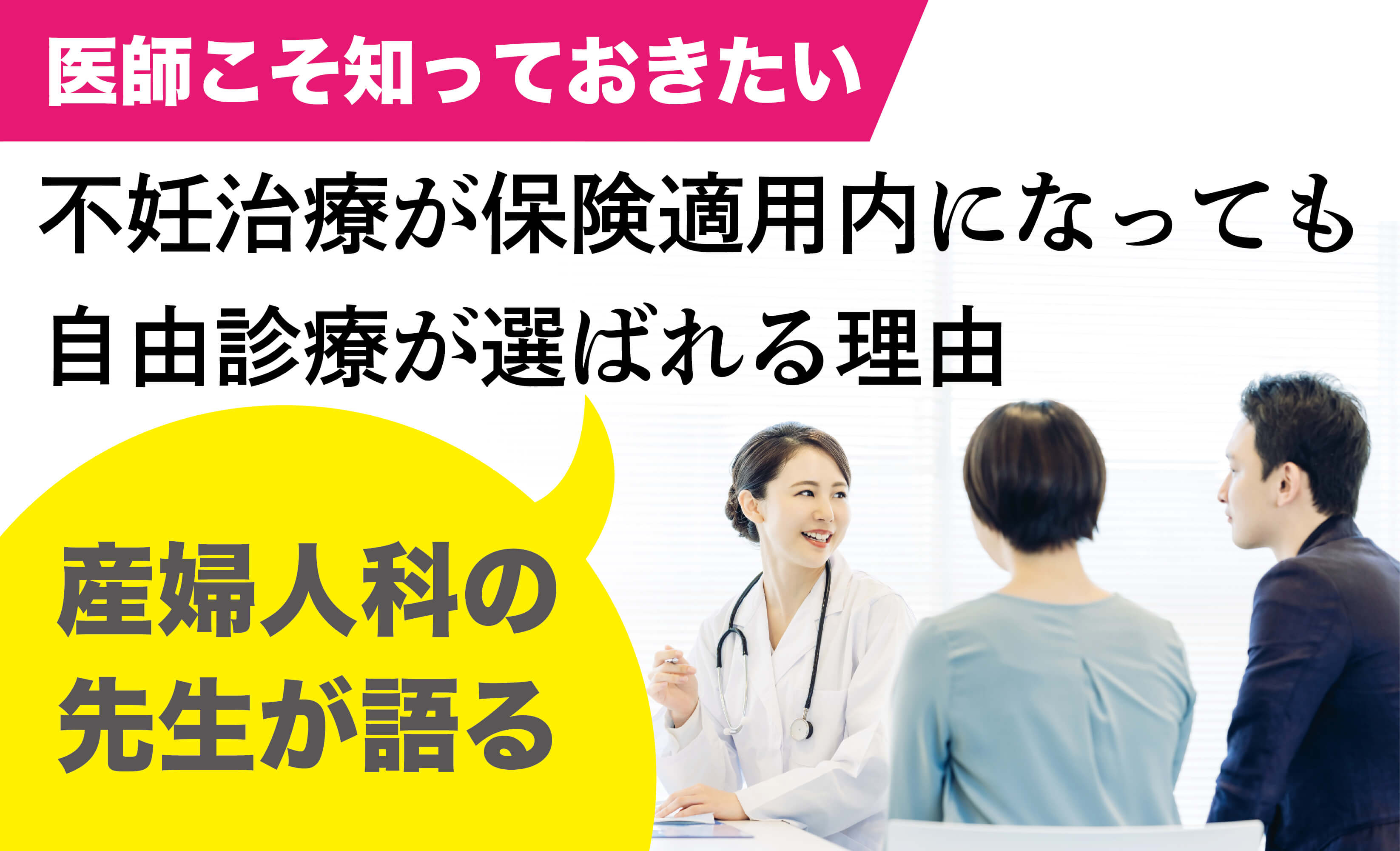
医師こそ知っておきたい。 産婦人科の先生が語る、不妊治療が保険適用内になっても自由診療が選ばれる理由
2022年4月から、基本的な不妊治療が保険適用となりました。これまで子どもが欲しくても高額な治療費のために諦めなければならなかった方も、治療を受けられるようになりました。とはいえ、保険診療を望む患者に対し、一律に保険適用内の治療を提供していると、“こんなはずじゃなかった……”と後悔が残る結果となってしまう可能性があります。
今回は、不妊治療にまつわる保険診療の落とし穴をお伝えします。不妊治療に直接関わりのない方でも、医師の皆さんにはぜひ知識として知っておいていただきたいと思います。 -
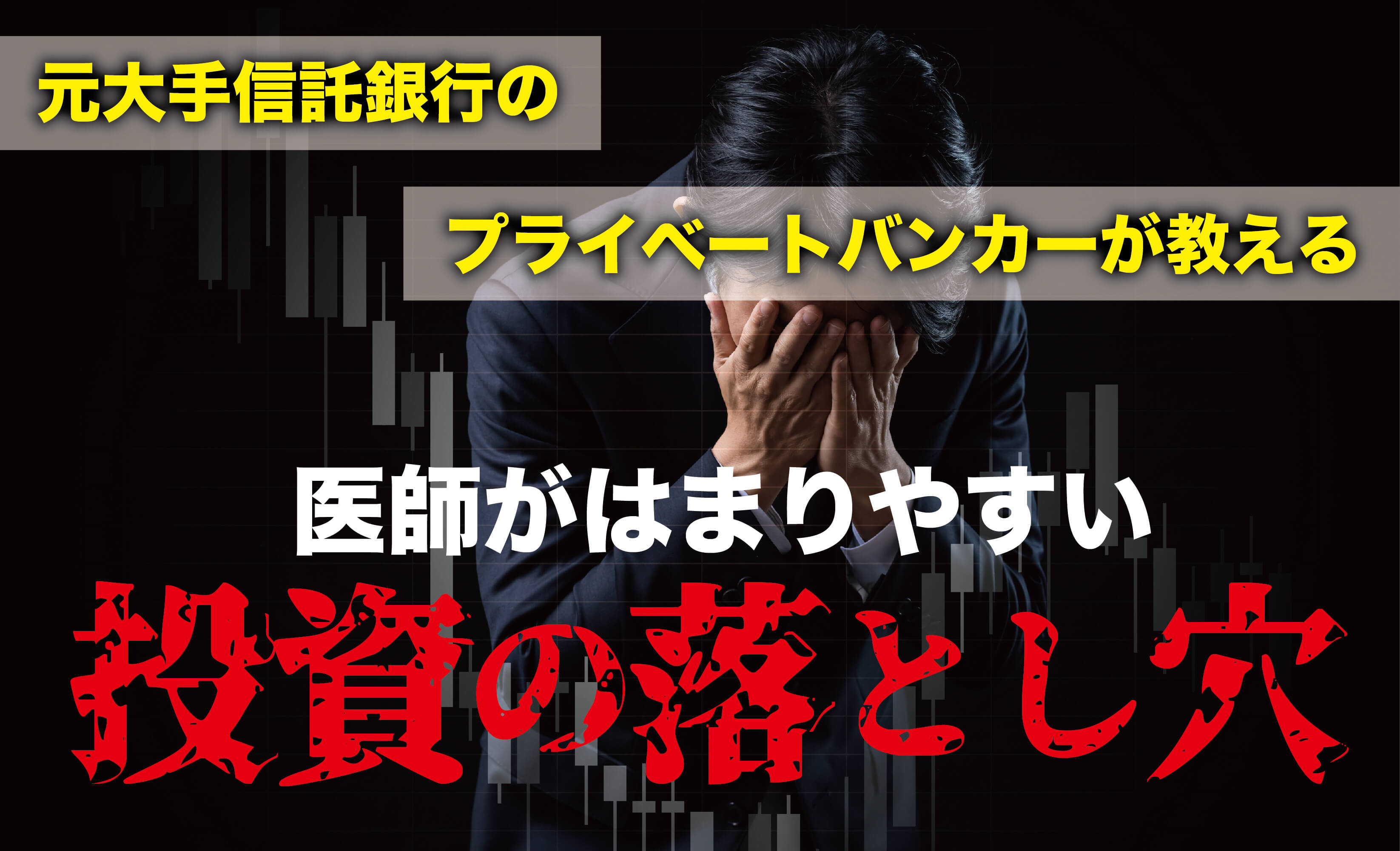
【元銀行員が教える】医師がはまりやすい「投資の落とし穴」
人生100年時代といわれる今、すでに資産形成を行っている方や資産形成を考えている方は多いと思います。資産形成といえば「投資」が最初に頭に浮かぶと思いますが、投資や金融商品についての専門的な知識をもっていない方のほうが多数派でしょう。そのため、元銀行員の資産形成アドバイザーである筆者のもとにも、「怪しい投資話に騙されて大金を失ってしまった…」という相談がたくさん寄せられてきます。
今回は、特に医師がはまりやすい「投資の落とし穴」について、気を付けていただきたいポイントをお伝えします。 -
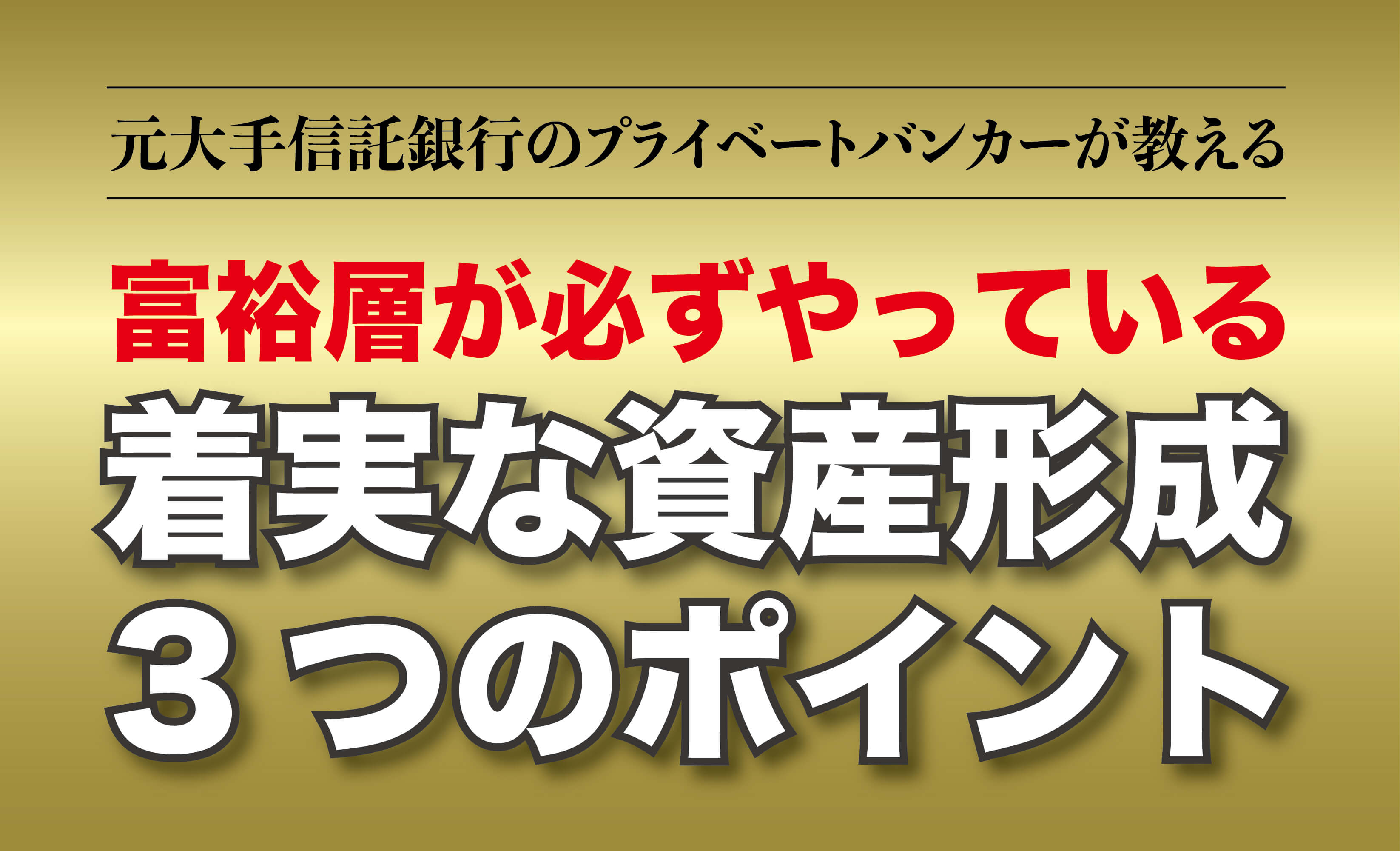
【元銀行員が教える】富裕層が必ずやってる「着実な資産形成3つのポイント」
人生100年時代といわれる今、すでに資産形成を行っている方や資産形成を考えている方は多いと思います。資産形成といえば「投資」が最初に頭に浮かぶと思いますが、実は投資のような「プラスの運用」だけではなく、「マイナス運用」と呼ばれる節税なども非常に重要です。今回は資産形成コンサルタントの筆者が、医師の皆様に知っていただきたい資産形成のポイントを解説します。
-
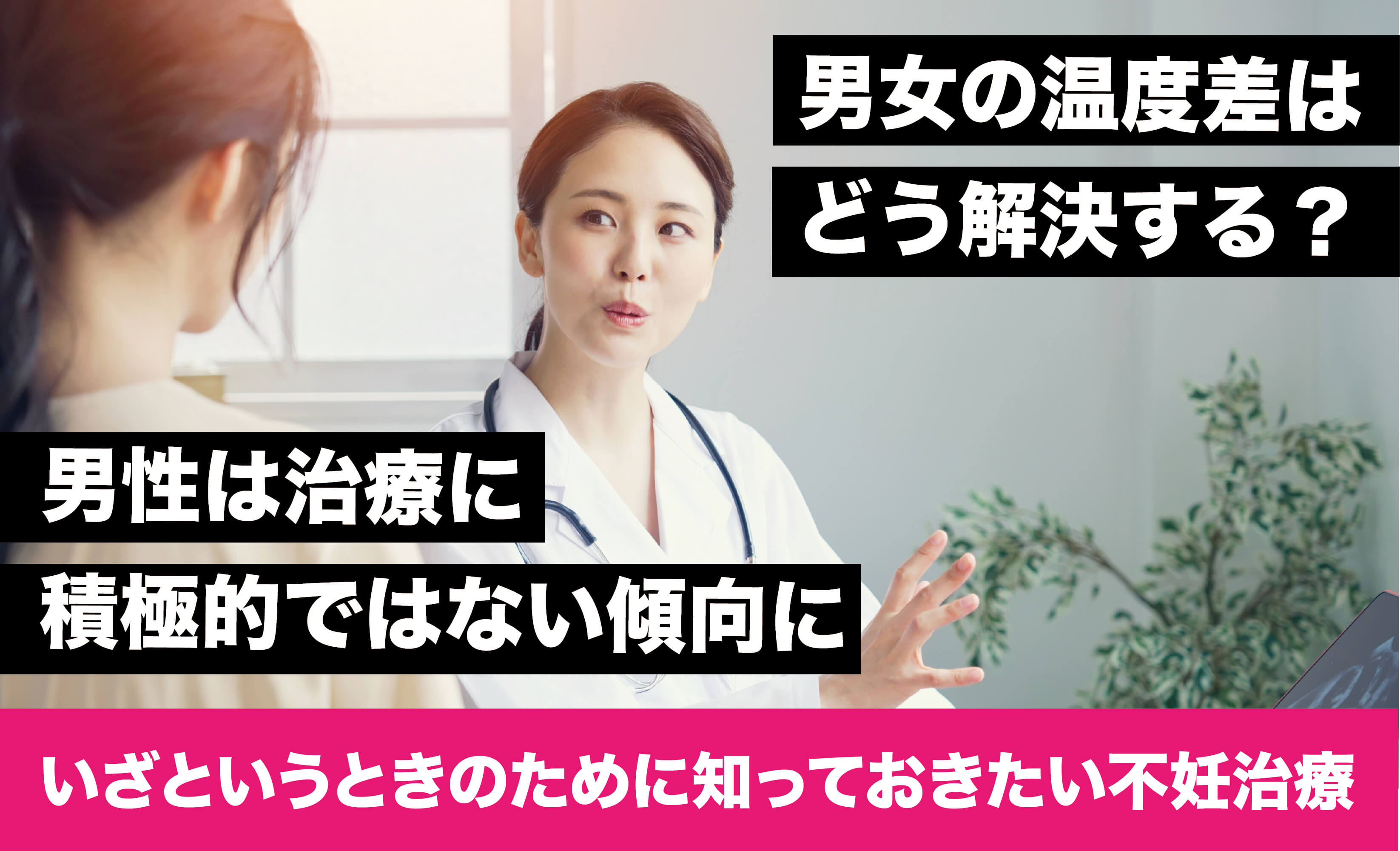
いざというときのために知っておきたい不妊治療〜男性は治療に積極的ではない傾向に 男女の温度差はどう解決する?〜
不妊治療や検査を受けたことのあるカップルは夫婦全体の約4.4組に1組といわれており、今も増え続けています。最近では男性不妊も女性の不妊と同程度であることが明らかになってきましたが、不妊治療では特に女性の体に大きな負担がかかります。なかなか妊娠しないことに対する不安や経済的負担、治療に合わせて仕事を調整せざるを得ないこと、そしてパートナーの男性が協力的でないという理由で、肉体的にも精神的にも負担を強いられることは珍しくありません。
今回は、不妊治療を専門とする産婦人科医である私が、今の不妊治療のリアルをお伝えします。不妊治療に取り組む女性の悩みや、不妊治療で起こる男女の温度差をどう解決すればいいのか、私の実体験もあわせてお伝えしていきたいと思います。
※生殖補助医療による出生児数:公益社団法人日本産科婦人科学会「ARTデータブック(2020年)」 -
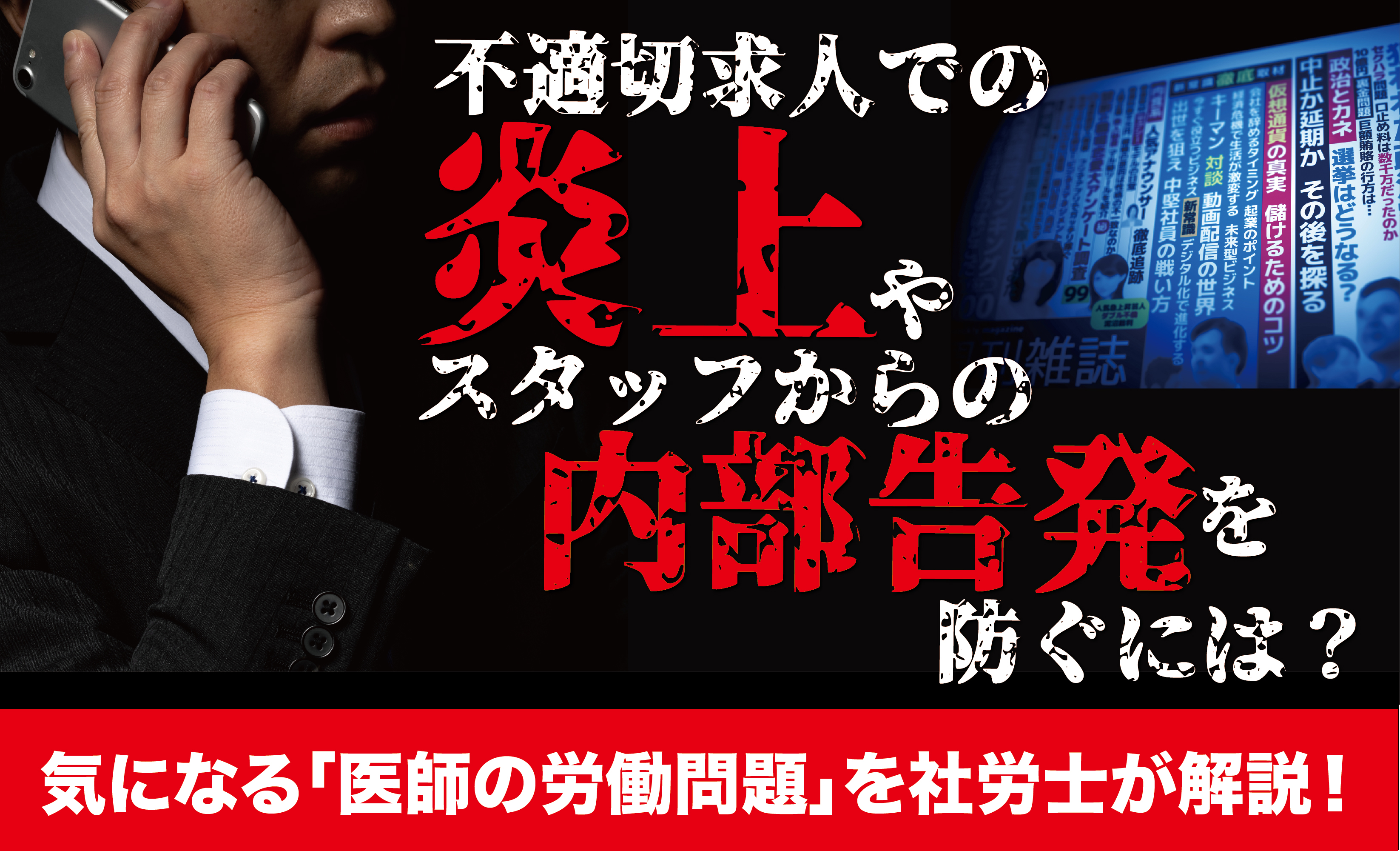
気になる「医師の労働問題」を社労士が解説! 不適切求人での炎上やスタッフからの内部告発を防ぐには?
近年、働き方改革にともなう残業時間や働き方の見直しにより、勤務医の労働問題や悩みが浮き彫りになっています。本記事では社労士目線で勤務医が気をつけるべき労働問題や、多くの医師が感じると思われる疑問点について紹介します。
※個人情報保護のため、事例は趣旨を曲げない範囲での脚色・改変を加えています。 -
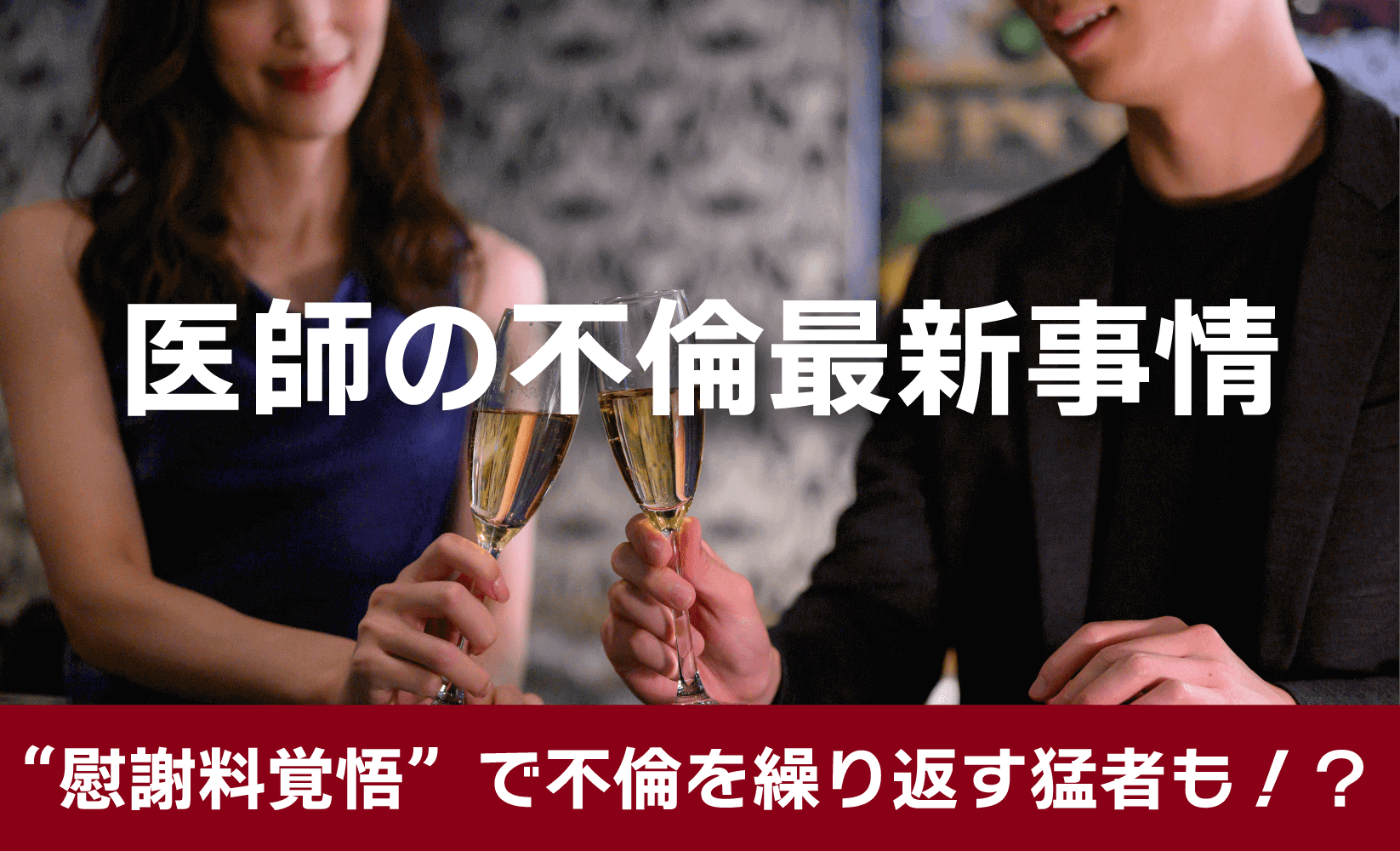
“慰謝料覚悟”で不倫を繰り返す猛者も!? 医師の不倫、最新事情
女優の広末涼子さんとミシュラン一つ星レストラン「sio」のオーナーシェフ・鳥羽周作氏とのW不倫が世間を騒がせていますが、男女問題はどこにでも発生するものです。「ジャパン・セックスサーベイ2020」※(協力:日本家族計画協会=20歳から69歳の男女5029人対象)の調査によると、浮気・不倫経験があると答えた男性は67.9%、女性は46.3%でした。特に若い世代に多く、20~40代の男女のおよそ3人に1人は現在進行形で特定の1人と浮気しているという結果が出ています。2017年の前回調査では男性が37.0%、女性が24.4%だったため、男女ともに大きく増加しており、不倫・浮気へのハードルが下がっていることが分かりました。
意外と身近にある不倫――。医師の場合は、どこで、どんな相手と関係が始まるのでしょうか。今回は、不倫の最新事情を紹介します。 -
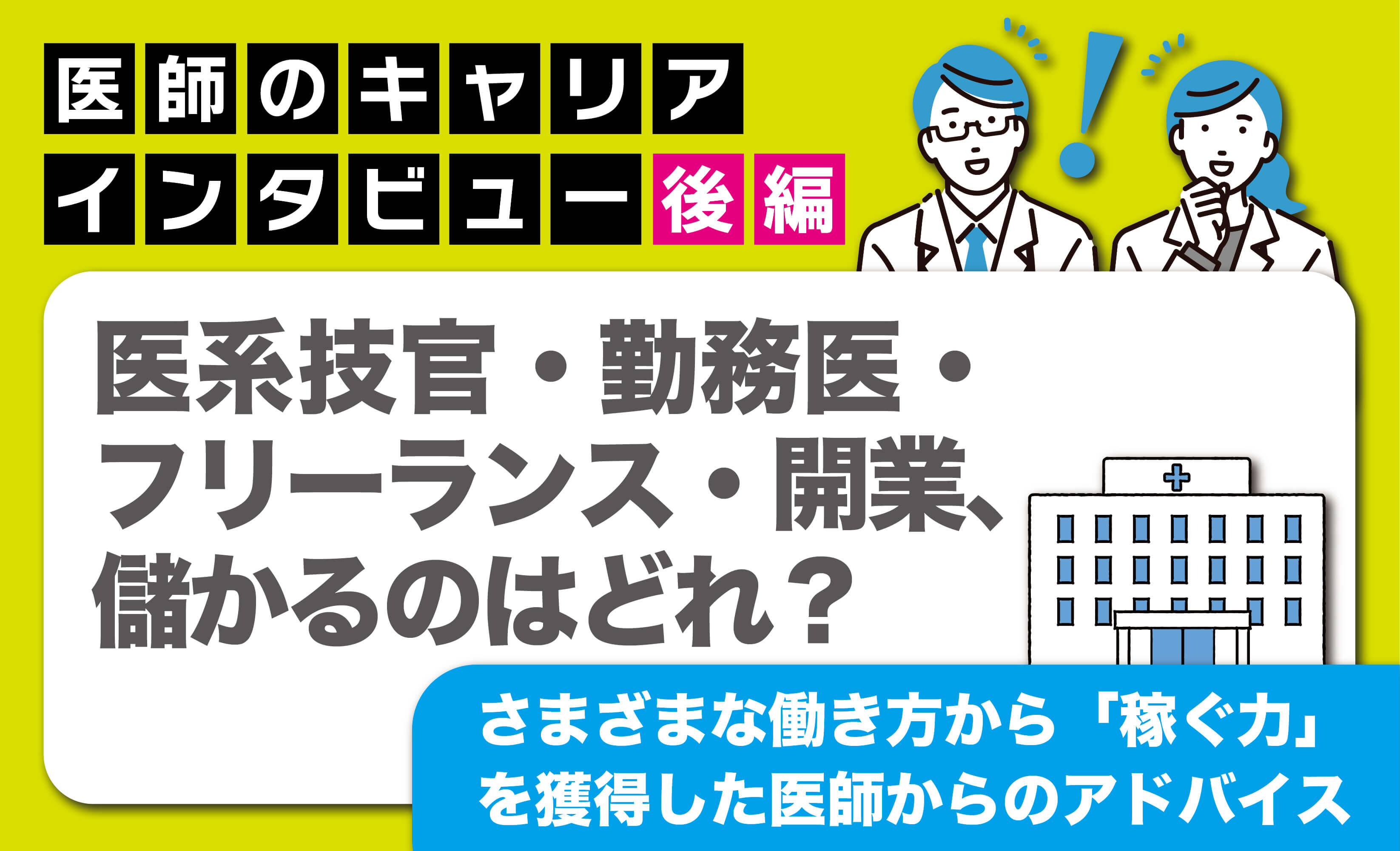
【キャリアインタビュー後編】医系技官・勤務医・フリーランス・開業、儲かるのはどれ? さまざまな働き方から「稼ぐ力」を獲得した医師からのアドバイス
多彩なキャリアでの経験をお持ちの渡邊譲先生にお話を伺いました。大学病院に10年間勤務したのち、厚生労働省医系技官として1年間従事し、その後フリーランスを経て現在は開業しクリニック経営に携わられている渡邊先生。後編である今回は、多彩なキャリアを経験するなかで培われた「お金」と「働き方」のバランスを取るコツについて、お話しいただきます。
-
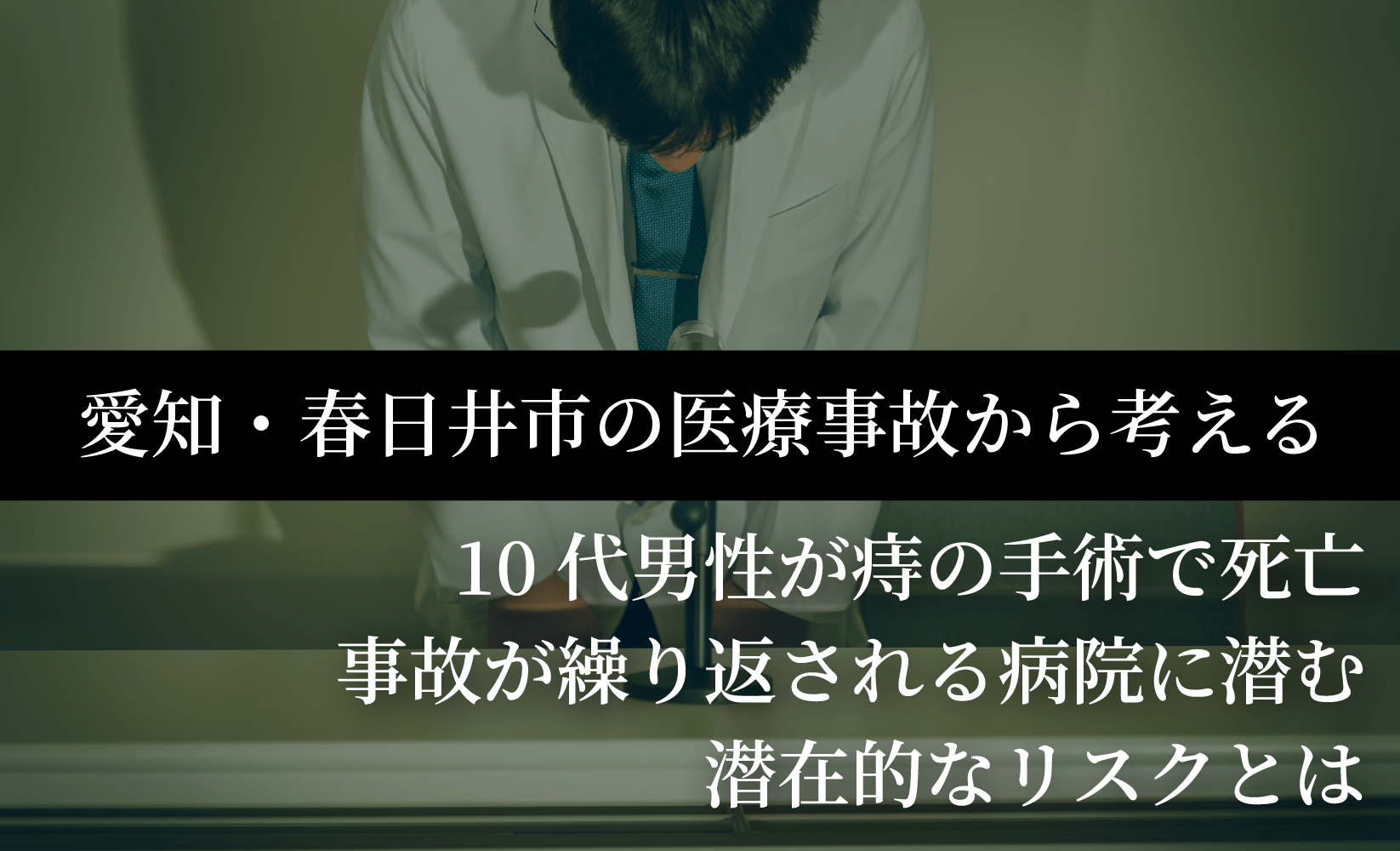
【愛知・春日井市の医療事故から考える】10代男性が痔の手術で死亡、事故が繰り返される病院に潜む潜在的なリスクとは
2023年6月、愛知県立医療育総合センター中央病院(同県春日市)は、21年5月に重度の脳性麻痺で通院していた当時10代男性が、痔の手術後に出血性ショックで死亡する医療事故があったことを発表しました。同病院では2021年5月に別の男性患者(当時36)に、基準値の約15倍の下剤を処方し死亡する医療事故を起こしています。なぜ短期間に医療事故が繰り返されてしまったのでしょうか? 対策をしてもそれを妨げる、変え難い構造的な問題があったのでしょうか? 今回の事例をもとに、医療事故対策について考えていきます。
-
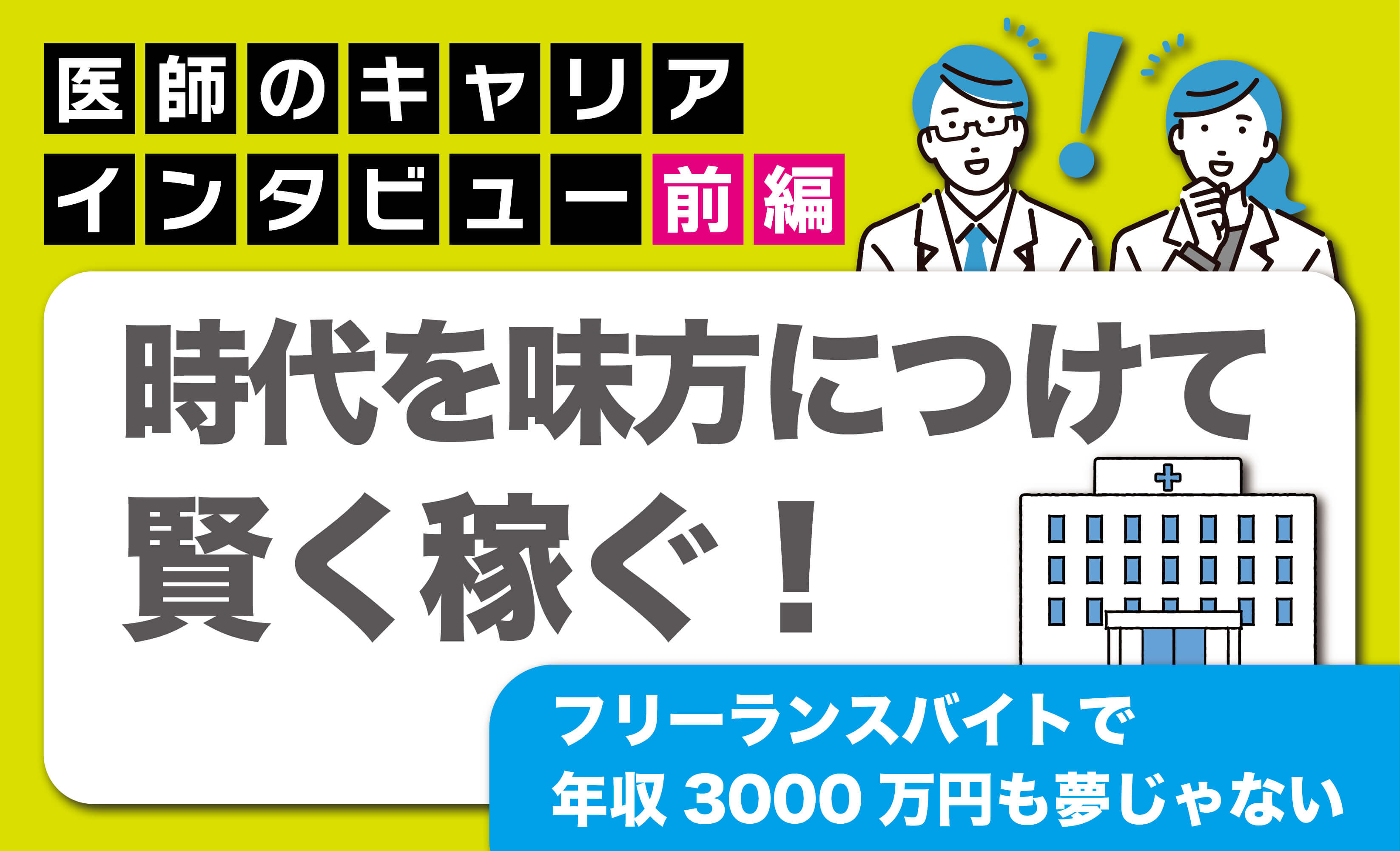
【キャリアインタビュー前編】時代を味方につけて賢く稼ぐ! フリーランスバイトで年収3000万円も夢じゃない
今回は、多彩なキャリアでの経験をお持ちの渡邊譲先生にお話を伺いました。大学病院に10年間勤務したのち、厚生労働省医系技官として1年間従事し、その後フリーランスを経て現在は開業しクリニック経営に携わられている渡邊先生。前編である今回は、医師免許を活かしてフリーランスとして効率よく稼ぐヒントについて、お話しいただきます。
-
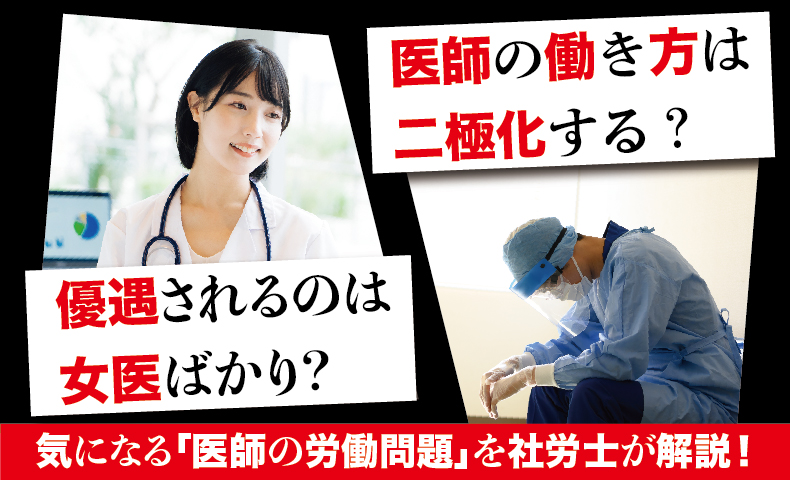
気になる「医師の労働問題」を社労士が解説! 医師の働き方は二極化する? 優遇されるのは女医ばかり?
近年、働き方改革にともなう残業時間や働き方の見直しにより、勤務医の労務問題や悩みが浮き彫りになっています。これまでも時間外労働が年間960時間を超えている医師は、時短に取り組む努力を求められていましたが、医師の中でも体力を活かして存分に勤務時間やオペ回数を増やしてキャリアや経験を積み上げながら働きたい方と、ワークライフバランスを重視して働きたい方がいるでしょう。
また、勤務先の残業時間の上限変化がある場合や、小規模で人手不足に悩むクリニックなどは、どのような点に気をつけて働けば良いのか、悩みは尽きないことと思います。
本記事では、社会保険労務士目線で勤務医が気をつけるべき労働問題や、働き方に関する問題、多くの人が抱える疑問点について紹介します。
※個人情報保護のため、事例は趣旨を曲げない範囲での脚色・改変を加えています。 -
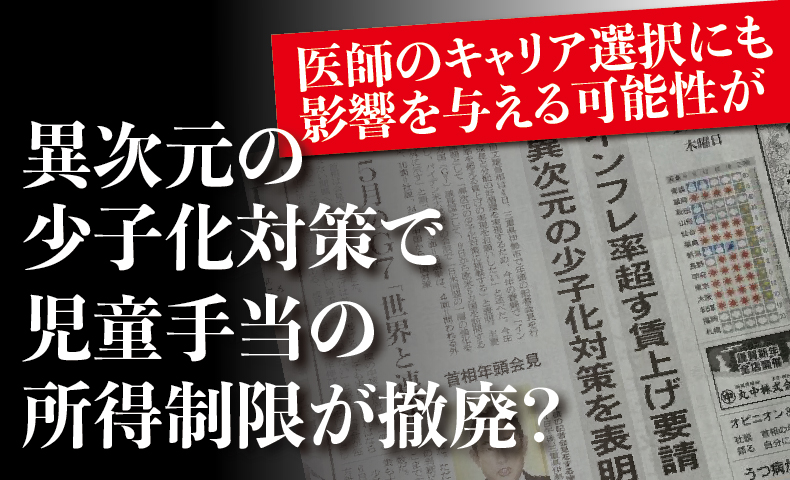
異次元の少子化対策で児童手当の所得制限が撤廃? 医師のキャリア選択にも影響を与える可能性が
2023年6月13日、政府は少子化対策として「こども未来戦略方針」の内容を正式に発表しました。これは児童手当の拡充のほかにも、子育て世代への支援強化や給付の増加など、さまざまな取り組みを含んでいます。これは医師の方にとってはどう影響してくるのでしょうか?現在発表されている素案をもとに、実施された場合に医師に与える影響をまとめました。
-
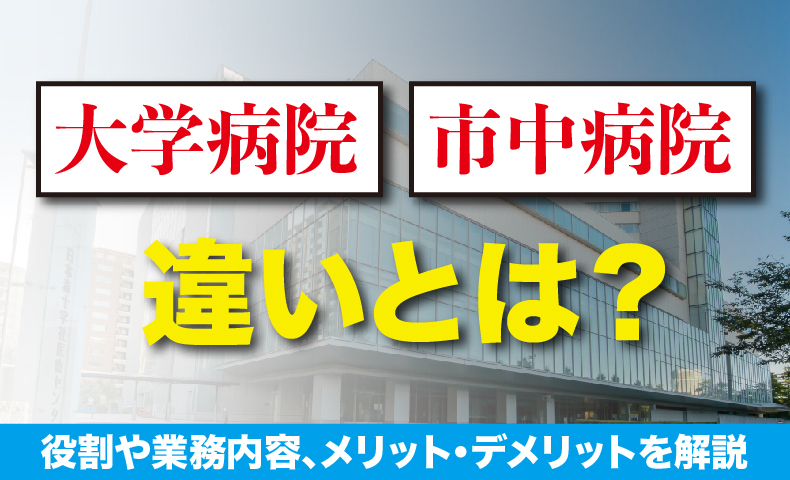
大学病院と市中病院の違いとは? 役割や業務内容、メリット・デメリットを解説
医学部を卒業した後は、ほとんどの方が研修医として大学病院や市中病院で医師として診療にあたります。同じ医師として働くとしても、大学病院と市中病院ではそれぞれ異なる役割や特徴があることをご存じでしょうか?他にも診療内容の充実度や専門性、設備の面でもさまざまな違いがあり、どちらもその地域において重要な役割を果たしていることは間違いありません。
そこで今回は、大学病院と市中病院の役割や業務内容の違いや、それぞれの病院で働くメリット・デメリットを解説します。 -
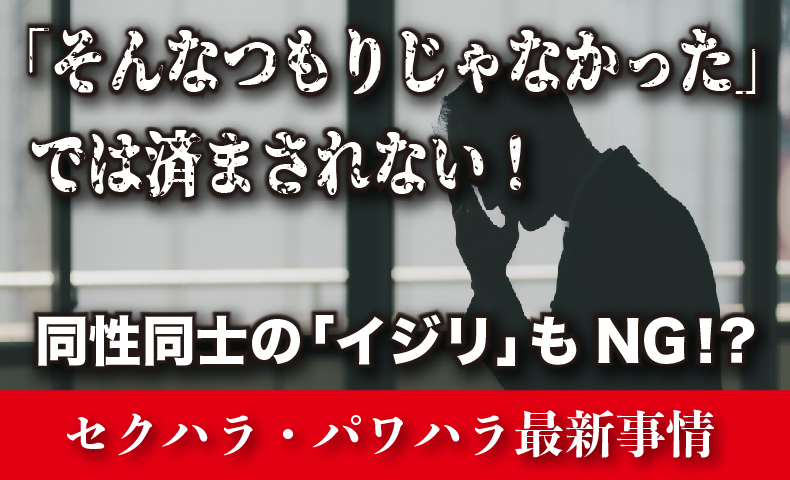
「そんなつもりじゃなかった」では済まされない!同性同士の「イジリ」もNG!?セクハラ・パワハラ最新事情
22年4月1日から中小企業に対する「労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」(大企業は20年6月から)が施行されて、セクハラやパワハラを含むハラスメント防止措置は事業者の義務になりました。職場でのセクハラやパワハラの被害に遭った場合、以前より訴えやすい環境が整ってきたといえるでしょう。
しかし一方で、「コミュニケーションのつもりだったのに、部下や取引先からハラスメントとして訴えられてしまった…」といったリスクが高まったともいえるかもしれません。そこで今回は、病院や職場で発生したハラスメントの事例をご紹介します。 -

医師のお忍びデートや会食におすすめ! 都内の隠れ家寿司店5選
ハードワークが続くと、「ちょっと贅沢なディナーでも」という気分になりますね。そんな日には「やっぱり寿司だね!」という方も多いでしょう。マグロやサーモンなど赤身の魚にはDHAやEPA、ビタミンD・Bが、アジやサバなど青魚にはDHAやEPAのほか、カルシウムやタウリンが豊富です。つまり、ハードワークな医師の疲労回復にはうってつけというわけです。
今回は、旬の握りだけでなくおつまみや椀物、デザートまでがセットになった「おきまり」コースのある都内の隠れた名店をご紹介します。大切な人とのデートはもちろん、会食でのおもてなしにも覚えておくと便利ですよ。
※メニュー内容は日によって変更の場合があります。 -
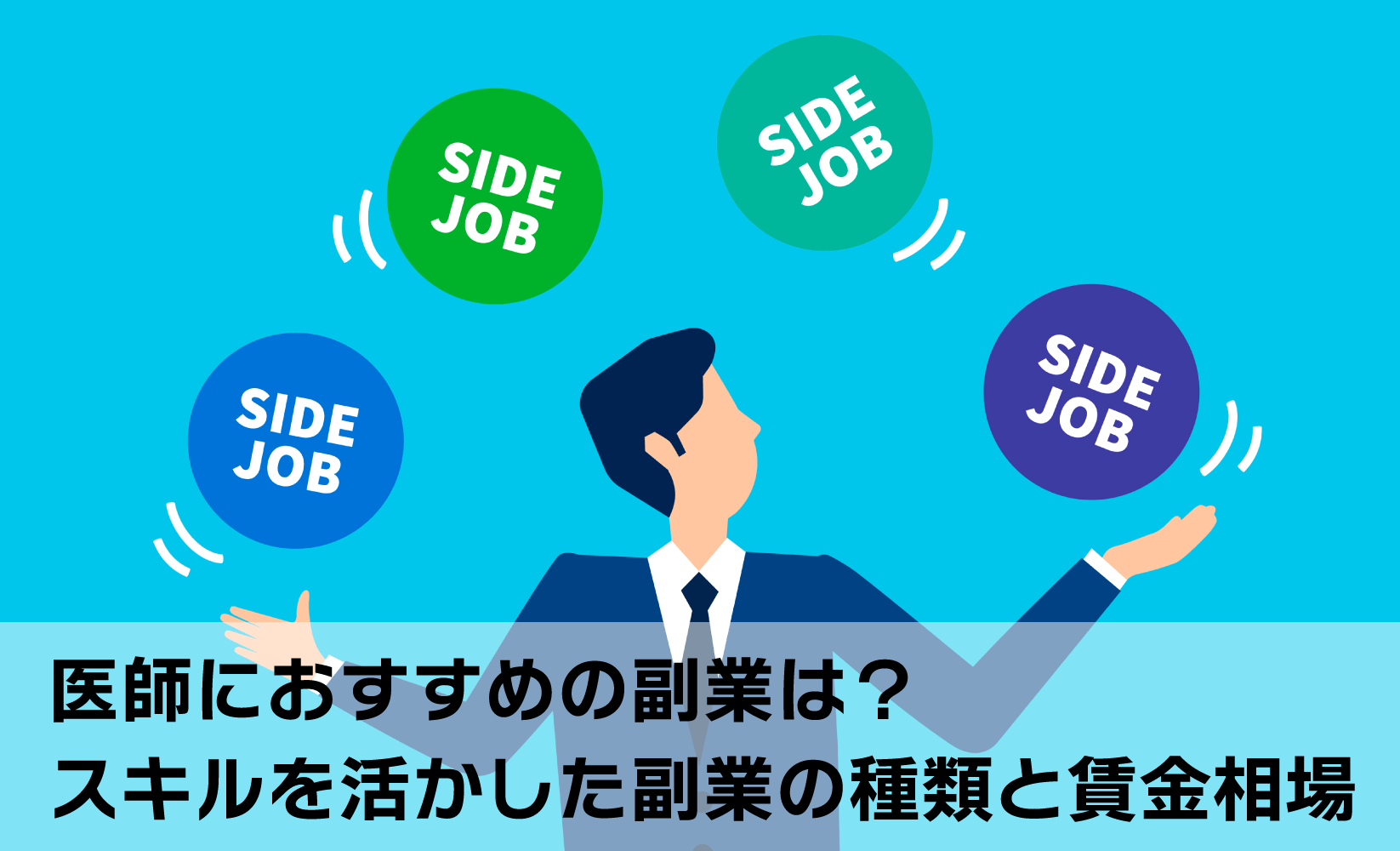
医師におすすめの副業は? スキルを活かした副業の種類と賃金相場を紹介
医師の方のなかには、本業は医師として働きながら、追加の収入や経験を得るために副業をされている方も多くいらっしゃいます。20~80代の男性医師・女性医師938人のうち、副業をしたことがある医師は半分以上というデータもあるほどです。
そこで今回は、医師におすすめの副業にはどのような種類があるのか、賃金相場はどの程度なのかを調査してみました。
※参考:株式会社医師のとも「副業に関するアンケート調査」 -

開業を検討している医師のための開業ローン事情
勤務医の方々の中には、近い将来、クリニックや診療所を開業したいと考えている人も多いのではないでしょうか。
そこで、いちばん気になる点といえば、開業資金をどのようにして調達するかです。自分の預貯金、親族からの借入等、さまざまな調達方法の中にはローンの利用という方法もあります。
今回は医師のための開業ローンについて詳しくご紹介します。 -

医者のモテ期はいつ? 1年目と10年目にモテ率が高まるワケ
「医者はモテる」というイメージをお持ちの方は多いと思います。医師は経済面で安定しており、また社会的地位も高いため、男性医師の場合、多くの女性から言い寄られる機会も多くあるでしょう。しかし医師として経験も収入も十分とはいえない研修医1年目でも「モテ期だった!」と話す医師もいるようです。その理由は一体何なのかを探りました。
-
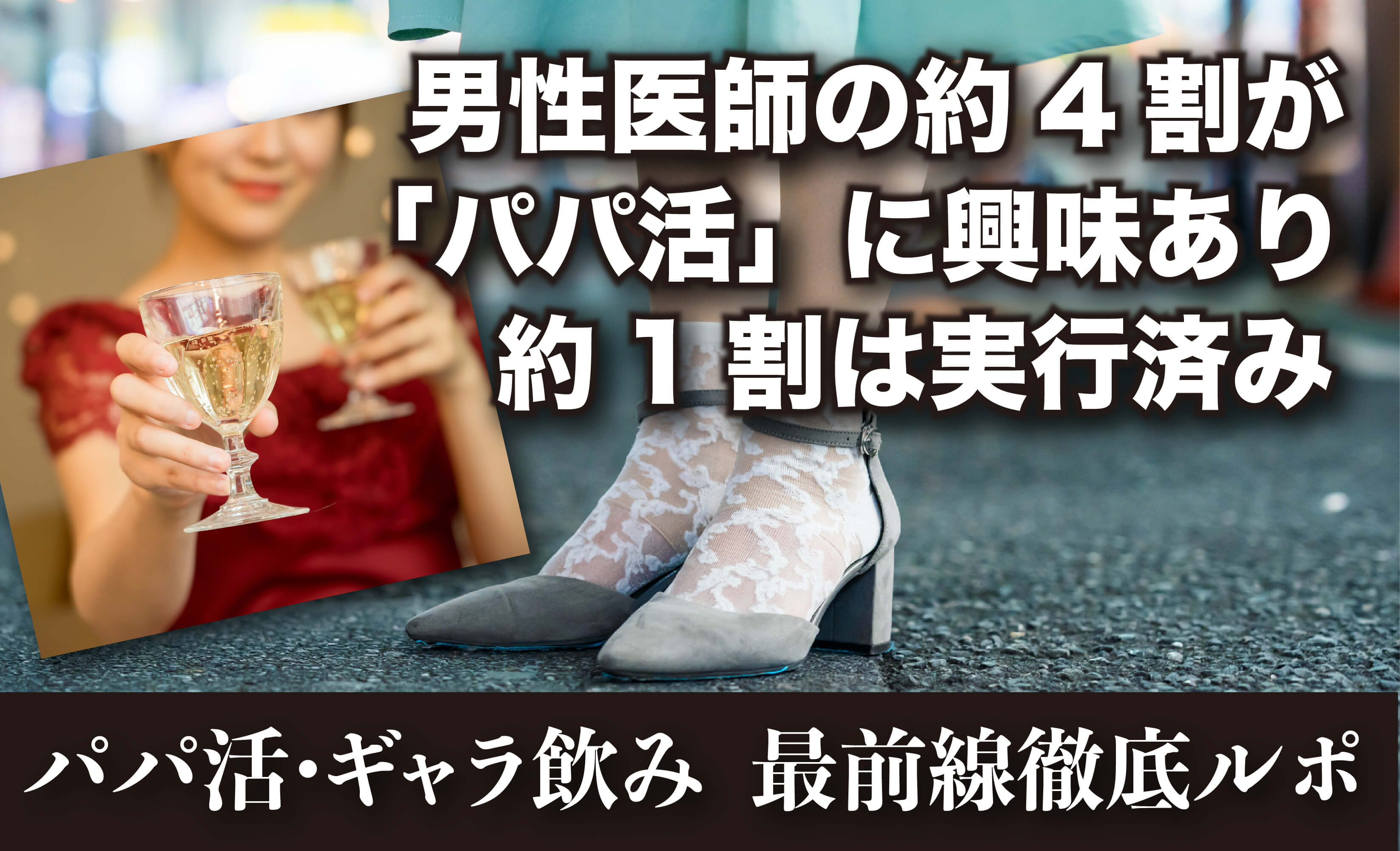
男性医師の約4割が「パパ活」に興味あり、約1割は実行済み 〜パパ活・ギャラ飲み最前線徹底ルポ〜
いま、パパ活市場が活況です。コロナ禍でキャバクラやラウンジなど「プロの女性」たちがお店の休業などで稼げなくなり、個人的なやりとりで完結するパパ活市場に大量に参入。その効率の良さから、コロナの感染者数が落ち着いてもお店に戻ることなく、パパ活を続ける女性が多いようです。なかには、年間5000万円以上稼ぐ“パパ活のカリスマ”や、グループLINEを駆使して数100人の女の子を管理するギャラ飲み仲介者も……。
夜の街を盛り上げるパパ活の最前線を紹介します。 -
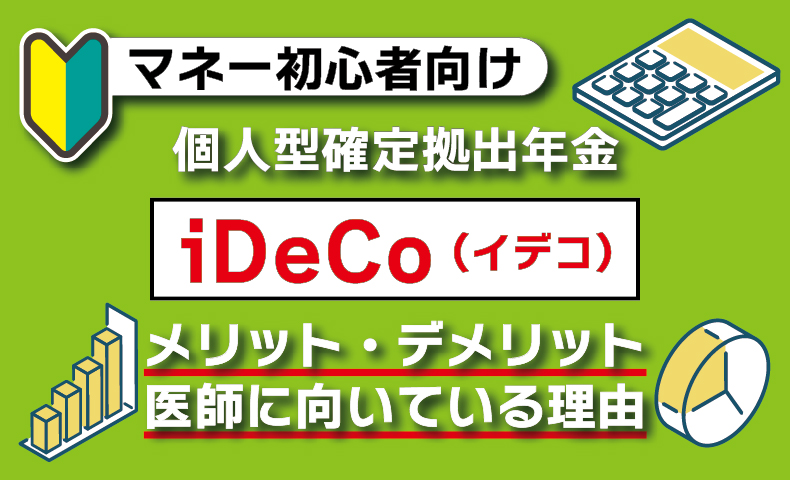
【マネー初心者向け】個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)とは? iDeCoが医師に向いている理由
所得の多い医師であっても、老後資金に不安を覚える方は多いのではないでしょうか。「老後2,000万円問題(今では3,000万円問題とも)」が大きく騒がれ、退職金や年金だけを頼りにするのではなく、自身で資産形成をする重要性を感じた方もいらっしゃると思います。老後に向けた資産形成をキャリアの早い段階から始めるなら、「個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)」がおすすめです。
今回は、iDeCoとはどのような制度で、どのような加入条件があるかを紹介したうえで、なぜiDeCoが医師に向いているかを分かりやすく解説します。 -
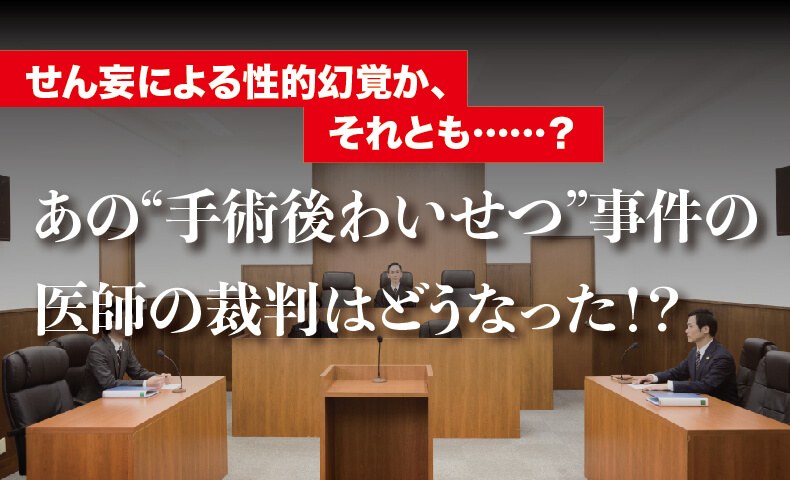
せん妄による性的幻覚か、それとも……? あの“手術後わいせつ”事件の医師の裁判はどうなった!?
まじめな乳腺外科の専門医が、ある日突然刑事事件の容疑者に……。そんな悪夢のような事件の裁判が、東京高裁で続いています。
2016年、ある男性医師が女性患者に乳腺腫瘍摘出手術を施した後、女性の胸をなめるなどのわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつの容疑で逮捕されたのです。
今夏で逮捕から7年。いまなお続く裁判は、なぜここまで時間が掛かっているのか。そして、事件の真相はどこにあるのか。これまでの経緯を振り返り、今後の展望を見通します。 -
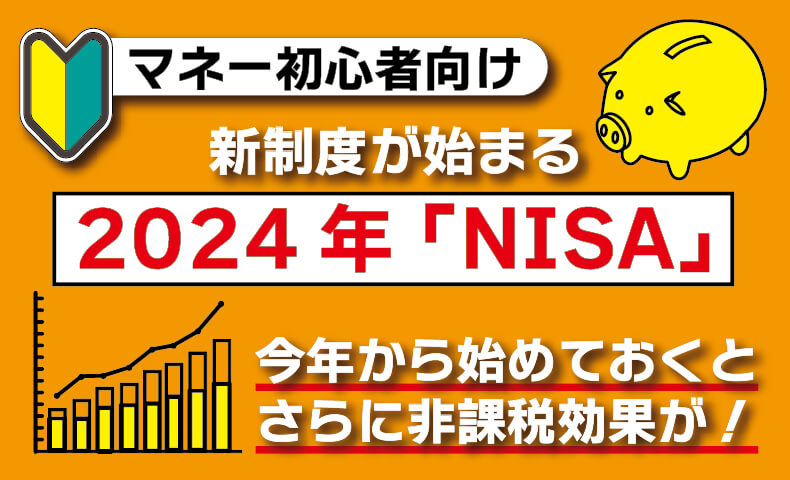
【マネー初心者向け】2024年に新制度が始まる「NISA」今年から始めておくとさらに非課税効果が!
来年から新しい「NISA」が始まることをご存知の方は多いのではないでしょうか?
「制度が変わることは知っているけど、どのように変わるのかわかっていない」「そもそも今のNISAが理解できていない」という方も多くいらっしゃると思います。
NISAは手軽に始めることができ、たくさんの金融機関が参入していて比較的スムーズに運用することが可能です。資産形成には興味があるけど仕事が忙しい、資産形成について考える時間がない、という医師にこそ向いているのです。
ここでは医師にこそ知っておいてほしい、新しいNISAの概要や、これまでのNISAとの併用について紹介します。 -
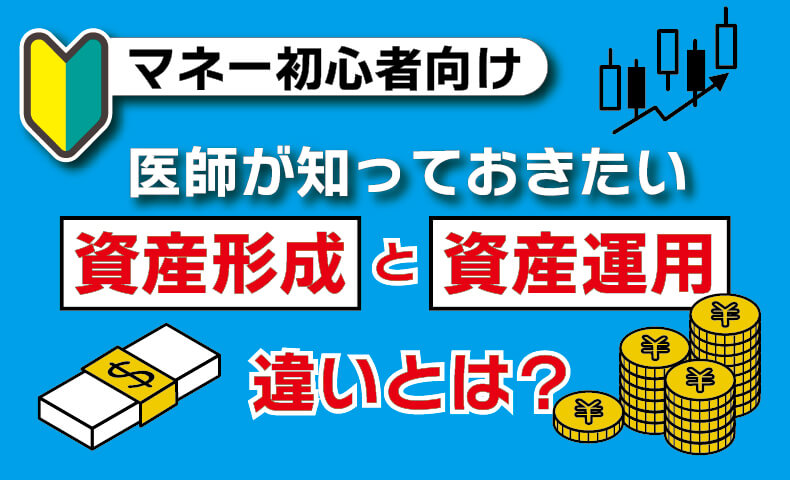
【マネー初心者向け】医師が知っておきたい、資産形成と資産運用の違いとは?
「老後2000万円問題」が近年話題になり、老後に向けて資産運用を始める人が増えています。資産を増やすための方法として、「資産形成」と「資産運用」があります。どちらも似たような言葉ですが、意味は若干異なります。
この記事では、資産運用に初めて取り組む医師の方に向けて、資産形成と資産運用の違いや、資産形成が必要な理由、資産形成・運用の手段を紹介します。 -

スポーツカーも経費になるってホント? 医師だからこそできる、おすすめの節税ワザ
稼げば稼ぐほど税負担が重くなる累進課税は、多くの勤務医・フリーランス医師にとって大きな悩みのタネかと思います。ふるさと納税や住宅ローン減税など、“王道”と呼ばれる節税をすでに実行されている方も多いでしょう。
今回は、税理士である筆者が、多くの医師をアドバイスしてきた経験をもとに、「医師におすすめの節税対策」や「医師だからこそできる節税ワザ」、そして「やってはいけない節税対策」について、解説していきます。
※個人情報保護のため、事例は趣旨を曲げない範囲での脚色・改変を加えています。 -

お忍びデートにおすすめ!“知る人ぞ知る”都内のカジュアルイタリアン5選
デートで食事するなら、マナーやドレスコードを気にしなければいけないオーセンティックなレストランでなく、もっと気軽に美味しい料理とワインを楽しめる店を選びたいもの。ビストロや、カジュアルイタリアンなどがおすすめです。とりわけ、食材にこだわりがある店や、ヘルシー志向の店なら女性も行きたくなるもの。デートで行ってみたい、“知る人ぞ知る”都内の人気5店をご紹介しましょう。
※掲載のメニューは一例です。日によって変更の場合があります。
-

【女医の選択】CASE.2 産婦人科医のキャリア
国家資格をもつ専門職である医師は、比較的男女平等が進んでいる職種といえます。しかし、診療科や職場によっては男性優位な場所も多く、記憶に新しいところでは医学部入試における女性差別が発覚するなど、女性医師には特有の苦悩があるのもまた事実かもしれません。
このシリーズでは現役の女性医師にインタビューを行い、就職先や専門医の取得など、「後戻りしにくい、人生において重要な選択」の局面で「どのような考えのもとで、その道を選び取ったのか?」について深掘りしていきます。
女性医師のみならず、医学生、ひいては医師全般にとって、「生きること・働くこと」を見つめ直すきっかけになれば幸いです。
-

【女医の選択】CASE.1 麻酔科医のキャリア
国家資格をもつ専門職である医師は、比較的男女平等が進んでいる職種といえます。しかし、診療科や職場によっては男性優位な場所も多く、記憶に新しいところでは医学部入試における女性差別が発覚するなど、女性医師には特有の苦悩があるのもまた事実かもしれません。
このシリーズでは医療の現場で働く女性医師にインタビューを行い、就職先や専門医の取得など、「後戻りしにくい、人生において重要な選択」の局面で「どのような考えのもとで、その道を選び取ったのか?」について深掘りしていきます。
女性医師のみならず、医学生、ひいては医師全般にとって、「生きること・働くこと」を見つめ直すきっかけになれば幸いです。
-
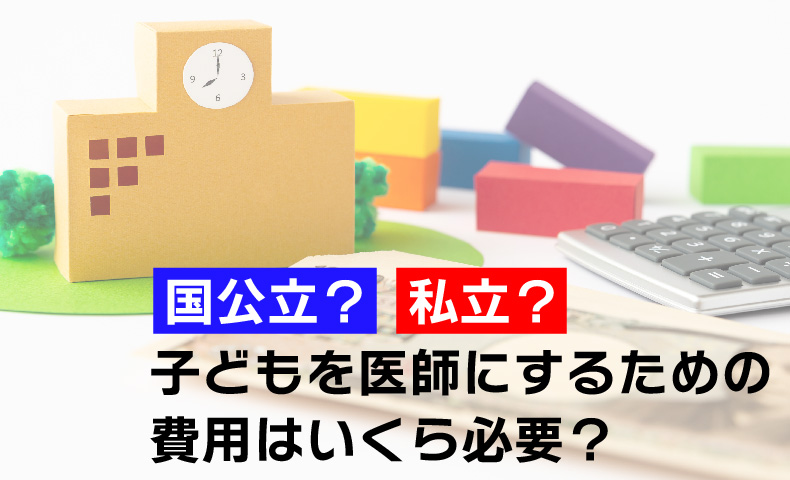
子どもを医師にするための費用はいくら必要? 国公立・私立などパターン別に解説
現在医師をされている方であれば、我が子にも同じように医師になってほしいと思う方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。子どもを医学部に進学させる場合、多くの費用が必要です。選択肢によってかかる費用が大きく異なるため、それぞれいくら教育費がかかるのか把握しておくことが大切です。今回は、幼稚園から大学までのパターン別の教育費、学校外でかかる費用などを紹介します。
(※各調査の数値は2023年5月時点で公表されているものを記載しています) -

医師の働き方改革2024とは? 改革のポイントをわかりやすく解説
2024年4月1日から「医師の働き改革」がスタートします。「医師の働き方改革」とは、政府が主導する医師の勤務環境改善における制度や、それに伴って医療機関などに求められる取り組みの総称です。
本記事では、「医師の働き方改革」が行われる背景や対象者、改革のポイントについて解説します。専門家のコメントも紹介しますので、参考にしてみてください。 -

開業以外の道もある! 最近増えている医師の起業とは
インターネットの普及により勤務医同士の情報交換が容易にできる近頃では、医師が起業をすることで、社会に好循環をもたらそうとする動きが非常に多く見受けられるようになりました。
医師の起業には、勤務医にとって「開業以外の道」という新たなキャリアを生み出すメリットもあると考えられます。
そこで今回は、理想と現実のギャップが生じやすい医療現場の実情をご紹介しながら、そんな環境下で働く医師だからこそできる起業の特徴を徹底解説していきます。 -

【社労士執筆】フリーランス医師が加入できる保険とそのメリット・デメリット
フリーランス医師が加入できる保険の種類について解説いたします。
1. 国民健康保険
国民健康保険は、個人事業主やフリーランスなど自営業者が加入する医療保険です。次に述べる医師国保、任意継続に加入条件により加入出来ない場合でも国民健康保険には加入できます。
2. 医師国保
医師国保(医師国民健康保険組合)とは、各都道府県の医師会が運営する保険制度です。医師会に所属する医師(従業員が5人未満の個人事業所の事業主)と家族、事業所の従業員が加入の対象となります。
3. 任意継続(勤務医を退職した会社の健康保険の継続)
勤務医の場合、勤務している病院の社会保険に加入していることがほとんどです。勤務医を辞めて開業医やフリーランス医師となった場合、退職後に任意継続を選択加入することができます。ただし、退職後20日以内に手続きを行わなかった場合は、加入できないなどの制限があります。 -
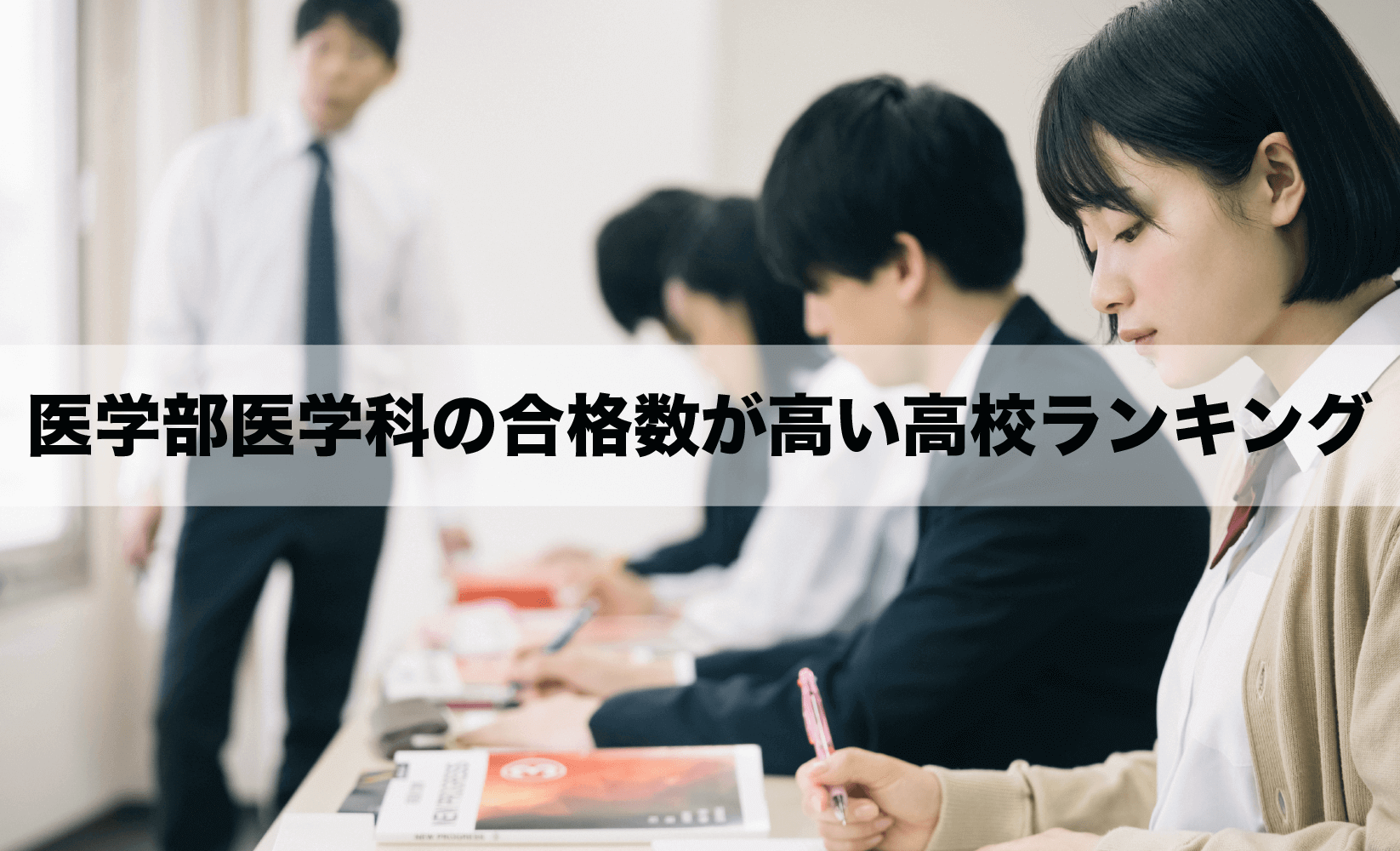
【2022年の合格実績を分析】医学部医学科の合格数が高い高校ランキング
2023年入試が終了しました。お子さまや身内の方がこの春「サクラサク」となった医師の皆さま、おめでとうございます。
本記事では、最難関の医学部医学科への合格者数が多い高校(全国)をランキングにして、高校の傾向と特徴を紹介しました。2023年の最新の数値については、主要な情報がまだ出揃っていないため、2022年の情報を集約し、2023年入試の傾向についても解説します。2024年入試の参考になれば幸いです。
(※2023年入試については、主要な情報が揃いしだい、最新情報をお伝えします) -

お忍びで訪れたい!カップルで入れる都内のプライベートサウナ5選
コロナ禍を経てもサウナ人気はいまだ衰えず。人気の施設は○時間待ち、入っても休憩場所は椅子取りゲーム状態……そんなストレスから解放してくれるのが、近年続々とオープンしつつあるプライベートサウナだ。会員制で高級感を売りにした施設も多く、あらかじめネット予約できるので安心。一部は男女での利用もできるとあっては、デートに使わない手はない。いま“アツい”プライベートサウナをご紹介。
-

【2023年10月スタート】勤務医も登録が必要?医師が知っておきたいインボイス制度
2023年10月1日から「インボイス制度」が開始します。言葉はよく目にするけれど、実際のところ「インボイス制度って何?」「登録しないとどうなるの?」「自分は登録が必要?」など疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。特に医師の方であれば、勤務医か開業医か、副業をしているかしていないかで様々なケースが考えられます。今回は、インボイス制度とは何か、対象となるのはどんな人か、登録には何が必要なのか、などを分かりやすく解説します。
-
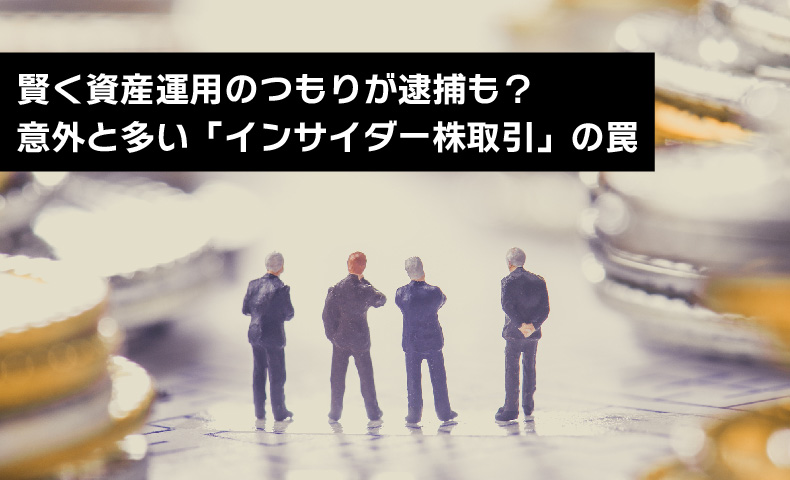
医師こそ注意!「インサイダー株取引」の罠!〜製薬会社からの情報での株取引はアウト?〜
勤務医の資産運用といえば、不動産投資や為替取引、そして株取引が定番かと思います。株取引については、証券会社が扱う「インデックスファンド」(指数連動型投資信託)に投資してそのまま放置、という方も多いと思いますが、なかには個別株を頻繁に売買する“野心家”の方もいることでしょう。
しかし、そんな方が意外と陥りやすいのが「インサイダー取引」の罠。日常的に製薬会社・医療メーカーの内部情報に接しているほか、交友関係が広く、他業種のエグゼクティブにも知り合いの多い勤務医のみなさんにとって、株の違法取引は決して「他人ごと」ではないのです。 -

不動産投資を始めた医師が「今が一番充実している」と語る理由
大学病院の医局を飛び出し、フリーランスの訪問診療の医師となった渡邊譲さん。
24時間365日働き詰めと感じていた毎日から脱し、やりたかった勉強を始めたりと充実した毎日を過ごしているそう。
そんな渡邊さんが、今すっかり魅せられているのが不動産投資なのだとか。
不動産投資のどこに魅力を感じたのか、投資を始めたことで描き始めた将来のプランについてなど、じっくりと伺いました。 -

【現役医師連載コラム】初期研修先をブランド病院にするデメリット
初期研修先の病院を選ぶ時、どうしても頭の中でチラついてしまうのが、ブランド病院ではないでしょうか?おそらく医学生の方のイメージとしては
・なんとなくキラキラしていそう
・初期研修をそこでやれば、人生が明るくなりそう
・とりあえずそこに行っておけば、後悔はないかなってという感じでしょうか?
「あ!それって私のことかも…」
と思った方は、ちょっとまった。初期研修先をブランド病院に選択してしまうことの、デメリットって把握していますか?
ブランド病院は、イメージが先行し過ぎていて、どうしてもメリットばかりが輝いて見えます。
しかし当然のことながら、選択をするという事は他の可能性を切り捨てるという事。メリットの裏側には必ずデメリットが存在します。
今回は、そんなブランド病院で初期研修をする事のデメリットについてです。
-

抜群の節税効果 親子間のクリニック生前承継
多くの開業医が考えるテーマの一つに「事業承継」があります。事業承継というと、年老いて働く気力や能力が下がってから行うものというイメージがありますが、早い段階からクリニックの生前継承を行う方法もあり、これは計画的に行うとメリットが大きいといわれています。あらかじめ準備をしておくことに損はないので、生前承継に必要な知識を親子で確認してください。
-
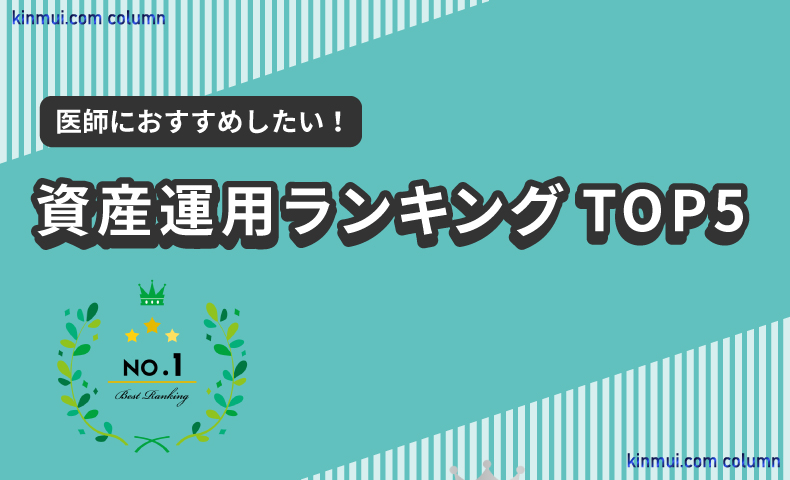
医師におすすめしたい資産運用ランキング5選! ≪投資商品を選ぶ際のポイントも教えます≫
「保有している資産を運用して増やす方法を知りたい」
「資産運用のおすすめの方法が知りたい」
自身の資産の運用方法について上記のような悩みを持っている勤務医を含む医師の方は多いと思います。
資産運用の方法には不動産投資や投資信託などのさまざまな方法があり、どの方法が自身に最適な方法なのかわからない方が少なくないためです。
そこで、この記事では資産運用のおすすめの方法をランキング形式で紹介していくので、ぜひ最後まで読んで資産運用をするときの参考にしてください。 -
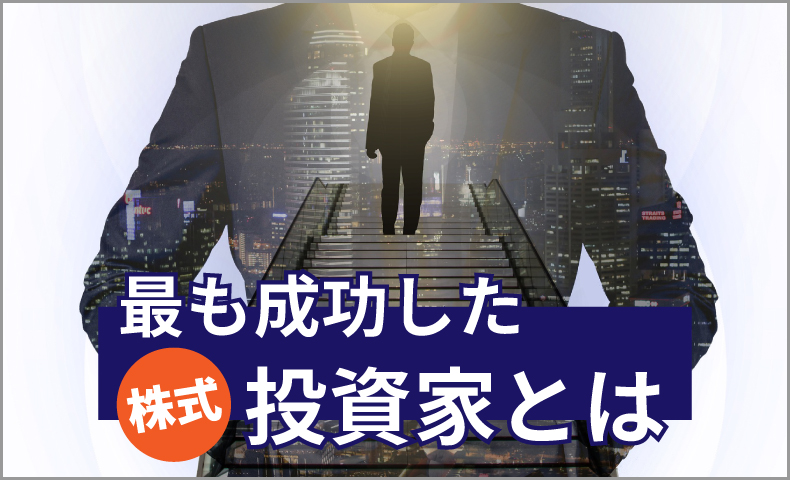
【現役医師連載コラム】株式投資の世界で「最も成功した投資家」と、その手法
こんにちは、医師で投資家の大石です。
いきなりですが、株式投資の神様と言えば、誰を思い浮かべるでしょうか?
おそらく十中八九、ウォーレン・バフェットと答えるでしょう。
しかしながら、その答えは間違っています。確かに、ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイは、過去50年にわたって驚異的な運用リターンを出し続けています。その手法もいわゆるバリュー投資、企業価値の本質を見抜くという知的なイメージの手法を採用していて、かつバフェット自信がお金持ちであるにもかかわらず、ハンバーガーとコカコーラが大好きという節約っぷり。まさに日本人が好きそうなエピソードが満載なので、投資の神様として扱われています。
今回は、株式投資の世界で最も成功した投資家と言われている、ジム・シモンズについて解説していきます。 -

怪しい不動産営業マン「要注意フレーズ」3点
「不動産営業マン」といっても様々。非常に親身になってアドバイスをしてくれるケースもあれば、ただ売りつけるだけで、あとは「ほったらかし」にされる場合もあります。後者のような怪しい不動産営業マンを簡単に見わけるには、営業トークのフレーズに注目してみてください。
-
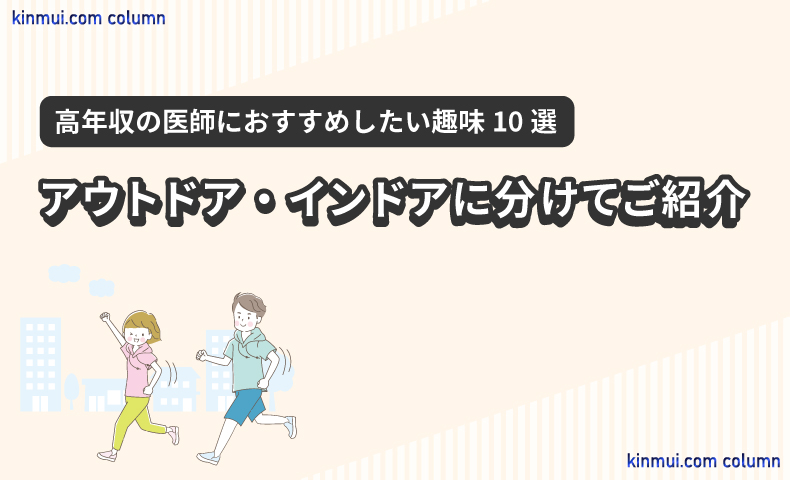
高年収の医師におすすめしたい趣味10選!アウトドア・インドアに分けてご紹介
医師(勤務医)で仕事が忙しく自由時間が少ない方は、新しい趣味を探すことが難しくなりがちです。そのため「趣味に割く時間が少ない」と嘆いている方もいるかもしれません。しかし起床や就寝前の時間や通勤時間などの限られた少ない時間で始められる趣味もあります。ストレス解消や共通の趣味を持った方との出会い、健康維持などそれぞれの目的に合った趣味を見つけてより人生を豊かにしていきましょう。
本稿では、高年収の医師におすすめしたい趣味10選をアウトドア・インドアに分けて紹介します。 -
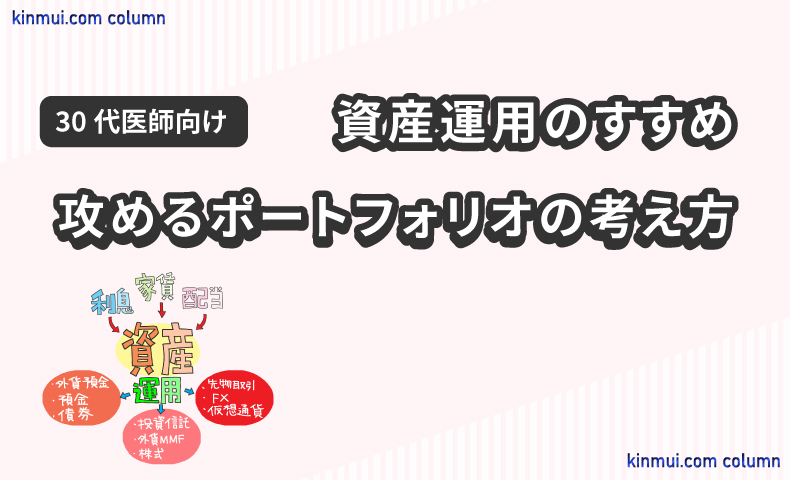
【30代医師におすすめする資産運用】攻めるポートフォリオの考え方
資産運用では、リスク分散する観点から資金のすべてを1つの投資先に集中させることは推進されません。リスクの度合いによって投資先を分けその内訳を考慮しながら組み合わせを構築していくのが基本です。このように投資先を組み合わせる内訳のことをポートフォリオといいます。ポートフォリオは、収入や資産運用の目的、年齢などによって最適な内訳が異なるのが特徴です。
特に年齢が若い人は資産を運用できる時間が長く現役世代として本業の収入も長期間期待できるため、ポートフォリオの構築においても有利な立場にあります。30代の人たちは、収入面でも運用に回せるお金が多くなる一方で運用の時間が十分にある傾向のため、最も有利な位置にあるといってもよいでしょう。
30代の人たちにとって最適なポートフォリオとはどんなものでしょうか。今回は、30代の人たちの視点でおすすめのポートフォリオを紹介します。 -
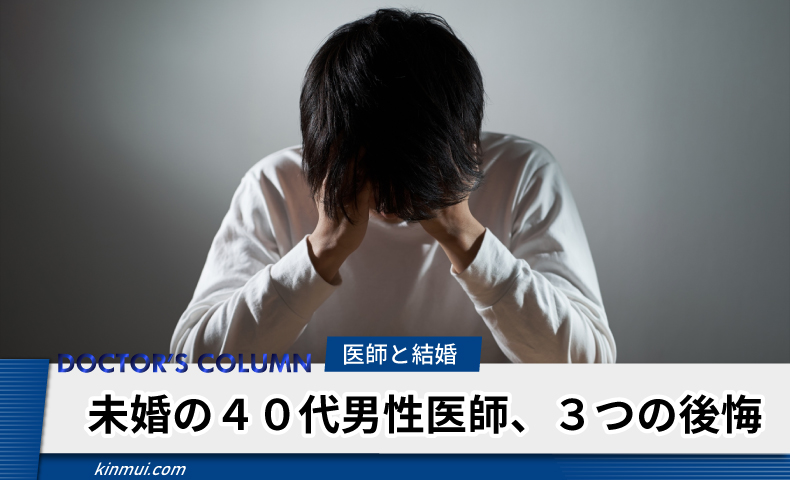
【現役医師連載コラム】医者になれば結婚はいつでも良いと…未婚の40代男性医師、3つの後悔
「医者になれば、結婚はいつでもできるでしょ!」
そう思っている先生は、いらっしゃいませんか?
実際僕も、周りに「男は医者ならしばらく結婚しなくて良いでしょ〜」と言われて、そんなもんかなあ?と思って、のらりくらりと生活していた時期もありました。
しかしながら実際、周りを見てみると…結婚意欲があるものの、なかなか結婚まで辿り着かない男性医師も、世の中います。
実際、僕が話を聞いてみて印象深かった「未婚の40代男性医師」から聞いた話を、今回はまとめました。
-
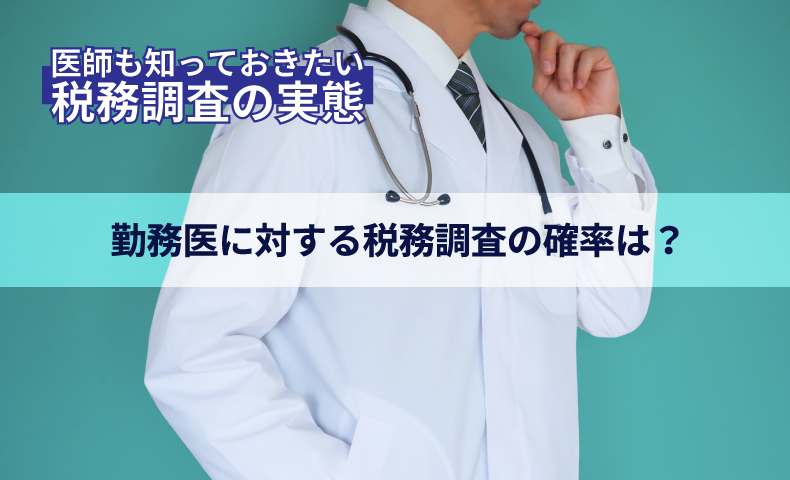
【税理士連載コラム】医師も知っておきたい税務調査の実態「勤務医に対する税務調査の確率は?」
前回の記事≪医師も知っておきたい税務調査の実態「税務調査は断れるのか?」≫で、もし税務調査に入られたら断ることは出来ないとしました。では税務調査に入られる確率はどの程度のものなのでしょうか?
-

30代の医師は資産形成をすべき! その理由と重要な意識改革について
医師は安定した高収入が得られると考えられています。しかし、高収入だからといって将来が安泰というわけではなく、老後に備えての資産形成は必要不可欠です。この記事では、たとえ高収入の医師であっても早くからの資産形成がいかに重要かを開設します。
資産形成が必要な背景、資産に対する意識改革について解説し、長期に亘る資産形成の考え方についてもまとめます。資産形成をしっかり考えたい医師の方は、ぜひご一読ください。 -

「確定申告は税理士に丸投げ」で大丈夫? 意外と知らない税理士の実態
日々診療などで多忙な医師のみなさんは、勤務医であれ開業医であれ、確定申告などの「税務」について、税理士に任せっきりになっているケースが多いようです。しかし、「確定申告は税理士に丸投げ」は思わぬリスクもはらんでいます。具体的にどのような危険性があるのでしょうか。それに対して、どのように対応すればいいのでしょうか。
-
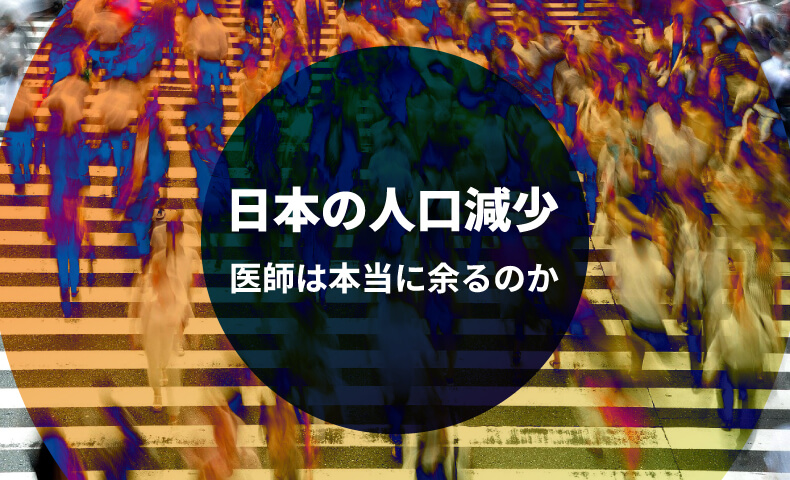
【現役医師連載コラム】日本の人口減少、医師は本当に余るのか
最近、こんな言葉を耳にしませんか?
・日本の人口減少
・先が見えない未来
・AIに仕事が奪われる週刊誌、ネットニュース、ワイドショー、あらゆるメディアでよく見ますよね。中にはもう見飽きた、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実際、これらは嘘ではありませんが、恐怖が先行するあまり正しく噛み砕いて理解している人は、少ないと思います。
今回は、そんな日本という国の人口減少と、医師が本当に余るのかどうか、という事について解説していきたいと思います。
-

「郊外マンション」は時代遅れ? 投資上級者の医師が狙うタワーマンション3選
1960年代からはじまった「マンションブーム」。それから40年余りが経過し、耐震性、居住性に問題がある「ヴィンテージマンション」は建替えとなり、ピカピカのタワーマンションに生まれ変わっています。それと並行して、「武蔵小杉」をはじめとする、郊外のターミナル駅や大企業の工場跡地などにも、新鋭のタワーマンションが建ち始めました。
不動産選びで重要なのは、一に立地。しかし都心は価格が高騰しているので、投資家の食指は郊外のタワーマンションへ動いている様子。都心から離れても、利便性の良い郊外物件を選ぶべきか? 価格が高くても、あらゆるインフラが整った都心物件を選ぶべきか? いったい、「真に価値のあるマンション」って、どんなマンション? -

課税証明書・納税証明書の取得方法と種類について詳しく解説
住宅ローンや融資などの契約の際に必要になることが多い課税証明書や納税証明書。医師の中でも勤務医の収入は給与所得なので、基本的に税金に関する手続きは勤務先の病院で行われているはずです。ただし、課税証明書・納税証明書が必要になった場合は、自分で申請・取得する必要があります。
この記事では、課税証明書・納税証明書の取得方法や種類について詳しく解説していきます。 -
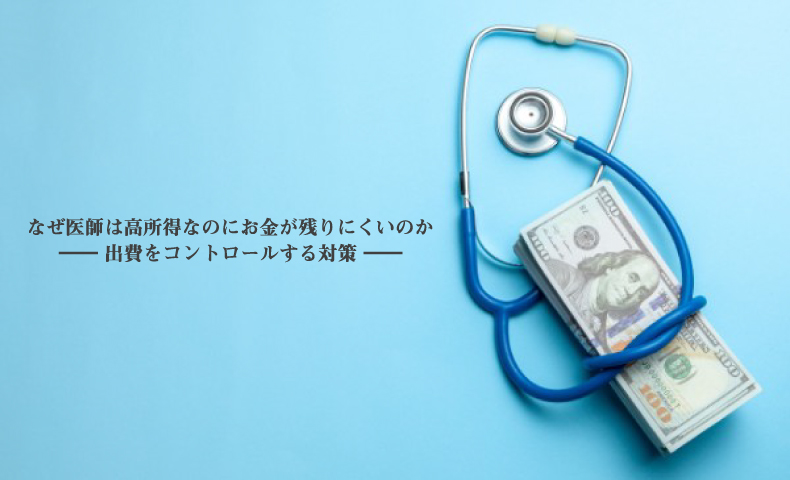
なぜ医師は高所得なのにお金が残りにくいのか 出費をコントロールする対策
医師といえば、高所得な職業の代表です。しかし、勤務医のなかには「それなりに収入はあるけれど、手元にキャッシュが残らない……」と感じている人も多いのではないでしょうか。この記事の前半では、医師の出費を整理し、後半では出費をコントロールするための対策を解説します。
-

勤務医がプライベートカンパニーを持つメリット・デメリット
節税対策としてプライベートカンパニーを設立する勤務医がいます。でも、「節税ができる」というメリットだけで、デメリットはないのでしょうか? そこで今回は、勤務医として働いている医師がプライベートカンパニーを持つメリット・デメリットについて解説します。
-

【前編/30代医師夫婦×担当営業対談】30代医師夫婦が子育てしながら不動産投資を始めたワケ
資産形成や税金対策に有益な不動産投資。高額所得者の医師にとってメリットが大きい投資法であり、始めるタイミングは若ければ若いほうが有利です。とはいえ、仕事が多忙で情報収集する暇がなかったり、調べてみたものの踏ん切りがつかなかったりと、不動産投資に向き合う機会を見つけるのは難しいもの。何より周囲に不動産投資をしている人がいないと不安ですよね。
そこで、今回は夫婦で不動産投資を実践されている、30代の松尾ご夫妻と営業担当の佐々木大地の対談を実施。「不動産投資に興味はあるけど、実際にどんな人が行っているのかを知りたい」という方は必見です。前編では、お二人の出会いから不動産投資を検討することになったきっかけについてお届けします。 -
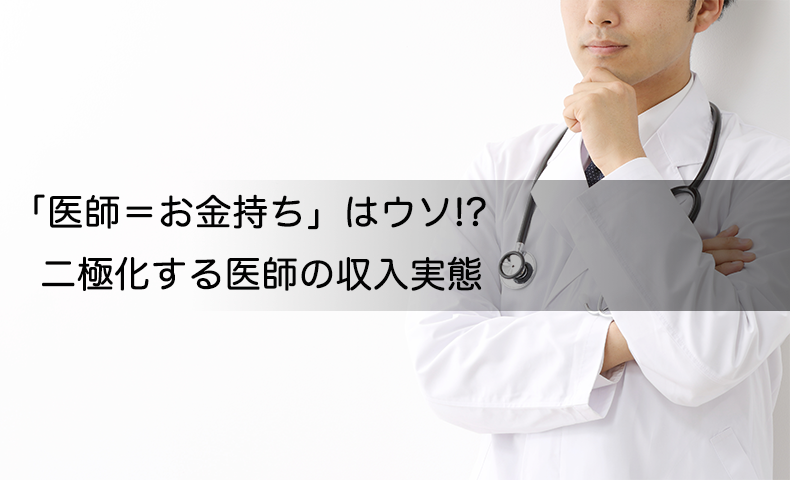
「医師=お金持ち」はウソ!? 二極化する医師の収入実態
医師といえば「高年収」というイメージがあります。もちろんサラリーマンの平均年収よりは稼いでいる医師が多数派を占めますが、一方で同じ職業とは思えないほどの年収の医師もいます。ここでは二極化する医師の実態を紹介します。
-
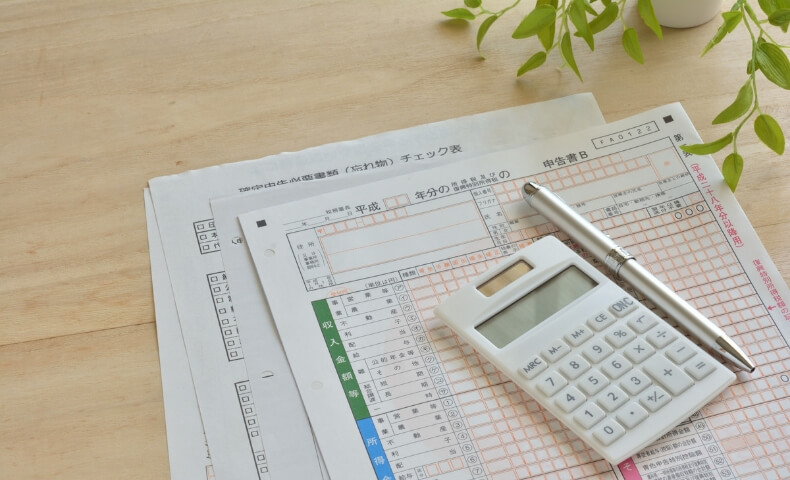
確定申告の肝となる控除額を最大限に増やすには?
確定申告はシンプルに考えると「収入から経費と控除を差し引いた額」から算出されるため、控除を抜かりなく手続きすることは節税の観点から非常に重要です。そこで今回は経費と節税の違いや確認したい重要な控除について解説します。
-
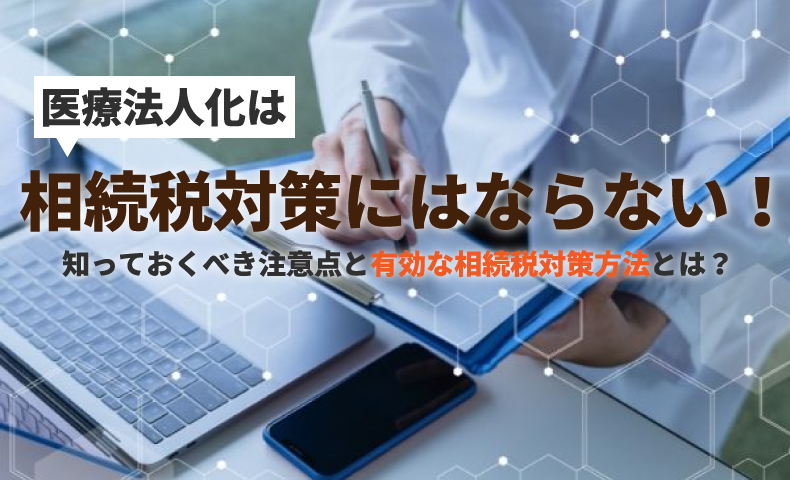
医療法人化は相続税対策にはならない!知っておくべき注意点と医師に有効な相続税対策方法とは?
医師に限らず、事業規模が拡大する際には法人化によって節税できることはよく知られているところですが、相続税対策となると話が変わります。
特に医師の中でも開業医の相続は特殊であることから、対策を怠ると多額の相続税が発生します。
相続される側が負担にならないためにも、早いうちから計画的に相続税対策を講じることが大切です。 -
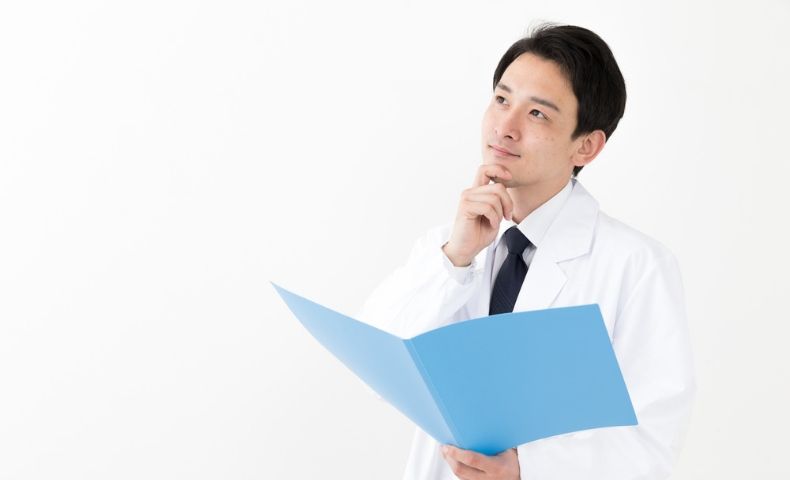
開業医が抱えやすい「患者が来ない!」という悩みをどう解決する?
開業医として成功するためには、患者さんが来ない問題への対処を早めに講じる必要があります。こうした状況としっかり向き合うドクターは、すでに医院が飽和状態の激戦区であっても、少しずつ軌道修正をおこないながら長きに亘り経営を続けていける傾向があります。
一方で、最も大事にすべき患者さんを軽視するクリニックでは、どんなに高立地に開業をしても、売上減や閉鎖のリスクと隣合わせの経営状態が続く可能性は非常に高いと捉えた方が良いでしょう。
そこで今回は、多くの開業医が抱える「患者が来ない」という問題について、考えられる原因とすぐに実践できる対処法をご紹介していきます。
-

医師の診療科別年収ランキング 高収入は診療科で決まるのか?
診療科による医師の年収の違いが気になる方もいるかもしれませんが、必ずしも診療科だけで年収が決まるとは言えないようです。また長時間労働で多くの収入を得ている現実もあり、高収入ではあるものの疲弊している医師の姿がうかがえます。
今回の記事では診療科別の年収ランキングと、さらに高収入を得ている医師の勤務実態などをお伝えします。どのようにして高収入を目指せばよいのか、考えるきっかけにしてみてください。 -

「子どもを医学の道へ進ませたい」医学部の費用を捻出する方法は?
子どもを医学部に入れるためには学費をはじめ、多くの資金が必要になります。でも、現実的に「その費用をどのようにして捻出するのか」という点について、綿密な計画を立てられている人はそう多くはないものです。「高収入」と言われている医師ですが、実は手取りが少ない、貯蓄が困難という現実があります。今回は、その実態を解説するとともに、子どもの学費 + 自身の老後のために“計画的な資金の捻出”の必要性を説きます。
-
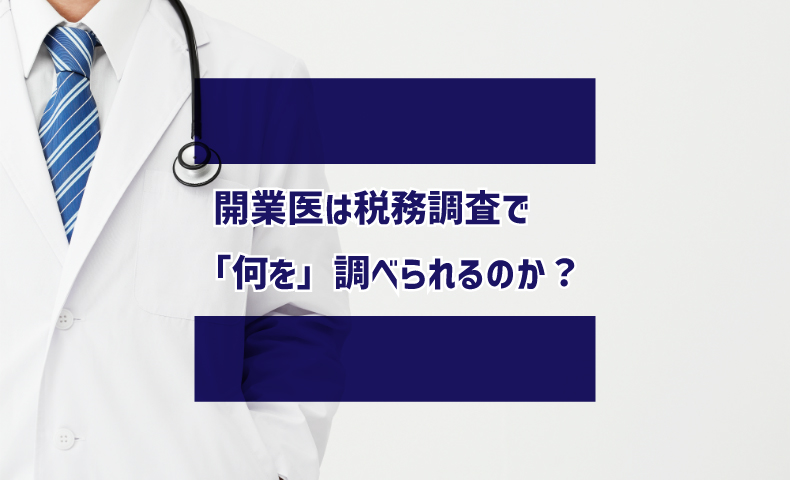
重い税負担も…開業医は税務調査で「何を」調べられるのか?
高額所得者である医師にとって、確定申告は1年間の税務を確認できるチャンスです。手元により多くのキャッシュを残すため、上手に節税することも重要ですが、一部にはそれを取り違え、「脱税」に走ってしまうケースもあります。そんな悪質な医師たちがどんな落とし穴に堕ちるのか。一方、日頃まじめに業務に従事している医師が脱税の疑いをかけられたら、どう対処すればよいのか。突然の「税務調査」への対策や、ちょっとしたミスで課せられる税ペナルティについて解説します。
-
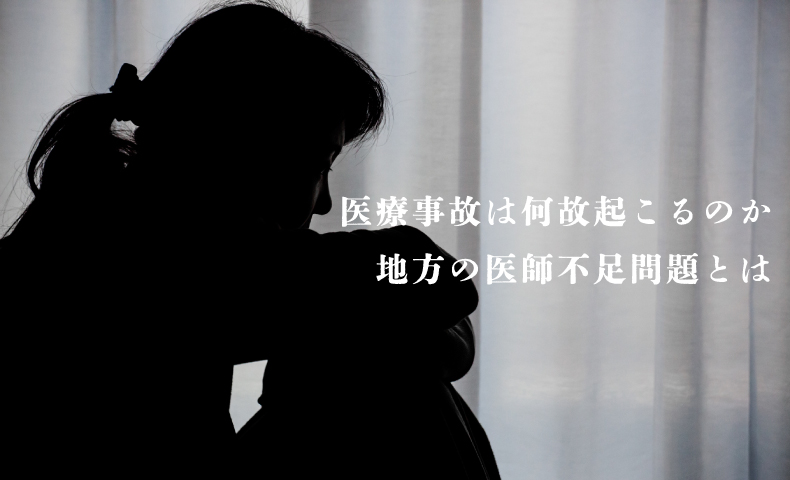
【現役医師連載コラム】輪島市の新生児死亡、防ぐためにできる事
今回は、ちょっとヘビーなニュースについて取り上げたいと思います。
【石川】医療事故で新生児死亡 市立輪島病院 5825万円を賠償
以下、抜粋です。 -

勤務医をしながら社長に! 法人化で狙える節税効果
日本の累進課税制度では、高収入の医師(勤務医)には高い税金が課せられます。しかし、勤務医として働いている医師のままでは節税策にも限界があり、悩ましい問題です。
そこで節税策の一つとしておすすめなのが、「法人の設立」です。本コラムでは、勤務医の法人「メディカルサービス法人」に関して、どのように節税できるのかまで解説します。 -

多忙すぎる仕事がネックになる!? 医師の婚活事情
仕事がハードなせいで、医師は男女問わず晩婚になりがちです。急患が出たためにせっかくの予定が台無しになってしまうなど、仕事のためにプライベートを犠牲にすることも多く、そのせいで恋人との関係が破綻するケースも少なくないようです。
では、多忙な医師はどうやって婚活をすればよいのでしょうか。女性・男性それぞれの立場からみていきましょう。 -

医師が投資をするなら要チェック!医療関連の株式銘柄5選【2021年版】
「テンバガー(一〇倍上がる株)を見つけるには、まず自分の家の近くから始めることだ」
出典:ピーター・リンチの株で勝つ―アマの知恵でプロを出し抜け
これは著名投資家、ピーター・リンチの金言です。つまり「自分の家の近く=日常生活」に株式投資で大成功するヒントがあるということです。これを医師や医療関係者にあてはめて医療関連銘柄にフォーカスしてみてはいかがでしょうか。本記事では、その手がかりになる今注目の医療関連5銘柄を紹介します。 -
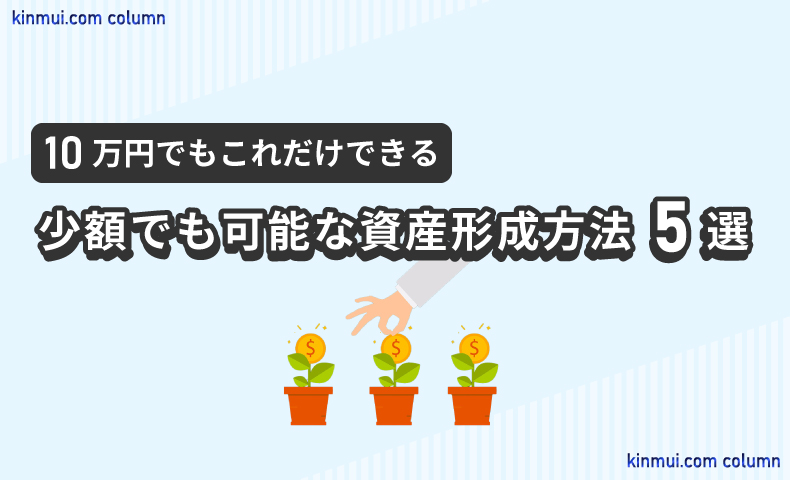
10万円でもこれだけできる!少額でも医師に有効な資産形成方法5選
20代から30代といった若い世代の医師の方々にとって、資産形成はまだまだ先の話に映るかもしれません。しかし、資産形成は時間をかければかけるほど効果が大きく、そしてリスクを分散することができるため、実は資産形成で最も結果を出しやすいのは若い世代の人たちです。
言うまでもありませんが、そのためには資金が必要です。まだまだ収入に余裕がない方も多い世代ということで資産形成を始めるだけの十分な資金がないと感じていても、10万円なら用意できるという方は多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では10万円以下で始められる少額からの資産形成に的を絞り、数ある投資方法の中から有効性の高いものを5つ厳選しました。資産形成の必要性を理解しているものの、その資金がないとお感じの方も今すぐ取り組めるものばかりなので、ぜひ参考にしてください。 -
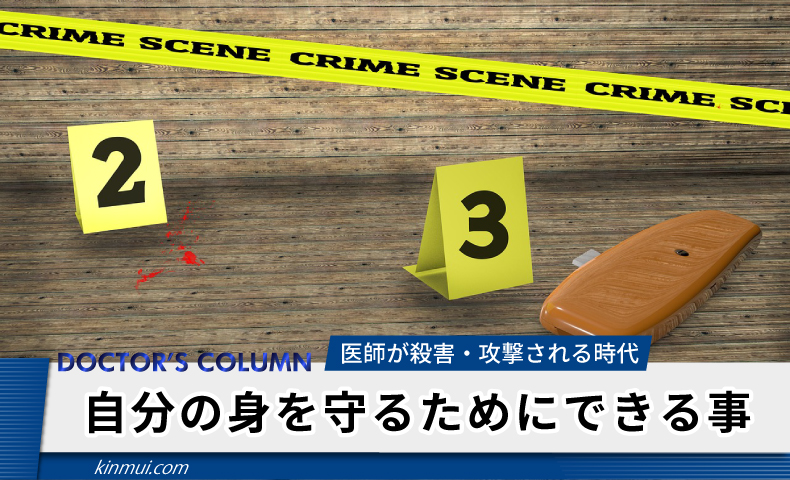
【現役医師連載コラム】医師が殺害・攻撃される時代…自分の身を守るためにできる事
安倍元総理の銃殺事件は、かなりショッキングな内容でした。
昨今は政治家だけでなく、下記のように医師が殺害・攻撃される報道が急激に増えてきているように思います。
引用:NHK「安倍元首相銃撃 真後ろに気取られ斜め後ろの容疑者に気付かず」
医師が殺害・攻撃される時代、自分の身を守るために医師ができる事は、一体何なのでしょうか? -

開業する際の資金繰りと計画
医師が開業を考える際に、最も大きなハードルになるのが「開業資金」です。自分の城を構えるためには資金が必要で、その金額は決して安いものではありません。そこで今回は、開業資金がどのぐらい必要で、用意する方法はどのようなものがあるのか。また、「クリニック供給過多」といわれる現代で、勝ち残っていくための開業プランの立て方などを紹介します。
-
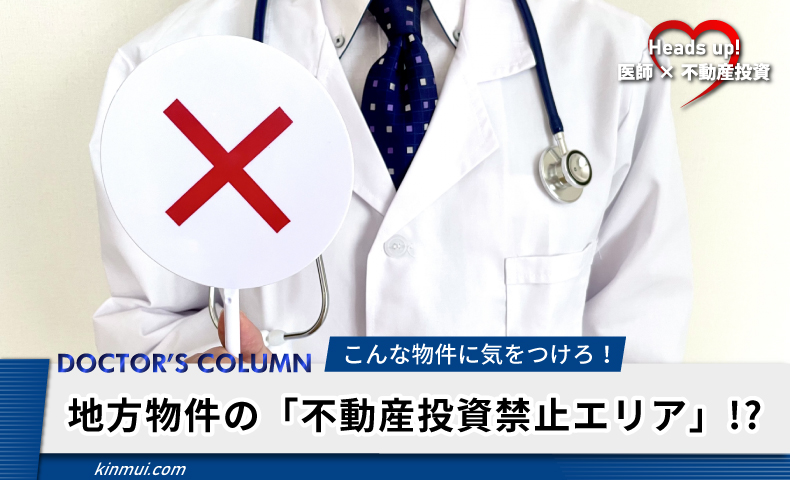
【現役医師連載コラム】地方物件には「不動産投資禁止エリア」があるって話
前回の「こんな物件に気をつけろ!本当は怖い地方物件…」に引き続き、今回も地方物件×不動産投資の怖い話です。
前回の記事では、主に物件の条件についてと、周辺を取り巻く会社の質と数についてでした。今回は、エリアそのものです。
世の中には、不動産投資をしてはいけないエリアというのが、存在します。
してはいけない、これが何を指し示すのか?
シンプルです。不動産投資をそのエリアでしてしまうと、確実に損をするエリアです。
元々の地主でさえ、つまり土地をタダで持っている人たちでさえも、苦労している事でしょう。
どんなエリアが該当するのか?見ていきましょう。 -

開業する前に知っておきたい成功と失敗のパターン
勤務医として働く医師の将来のキャリアの一つとして「開業」があります。自分の城を構えて、オーナーとして働くことに夢を見る医師は少なくありませんが、実際は開業した全員が成功しているわけではなく、人知れず失敗してしまい、厳しい現実に直面している医師の方もいます。失敗を防ぐために必要なのは準備です。
そこで今回は、開業の成功と失敗のパターンを紹介します。 -

株、FX、太陽光発電……メジャーな投資に潜むリスクとは?
不動産以外にも株、FX、太陽光発電など投資対象はさまざまです。しかし、これらは資産防衛の観点から見るとリスクが大きくおすすめできません。代表的なリスクを個別に見ていきましょう。
-

【現役医師連載コラム】心も豊かに。医師が副業で得られるお金以外のメリット5つ
老後2000万円問題を筆頭に、日本でもお金の問題が注目される時代になりました。それらの話題が延長して、副業や投資など「一昔前なら怪しいと言われていたもの」が、フツーに語られるようになりました。
医師も例外ではありません。
医師が副業するということは、イメージがつきにくいかもしれません。医師といえば高収入で安定した職業の、代表格のようになっていますからね。しかしながら実際に、副業や投資によって得られるメリットについて、事前に理解してからであれば、少し抵抗感が減るはずです。
今回はそんな、医師が副業で得られるお金以外のメリットについてです。 -

【現役医師連載コラム】医師は「不動産投資をする理由」を、見失うな
最近、医師といえども日本という国の先行きの不透明感からか、それとも累進課税と社会保険料の重さからか、不動産投資というワードがかなり浸透してきたように思えます。
実際、SNSや書籍でも、医師と不動産投資のコンテンツは増えてきました。
僕自身、医師をしながら不動産投資を開始したのはもう3年前になります。3年やってみて、やっと見えてくる事も多々ありました。 -
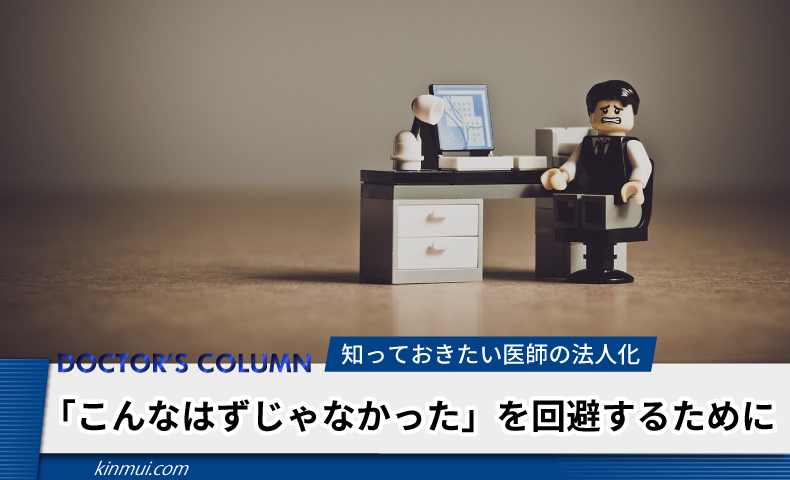
【現役医師連載コラム】医師が法人を持つ、メリットとデメリット
よく「医師が法人を持つと良い」という文言がありますが、具体的に何がどう良くて、その根拠は何で、デメリットは何なのか、という事を網羅的に把握している方は少ないように思えます。
今回は、これらについて簡単にまとめました。 -
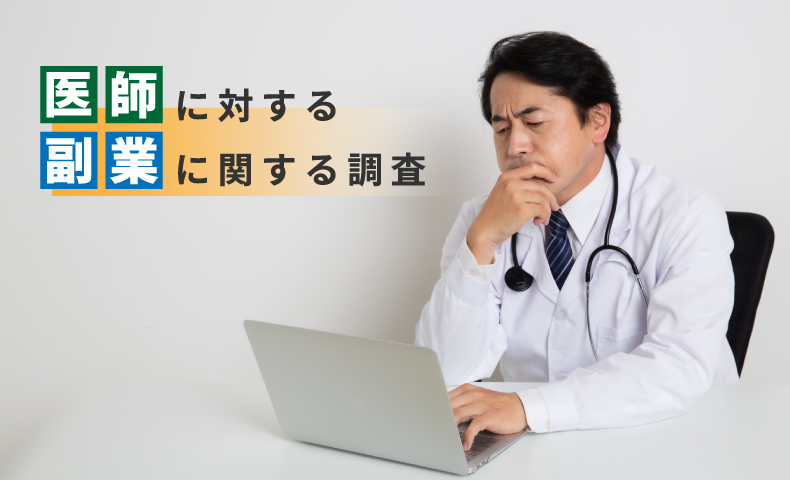
医師に対する「副業」に関する調査
株式会社ブルーストレージ(静岡県静岡市)は、Webアンケートを用いて、医師に対する「副業」に関する調査を行いました(有効回答798名)。
<調査概要>
調査方法:アンケート
調査媒体:SNS
調査対象:医師
調査主体:株式会社ブルーストレージ、Webマーケティングチームアンケート内容「医師の方にお尋ねします、バイト以外で副業を」
1.既に始めた
2.始めたい
3.始めるつもりはない択一回答方式。
-

「事業は順調だけど、相続が心配…」開業医の不安をFPが解消!【後編】
今回も引き続き、20年間メガバンクに勤務されたご経験をお持ちの洲濵拓志氏をお迎えして、開業医の事業や資産に関する悩みについてのスペシャルインタビューをお届けします。
後編は「資産の相続」と「事業の承継」をキーワードに、金融業界と不動産業界での現場経験が豊富な洲濵氏にお話を伺いました。 -

【連載】医師と学ぶ資産形成|精神科医 前田先生 Part.2
医師の方と一緒に資産形成や税金対策を学んでいくスペシャルコンテンツ。前回は精神科医、前田先生のライフプランと資産形成の悩みを伺いました。
第2回目の今回は、「低金利」「インフレ対策」「将来の備え」をキーワードに、資産形成が必要な理由をコンサルタントが解説しています。 -
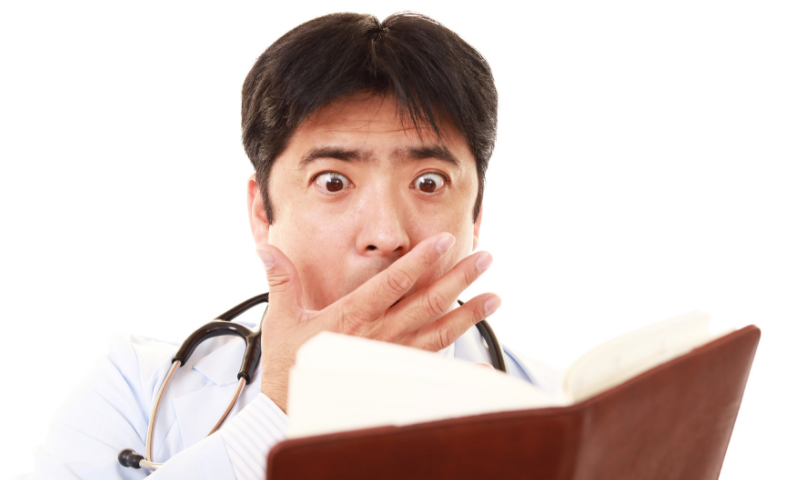
高収入の医師も注意が必要! 高額所得者が投資に失敗する理由
投資をする際に金融機関から融資を受けてはじめることがあります。不動産投資など多額の初期費用がかかる投資方法の場合は、いかに高収入の医師であっても大半はローンを組んでまかなうことが一般的です。
金融機関は融資をする際、借り手の返済能力、不動産投資の場合は物件の将来性や運用計画などから評価を行い、実施するかどうかを判断します。仮に一般的な収入のサラリーマンが融資に申し込んだ場合は、投資に失敗すると本人の給与だけでは返済ができない可能性があるため、シビアに物件について調査が行われます。
しかし、高収入の医師の場合は「返済能力が高い」ため、物件に対する調査時間があまりかけられずに融資が決定する場合があります。投資に失敗したとしても、毎年得られる高収入によって返済が可能と判断されるからです。
これは医師にとって「うれしい」ようでもありますが、実際は「怖い」ことです。物件に対して融資のプロである金融機関によるシビアな目線でチェックをしてくれれば、不動産投資で失敗する確率を自分だけで判断するよりも低くすることができるからです。高収入であるがゆえに、このチェックの過程がパスされてしまうわけです。
これを防ぐためには、医師は自分でプロの不動産コンサルタントなどにチェックしてもらう方法などがあります。自分の資産は自分で守るという感覚が投資には不可欠です。 -

クレジットカードを見直し、使えるカードを厳選
クレジットカードは「誰もが1枚は持っている」ものでありながら、まだまだ“現金社会”の日本ではクレジットカード利用がメインの人は少ないのが現状です。ですが、確実に流れは変わっていて、政府は消費税が10%となることを機に“キャッシュレス化”を推進しています。そこで今回は、今もっているクレジットカードはメインとして使うのにふさわしいのか、というところを検証してみましょう。
-

投資物件はどう選ぶ?10年運用シミュレーション 郊外の築古ワンルームマンション編
「とても安い郊外の物件が気になるけど、長い目でみるとどうなんだろう」
不動産投資を検討する際、その入り口となるのが投資物件の選び方です。同じ築古物件であっても、都心と郊外では運用方法が変わってきます。
この記事では毎回モデルケースを設定し、購入から10年後までの収支をイメージしていきます。
今回のモデルケースは「郊外の築古ワンルームマンション」です。(文章中の金額はあくまでもモデルケースを想定した概算金額です) -

医療M&Aのメリットと買い手が付くためのポイントは?
病院の経営立て直しや後継者不在の中で事業承継を実現する方法の一つに「医療M&A」があります。医療M&Aは、買い手にも売却する側にもメリットが多い方法です。地域の医療を守るために必要な医療M&Aのメリットと買い手が付くポイントについて考えます。
-

倒れる前に! 開業医が自らの健康と家族を守るためにできること
個人経営の開業医は、長時間の診療だけでなく雑務にも追われるため、自らを過酷な労働環境下におきがちなものです。知らず知らずのうちに体を壊してしまい、気がついたときにはメンタルに不調をきたしていたなど、特に指摘してくれる上司や同僚が存在しない開業クリニックは心身のケアに注意が必要です。まずは医師自身が健康でなければ、地域の医療を担うことなどできません。
-

資産形成は早めに始めるのが肝! 若いうちに知っておくべき投資のルール
資産形成をはじめてますか? 「まだ若いから自分には早い」と思った勤務医として働く若い医師の方は、ぜひこの記事を最後まで読んでください。資産形成は「早くからはじめること」が最も重要なポイントなのです。本コラムでは、その理由と、早くから資産形成をはじめることのメリットをご紹介します。
-

資産の多い医師が知っておくべき生前贈与の基礎知識
医師は、一般の人よりも高収入であるため、当然ながら資産がたまりやすい傾向にあります。厚生労働省が公表しているデータによると、医師の平均年収は1,200万円を超え、生涯賃金は約6億円にも及びます。日本の平均年収がおよそ500万円、平均生涯賃金が約2億5,000万円なので、いかに医師の報酬が高いかが分かります。
しかし、資産が多いということは、相続対策をしっかり行わないと、いざ相続というときに莫大な税金を支払うことになります。相続税の最高税率は55%にも及び、一般的に相続は三代続くと資産の大部分を失うといわれています。相続税は、誰しも逃れることができないものですが、時間をかけてしっかり対策を行うことは可能です。
今回は相続対策で有効な方法である暦年贈与について解説します。 -
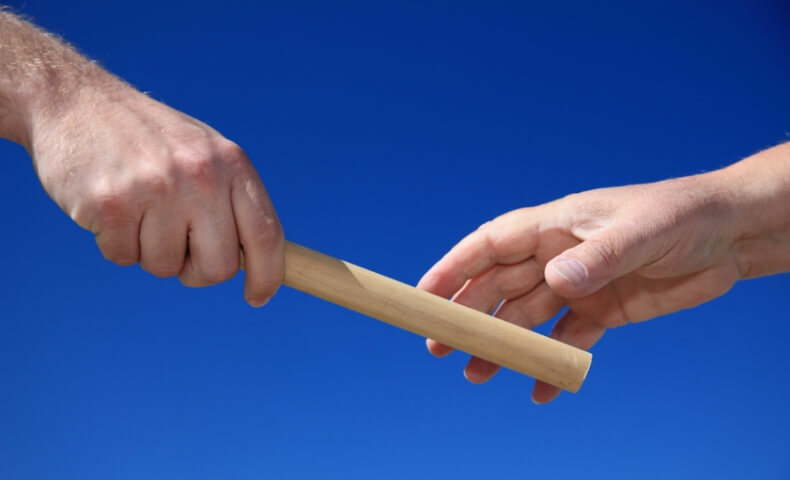
資産が多い医師なら必要不可欠な知識! 相続の基本的なルール
誰かが亡くなった時に、その人の財産を受け継ぐことを「相続」と言います。相続には、法律で決められたルールがあり、それに従って財産が分割されます。
いざ相続する立場になったときに慌てないためにも、相続の基本的なルールや流れを理解しておきましょう。 -
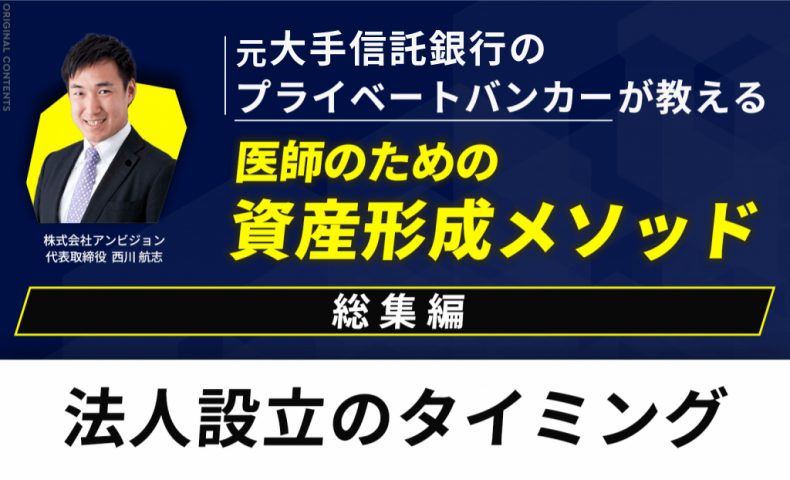
【元銀行員が教える】医師にできる「 法人化に至るまでの資産形成メソッド」
本記事は過去に勤務医ドットコムが開催したセミナーの内容を記事にしています。
記事「医師だからこそできる! 「資産管理会社」を使った節税対策とは?」前編・中編・後編では、「税対策のために資産管理会社の設立が必要」というお話をしてきましたが、私たちが最も多く質問が、「法人化はどのタイミングですればいいのか」というものです。
今回の記事では、法人を設立すべきタイミングについての質問に回答していきましょう。 -

ふるさと納税の手順を解説
自治体からの返礼品が豪華になり、総務省から各自治体に「返礼品の比率を寄付額の3割までに」と上限の要請をしたほど過熱化している「ふるさと納税」。納税をすれば食べ物などの返礼品をもらえるなど、何となくのイメージはできても、具体的にどのような仕組みなのか説明できない人もいるでしょう。そこで今回は、ふるさと納税の仕組と、実施するための手順を詳しく解説します。
-
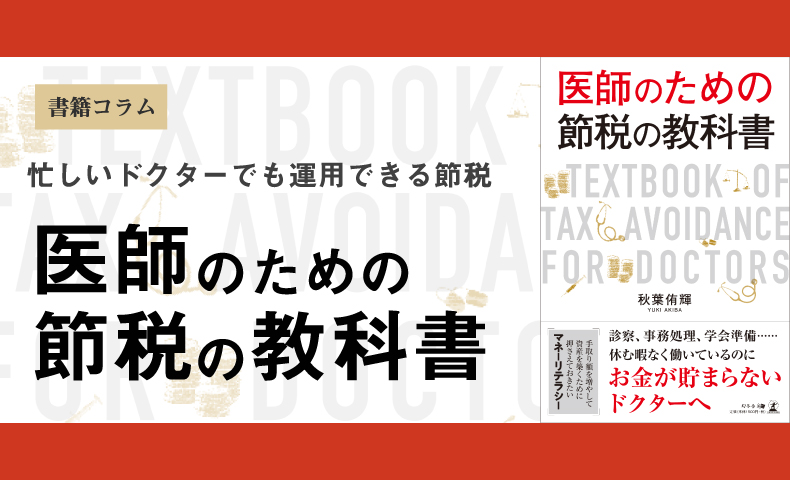
書籍連載コラム「医師のための節税の教科書」
毎日の診察、電子カルテの入力や処方箋作成などの事務処理、論文執筆といった学会準備……。
仕事の忙しさにかまけて、自身の将来を見据えた資産形成や貯蓄が手つかずになっている医師は少なくありません。
-

医師におすすめの投資の方法とは
今、必要としない資産を投資という形で運用してさらに財産を殖やすことだけでなく、節税することもできるのです。投資はリスクを伴うというイメージがありますが、安定した収入を得られる投資や、節税のための投資も存在しています。数十年後の生活のため、投資の方法をご紹介いたします。
投資の種類にはどういったものがあるのか。探すと数々の投資手法は出てきますが、代表的なものを紹介します。リスクとリターンに関しては投資手法や取り組み方によって変わってきますが、自分に合う方法を見つけることが大切です。
では投資の種類にはどのようなものがあるのでしょうか。ひとつひとつみていきましょう。 -

【現役医師連載コラム】これからのクリニック経営とLTV
前回の記事<医師でも知っておきたいLTVという考え方>では、普通に医師として生きているとLTV(Life Time Value)という考え方とはあまり触れないけど、最近注目されているから知っておいて損はないよ、という話でした。
さて今回は、このライフタイムバリューが、医療とどう関係があるのか?解説していきます。 -
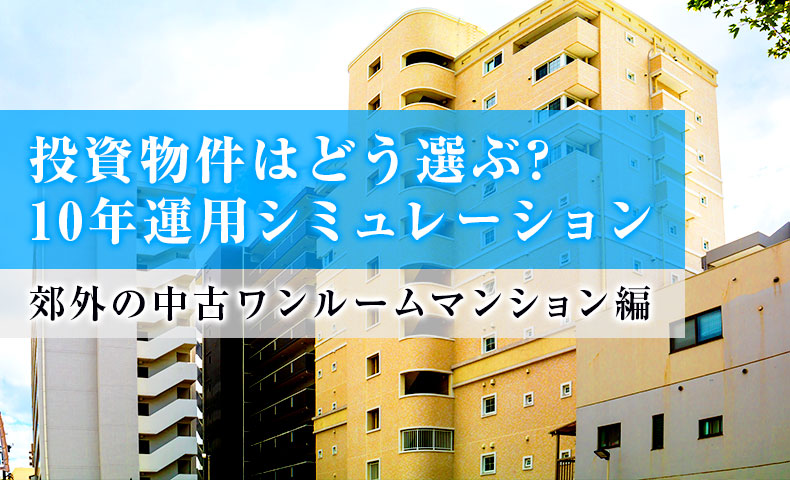
投資物件はどう選ぶ?10年運用シミュレーション 郊外の中古ワンルームマンション編
「郊外エリアの中古物件が気になるけど、都心エリアとの違いはどうなんだろう」
不動産投資を検討する際、その入り口となるのが投資物件の選び方です。同じ中古物件でも、都心エリアと郊外エリアでは運用方法が変わってきます。
この記事では毎回モデルケースを設定し、購入から10年後までの収支をイメージしていきます。
・過去記事「都心の中古ワンルームマンション編」
今回のモデルケースは「郊外の中古ワンルームマンション」です。
(文章中の金額はあくまでもモデルケースを想定した概算金額です) -
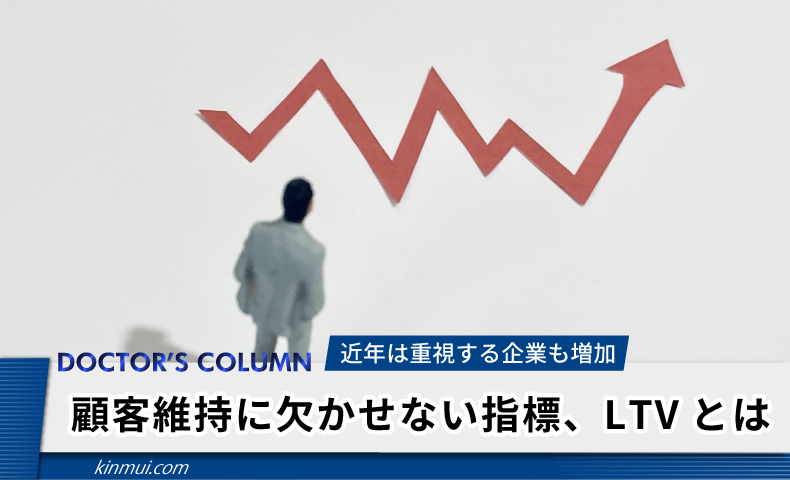
【現役医師連載コラム】医師でも知っておきたいLTVという考え方
いきなりですが、皆さんはLTVという考え方をご存知でしょうか?
投資の世界でLTVはLoan To Valueの略語で、資産価値に対する融資割合で、主に銀行が使う言葉です。
今回解説したいLTVは、残念ながらLoan To Valueではありません。投資の世界ではなく、マーケティングの世界、ビジネスの世界におけるLife Time Valueの概念です。 -

【現役医師連載コラム】最近なんか上手くいかない…医師の生産性を下げる5つの悪習
医師として働いていると、毎日の業務に忙殺されて、ふと自分の立場を客観視できない場合があります。
結果的に体調を崩してしまったり、メンタルに不調を来したり、まさに「医者の不養生」になってしまう事も少なくありません。
今回は「気がついたら医師の生産性を下げてしまう」5つの悪い習慣についてです。 -
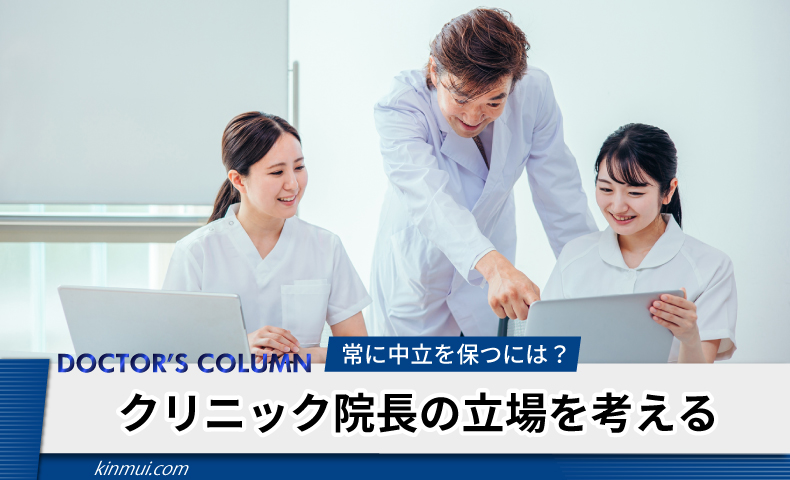
【現役医師連載コラム】クリニック院長が気をつけたい、スタッフとの接し方
こんにちは。今回はクリニックの院長に向けて「スタッフとの接し方」について、考えていきたいと思います。
院長という立場から、クリニックのスタッフにどう接して良いか、分からない時って、正直なところありますよね。
いくつかある注意点の中でも、重要な事について今回はまとめました。 -
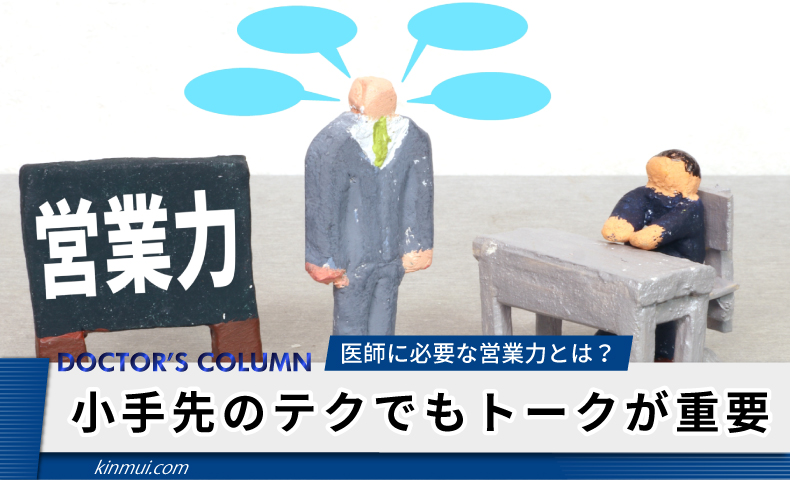
【現役医師連載コラム】医師に必要な「営業力」とは−後編−
前回の記事<医師に必要な「営業力」とは−前編−>では、医師に必要な営業力とは「信頼関係と小手先のテクニック」の2つで、どちらか片方がなくても成立せず、かならず2つ必要だという話をしました。
後編では、信頼関係の構築の次、小手先の営業テクニックについてです。
ここから先は、一般的な営業テクニックと同様です。言ってしまえば世の中には広く出回っている小手先のテクニックですが、小手先のテクニックさえ営業トークとして自然に話せる医師はあまりいません。
うまく使いこなせれば、それだけで大きな差別化要因になります。 -

【現役医師連載コラム】現役医師×不動産投資家が振り返る、2021年の不動産投資市場
皆さんこんにちは、医師兼不動産投資家の、大石です。
もうすぐ2021年も終わりですね。今年は色々ありました。オリンピック、選挙、首相交代、新型コロナウィルスデルタ株、オミクロン株…あげればキリがありません。
そんな2021年でしたが、不動産も結構いろいろありました。今回は不動産という切り口から、2021年を振り返ってみたいと思います。 -

不動産投資における「収益還元法」とは
条件が整った投資向け不動産物件。大きな投資金額となるため、「これは良い買い物になるか?」と自問自答される方も多いことでしょう。
人によっては「賭け」に出る方もいるかもしれません。でも収益還元法を知っておくと「賭けで物件を買う」というリスクを減らすことが可能になってきます。
客観的に物件の品定めもできるようになります。ここでは不動産投資における「収益還元法」に着目し、その考え方や計算方法に関してお伝えします。
-

医師の懐事情と老後資金形成のための資産運用
収入も多いが支出も多い……。これが医師の懐事情の実態ではないでしょうか。「稼いでも、稼いでも、手元にお金が残らないなぁ」という悩みを抱えている医師の方は“高所得貧乏”にならないよう、賢い資産運用や投資で資産形成を考える必要があります。同僚の医師はすでに始めていて、同じ収入でも多額の貯蓄をしているかもしれません。
-

医師の転職事情 待遇を優先する?キャリアを優先する?
勤務負荷を軽くしたい。
もう少し年収を高くしたい。
キャリアプランを実現したい。
医師の転職にはさまざまな理由があります。
実際の転職にあたっては、待遇を優先するか、それともキャリアを優先するかなど、考慮すべき点がさまざまあります。
この記事では、医師の転職事情について多角的にご紹介していきます。 -
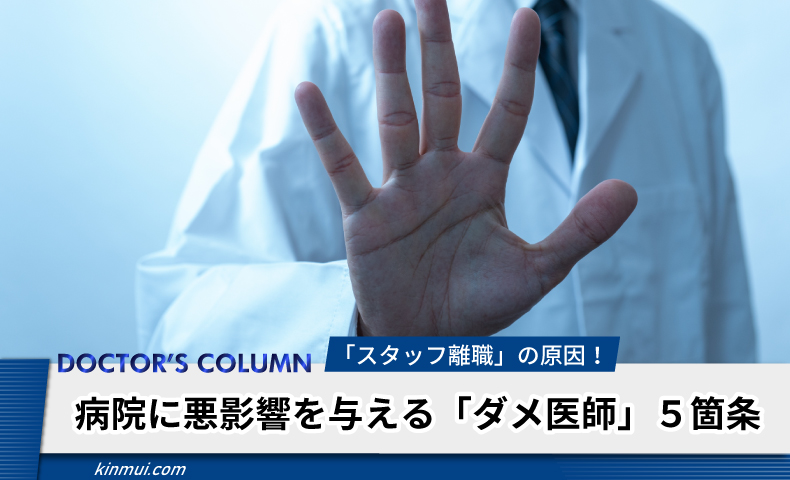
【現役医師連載コラム】「スタッフ離職」の原因!病院に悪影響を与える「ダメ医師」5箇条
どんな職場でも、職場に悪影響を与える人は必ずいます。病院も例外ではありません。
そのようなスタッフは、病院からすれば「悪性腫瘍」のような存在です。単独で問題を引き起こしているならばまだしも、周囲に悪影響を与え、離職が進み、人が減る事でギスギスした空気が蔓延、さらに離職が進んでいきます。腫瘍が病院の中を転移していくイメージです。
まさに「離職スパイラル」の最初の起爆剤にもなり得るわけです。
そういった離職スパイラルを引き起こされるのは、病院の経営・運営サイドからすれば、大問題です。一体どういった医師が、病院に悪影響を与えるのでしょうか? -
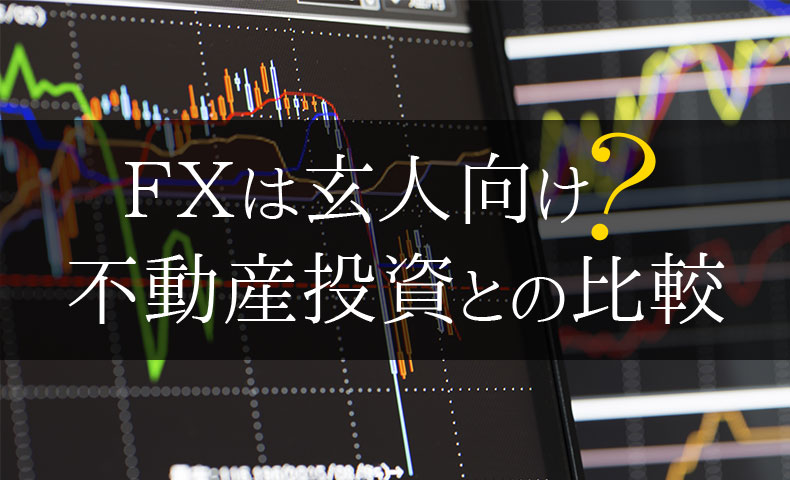
FXは玄人向け?不動産投資との比較
「FXと不動産投資、どちらが難しいのだろう……」
投資の手法には、不動産投資以外にもいくつか種類があります。それぞれの特徴をおさえ、不動産投資と比較してみましょう。
今回は「FX」にスポットをあてます。 -
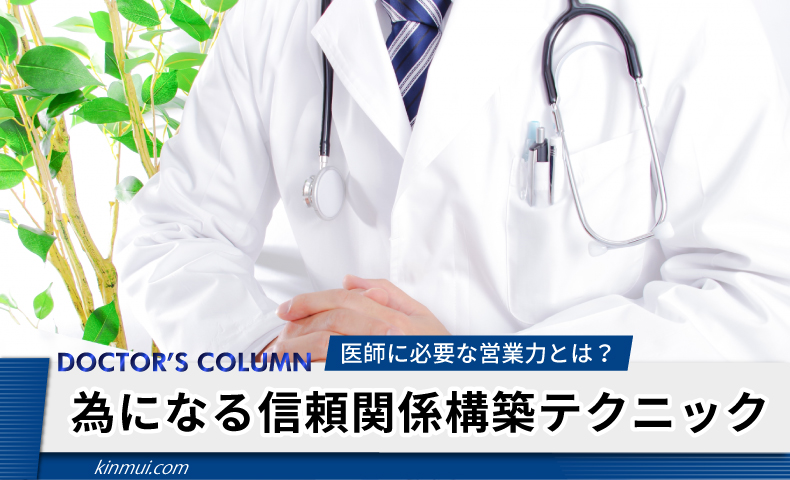
【現役医師連載コラム】医師に必要な「営業力」とは−前編−
僕の感覚的な話ですが、うまくいっている自由診療領域の院長は、営業マンとして優秀な方が多いと感じています。
人柄としては、カラッとしていて快活。見た目としては、笑顔が眩しい、髪の毛は短くカットされていて、適度に運動しているであろう、鍛えられた肉体をお持ちの先生。そんな感じのイメージです。
なぜ、うまくいっているクリニックの院長は、営業マンとして優秀なのか?考えてみました。 -

【連載】医師と学ぶ資産形成|精神科医 前田先生 Part.5
医師の方と一緒に資産形成や税金対策を学んでいくスペシャルコンテンツ。精神科医前田先生とお送りする連載第5回目の今回は、不動産投資が生む節税効果について解説します。
-
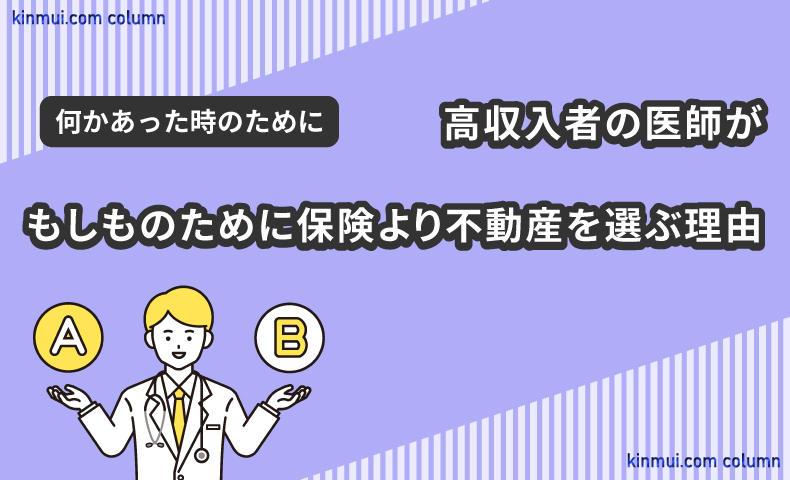
高収入者の医師がもしものために保険より不動産を選ぶ理由
不動産投資はリスクが高いと思われがちです。しかし、内容や仕組みを知ればハイリスクな投資ではないことが分かります。例えば、不動産投資は生命保険の代わりになる点はメリットの一つです。万が一のとき、残された家族が生活に困らないように、多くの方は生命保険の加入によって準備をしてると思います。しかし、必ず生命保険で準備する必要があるのでしょうか。
今回は、賢く遺族へ資産を残す方法として高所得者の医師が行っていることを解説します。 -
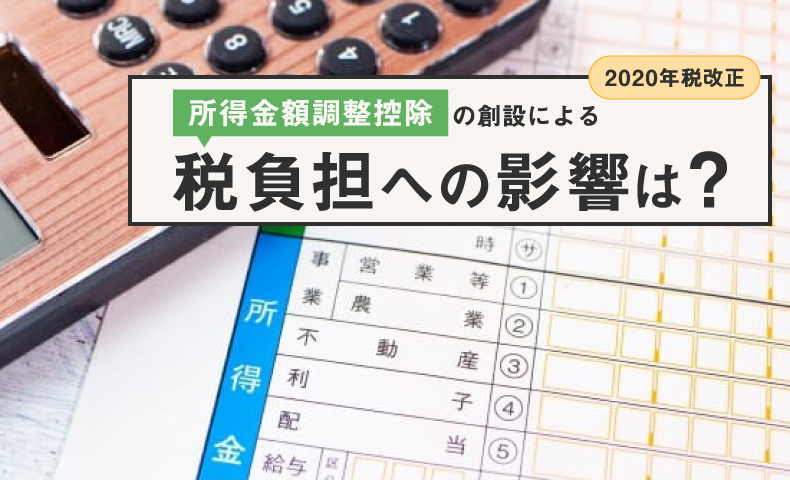
2020年税改正 所得金額調整控除(子ども等)の創設による税負担への影響は?
2020年分の所得税および住民税については、税制改正の影響を受けた変更点が多く見られます。給与所得者については、どれくらいの影響を受けるのでしょうか。申告の際に気を付けるべき点とはどのようなものか、についても見ていきましょう。
-

開業医が必ず行う確定申告の仕組みとポイント
開業医が必ず行わなければいけない手続きの一つに「確定申告」があります。確定申告は開業医など独立して働いている人にとっては“ずっと付き合っていかなければいけないイベント”なので、その「仕組み」や「注意しておくべきポイント」などをしっかり理解しておくようにしましょう。
確定申告は「つい忘れてしまった」で済まされない税金の手続きです。特に開業医1年目の医師の方は、ぜひこの機会にチェックしておいてください。 -

【現役医師連載コラム】外科系専門医の給料を確実に上げる、たった1つの方法
いきなりですが、日本の医療制度で、なぜか外科系の専門医の先生って、不遇ではないでしょうか?
■ 慢性的な人員不足で、基本的に激務
■ 手術などは高難易度で、習得に時間も労力もかかる
■ それでいて給料はそれほど高く無く、何ならやや低い
■ それを見た若手医師が、外科系を避けてさらに人不足と、あまりにも不遇です。負のループに陥っているようにも、思えます。
このループが好転するとすれば■ 手術などは高難易度で、習得に時間も労力もかかる
■ しかしながら給料がとにかく高いので、人が集まる
■ 人員不足が解消されてきて、激務とは言えないレベルに
■ それを見た若手医師が、外科系に憧れてさらに人員が充となるはず。
しかしながら、今の日本の医療制度で、実際にはこうなっていません。
一体なぜなのでしょうか?何か解決策は、あるのでしょうか? -

投資物件はどう選ぶ? 10年運用シミュレーション・都心の中古ワンルームマンション編
「都心エリアの中古物件が気になるけど、新築との違いはどうなんだろう」
不動産投資を検討する際、その入り口となるのが投資物件の選び方です。同じ都心エリアにある物件でも、新築と中古では運用方法が変わってきます。
この記事では毎回モデルケースを設定し、購入から10年後までの収支をイメージしていきます。
・前回記事「都心の新築ワンルームマンション編」
今回のモデルケースは「都心の中古ワンルームマンション」です。(文章中の金額はあくまでもモデルケースを想定した概算金額です) -
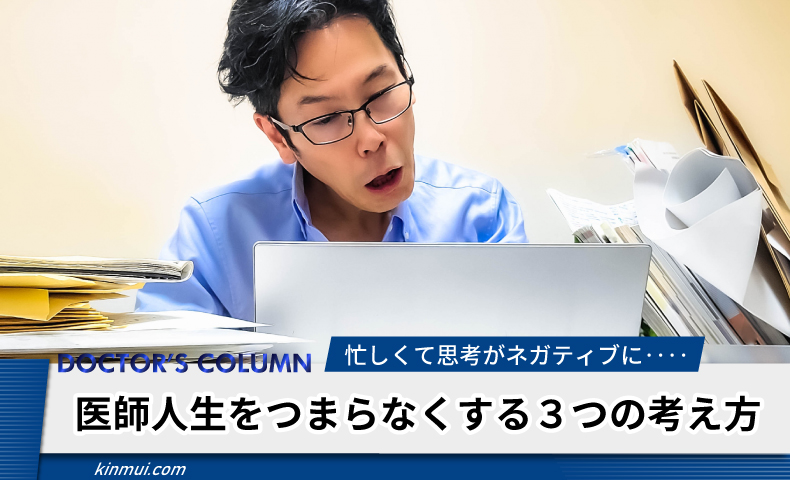
【現役医師連載コラム】医師人生をつまらなくする3つの考え方
医師として日々仕事に追われ、忙殺されていると、ふとネガティブな考えが頭の中を支配します。実際、僕もものすごく忙しく働いている時は、そうでした。
しかしながらそこから脱却してみて分かった事は、医師人生をつまらなくするのは自分自身で、特に自分の頭の中、即ち「考え方」であるという事がわかりました。
今回はそんな、医師人生をつまらなくする3つの考え方についてです。 -
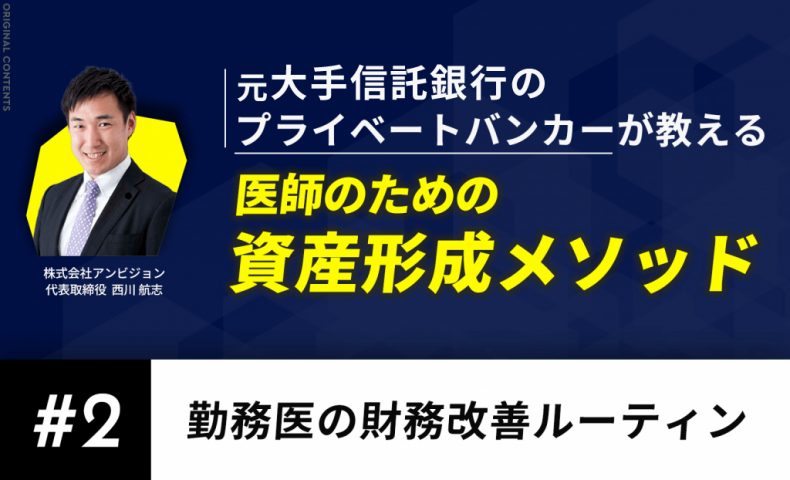
【元銀行員が教える】医師にできる 「資産管理会社」を使った節税対策とは?【中編】
本記事は過去に勤務医ドットコムで開催したセミナーの内容を記事にしています。
所属の病院だけでなく、アルバイトもかけもちして、寝る間を惜しんで長時間働いていたり、仕事が忙しくて家族との時間を作ることができなかったり……。
さらに、「お医者さんの子供はやはり将来お医者さんに」という傾向もあり、教育費はどうしてもかかりますし、住む環境でも、物価が高い地域に生活する方が多く、支出は多くなります。
さらに、所得が高く社会的信用があるため、社会保障、福利厚生等の補助制度がほとんど使えません。
時間も制度補助もなく、そして支出が異常に多く、結局手元にお金が残らない――。本記事では、勤務医の方々のそんな厳しい実情を打破する解決策についてお話ししていきましょう。 -

【現役医師連載コラム】こんな物件に気をつけろ!本当は怖い地方物件…
前回、前々回の「現役医師が警告!こんな不動産業者には注意」と「こんな物件に気をつけろ!医師が陥りやすい不動産投資の罠」に引き続き、今回も不動産投資の怖い話シリーズです。
地方物件の良さとして、競合が少ないとか、利回りが高いとか、メリットもありますが、裏返せばデメリットも当然のように存在します。
しかしながら、地方物件のリスクについては、いざある程度やってみないとわからなかったり、外からは判明しにくい、言葉や数字になっていないリスクが存在するため、そのリスクを取れず、結果的にそれほど競争が激しくない、という状況に陥っている部分が、あると思います。
今回はそんな地方物件のリスクについて、読者の方に理解して頂いて、リスクをうまくヘッジしてリターンだけ享受できるようになれたら、幸いです。 -

忙しいドクターにピッタリな「ほったらかし投資」とは
開業か勤務かに関わらず、ドクターは多忙です。診察中は患者さんに集中し、他のことは考えられないのが普通でしょう。しかし、ビジネスマンや自営業者と比較しても、資産はお持ちの方が多いのも事実です。
厚生労働省が発表した2019年の「賃金構造基本統計調査」によると、40歳医師の平均年収は、約1,169万円です。
もちろん、開業や勤務、診療科によって年収は大きく変わってくるでしょう。可能な限り資産運用した場合と全くせずに定期預金を置きっぱなしにした場合では、老後の資産が大きく変わってきます。
そこで、今回は多忙なドクターにピッタリな、「ほったらかし投資」の一手法である、「ロボアドバイザ―投資」について見ていきましょう。 -
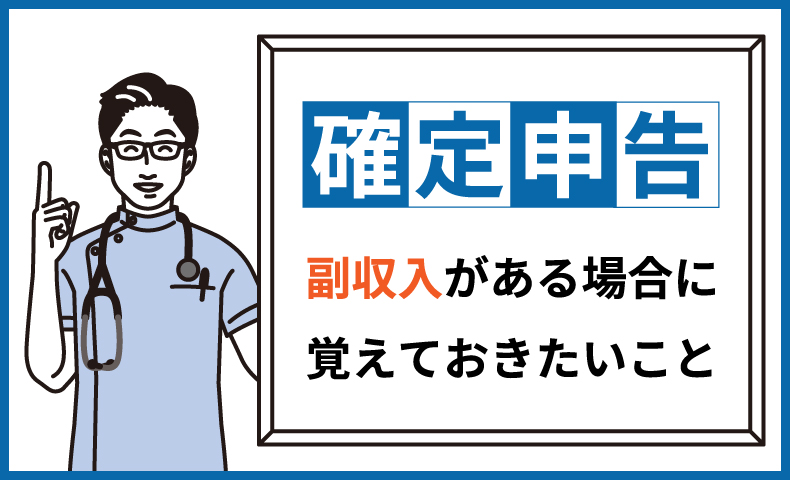
確認しておこう!副業で得た収入を確定申告する際の留意点
働き方改革の一環として2018年1月に厚生労働省により策定された「副業・兼業の促進に関するガイドライン」により、1つの勤め先に自分の人生を委ねる今までの働き方だけでなく副業や兼業などの柔軟な働き方が注目されるようになってきました。給与所得以外の収入については、自分で申告することが必要です。
しかしこれまで給与所得だけで生活してきた勤務医の医師にとっては、申告に対する知識がないことから「どのように手続きを行えばいいのか」などを知っておく必要があります。
-

医師だからこそおすすめな投資方法とは
上手に投資をして資産を増やし、生活のクオリティを向上させている医師がいます。その一方で、投資に全く興味がなく、「資産形成が思うようにできない」と悩んでいる医師もいます。両者の違いは何でしょうか? 大きなポイントは“投資の実態”を知っているかどうかでしょう。そこで今回は、医師におすすめな投資方法についてご紹介します。
-

【連載】医師と学ぶ資産形成|精神科医 前田先生 Part.3
医師の方と一緒に資産形成や税金対策を学んでいくスペシャルコンテンツ。
精神科医前田先生との連載第3回目となる今回は、さまざまな資産運用についてそれぞれのメリット、デメリットを詳しく解説します。 -
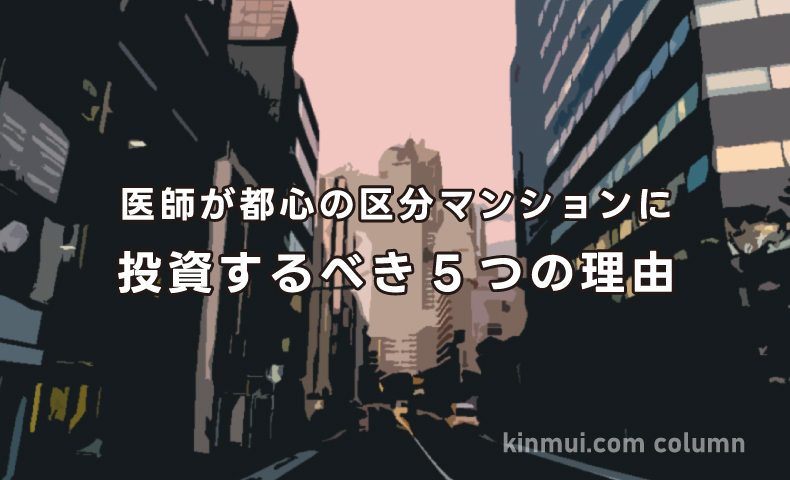
【低利回りなのに?】医師が都心の区分マンションに投資するべき5つの理由
勤務医を含めた医師が不動産投資を始めるにあたっては、まず投資目的および投資方針を定めることが必要です。しかし「一棟物件と区分マンションのいずれを投資対象とするか」と迷っている医師の方も多いのではないでしょうか。どちらの投資対象を選択するかで投資手法や投資のゴール、狙うべきキャッシュポイントおよび利回りなどはすべて異なります。
医師が副業として不動産投資を行う場合は、利回りが低いとしても都心の区分マンションを投資対象にするのがおすすめです。「都心または地方」「一棟または区分」といういくつかの組み合わせの中で都心の区分マンションに投資を推進する理由はどうしてでしょうか。本記事では、低利回りでも都心の区分マンションを推進する理由や優位性について解説します。 -

忙しいけれど家事はしっかりやりたい!女性医師の時短家事術
不規則でハードワークな医師という職業。結婚をしていたり、お子さんがいて育児もあればなおさらでしょう。独身だとしても働き盛りゆえ、自由な時間を捻出しづらいもの。
そこで、毎日必要な家事をおろそかにするのではなく、時短にしてみてはいかがでしょう?効率よく、しかも快適な時短家事術をまとめました。 -
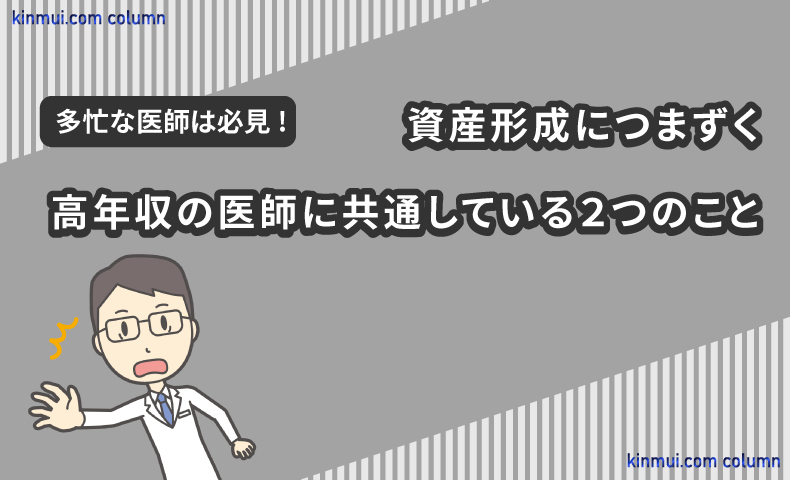
資産形成につまずく高年収の医師に共通している2つのこと
先の見えない世の中、将来のために投資をして資産を増やしておこうと考える方は多いかと思います。資産形成は年収が高いほうが有利な気がしますが、意外にも、高年収の方ほどつまずきやすい傾向があります。今回は高年収の方に共通した資産形成のつまずきポイント2つをまとめました。
-
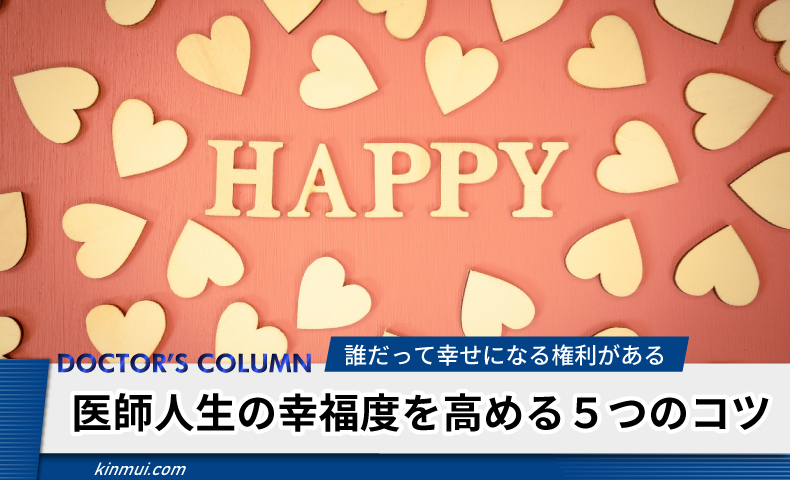
【現役医師連載コラム】医師人生の幸福度を高める5つのコツ
「幸せになるため、努力して医師になったのに…」
そんな気持ちで、今幸福感を感じる事ができていない医師は、一定数いるのではないでしょうか?
医師を目指した理由が何であれ、きっと根底には「良い未来が待っている」という期待感を胸に努力をしてきたはず。
もし今、その期待に対して答えられていないのなら…昔の自分が、可哀想ですよね。
今回は、医師人生の幸福度についてです。 -

地方勤務医による不動産投資実践④ 私がはじめて不動産投資を行ったときの話:後編
『地方勤務医の不動産投資ブログ』のt-nakaです。今回は前編からの続きで無事に購入を終え、その後の経過と考察についてです。
-
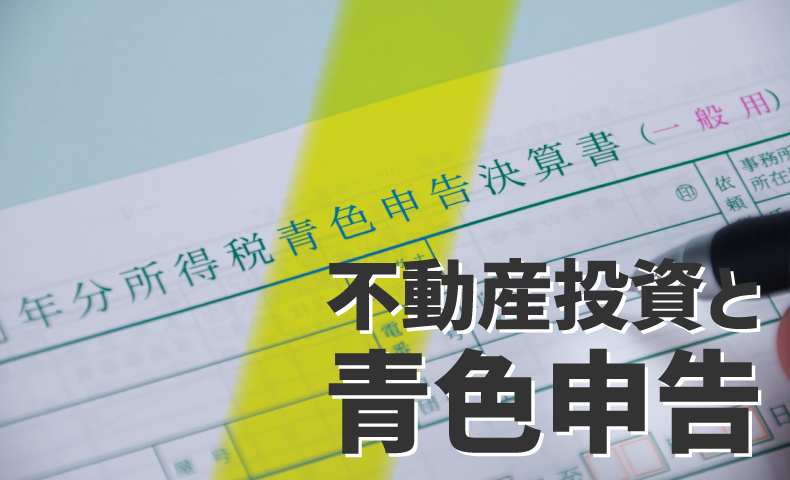
不動産投資をしている医師が確定申告で利用したい青色申告
不動産投資を行っている医師で特に勤務医の方が気を付けたいのは確定申告が必要だということです。申告にあたっては青色申告を利用することで節税につながります。不動産投資で青色申告を利用するにはどのような条件があるのでしょうか。不動産投資で計上すべき収入や経費とあわせ、青色申告必要書類の書き方などを具体的に解説します。
-
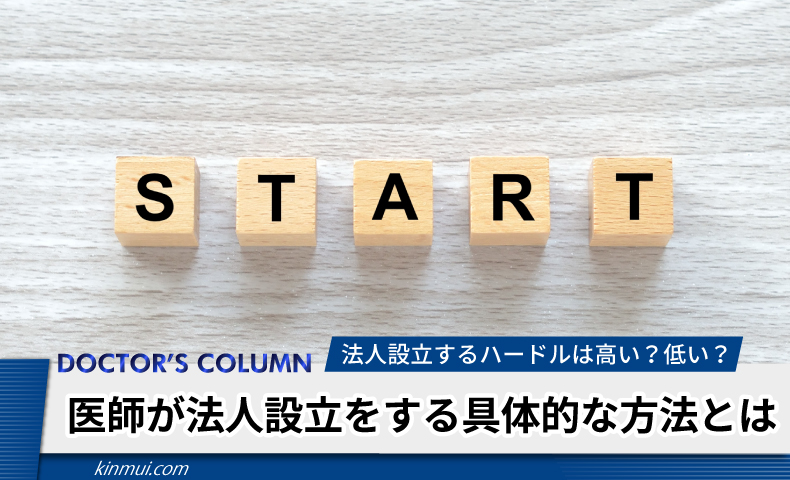
【現役医師連載コラム】医師が法人設立をする、本当のハードル
こんにちは、医師で不動産投資家の大石です。
今回は、医師が法人を持つ上で
■ 一体どんなハードルがあるのか
■ 具体的にはどれくらいの高さのハードルなのか
■ ハードルを超えるためにできる事は何か
を、具体的な事例を考えていこうと思います。 -
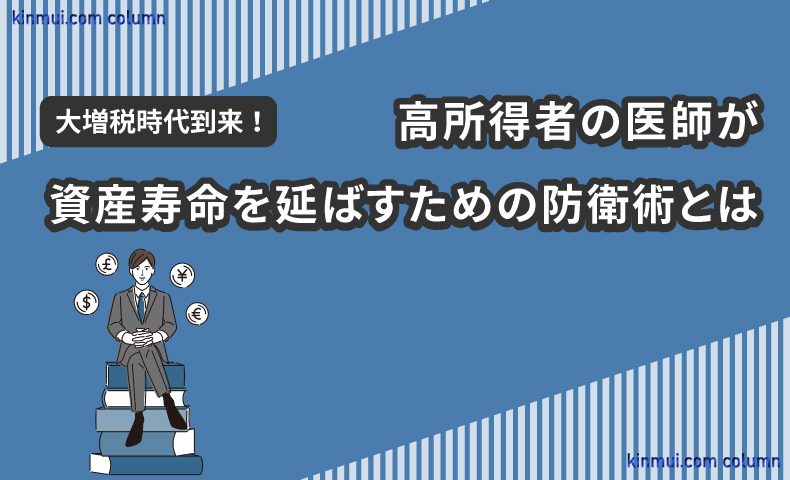
大増税時代到来!高所得者の医師が資産寿命を延ばすための防衛術とは
2020年から所得税の給与所得控除の上限金額が減り、基礎控除も所得により段階的に減額していく仕組みに変わりました。医師を筆頭とした高所得者ほど影響を受けやすい今回の改正ですが、今後もこのような改正がないとは限りません。本記事では、ますます高齢化が進み年金不安も叫ばれる中で自分の資産を守り、資産の寿命を延ばす方法を考えてみましょう。
-

【連載】医師と学ぶ資産形成|精神科医 前田先生 Part.4
医師の方と一緒に資産形成や税金対策を学んでいくスペシャルコンテンツ。
精神科医前田先生との連載第4回目の今回は、医師の投資先として不動産が選ばれる理由を説明します。 -
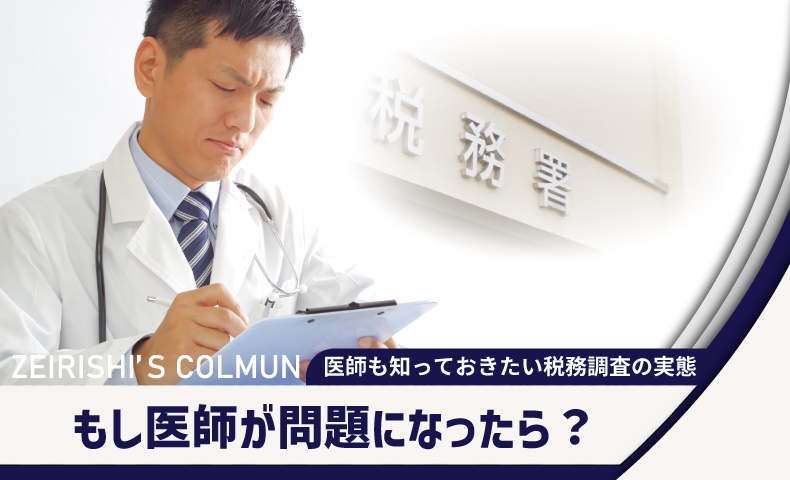
【税理士連載コラム】医師も知っておきたい税務調査の実態「もし医師が問題になったら?」
日本では、所得税、法人税、消費税、相続税といった基幹税においては申告納税制度が採用されています。
申告納税制度とは、納付すべき税額を納税者自らが計算し確定すること(我々税理士はそのお手伝い)を原則とする制度です。
仮にその原則通りに税額計算を納税者の手に全面的に委ねたとしたら誰だって進んで税金を納めたくないと考える方が多いはずなので、納税者が法に定められた通りに申告し納付するということはまず期待できません。 -
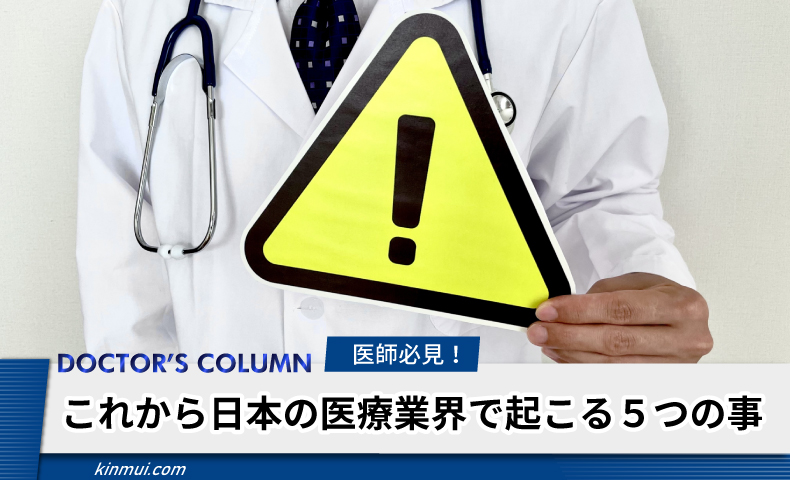
【現役医師連載コラム】医師必見!これから日本の医療業界で起こる5つの事
今、日本の医療業界は変革を迫られています。
新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、その大きな変革の波に対応するべく、動いている医療業界ではありますが、コロナが落ち着いたとしても、日本の医療業界が落ち着く事は無いでしょう。
なぜならば、大きな波が押し寄せる事が、わかっているからです。
一体どんな現象が起こるのか、それに対応するために医師には何ができるのか。
考えていきます。 -

【現役医師連載コラム】医師が不動産投資における「嫁ブロック」を打破するコツ
皆さんこんにちは、医師で不動産投資家の大石です。
いきなりですが、医師が不動産投資をする際、ハードルになるのは何だと思いますか?
ぶっちゃけますと、家族や親族です。
医師であれば融資が出ないとか、そういう事はまず無いのですが、保証人が必要なケースがあります。当然ながら、家族や親族に保証人になってもらうのであれば、まず何をどういう理由でお金を借りるのか、説明しないわけにはいきませんよね。
その時、軽い気持ちで説明して、思いのほかオッケーをもらえない、家族や親族から何なら反対される、なんて事もあります。
今回は、そんな医師が不動産投資を始める上で1つのハードルになる「家庭」の問題です。 -
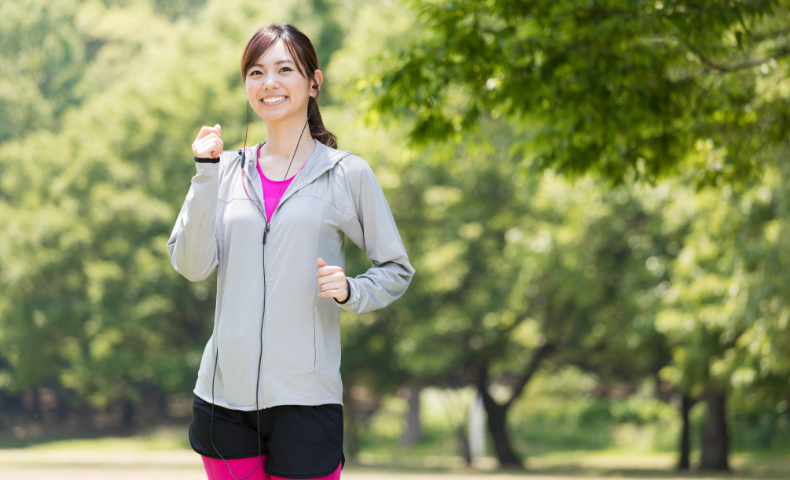
多忙な医師が実践すべき簡単健康術
患者の健康のために、日々ハードワークを続ける医師。多くの人から感謝される素晴らしい仕事ですが、医師の家族からすれば「多忙で倒れないか」「本人の体も大切にしてほしい」と常に心配が絶えないものです。そこで今回は、医師が実践すべき「簡単健康術」をまとめます。ぜひ今日からやってみてくださいね。
-
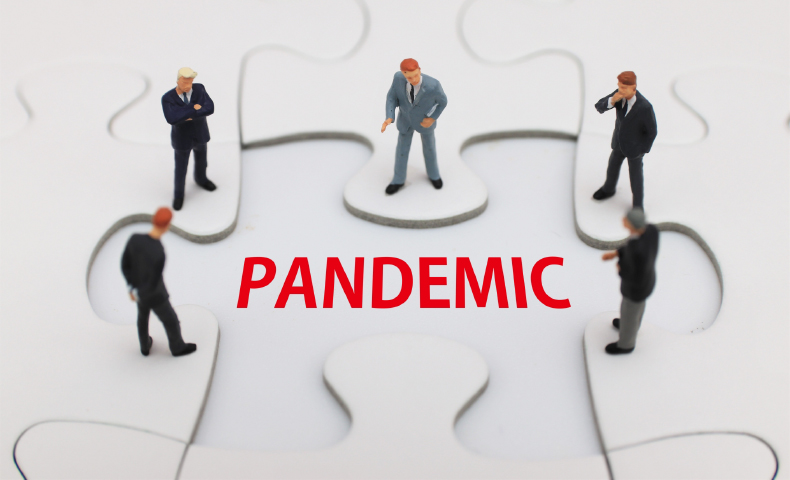
【医師執筆】コロナ禍で変わった医療業界の今後
東京都内では第2波で一日あたりの感染者数が次第に増えてきている現在ですが、今回のCOVID-19は今までの医療業界の流れやルールを大きく変えることになるでしょう。
今後、あらゆる医療は常に新型コロナウイルスのことも考慮した体制を取る必要があります。
現在、私は某大学病院で内科医をしつつ、市中病院で3次救急もやっていますが、この半年でいろんな変化が起きました。
今回は医療業界の中でも私が勤務する①大学病院の内科、②3次救急の現状と今後についてお伝えできればなと思っています。 -

「高収入だけど、老後の生活が心配…」勤務医の悩みをFPが解消!Part.2
今回も引き続き、20年間メガバンクに勤務されたご経験をお持ちの洲濵拓志氏をお迎えし、勤務医の「お金の悩み」についてのスペシャルインタビューをお届けします。
第2回目は、勤務医の老後に向けた資産形成について、ファイナンシャルプランナーである洲濵氏にお話を伺いました。 -
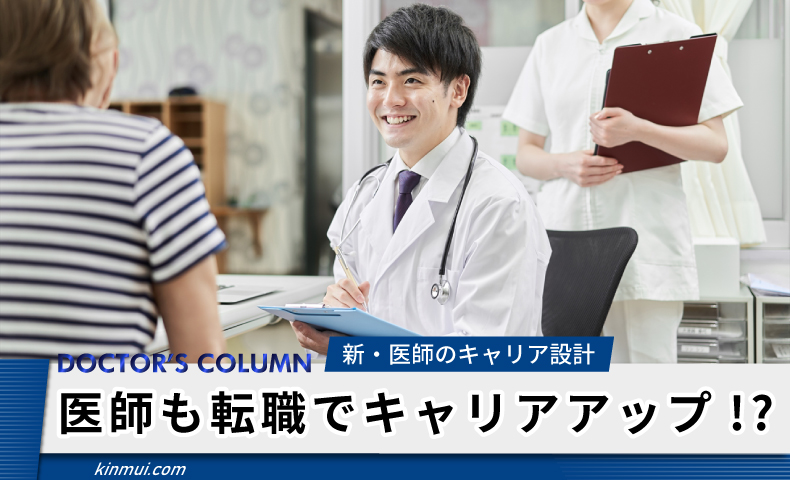
【現役医師連載コラム】医師の転職がフツーの時代、新・医師のキャリア設計とは?
少し前まで、医師だけで無くサラリーマンでさえ、転職は珍しいものでした。
今となってはどうでしょうか?サラリーマンに至っては「転職してステップアップして行かない方が、おかしい」という意見さえ、散見されます。
流石に医師に、この理論をそのまま転用するのは、少しおかしいとは思いますが…とはいえ医師も転職がフツーの時代になってきました。
明らかに時代の潮目が変わった昨今、医師のキャリア設計も、既存のものとはまた別で、組み替える必要が出てくると思われます。 -

【現役医師連載コラム】医師は病院のリーダー!優れたリーダーに必要な3つの絶対条件
医師は病院内において、あらゆるチームにおけるリーダーの役割を果たさねばなりません。医師免許があるがゆえ、決定権が医師にあるアクションが病院には多く、リーダーに医師がいないとあらゆる意思決定が遅れてしまうからです。
しかしながら、医師としてのスペシャリティ、専門性の高さと、組織におけるリーダーとしての力は必ずしも比例しません。
今回は、医師が病院のリーダーとして力を発揮するために、必要な条件についてです。 -

家庭の事情? ハードワーク? 医師が転職を決断する理由とは
社会的地位が高く、患者さんから感謝されることの多い医師も、決して“万能の神”ではなく、“ひとりの人間”です。生きていれば何かのきっかけでつまづくこともあり、仕事においてもそれは同じで、さまざまな理由から職場を変えることもあるでしょう。医師はどんなきっかけで、今の職場を離れる決心をするのでしょうか?
-

【医師執筆】withコロナ時代を乗り切る~勤務医編
2020年7月10日時点で東京都内のコロナ感染者数が1日200人以上と第2波が来つつある中、コロナウイルスが落ち着くまでwithコロナというスローガンが建っています。
今後、コロナウイルスがどういう結末をたどるかわからないためある意味ではこのスローガンは正しいと言えるでしょう。
勤務医として働く医師だけでなく医療従事者全員も常にコロナウイルスが蔓延していると考えながら医療に励む必要があります。 -
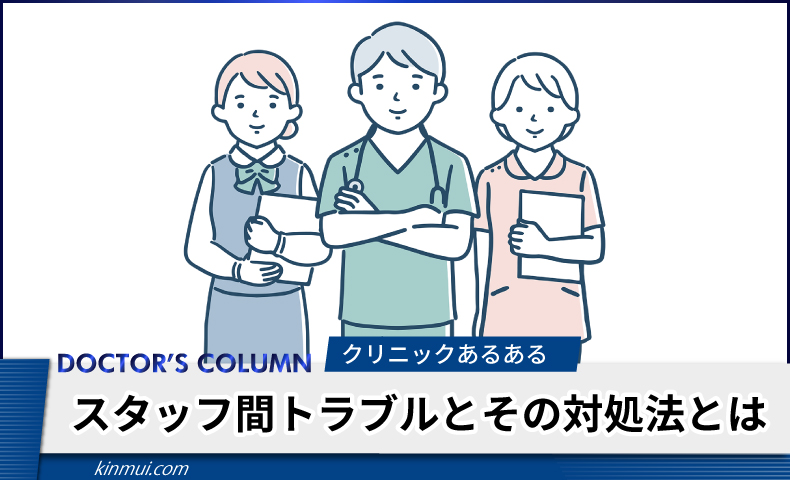
【現役医師連載コラム】クリニックでよくあるスタッフ間トラブルとその対処
院長の頭を最も悩ませるもの、それは「スタッフ間トラブル」です。言ってしまえば、人間関係のトラブル。
病気は治せるけど、人間関係を修復させるのが不得意な先生、結構いらっしゃるのではないでしょうか。
今回はそんな、クリニックでよくあるスタッフ間トラブルと、その対処についてです。 -
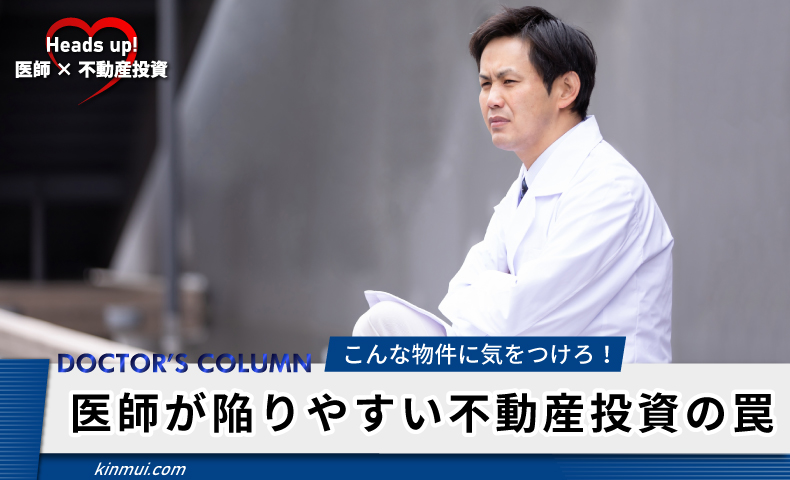
【現役医師連載コラム】こんな物件に気をつけろ!医師が陥りやすい不動産投資の罠
前回の記事<現役医師が警告!こんな不動産業者には注意>に引き続き、今回も不動産投資の注意点についてです。
今回フォーカスするのは、物件ベースです。不動産投資において、物件を吟味する事は当然重要なのですが、吟味をする上で注意しなければいけない、避けなければいけない物件が存在しますので、解説していきます。
特に、このような方は注意しなければなりません。
・とにかく仕事が忙しい
・プライベートの時間はなかなか確保できない
・性格的には、結構せっかちな方だと思う
・あんまり不動産に時間を割きたくない、考えたくない
少しでも「自分が当てはまるかも…?」と思った方は、注意して下さいね。 -

勤務医が今からできる資産形成とは? 税理士法人代表×不動産会社代表
高所得者を中心とした増税や働き方改革などめまぐるしく変化する現代において、収入について考える機会が増えた勤務医の方も多いのではないでしょうか。とはいえ、忙しい毎日の中で、そのために割ける時間も限られていることだと思います。今回は、勤務医が今からできる資産形成と税金対策から不動産会社の見極め方まで、共にドクターを専門とする、税理士法人代表と不動産会社代表に語り合っていただきました。
-

北海道リレーインタビュー VOL.1小林範子先生(北海道大学病院婦人科 講師)
北海道で活躍されている医師の方にインタビューを行い、ご自身の取り組まれている医療分野やキャリア、資産形成などについてお聞きする本企画。
第一回は北海道大学病院婦人科の小林範子先生にお話を伺いました。女性医師として第一線でご活躍されている小林先生はどのようにしてキャリアを築かれ、医療現場にどんなご意見をお持ちなのでしょうか。 -

【現役医師連載コラム】変化する時代と、キャリア別の「専門医」の価値
医師にとって「専門医」という概念は、切っても切れない関係にありますよね。
そんな「専門医」ですが、近年は国の介入を受けて新専門医が始まっております。おそらくそろそろ新しい制度で専門医を取得した先生方が、チラホラいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、そんな「専門医」の必要性を、時代の変化に合わせて、キャリア別にどういう選択をしていくのが良いのか、検討してみたいと思います。 -
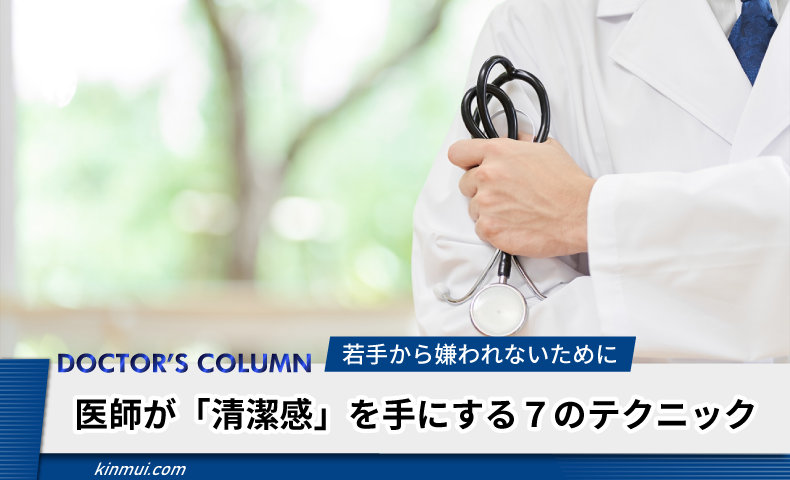
【現役医師連載コラム】若手から嫌われないために。医師が「清潔感」を手にする7のテクニック
一般的なサラリーマンであれば、清潔感は営業成績に直結します。清潔感を得る努力を怠るわけにはいかないのです。
しかしながら病院で働いている医師であれば、正直なところお客さんである患者さんにとって、清潔感は重要な価値観ではありません。病院で働いている医師の清潔感は、ないがしろにされがちです。
では、医師は清潔感が無くても良いのでしょうか?患者さんが強く求めていなければ、無視してしまっても良いのでしょうか?いいえ、医師の清潔感について厳しい目で見る人たちがいます。同じ病院で働いているスタッフです。
特に若手の医師、研修医、看護師は医師の清潔感に対する目は厳しいと言えます。若手から嫌われないためにも、清潔感にまで気を配れる医師は優秀です。 -

医師のワークライフバランスと充実したセカンドキャリアの選び方
ワークライフバランスのために職場を変えることもキャリア形成の一つの方法です。国を挙げて働き方改革が推進されている現在、こうしたワークライフバランスを重視したセカンドキャリアを選択する医師が増えてきています。
本コラムでは、働き方を変えることで生活はどう変わるのか、ワークライフバランスが保てる医師の働き方、セカンドキャリアを充実させるために必要なことを詳しくご紹介していきます。 -

ファイナンシャルリテラシーを身につけて、お金と上手に付き合おう
世界の先進国の中でも「群を抜いてファイナンシャルリテラシーが低い」と言われている日本人。
勤勉で真面目ではあるものの、お金の使い方と向き合っている人は少ないようです。でも、お金は生きていくうえで欠かせない大切なもの。そこで今回は、お金を守る、増やすにはどうしたらよいか、お金を上手に使うにはどうすればよいかを解説します。 -
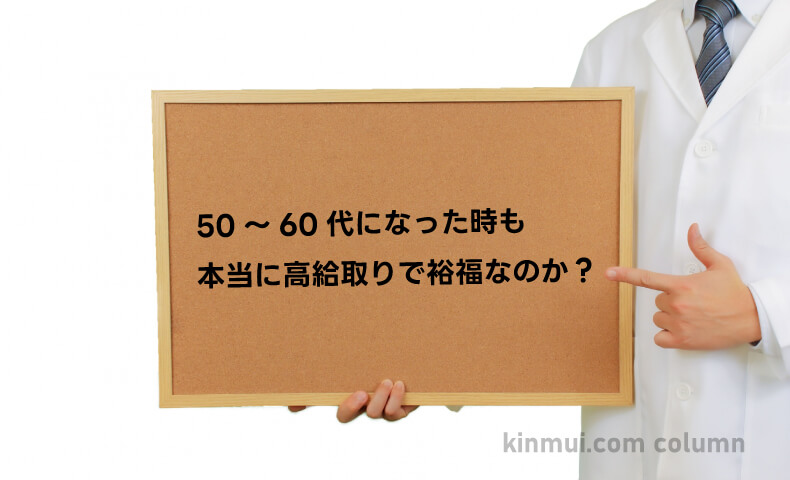
30代医師が50~60代になった時も、本当に高給取りで裕福なのか?
経済不安、コロナ禍と次々と襲ってくる不測の事態。世界経済と国の将来が不安定になっていく中、数十年後に医師という職業は、今のシニア世代が享受するような高収入で安定した職業なのでしょうか?今回は医師を取り巻く職場環境の変化、将来の資産形成を含めたお金の話をまとめました。
-
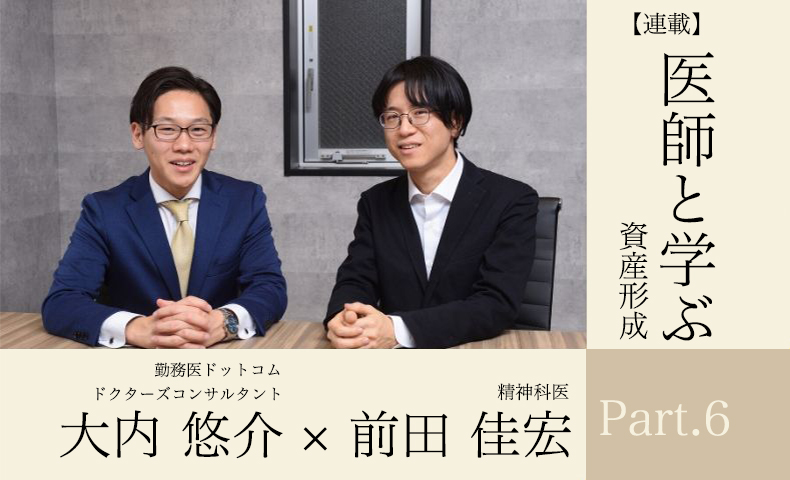
【連載】医師と学ぶ資産形成|精神科医 前田先生 Part.6
医師の方と一緒に資産形成や税金対策を学んでいくスペシャルコンテンツ。精神科医前田先生の連載最終回となる今回は、セミナーの参加者さまからもご相談が多い物件選びのポイントについて解説いたします。
-

地方勤務医による不動産投資実践② 区分マンション投資について―もしも都市部に住んでいたら(大都市圏の場合)
こんにちは、『地方勤務医の不動産投資ブログ』のt-nakaと申します。今回の区分マンション投資についての話題ですが、自分が都市部に住んでいたらどのようにするかを考えてみました。
高所得者は不動産投資を行うと節税ができるという謳い文句がありますが、半分正解で半分間違いだと思います。給与所得と不動産所得は損益通算をしなければならないので、赤字になれば高い税率分が還付されるし、黒字になれば高い税率分を納税しなくてはいけないのです。不動産購入初年度は登記費用や不動産所得税などがあるため赤字化は容易ですが、それ以降は毎年赤字で節税とはなかなかいきません。赤字ということはその分儲かっていない状況ということなので、投資としても割に合わないと思います。
最近、副業が話題に上がること多くなりましたが、医師に対する金融機関に対する信用は大きいもので、不動産投資というよりは、長期的に不動産賃貸業を副業で行う方向をおすすめします。自分の場合も大都市圏に住んでいたら同じように考えると思います。そうなると5戸10室以上で事業規模とし、確定申告で青色申告を目指すことになります。
開業をすることをあまり考えていない勤務医であれば、いわゆるサラリーマンであることのメリットと事業主であることのメリットを両方享受できる可能性があります。勤め先の社会保険に入りながら、間接経費まで使えるのは大きなメリットです。また、妻が専業主婦のケースの場合は配偶者控除が使えなくなってしまいましたが、手伝ってもらい青色専従者給与といった形で経費とすることも可能です。
以上のようなことから、まずは税金面で優位になれる5戸10室を目指すことになると思います。 -

勤務医の健康事情(勤務時間と食事について)
勤務医として働いている医師の健康事情について『日本医師会』が1万人の勤務医を対象に行ったアンケートが公表されています。今回はそのアンケートと他資料をもとに、勤務時間や食事などの「勤務医の健康事情」について考察します。
-

投資物件はどう選ぶ?10年運用シミュレーション 都心の築古ワンルームマンション編
「都心エリアの築古物件が気になるけど、中古物件との違いはどうなんだろう」
不動産投資を検討する際、その入り口となるのが投資物件の選び方です。同じ中古物件であっても、築古となると運用方法が変わってきます。
この記事では毎回モデルケースを設定し、購入から10年後までの収支をイメージしていきます。
・過去記事「都心の中古ワンルームマンション編」( https://ft-academy.jp/2018/03/23/used_rent_simulation/ )
今回のモデルケースは「都心の築古ワンルームマンション」です。(文章中の金額はあくまでもモデルケースを想定した概算金額です) -
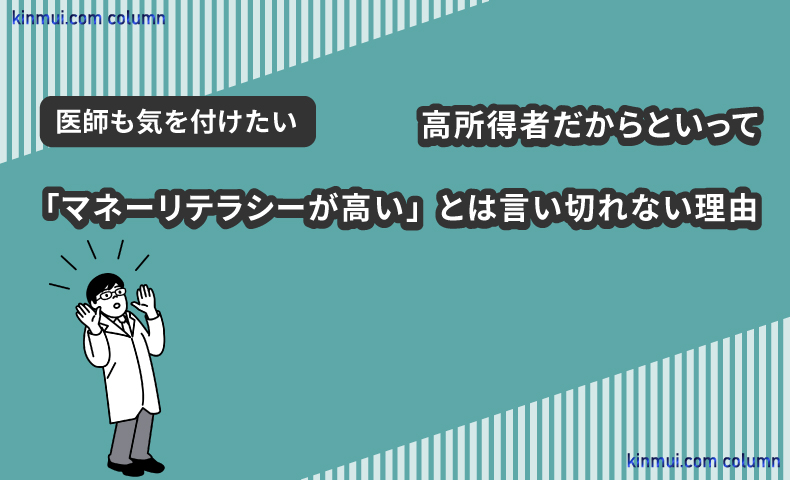
【医師も気を付けたい】高所得者だからといって「マネーリテラシーが高い」とは言い切れない理由
「すでに億単位の資産を保有している人」「数百万円規模の資産を保有している人」では、どちらがお金のことを深く理解していると感じるでしょうか。
一般的に考えるのであれば保有資産が大きい人ほどお金を味方につけていることが推測されます。よりお金のことを深く理解して使いこなしていると答える人も多いでしょうが、実際にはそうとは限りません。
数百万円規模という現実味のある資産規模の人には「資産をもっと増やしたい」という思いがある可能性が高いのではないでしょうか。また保有している資産規模では安心の老後を迎えられないと危機感を持っているかもしれません。2020年6月には金融庁でさえも「老後資金が2,000万円不足する」と指摘したわけですから「もっと資産形成を進めて安心を得たい」と考えるのは自然なことです。
お金に対する理解のことをマネーリテラシーといいますがこの比較のように「お金を多く持っているからといってマネーリテラシーが高い」とは言い切れない部分があります。むしろ高所得者や先祖代々の資産家に生まれた人のほうがお金を特に増やす必要性を感じない人もいるでしょう。なかには多くの資産を預貯金にしていたり金融機関から助言された通りに運用していたりする人も少なくありません。
すでに大きな資産を保有している人は、そうでない人と地位が逆転することはないと感じている人もいるのではないでしょうか。しかしマネーリテラシーの格差が広がると逆転が起きることも絵空事ではなくなります。これから求められていくのは「お金を持っている」「お金を稼ぐ」といったことだけではなく「お金を守って育てる方法」です。
本記事では、そのための基礎となるマネーリテラシーについて解説します。 -

不動産投資で経費として計上できる項目にはどのようなものがあるか
「不動産投資」は、「不動産事業・賃貸経営で長期的に利益を得る」ための投資です。
不動産事業では、賃貸経営の収支決算を行うことで所得税を節税することもできます。
今回は、そういった税金と密接な関連のある経費について、不動産投資(賃貸経営)で経費として計上できる項目にはどのようなものがあるかをまとめました。 -
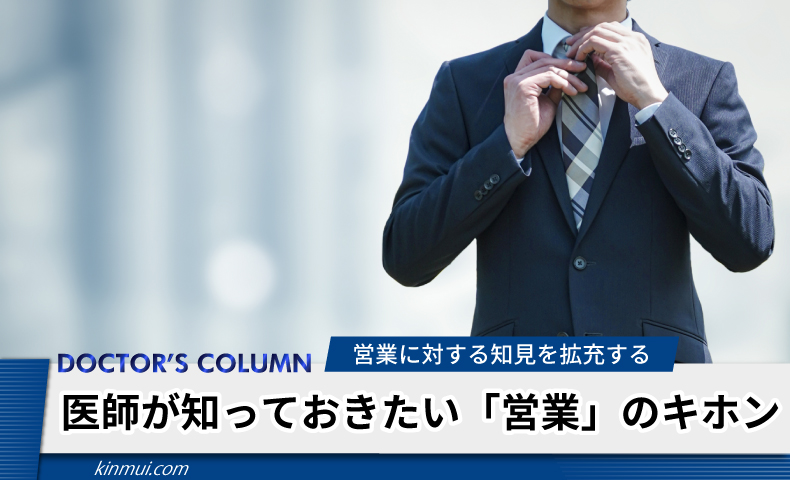
【現役医師連載コラム】医師が知っておきたい「営業」のキホン
医師という立場上、営業マンから営業される事は結構あると思います。
営業というスキルは、実はかなり世の中に広く伝わっており、また高い影響力を持っています。
例えば、今や高学歴の新卒大学生がこぞって入社したがる、サイバーエージェント。この会社も実は、IT関係のイメージがありますが、元々は営業会社です。創業者である藤田さんの書籍や、旧ライブドアの方の書籍を見ると、よくわかると思います。今も営業という社風は、濃く残っているようですね。
営業というスキルは、使えば強力です。そして知っていれば、営業される側になった時の守りとしても効果を発揮します。営業の知見を頭に入れておく事で、人生におけるあらゆる営業行為にまつわる、攻撃力と守備力を高める事ができます。
1つの知見で攻守ともにスキルアップする知識は稀有ですので、キホン的な事だけでも覚えておくと良いでしょう。 -
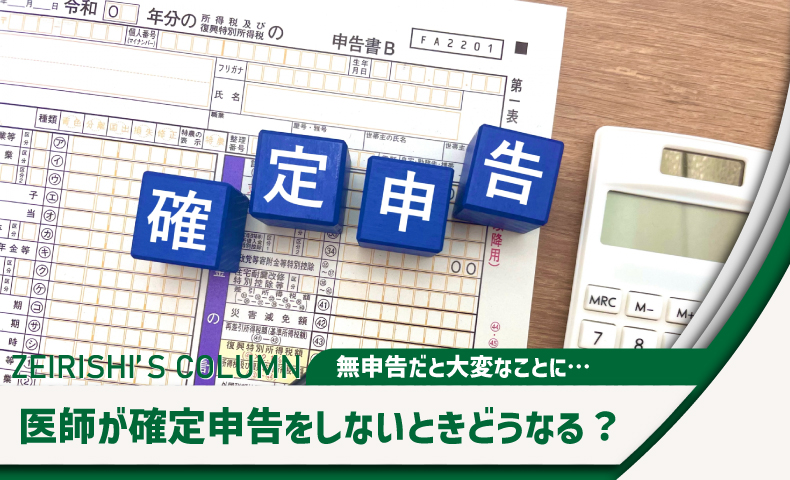
【現役税理士連載コラム】医師が確定申告をしないときどうなる?
令和3年11月に国税庁から、「令和3年事務年度における所得税及び消費税調査等の状況」について公表されました。(勤務医師の税務調査事例については、次回に譲りますが、)
「4 無申告者に対する調査状況」にも記載しているとおり、無申告者に対しては、税務署としても的確かつ厳格に対処するため、増加傾向にあります。私どもの事務所にも、無申告の方から調査立会の依頼が今年は多くかかってきていることから、コロナがおさまりつつある中で調査が増えつつある状況が伺えます。医師の方の場合で、確定申告をしない理由として様々考えられますが、医師の方が申告をしない場合は、主たる所得が大きいため申告漏れの税額も大きくなるため、注意が必要になります。
それでは、無申告の場合にどのような影響があるか、一般的なケース、医師の場合に特に注意が必要なケースについてみていきたいと思います。 -

【withコロナでスタイル変化】医師を始めとした高所得者に人気のゴルフとは
医師(勤務医)やビジネスの成功者に人気のゴルフですが、未経験者にとっては「なぜそれほど好まれるのか?」と不思議に感じる人もいるのではないでしょうか。また関心はあってもどんなコロナ対策が取られているか気になる人もいるかもしれません。
コロナ対策のおかげでゴルフはより一層初心者が挑みやすい環境になっています。本記事では、withコロナでスタイルが変化しているゴルフの魅力について解説します。 -
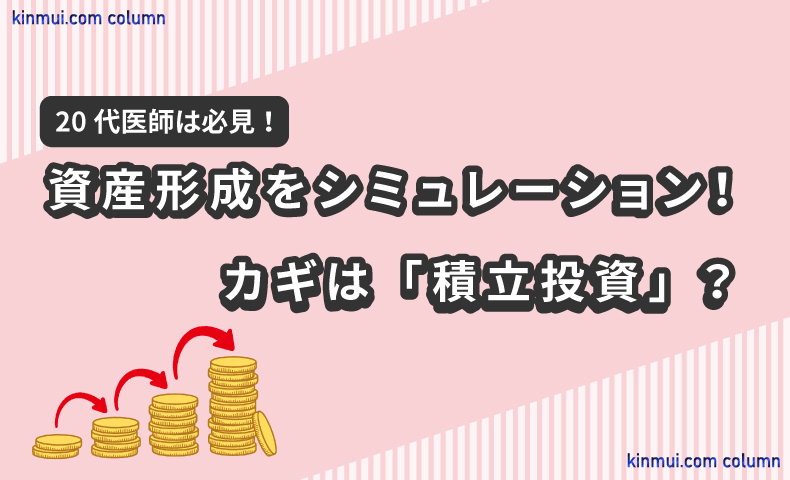
20代医師の資産形成をシミュレーション!鍵は「積立投資」
「人生100年時代」という言葉が一般的になったり、コロナ禍において経済の先行きが不透明になったり、20代の医師であっても資産形成に興味がある人は多いことでしょう。
資産を形成するにはいろいろな方法がありますが、20代の医師が資産形成するときに鍵となるのが「積立投資」です。しかし、毎月いくらを積立して、利率何%でどれくらいの期間、運用し続けたらどれくらいの金額になるか、ぱっと回答できる人は少ないのではないでしょうか。
今回は、積立投資とは何か、医師でもなぜ20代の資産形成に積立投資が有効なのか、20代が積立投資で資産形成する場合のシミュレーションなどを解説します。 -

融資に大きく影響する個人信用情報と開示方法
融資に大きく影響するものとして、個人信用情報があります。ここでは、個人信用情報の概要や役割、具体的な開示方法について解説していきます。
-
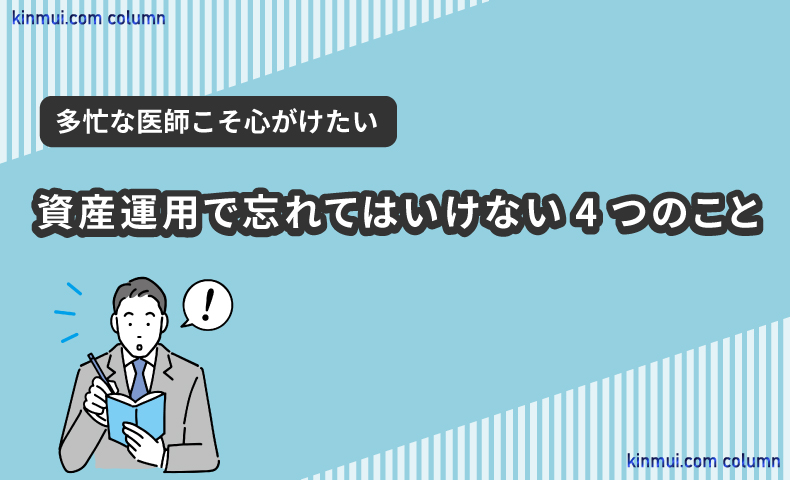
特に多忙な医師こそ心がけたい!資産運用で忘れてはいけない4つのこと
医師中でも特に勤務医や経営者、高収入の会社員といった人は、仕事が忙しいだけでなく仕事以外の時間を勉強や自己研さんなどに有効活用している人も多いのではないでしょうか。一方で、そのままでは資産運用に回せる潤沢な資金があっても「運用するために割く時間と労力がない」という状況に陥りかねません。属性が高い人は、銀行や証券会社、不動産会社などからの営業電話も頻繁にかかってきます。多種多様な金融商品や不動産の資産運用を勧誘されるのです。
このような背景から多忙な人たちは、資産運用に関する知識がない状態で営業パーソンに勧められるまま巨額な資金を投じている人も少なくありません。結果として巨額な借金を背負ったり損失を出したりすることもあります。これは、資産運用に関する知識や割く時間がないことが原因なのではありません。
多忙な人たちに適した資産運用の方法を知らないことが根本的な原因なのです。本業が忙しく資産運用に時間を割けないのであればそれを前提とした資産運用の方法を心得ておきましょう。本記事では、多忙な人たちにとって資産運用で忘れてはいけない4つのことについて解説します。 -

女性医師が働き続けるためのヒント
女性医師は、男性医師よりも、結婚や出産・育児によって“キャリアの中断”を余儀なくされるケースが多いものです。しかし、その実情はあまり知られていません。そこで今回は、女性医師の置かれた現状を把握するとともに、女性医師が働き続けるための工夫やヒントを探っていきます。
-

勤務医でも確定申告が必要なケースとは?
毎年2~3月になると、「確定申告」という言葉をよく聞くようになります。確定申告は正しく納税をするための手続きのことですが、勤務医として働く人の中には「確定申告は開業医が行う手続きで、勤務医の自分には関係ない」と思っている人もいるかもしれません。
しかし、実際はそうとも限りません。実は勤務医として働いている人でも「確定申告が必要なケース」があります。今回は、その具体的なケースと、ノウハウについて解説します。 -
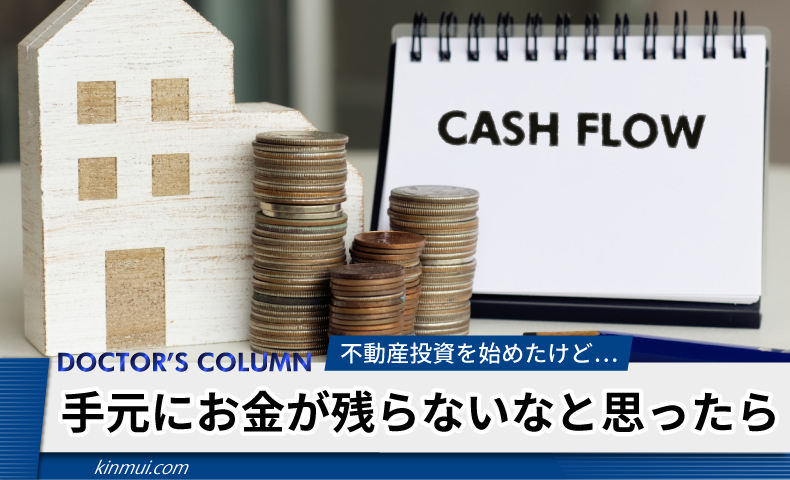
【現役医師連載コラム】不動産投資でキャッシュフローが出ない時の対処法
こんにちは、医師で不動産投資家の大石です。
「不動産投資を始めたは良いけど、思ったより手元にお金が残らないな」
と思う方、いらっしゃると思います。
これは「キャッシュフローが出ない」という言葉に置き換えることができますが、このような状態に陥っている状態から、脱出するためにできることは、実は結構たくさんあります。
全てが実行できるかは状況次第ではありますが、もしこの記事を見ている方で「うんうん、確かに全然手元にお金が残らないな」という方は、少しでも参考になる要素があると思います。自分の手元の物件と見比べて、実践に移してみて下さい。 -

地方勤務医による不動産投資実践③ 私がはじめて不動産投資を行ったときの話:前編
こんにちは、地方在住アラサー勤務医のt-nakaです。
本業のかたわらでアパート2棟(3DK×6部屋、2K×6部屋)、貸家1戸の不動産投資をしております。2016年に本格的に参入し、青色申告事業者として家賃収入はおよそ1,000万円/年、借入金は8,000万円です。
アパート2棟目の購入がほぼ確定してから『地方勤務医の不動産投資ブログ』というブログを書き始め、現在に至ります。今回は不動産投資を始めるに際し、最もハードルの高い「不動産の購入」について、自分の経験とそれに対する考察について書いていきます。実際に不動産を購入したのは2016年5月と2018年8月と最近なので、これから不動産投資を始めたい、始めたばかりという方にとって少しでも参考になればと思います。
属性としては、某地方都市で勤務医をしており、家族構成は専業主婦の妻と子ども3人です。あくまで自分の属性をもとした不動産投資の経験・戦略等になりますので、ご容赦ください。 -
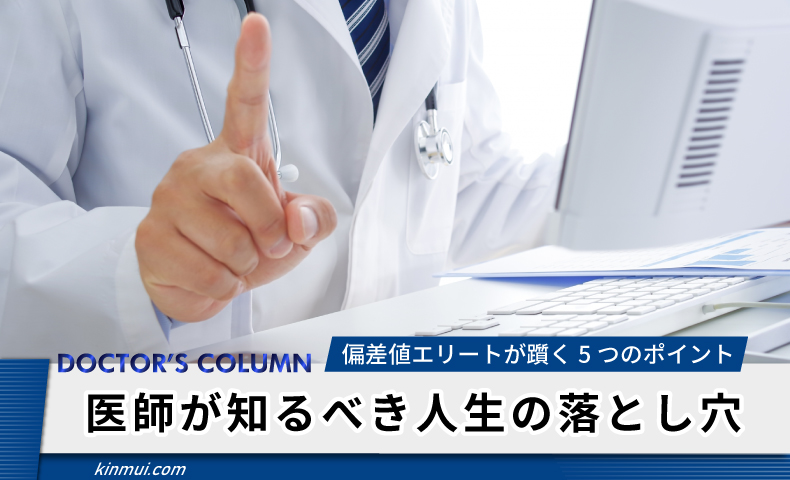
【現役医師連載コラム】偏差値エリートの医師が知っておきたい、5つの落とし穴
医師という生き物は、いわゆるエリートです。
近年の医学部人気もあってか、その傾向はますます強まっていると感じております。
僕自身は、地方出身で高校時代に塾なども特別通っておりませんでしたが、大学に入るとそのエリート具合に、驚愕しました。
そして同時に、それは弱点だとも思いました。
今回はそんな、偏差値エリートの医師ならではの、落とし穴についてです。
-
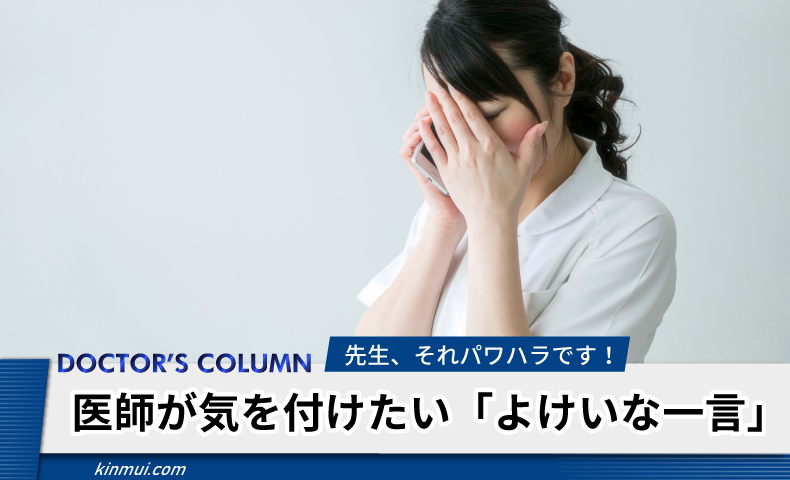
【現役医師連載コラム】“それパワハラです”医師の「よけいな一言」の例と、言いかえ方法
昨今、ハラスメントという言葉がとにかく浸透しました。
パワハラ、アルハラ、モラハラ…○○ハラスメントが、世の中に一体どれくらいあるのか、把握するだけでも困難です。中には度が過ぎるような、過度なハラスメント対策と思われるものもありますが…
窮屈な時代になりましたね。
とはいえ、中には本当に許されないハラスメントも存在します。
そんな「医療業界でのハラスメント」について
「まずこれは間違いなくハラスメントだけど、医療業界では黙認されている」
水準のハラスメント、危険水準のハラスメントについて、まとめました。 -

働き方改革が進む現在、注目される「産業医」という働き方
少子高齢化や労働スタイルの多様化など、働き方の変化の過渡期にある日本。政府は多様な働き方の実現を目指す政策「働き方改革」を推進していて、これは医療界にも大きな影響を与えています。たとえば、一般企業で働く産業医。社員のメンタルケアを行い、うつ病の予防に貢献する産業医はさらに重要な役割を持つようになるでしょう。
独立・開業とは別のステップアップとして注目が集まる産業医について詳しく解説します。 -
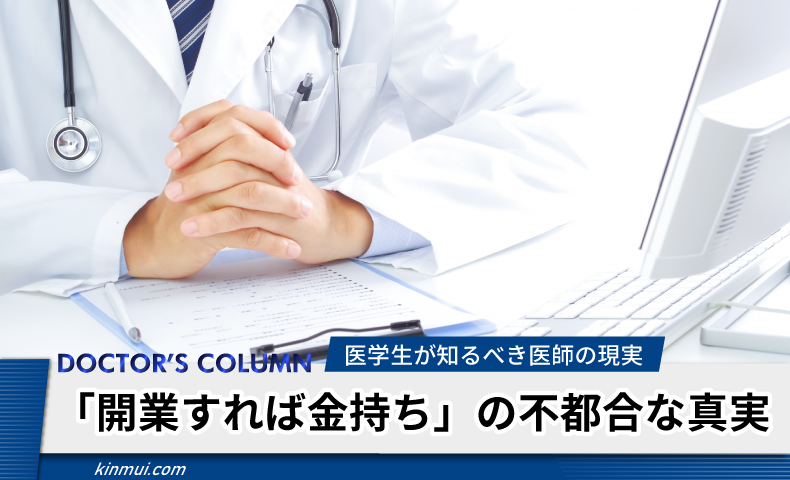
【現役医師連載コラム】医学生が知るべき「開業すれば金持ち」の不都合な真実
いきなりですが
「40〜50代くらいになったら、開業すれば良い」
と思っている医学生、研修医の方はいませんか?
その予想は、もしかしたら楽観的過ぎるかもしれません。
・開業したら金持ちになれる・医局内の出世にある程度限界が見えたら、開業だ
こんな医師のキャリアのイメージが、僕にはありました。
しかしながら実際、近年の日本の医療を取り巻く環境は大きく変わってきています。
特に、医療費削減の流れは強烈です。 -

【現役医師の投資履歴】2022年の繁忙期を終えて
みなさんこんにちは、医師で不動産投資家の大石です。
不動産の世界では、2月と3月が繁忙期です。退去も入居も、かなりの数がこの月に一気に流れ込みます。最近はコロナの影響で、転勤を若干あえてずらす企業なども出てきているようですから、4月に多少ずれ込むところもあるみたいですけどね。
さて、そんな繁忙期を終えて、医師である僕が不動産投資家として何をやって、一体どうだったのかという事について、話そうと思います。 -

【税理士連載コラム】ドクターが確定申告を家族に代理でしてもらうのは合法?違法?
一年間の所得に対してかかる所得税を申告・納付するのが、いわゆる確定申告です。
給与所得がある場合、不動産所得がある場合、一時所得がある場合、生命保険控除や住宅ローン控除がある場合など、個人個人によってそのケースは様々ですね。
確定申告の手引書を見ても自分がどこに該当するのかわかりづらく、手続きが煩雑で、忙しいドクターとしては家族や知人に代理でお願いしたいと考えるのも無理はありません。実際そうしているというのも珍しい話ではないでしょう。
しかし、そもそも確定申告を医師の家族などがするというのは合法なのでしょうか、それとも違法になるのでしょうか。 -
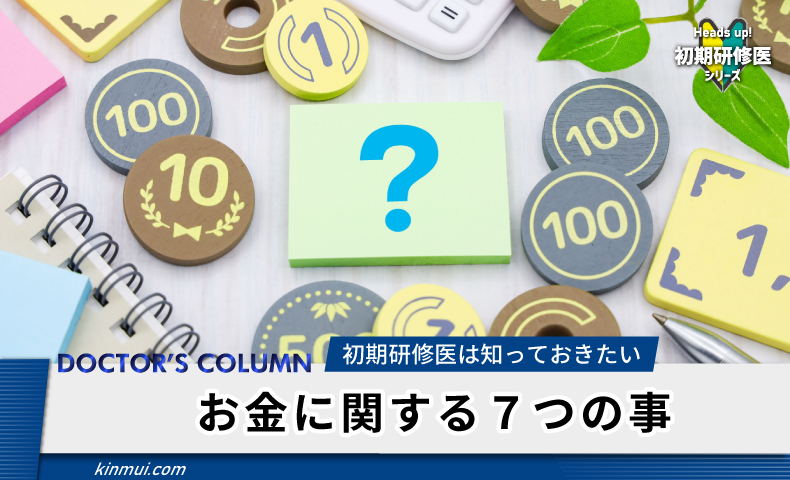
【現役医師連載コラム】初期研修医が知っておくべき、お金に関する7つの事
医学の勉強と部活や飲み会に明け暮れた医学生時代から一転、いきなり社会に出て初期研修医として活動する前に、お金について理解しておく事は非常に重要です。
今回はそんな中でも、特に重要だと思う事実を7つピックアップしました。 -
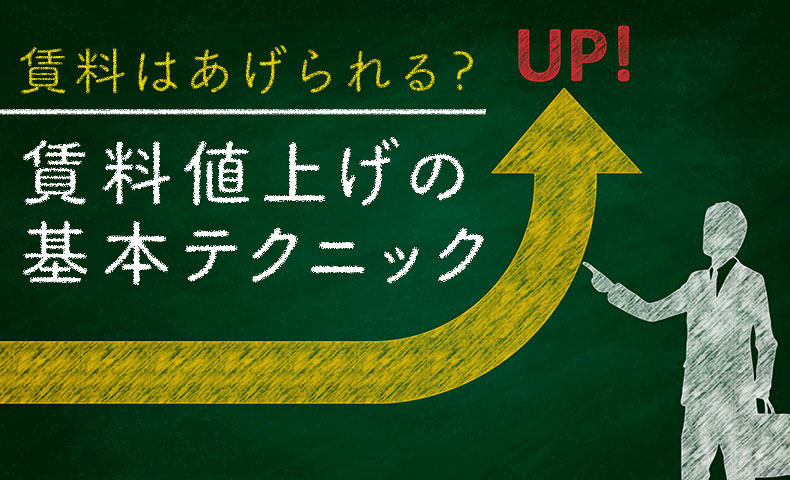
賃料はあげられる?賃料値上げの基本テクニック
「管理物件の賃料、なんとか上げる方法はないのだろうか……」
不動産投資を検討する上で、「賃料」は気になる要素のひとつではないでしょうか。
賃料が下がってしまったら、キャッシュフローが悪化して……と不安になります。
そんな賃料ですが、実は上げる方法があるのです。
本記事では、賃料をアップさせるための基本的なテクニックを紹介していきます。 -
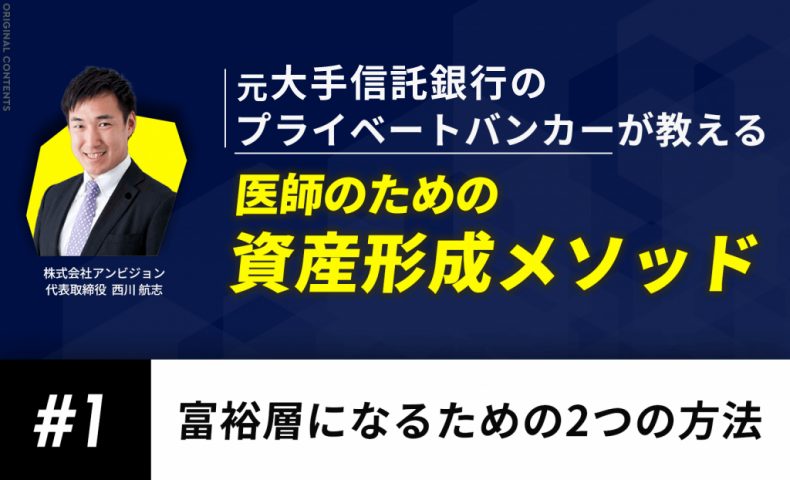
【元銀行員が教える】医師にできる 「資産管理会社」を使った節税対策とは?【前編】
本記事は過去に勤務医ドットコムで開催したセミナーの内容を記事にしています。
「富裕層って何?」「どうしたら富裕層になれる?」というのは、勤務医の皆さんであれば大いに気になるところでしょう。
私がこれまで勤務医の皆さんの資産形成コンサルティングをするなかで学んだのは、「富裕層の永続性」です。
この世の中は、お金持ちがさらにお金持ちになり続けるという仕組みになっており、この流れは今の時代、ITの進化でよりスピーディーになっています。
これは逆に言えば、その仕組みを学んで、流れに乗って一旦富裕層になってしまえば、永続的に富裕層でいられるということになります。
世の中の富裕層はほぼ100%、資産保有をしている資産家で、いわゆるキャッシュリッチの方はお金持ちではありますが、それだけではプライベートバンカーはつきません。富裕層になるためにはまず、資産を保有していくことを考える必要があります。
そこで本記事では、勤務医の皆さんが富裕層になるためのポイントを解説していきましょう。 -

「青色申告」で大幅節税!? 開業医なら知るべき確定申告の基礎知識
医師の中でも勤務医の将来は大きく2つにわかれます。大学病院で働いている場合、勤続して教授の道を目指す人もいることでしょう。一方で、多くの勤務医として働いている医師が望んでいるのは「開業」という道です。自身でスケジュールを管理でき、収入も増えることから、そのメリットは大きいといえます。開業後の利益を最大化するためにも、まずは「確定申告」の基礎知識を知っておきましょう。今回は、医療法人を設立しないパターンでご説明します。
-

【連載】医師と学ぶ資産形成|精神科医 前田先生 Part.1
医師の方と一緒に資産形成や税金対策を学んでいくスペシャルコンテンツ。
第1回目は、開業を目指す精神科医の前田先生のライフプランや資産運用法を取材しました。2回目以降はコンサルタントとともに先生の悩みを解決していきます。 -

【現役医師連載コラム】医師が不動産投資で失敗するのは、どんな時?
勤務医ドットコム読者の先生方、こんにちは。医師で不動産投資家の大石です。
医師で不動産投資をされる場合、まず気になるのが「失敗しないのか?」という事ではないでしょうか。そもそも、不動産投資における「失敗」とは、何でしょうか。
今回は、そんな不動産投資にまつわる失敗について、まとめて解説していきます。 -
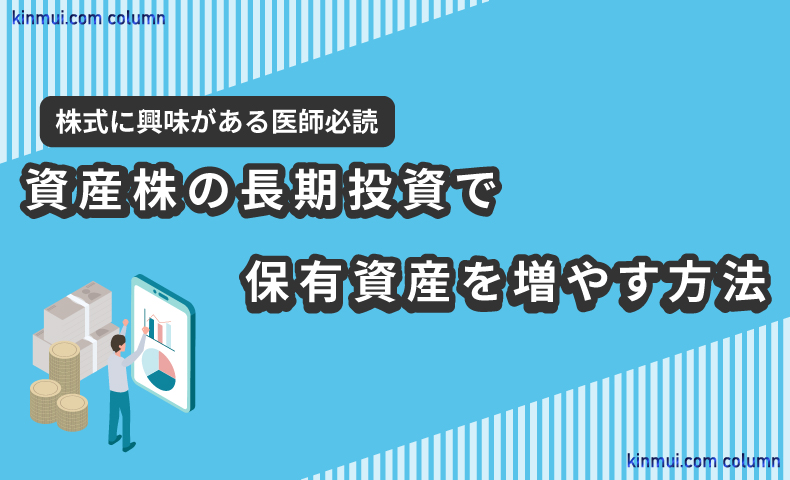
【株式に興味がある医師必読】資産株の長期投資で保有資産を増やす方法
株式投資には、値上がり益を狙うキャピタルゲイン投資と配当金や株式分割などで長期的に資産の増加を目指すインカムゲイン投資があります。安定的に資産の増加をもたらしてくれる資産株とは、どのような銘柄を指すのでしょうか。医師が資産株の長期投資で保有資産を増やす方法を考えます。
-

「私はコレでキャッシュを残しました」不動産投資で大幅節税に成功した医師の事例
医師(勤務医)にとって、年収2000万円達成はひとつの目標であることでしょう。複数の職場を兼務し、その数字を実際に見た時の喜びはひとしおです。でも、そこでおかしなことが起こります。確定申告後、その所得の3割以上もの金額を「所得税」として税務署へ支払わなければいけないのです。しかし、これはあくまで「税金対策」をしていない場合です。しっかりと対策をすれば、天国から地獄への転落は免れます。株などの金融投資をはじめ、資産形成の手段は様々ありますが、今回は、医師の中でも日々忙しい勤務医に最適な「不動産投資での節税」について、2つのケースを例に説明します。
-

【医師執筆】将来の収入に危機感をもつ医師が急増中
近年、医師不足が問題視され早急に医師の絶対数を増やすべく処置が取られています。
その結果医師の数は年々増えて来ている一方、日本は高齢化社会が進行し徐々に人口は減少傾向をたどっています。つまり今後、医者一人あたりの平均患者数は徐々に減少傾向をたどります。
その結果起こり得るのは医師の平均年収の減少でしょう。
タイトルにあるように、今現在、収入に危機感を持つ医者が急増しています。社会一般的に医者は高収入で、一度なってしまったら将来お金に困ることはない、という考えはすでに消えつつあります。
これからは医者も資産形成に関して早くに対策していく必要があるのです。 -
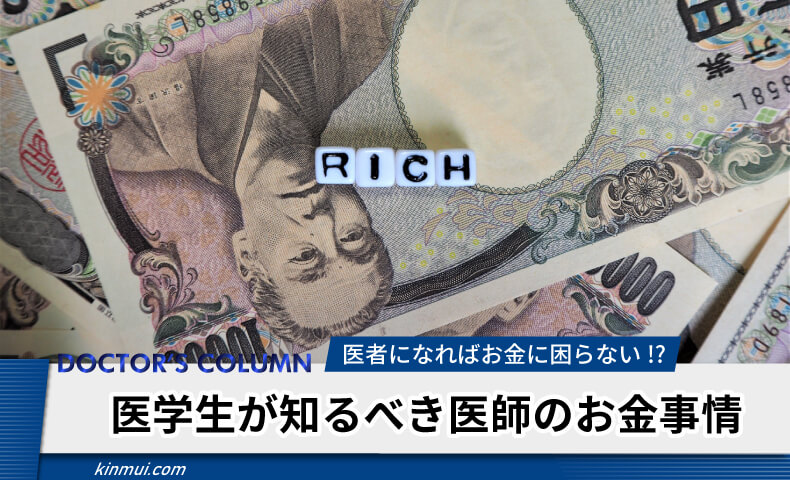
【現役医師連載コラム】医者になればお金は困らない…?医学生が知るべき医師のお金事情
「医者になれば、とりあえずお金には困らないでしょ」
と思っている医学生の方は、多いと思います。かくいう僕も、昔はそうでした。
しかしながら、実際に医師になって色々と経験し、人生のステージが進むにつれて、実感した事…それは
医師になったからといって、必ずしも「お金に困らない」という状況を作り出せるわけではない、という事です。
一体どういう事なのか?どのような医者が「お金に困る」事になってしまうのか?解説していきたいと思います。 -

【現役医師連載コラム】医療脱毛の流行、価格はどこまで下がるか?
最近、医療脱毛がかなり浸透してきました。どこにいっても、10代の子も中年の方も、医療脱毛です。
やはり日本の「皆んながやっているのだから、自分もやらないと」みたいな、同調圧力ってありますよね。それがある意味、新しい業態への爆発的な需要を生んでいる部分は、あると思いました。
さて、そんな医療脱毛ですが、一体これからどうなるのでしょうか?まだまだブームは続く?医療脱毛の価格はこれからどうなる?どういうやり方でやっていくのが、クリニックとしては良いのか?
考えていく必要があるでしょう。 -
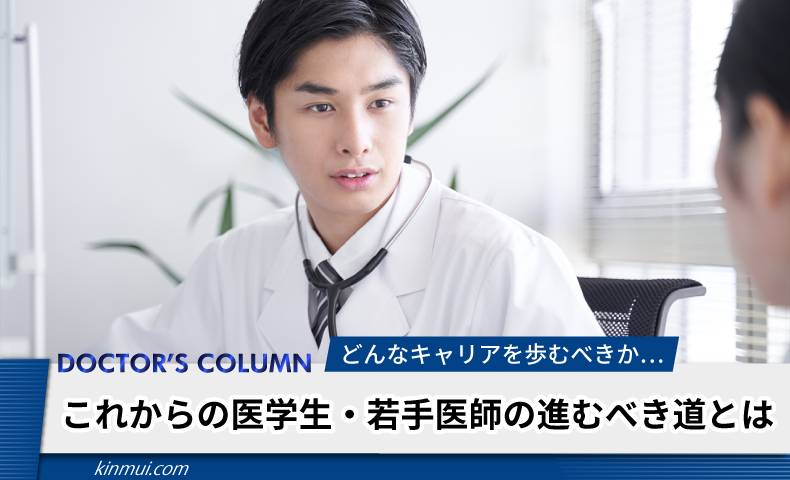
【現役医師連載コラム】これからの医学生・若手医師は、どんなキャリアを歩むべきか?
医師のキャリアは、ここ数年で激変したように思います。
専門医制度が新しくなった事はもちろん、女性医師の増加や、都市部への医師集中、自由診療への門戸が広く開かれ、そんな時に新型コロナウィルスがやってきました。
日本の人口減少に伴う患者数の減少予測も、そう遠くない未来にやってきて、そうなると日本国内における医師の人材需要も低減していく。そんな予測もあります。
さらに言えば、日本の財政から累進課税の強化を進め、高所得者である医師は事実的な増税を受け入れざるを得ません。
まさに日本の医師にとって、激動の時代がやってきています。
このような状況下で、若手の医師や医学生が、先人達が進んできたキャリアパスを自分も同じように歩む事に、疑問を呈する事はごく自然です。
そこで「今僕が医学生・若手医師なら、どのようなキャリアを歩むのか」を、考えてみました。 -
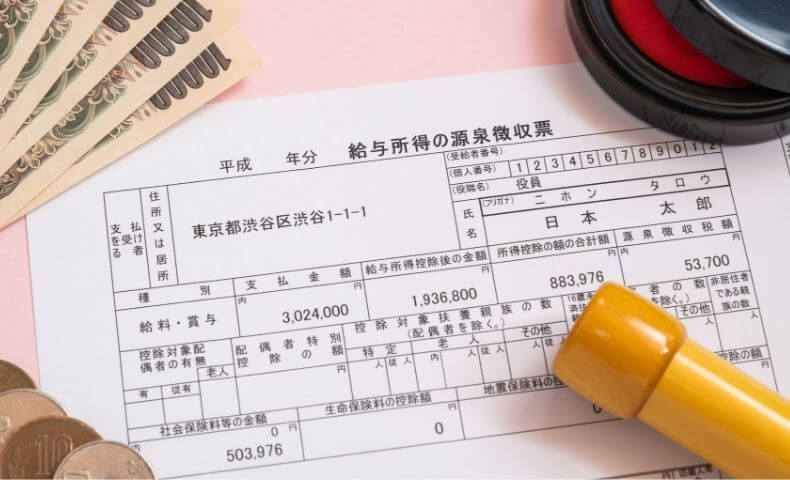
非常勤先が複数ある勤務医は特に注意! 修正申告が必要なケースとは?
勤務医として働いている医師の場合、「非常勤先が複数ある」というケースは珍しくありません。複数の医療機関から給与を受け取っている場合、通常は確定申告をして納税額を確定しますが、源泉徴収票の枚数が多いと記入漏れ、あるいは書類の紛失などにより申告漏れが発生することもあります。
申告漏れを税務署に指摘されると、場合によっては多額の税金を追加徴収され、悪質とみなされる場合には刑事罰が科される恐れもあります。また、不動産購入・開業時の融資などが受けられないケースもあります。
では修正申告が必要となるのはどのようなケースでしょうか。 -
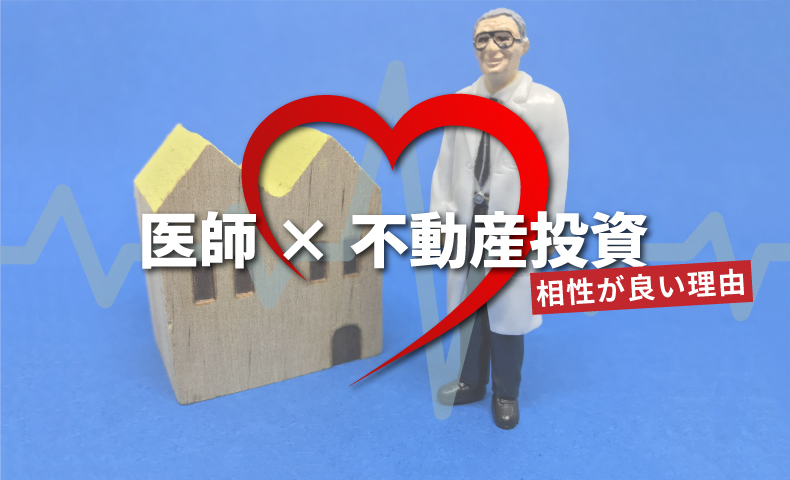
【現役医師連載コラム】医師×不動産投資、相性が良い理由
読者の先生方、初めまして。
現役医師で、株式会社ブルーストレージ代表の、大石と申します。普段は自由診療クリニックで勤務をしながら、会社の経営をしつつ、不動産投資家としても活動しております。
今回から、当メディアにて連載させていただく事になりました。
私は20代の頃から不動産投資を行っており、もうすぐ3年が経とうとしています。私の不動産投資の経験を、当メディアの読者の先生方に、少しでも共有できればなと思っております。 -
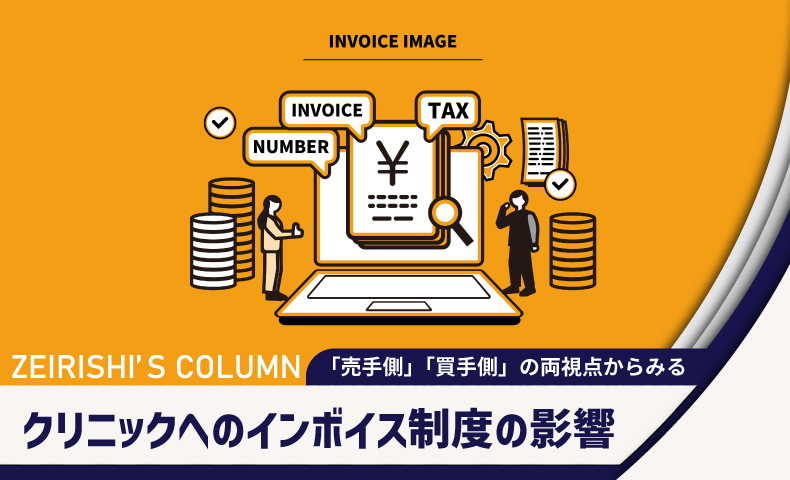
【税理士連載コラム】クリニックへのインボイス制度の影響 その2
「クリニックへのインボイス制度の影響―その1」では、簡単にどのような制度なのか、クリニックの売手側としての影響について簡単に解説しました。
但し、インボイス制度のクリニックへの影響を考えた場合、収入規模が大きいところや産婦人科や眼科のように自由診療の多い科については、クリニックの中でも消費税を払っている場合があります。
自院が課税事業者の場合は、自院の経理処理にあたっても注意点すべき点があります。今回は、収入の規模別に「売手側」、「買手側」の両視点からインボイス制度の影響について解説したいと思います。 -

医師の生涯年収の実態とは?不安定な収入を安定させる方法
世間一般のイメージでは、「医師=高収入」と認識されています。生涯年収はサラリーマンよりも高いのは事実ですが、勤務医や開業医、専門分野によって大きな開きがあることをご存知でしょうか?また、医師は退職金や企業年金が存在しないため、収入が安定しないリスクと常に隣り合わせの状態です。今回は、医師の生涯年収の実態と、安定な収入を得る方法について解説します。
-

不動産投資における管理費の相場はどのぐらい?
不動産投資家がアパートなど複数世帯に対する賃貸経営を行う場合は、本業と賃貸経営の二足のわらじは難しいため、物件管理を管理会社にお願いする方も多いでしょう。しかし、利回り等の兼ね合いから、どうしても発生する管理費の支出を抑えたいと考えることがあるのではないでしょうか。
ここでは物件管理を管理会社に委託する際の管理費の相場や、自主管理と比較した時に生まれるメリット、委託する管理会社選びのポイントについて解説してまいります。 -
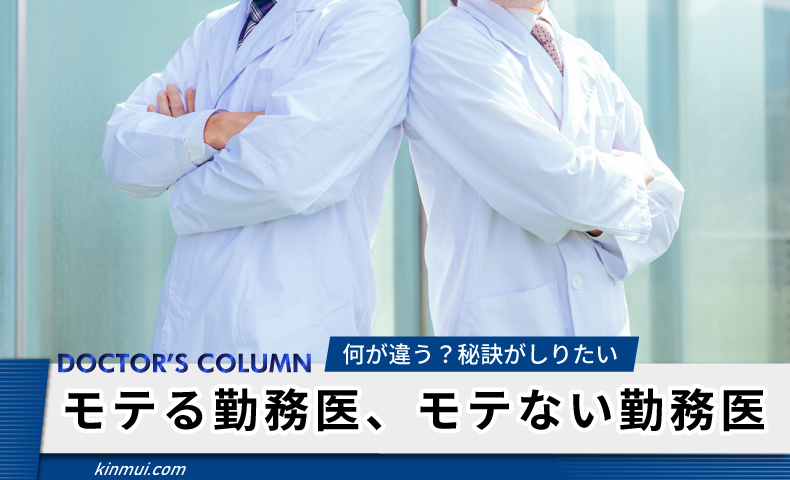
【現役医師連載コラム】モテる勤務医、モテない勤務医
同じ勤務医でも、モテる勤務医とモテない勤務医がいます。
一体なぜ…? -

【現役医師連載コラム】医師×不動産投資、法人設立で節税するって?
こんにちは、医師で不動産投資家の大石です。前回の記事<医師×不動産投資、相性が良い理由>では、医師と不動産投資の相性の良さについて、説明しました。
今回は、多くの先生にとって興味があるであろう、法人設立と節税を、不動産投資で行う事についてです。 -

【現役医師の投資履歴】初期研修医〜後期研修医 ≪前編≫
こんにちは、医師で不動産投資家の、大石です。
今回は、僕の過去について少し話そうと思います。
僕が医学部を卒業、医師国家試験に合格し、初期研修を終えてから、一体どのような方法で資産形成をしてきて、今に至るのか?
気になる方もいらっしゃるのではないのでしょうか。
実際、時代の流れや「その時だからできた」みたいな内容もありますから、全く同じやり方を踏襲するのは難しいと思いますが、少しでも参考になれば幸いです。 -
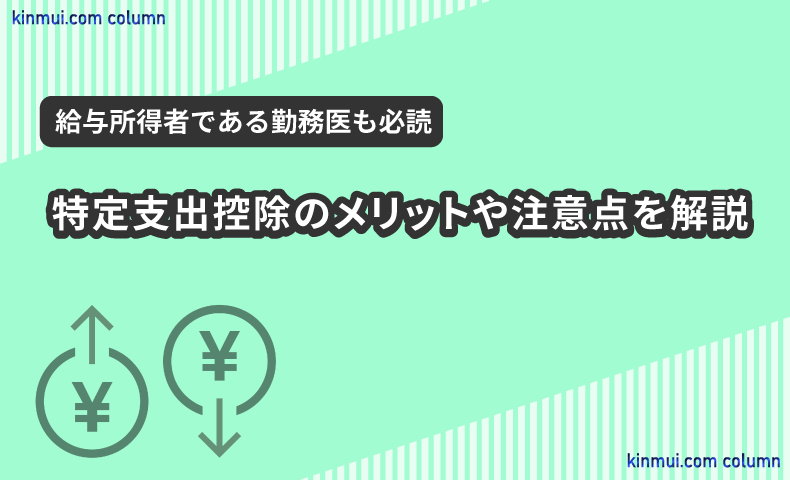
給与所得者である勤務医の特定支出控除とは?メリットや注意点も合わせて解説
今回の新型コロナウイルス感染拡大により在宅勤務が増えた医師の方もいらっしゃるでしょう。在宅でのオンライン診療に伴いパソコンや机、テレワーク用のWebカメラなどを新しく購入したり仕事に役立つ資格取得を始めたりした人も多いかもしれません。これらのパソコンなどの購入や資格取得の費用については、給与所得者である勤務医であっても必要経費として認められるのでしょうか。
-
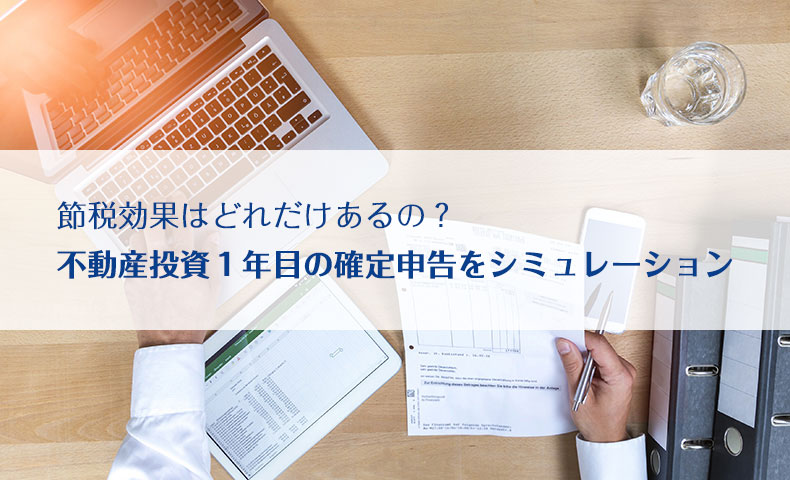
節税効果はどれだけあるの?不動産投資1年目の確定申告をシミュレーション!
「節税効果があると不動産投資をすすめられたけど、実際はどうなのだろう」
不動産投資を始めるにあたり、確定申告の際にどれだけの節税効果が見込めるか気になるところではないでしょうか。今回の記事ではモデルケースを設定し、不動産投資を始めた年の確定申告をシミュレーションしていきます。
(記事執筆時、2018年2月現在の内容で計算しています) -
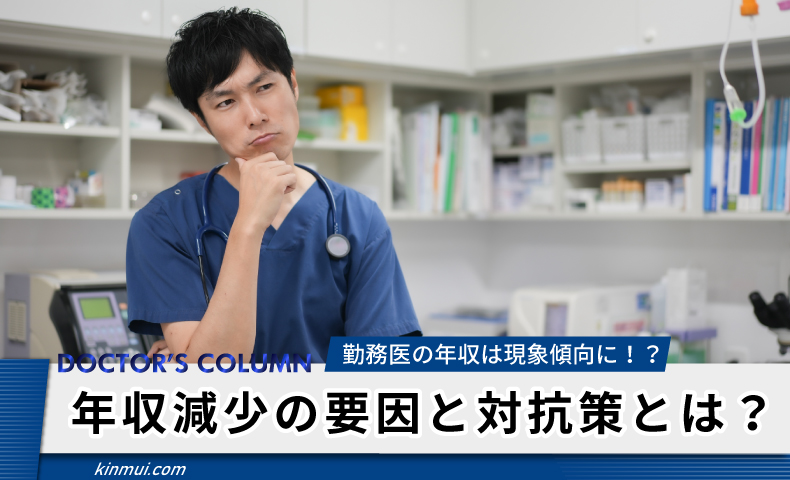
【現役医師連載コラム】勤務医の年収減少、要因と対抗策は?
勤務医の年収が、少しずつ減少していくのでは無いか、と僕は個人的に思っております。
今からお医者さんになろうとしている学生さん、研修医や若手の先生には、大変心苦しいのですが…おそらく避けられない未来かと思います。
「せっかく医学部に入ったのに、なんて事を言うんだ!」
「医師免許取ったら、それでオッケーじゃないのか…」
とお怒りの声が聞こえてきそうですが…
そこは抑えて頂き、勤務医の年収が減少する理由と、その対策について、僕なりの意見を述べていきたいと思いますので、ぜひ最後まで読んでください。 -
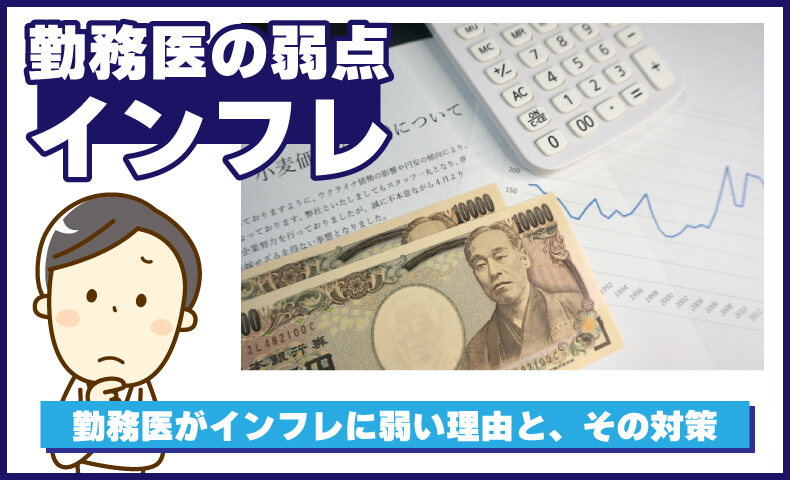
【現役医師連載コラム】勤務医がインフレに弱い理由と、その対策
前回の『勤務医の弱点「円安」と、その対策』に続いて、今回はインフレのお話です。
-

知っておきたい、開業医の確定申告と節税対策
勤務医で経験を積んだのちに晴れてクリニックを開業する医師は多いでしょう。そのとき気になるのが開業後の確定申告です。開業医と勤務医の確定申告にはどのような違いがあるのでしょうか。こんかいは、計上できる必要経費など開業医の確定申告の方法と所得控除を利用した節税方法について解説します。
-
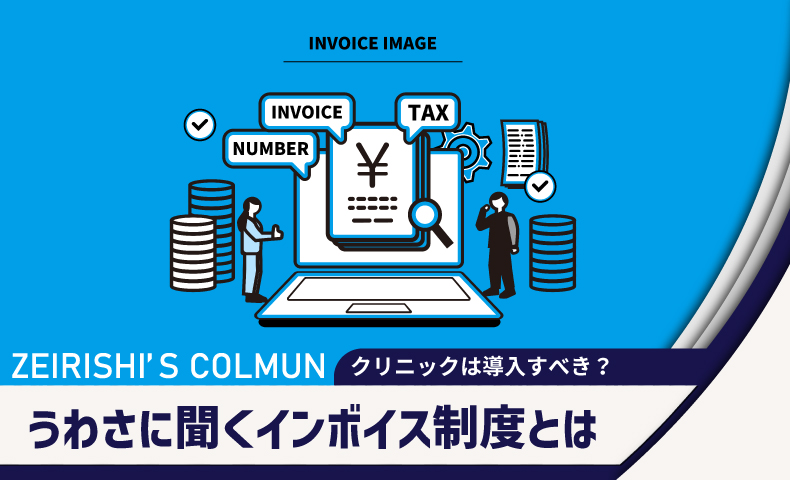
【税理士連載コラム】クリニックへのインボイス制度の影響 その1
令和4年に入り新聞をはじめインボイスという言葉が聞かれはじめました。
「うちにはインボイス制度って関係するんですか?」
「対応しないと何か損するんですか?」
という質問も最近(令和4年8月)になって多くなっています。
特に免税事業者の方からの質問が多いのが特徴です。
クリニックについては、その収入の大部分を保険診療が占めています。保険診療については、非課税取引という消費税を課さない取引となっているため、クリニックには免税事業者が多くなっています。今、クリニックこそインボイス制度への対応を検討する必要があります。
今回から数回に分けては、クリニックとインボイス制度について解説をしたいと思います。 -

期限ギリギリ…駆け込み申告で大失敗!確定申告でやりがちなミスとは?
控除が適用されるにも関わらず、申告し忘れたり、経費のつけ方を間違えて税金を多く払い過ぎたりするなど、誰もが失敗しやすい「確定申告の落とし穴」。税金の支払いが少なければ税務署から指摘がありますが、払い過ぎた場合は何も指摘されず、スルーです。気づかないうちに「大失敗」しているかもしれません。
国税庁のホームページでは、確定申告でよくある間違いについて、Q&A形式で公開しています。多くの人がミスしやすい項目とはいったい何なのか? 国税庁が掲げる「確定申告で失敗しやすい12のケース」について解説します。 -

夫婦で医師だった場合の保育園事情
医師同士の結婚は職場恋愛の延長戦上にあるため、珍しいものではありません。両親ともに医師の場合、子育てをしながら2人とも医師を続けていくためには“保育園探し”が重要なポイントになります。そこで今回は両親が医師だった場合の保育園事情について解説します。
-
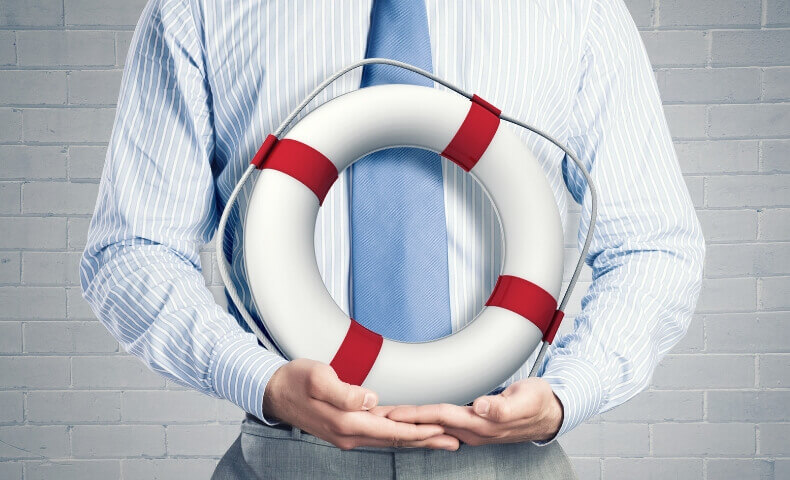
医師が入るべき生命保険とは?医師ならではの保険も紹介
医師は患者の命を守ることが仕事ですが、同時に自分自身と家族を守る必要があります。生きること、医師として働くことにリスクは付きものなので、しっかりとリスクヘッジをとることが求められています。備えあれば憂いなし。医師としての生活を守るために、準備できることは何かを解説します。
-

おすすめの資産形成ランキング 本業が忙しい人は何をすべき?
「人生100年時代」という言葉が一般的になってきました。寿命が伸びることは喜ばしいことですが、生活をしていくうえでは、どうしても一定のお金が必要です。つまり、寿命が伸びて老後生活が長くなるほど、老後資金は多めに必要になります。
また、結婚やマイホーム購入、子どもの教育といった「多額のお金がかかるライフイベント」をまだ通過していない人は、その都度、お金がかかります。
このように、老後やライフイベントに備えるためには、資産形成を進めておくことが重要です。しかし、現在は低金利環境なので、お金を銀行に預けておくだけでは、ほとんど資産は増えません(形成できません)。
また、本業が忙しい人は、なかなか資産形成についてじっくり考える時間がないかもしれません。そこで今回は、「ゼロから資産を形成する」という前提にて、本業が忙しい人に向けて、おすすめの資産形成方法をランキング形式で5つ紹介します。 -

もううんざり……不動産投資の電話営業
「また不動産投資の電話営業……なぜこんなにかかってくるのだろう」
職場に不動産投資の勧誘電話がかかってきた経験はありませんか。こちらが喋る間もなく話はじめ、勝手に話をどんどん進めていく場合がほとんどです。今回はこの迷惑な電話営業についてみていきましょう。 -

キャリアアップのため海外へ行くメリットとデメリット
「日本だけでなく、世界の医療の現場も見てみたい」、このような熱い思いを胸に抱きながら働いている医師の方も少なくないでしょう。でも、実際に医師として海外に行くためにはどのような方法があるのでしょうか? そこで今回は、「海外で活躍したい気持ちがある」、「キャリアアップのために海外勤務を考えている」という医師のために海外で働く方法を解説します。
-

儲かる診療科は「〇〇科」! 開業のトレンドを解説
内科、外科、整形外科、小児科、眼科、泌尿器など、さまざま科目が存在する医療の世界。医師が開業する際は専門性をもった科目で看板を掲げることになるわけですが、実際のところ、どの科目が最も儲かるのでしょうか?
-

勤務医が確定申告を行う際の注意点まとめ
医師の中でも勤務医は一般のサラリーマンと同じく、勤め先の病院やクリニックで源泉徴収と年末調整が行われるので、所得税の確定申告は原則として不要です。しかし、例外的に申告を行わなければならない場合もあります。
-

高所得の医師に人気がある高級モデルの小型車をランキング形式で紹介!
高級車は、高所得の方が自身のステータスを示すのに有効な方法の一つです。その中でも、小型車は狭い道や市街地でも運転しやすく燃費のいい傾向のため、人気を集めています。また高所得の医師の方は、自身のステータス性を示すことで相手から一定の信頼を得やすくなることが期待できるため、運転する車にお金をかけるメリットがあります。
しかしお金をかけてもメリットがない維持費用などのコストはできるだけ削減したいところ。このような需要に対応できるのが高級モデルの小型車です。この記事では、人気がある高級モデルの小型車上位7台をランキング形式で紹介します。 -

後期研修医が外勤やアルバイトをしたときの年収は?
「初期研修医」と「後期研修医」に分かれる研修医。後期研修医はアルバイトをすることが可能になるため、勤務先の医療機関以外でのアルバイト代が加わってくることが一般的です。
初期研修医と後期研修医の違いこの「副業で得た収入」は、年間20万円を超えると確定申告が必要になります。確定申告を忘れてしまうと延滞税や加算税などの対象になってしまうので、そうならないように必要な研修医の方は忘れずに申告をするようにしましょう。 -

開業を考える勤務医向け 「家族経営」の節税メリット
開業医に多く見られる家族経営という形態。クリニックは、家族経営のような“個人経営”か、または“医療法人”にするかによって控除対象などが大きく変わるため、これから開業を考えている医師はどちらの形態をとるか、事前にこの二つの違いを熟知しておく必要があります。そこで今回は家族で医院を運営する際に必要な税の知識を解説します。
-
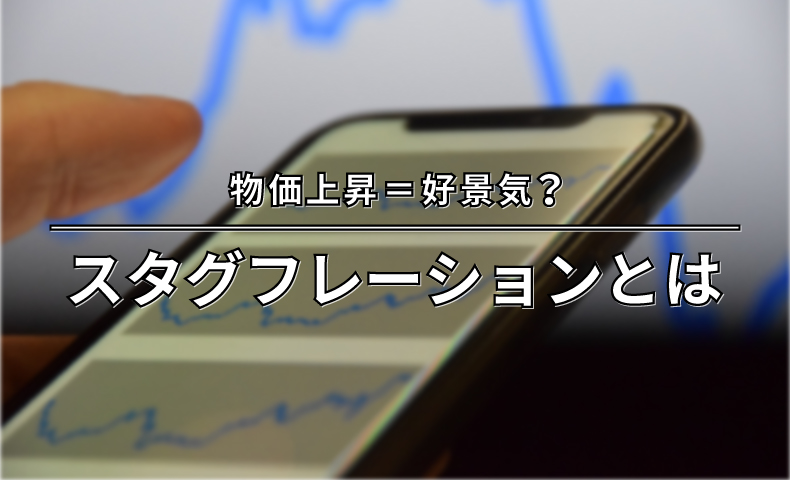
【現役医師連載コラム】スタグフレーションと、勤務医の取るべき投資行動
こんにちは、医師で投資家の大石です。
最近、物価が上がってきていますね。物の値段ももちろん上がっていますが、バイトなどの人件費も高騰しているようです。ロレックス、不動産など高級品の類も値上がりしており、色々な物の値段が上がり始めております。
物の値段が上がる、というとおそらく「インフレ」という言葉を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか?
今回起こるのはインフレなのか?本当に景気が良いのか?一体どうするべきなのか?勤務医が取るべき行動は?
考えていきたいと思います。 -
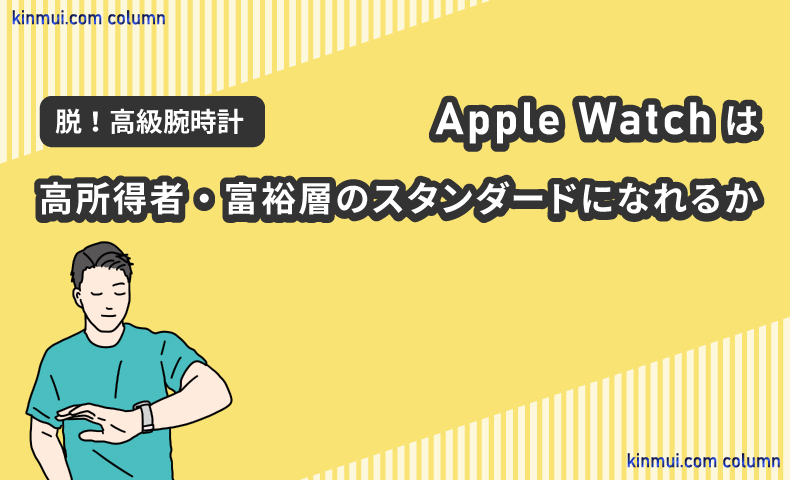
脱・高級腕時計?アップルウォッチは医師を始めとする高所得者・富裕層のスタンダードになれるか
高所得者や富裕層の腕時計といえば「ラグジュアリーブランド」や「スイス製」が一般的でした。しかし最近では、高所得者や富裕層のアップルウォッチ(Apple Watch)愛用者が増えています。アップルウォッチを選択する理由、高級腕時計マーケットの近未来などについて考察します。
-

男性医師でも育休の取得は可能?
女性対象の制度というイメージがある「育休」。子どもは男女のペアである両親から生まれるのですから、男性が育休を取得してもおかしくないはずですよね? 昨今では、男性も育休を取得しやすくなりつつありますが、実際、医師の世界ではどのようになっているのでしょうか? そこで今回は男性医師の「育休」について解説します。
-

税理士が解説!勤務医の確定申告の基礎
医師の中でも勤務医は一般のサラリーマンと同じく、勤め先の病院やクリニックで源泉徴収と年末調整が行われるので、所得税の確定申告は原則として不要です。しかし、例外的に申告を行わなければならない場合もあります。
第一は、給与収入が年間2,000万円を超えた場合です。この場合、勤めている病院等では年末調整をできないので、自分で確定申告することが必要になります。
第二は、主たる勤務先以外からも収入を得ている場合です。たとえば卒業した大学系列の病院に勤務して給与収入を得ているのとは別に、週に2、3回ほど別のクリニックなどでアルバイトとして働きそちらからも給料をもらっているようなケースです。
第三は、給与ではなく報酬という形の収入がある場合です。具体例としては、業務委託の形で診療の仕事を請け負って出来高制の報酬を得ているケースや、原稿料や講演料、テレビ等のメディアへの出演料などがあげられます。ただし、1年間に得た報酬の額が20万円以下の場合には申告の必要はありません。
確定申告の時期は、基本的に、所得を得た年の翌年の2月16日から3月15日までと決まっています。この3月15日は申告の期限であると同時に納税の期限でもあります。つまり、確定申告書を提出するだけでなく、追加で納めなければならない税金があれば、納税もあわせて行わなければなりません。申告期限と納税期限が同じであることは意外と認識していない人が多いようなので注意が必要です。
また、源泉徴収の形で税金を必要以上に納めていた場合には、確定申告をすることで還付を受けられます。つまり、払いすぎた税金が戻ってくるわけです。ちなみに税金の還付を受けるための申告であれば、翌年の1月1日から行えます。 -

地方医師と大都市圏医師の収入の違い
高収入で知られる医師ですが、同じ医師でも“収入の差”は存在します。勤務医か、開業医か、診療科は何か……。収入の差を生むのはさまざまな要素が存在します。また、一般の職種でも地方と大都市では給与水準が異なるものですが、医師の世界にもそれは当てはまるのでしょうか。そこで今回は、地方医師と大都市圏医師の収入についてそれぞれのケースを解説します。
-

激務=長時間労働とは限らない? 医師が激務と感じる要因
人はいつ何時、病に倒れるかわかりません。医師の仕事は時間を選べないため、長時間労働が当たり前の状況です。命を助けるという使命感から、どんなに激務であっても仕事を優先する医師が多いことでしょう。しかし、医師の仕事が激務という裏には、労働時間以外の要因が大きく関係しているのです。
今回は、医師が激務と感じる要因と、激務でもやりがいを感じる理由について解説します。 -

医師の過重労働と働き方改革
安倍政権が2016年に掲げた「一億総活躍社会」を実現するためにすすめられている「働き方改革」。これは医師の世界も例外ではなく、現在は厚生労働省により、医師の労働時間短縮や負担軽減などの議論が進められています。「医師の働き方改革」は近年ホットな話題ですが、実際の現場を見てみると、働き方改革の成果を実感できることが少ない、というのが現実かもしれません。医師の不足や偏りがあり、過重労働を感じている人が多い状況がある今、医師の働く環境について考えてみます。
-
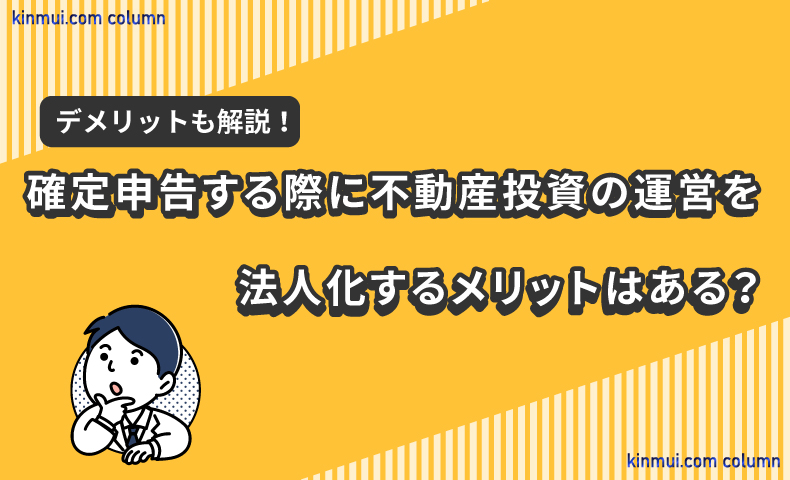
医師が確定申告する際に不動産投資の運営を法人化するメリットはある?
「不動産投資をしている場合、法人化したほうが良いか知りたい」「法人化するときの手順が知りたい」
不動産投資をしている勤務医を含む医師の中には、上記のように法人化について悩みを持っている方が多いと思います。
法人化することで相続税がかからないことや、所得税が法人税に変わることで節税になるといった利点があるためです。ただし、法人化にはデメリットもあり、適切なタイミングで法人化しないと節税にならないなどの注意点も多くあります。
そこでこちらの記事では、医師が確定申告の際に不動産投資の運営を法人化するメリットデメリット、そして法人化する手順について詳しく解説していきます。ぜひ最後まで読んで、法人化をする際の参考にしてください。 -

年収1500万円の節税!医師が行うべき税金対策とは?
年収1500万円以上を稼ぐ医師は、自分がどの程度税金を払っているのか把握していないという人も多いです。そこで、年収1500万円の場合に支払う税金額と、節税方法を解説します。
-

【現役医師連載コラム】なぜ不動産が相続税対策になるのか?
こんにちは、不動産投資家で医師の大石です。
いきなりですが、皆さんよく「相続税対策で不動産を買う」みたいな話って、聞きませんか?
良い物件だなと思って、買い付け入れたら「相続税対策の人が、現金一括で買っていってしまいました」みたいな。
よくよく考えると、なぜ不動産が相続税対策と関係があるのか、あまりわかっていない人もいるのではないでしょうか?
今回はそんな不動産と相続税対策ついて、少し深堀してみます。 -

キャリア? 子育て? 女性医師の働き方を考える
高度専門職である医師。最近は女性医師の割合が増加傾向にあります。
しかし、一般の働く女性と同様、女性医師の就業率もM字カーブ状になっています。結婚や出産・子育てのタイミングで、医療の現場から離れる女性医師が依然として多いのです。
医師としてのキャリアを選ぶか、子育てを選ぶか。
この記事では、女性医師をとりまく厳しい現状を紹介するとともに、どのようにすればキャリアと子育ての両立ができるかを考えていきます。 -
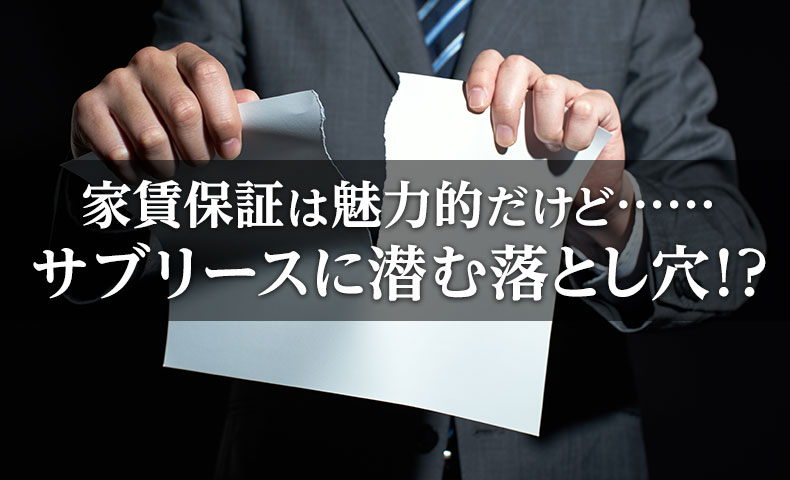
家賃保証は魅力的だけど……サブリースに潜む落とし穴!?
「安定した家賃保証としてサブリース契約を勧められたけど、大丈夫かな……」
不動産投資の物件を探しているとき、家賃保証があると安心ですよとサブリースを不動産業者からおすすめされたことはないでしょうか。
はじめて不動産投資をする場合、家賃収入が途絶えることへの不安はとても大きいものです。「その不安をやわらげます」といって、このサービスはおすすめされています。
そんな「サブリース」に今回の落とし穴は潜んでいます。 -

豊かなドクターが必ず持っている金融リテラシーとは?
医師のなかでも豊かな人とそうでない人とに二極化していることは、「医師=お金持ち」はウソ!? 二極化する医師の収入実態で触れたとおりです。それでは、医師のなかでも勝ち組となっている人たちはどのような金融リテラシーを持っているのでしょうか?
-

資産管理会社(法人)の設立と不動産投資のメリット
不動産投資における節税効果を最大化するために、資産管理会社を立ち上げることは効果的です。会社を登記し、法人として資産を管理することで、「他の資産との損益通算ができる」、「役員報酬の待遇が受けられる」、「経費計上できるものが増える」、「親族を役員として待遇することで利益を細分化できる」、「社会的信用度が上がる」といったメリットを享受できます。
本コラムではこれらのメリットや、さらにデメリットについてもご紹介いたします。 -
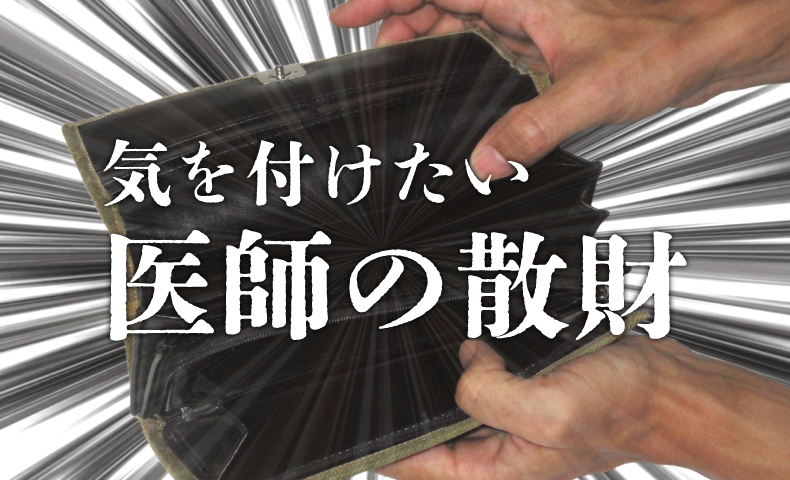
【現役医師連載コラム】勤務医こそサイフの紐を締めなければならない理由
皆さんこんにちは。いきなりですが、先生方は散財されますか?
僕は正直、美味しいものを食べたり飲んだりする時と、価値が保存される物を買う時は、割と金額が大きくても使ってしまいます。
特に後者の場合、不動産投資をやっているとわかりますが、バランスシートの資産に組み込まれ、値上がりすれば純資産がグイーンと伸びる図がイメージできてしまうので、なかなか躊躇いがありません。
さて程度の差こそあれ、全くしない、という方はいらっしゃらないと思います。
今回はそんな医師の散財、特に勤務医のサイフの紐についてです。 -
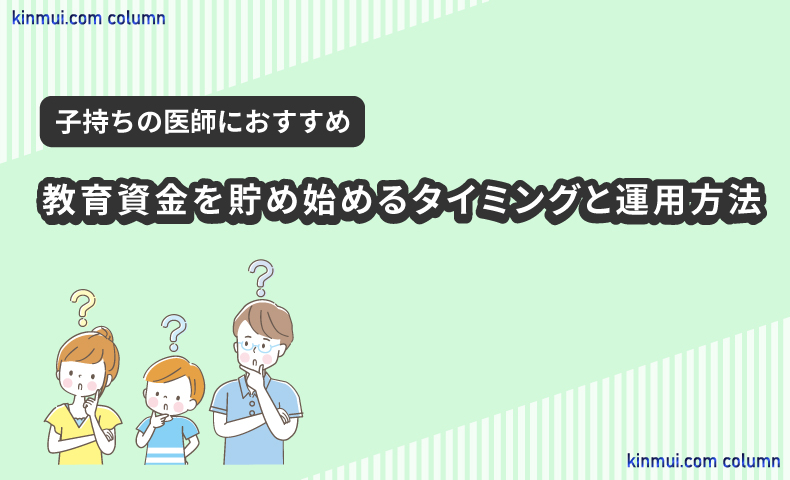
【子持ちの医師におすすめ】教育資金を貯め始めるタイミングと運用方法
お子さまが生まれてご家族が増えた医師の方が気になるのはライフイベントの中でも特に大きな出費となる「教育資金」。大学卒業まで子ども1人あたり数千万円かかるといわれている「教育資金」を、効率よく運用で準備していく方法を探っていきます。
-

【現役医師連載コラム】もう勤務医は辞めたい!開業を考えたら知るべき5つの真実
「もう勤務医はやってられない!」
そう思って、開業を視野に活動をし始める先生は、年々低年齢化している印象です。それくらい、勤務医の待遇が悪く、逆に開業医の待遇が良いという「格差」があるという事ですね。
さて、そんな開業ですが、果たして本当に「そんな夢のようなもの」なのでしょうか?
勢いで勤務医を辞めて、開業して後悔してしまう前に、知っておくべき事をいくつかピックアップします。 -
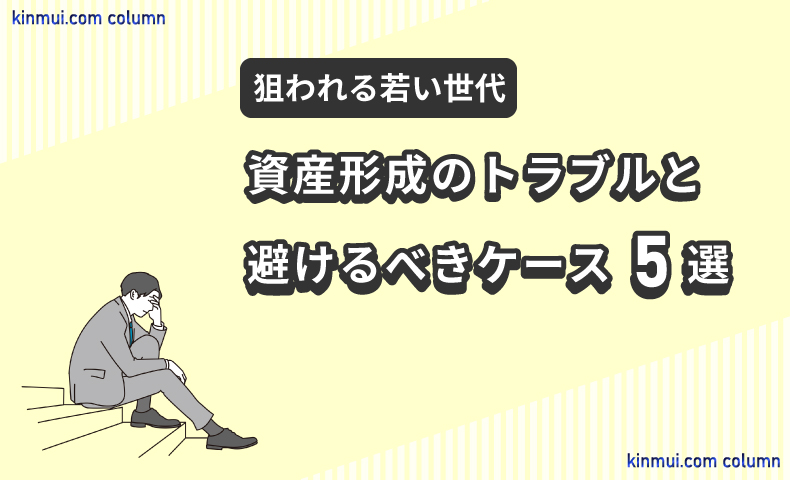
若い医師が注意したい資産形成のトラブルと避けるべきケース5選
20代から30代にかけての若い医師が投資トラブルに巻き込まれる事例が後を絶ちません。「人生経験が浅いから勉強代」といってしまうのは簡単ですが、働いて得た大切なお金を投資トラブルで失ってしまうことは、長い人生における資産形成にも多大な悪影響をもたらします。
これは言うまでもないことですが、資産形成はメリットとリスクが表裏一体です。「始めるだけ」でバラ色の世界がやって来るわけではありません。しかも、資産形成や投資についての経験があまりない人に向けて詐欺まがいの怪しげな話もうごめいています。
特に最近ではコロナ禍の影響もあって若い医師たちをターゲットにした投資詐欺の事例も散見されます。こういった手口への注意喚起も含めて資産形成のトラブルを知り、回避する方法を指南します。 -

医師が不動産投資で節税を行うなら減価償却がキーポイント
勤務医として働いている医師の節税対策を考える際、「不動産投資が最適」と言われます。その理由は「減価償却費を経費として計上できるから」です。この減価償却費とは一体どのようなものなのでしょうか? そこで今回は不動産投資には欠かせない減価償却について、概要や計算方法、注意点などを解説します。
-

北海道リレーインタビュー VOL.4中村太保先生(北海道大学名誉教授)
北海道で活躍されている医師の方にインタビューを行い、ご自身の取り組まれている医療分野やキャリア、資産・資金形成などについてお聞きする本企画。
第四回は、北海道大学名誉教授であり、歯科医院を経営する中村太保先生にお話を伺いました。長年、歯科医師の育成に携わり、日本口腔腫瘍学会理事、日本歯科放射線学会理事などを歴任された中村先生の目指す歯科医療とは、そして歯科医院を開業されて気づいたこととは、どのようなものだったのでしょうか。 -

医師が投資に失敗するパターンを紹介
「こんなはずじゃなかった……」。資産を増やそうと思ってはじめた医師が投資に失敗するケースは少なくありません。そもそも投資は確実にお金が増える方法ではないので、失敗する可能性はもちろんあるわけですが、誰もがしっかり増やしたいと思っているものですよね。そこで今回は、他人のふり見て我がふりを直すために、「医師が投資に失敗するパターン」を紹介します。
-
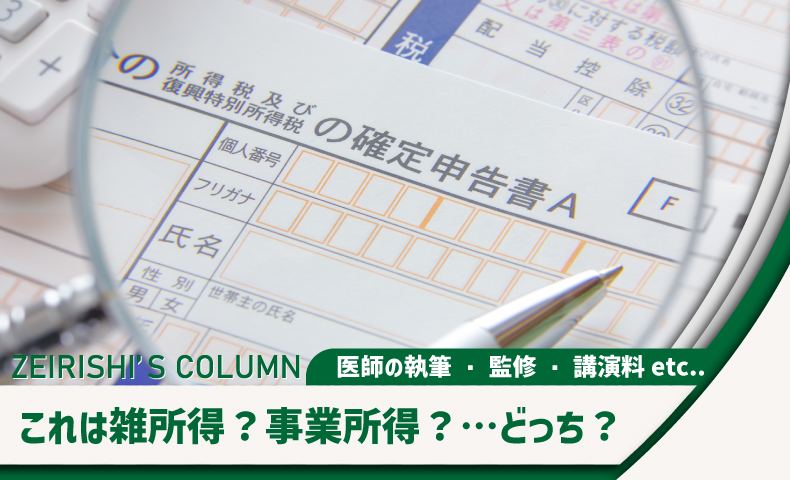
【現役税理士連載コラム】医師の執筆・監修・講演料などは雑所得?事業所得?
医師の中には、講演や執筆を行っている方もいらっしゃいます。講演や執筆に対して報酬や謝金が発生したときに疑問に思うのが「これは確定申告をしなければいけないの?」という点です。
実は、医師の方は、複数の病院で働いていて、確定申告をしている方が多いため、より問題を複雑化させます。
今回はそうした執筆・監修・講演料に関わる確定申告についてご紹介します。 -
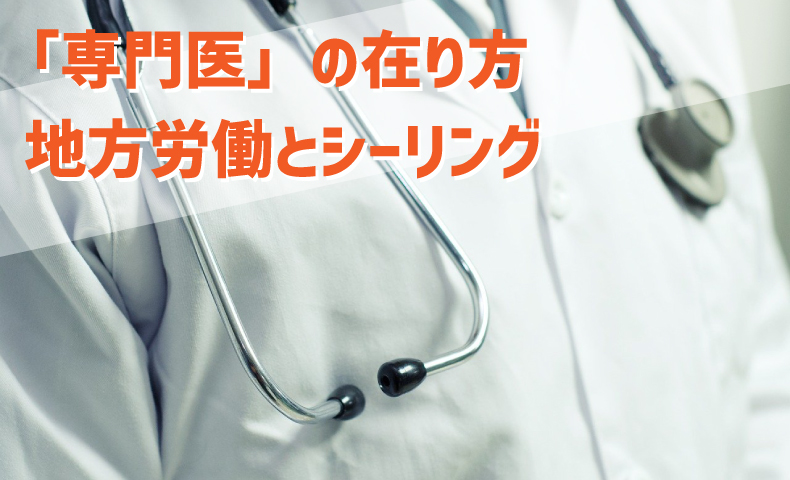
【現役医師連載コラム】専門医取得後の「地方労働」と、シーリングの失敗について
前回の記事<変化する時代と、キャリア別の「専門医」の価値>では、専門医の必要性と、キャリア別のその価値についてお話しました。
勤務医を続けるなら必要だし、開業医になるなら専門性よりも、サービス業としての価値を高めていく方向が効率的だよねという話でした。
さて今回は「結局若手は、専門医を取れば良いの?どっちなの?」という話について、考えていきたいと思います。
最終的なキャリアが決定していれば、前回の記事の内容だけで簡単に決断できたと思います。
しかし、普通は「勤務医か開業医か」なんて、まだ決まっていない若手医師の方が多いわけで、やりながら考えていくのが一般的ですよね。
思考を整理していきます。 -

資産の多い医師におすすめのプライベートバンク
富裕層向けの「プライベートバンク」の勢いが日本でも活性化しています。皆さんはもうプライベートバンクを利用していますか? 今回はまだ始めていないという医師の方のためにプライベートバンクについて詳しく解説します。
-
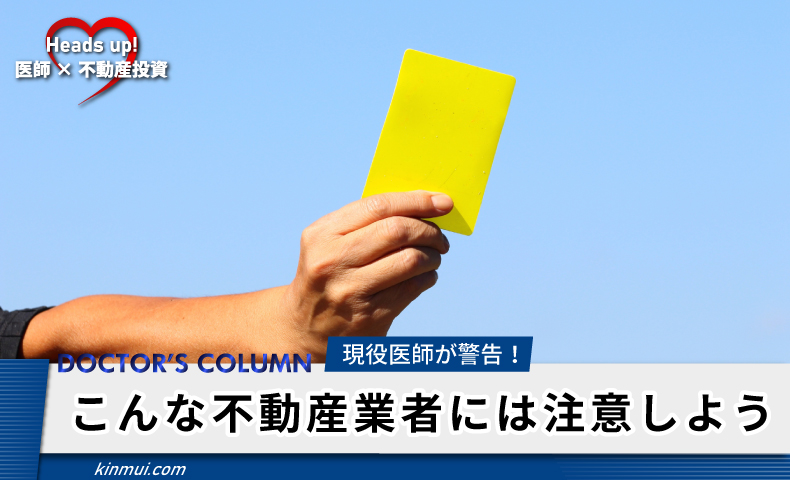
【現役医師連載コラム】現役医師が警告!こんな不動産業者には注意
かれこれ不動産投資歴、4年になろうとしています。今振り返ってみれば、この4年間、本当に色々な事がありました…。
具体的には
金額が低い、地方の築古ワンルームを中古で買おうとして、最初の物件だ!と息巻いていたら、修繕積立金が全く溜まっておらず、修繕積立金の増額予定が立っており月5万円くらいに到達しそうだった(当然、大規模修繕をしていないので共用部分がボロボロ)…
仲介業者が「鉄骨造だ」と言うから買い付けを出して、融資審査に出したら、銀行からは「融資承認は降りたけど、あれ鉄骨じゃなくて軽量鉄骨ですよ…」と言われた
などなど。他にも無限に話そうと思えば、話せます。
もちろん良い事もありますが、このように悪かった事も結構…。
今回はそんな中で「こんな不動産仲介業者に気をつけろ!」というのを、まとめたいと思います。 -

【税理士連載コラム】医師も知っておきたい税務調査の実態「税務調査は断れるのか?」
税務調査と聞くと、どのようなイメージをお持ちでしょうか? 古くは映画「マルサの女」や時折ニュースなどで報道されるように、スーツを着た無表情無機質な人々が情け容赦なく会社や家などに押し入り、ダンボールなどに書類を詰めてガンガン押収するということを想像されるかと思います。
このような税務調査は査察や強制調査と呼ばれます。しかし一般の納税者に対して行われることはほとんどなく、通常は任意調査という形で行われます。 -
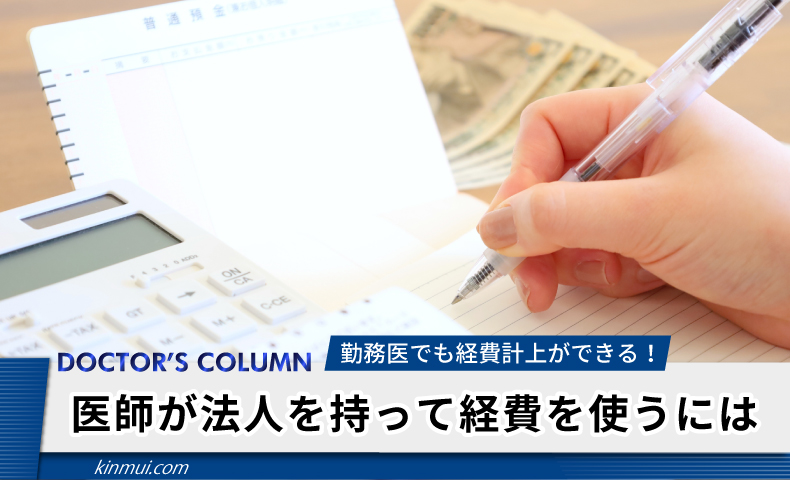
【現役医師連載コラム】医師が法人を持って経費を使うには
こんにちは、医師で不動産投資家の大石です。いきなりですが、医師をしていると
「税金高ぇ〜」
って思いませんか?僕はもう、何回も思いました。それと同時に
「経費って、使ってみてぇ〜」
とも、思っておりました。なんか響きだけでも、お得な感じがしますよね、経費って。
そんな経費ですが、経費を使うためには一体何をどうすれば良いのでしょうか?経費を使うために法人を持つには、どうするべきなのでしょうか? -

投資物件はどう選ぶ?10年運用シミュレーション・都心の新築ワンルームマンション編
「不動産投資を始めたいけど、どのような物件を選べばいいのだろう」
不動産投資を検討する際、その入り口となるのが投資物件の選び方です。物件を選ぶポイントとしては、築年数やエリア、利回りなどが思い当たるのではないでしょうか。
この記事では毎回モデルケースを設定し、購入から10年後までの収支をイメージしていきます。
今回のモデルケースは「都心の新築ワンルームマンション」です。(文章中の金額はあくまでもモデルケースを想定した概算金額です) -
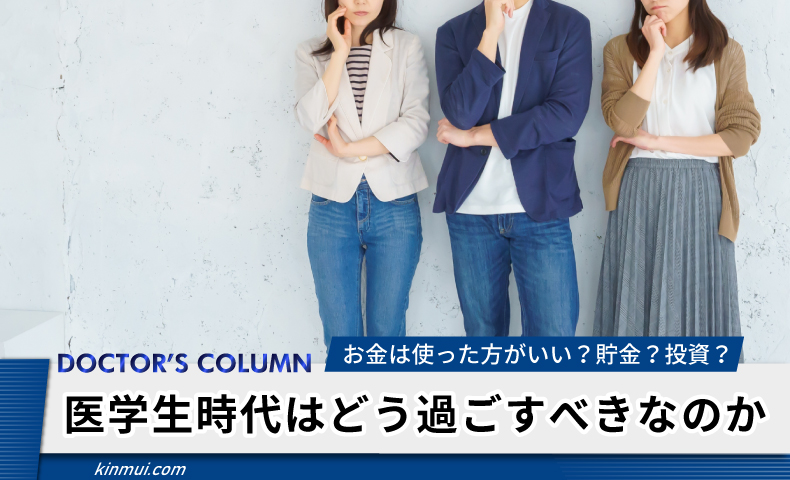
【現役医師連載コラム】医学生時代はどう過ごす?貯金は?投資はすべき?
話は少し飛びますが、最近の学生さんは、本当に真面目ですね。
将来のこと、お金のこと、結婚や子供のこと、キャリアのこと。
あらゆる「近い将来」のことを、事前に考えて生きている方が、多いように感じております。
スゴイなあと驚くとともに、そういったことを学生の頃から心配して気をつけないといけないくらい、社会がまた変化してきたという事でもあるのかなと思うと、少し可哀想な気も、してしまいます。
そんなところで、今回は医学生向けの記事です。
・医学生時代、どう過ごすのが良いか?・医学生時代から、お金を得るために何かできる事はあるのか?・医学生時代から、貯金や投資はするべきなのか?
など、疑問を抱えていらっしゃる医学生の方に向けて、僕なりの意見を述べていこうと思います。 -
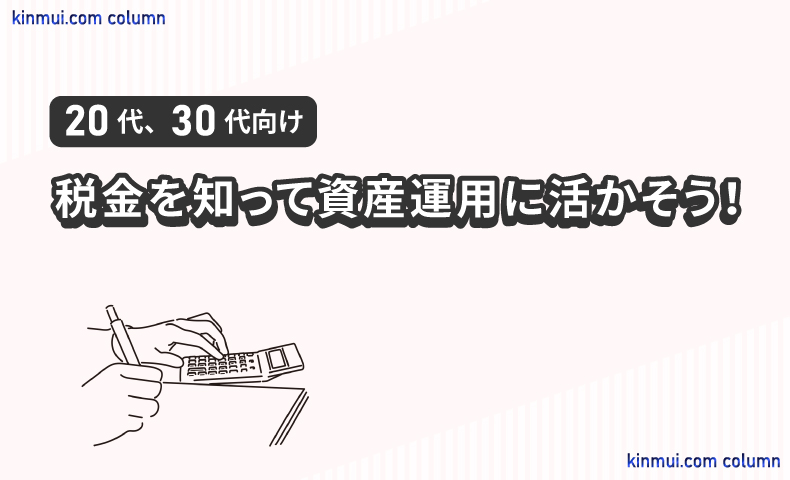
【若い医師向け】税金を知って資産運用に活かそう!
「税金」という言葉を耳にすると「取られる」「かかる」など、あまりプラスイメージが湧かない人も多いのではないでしょうか。しかし税金の仕組みを理解せず毛嫌いしてばかりではお得な情報を見逃してしまう可能性があります。現代社会において税金と関わることなく暮らしていくことは、ほぼ不可能といえるでしょう。
税金の仕組みを知っておくことでプラスになることも多いため、若いころから税金の知識を学ぶことは非常に大切です。本記事では、税金の仕組みや節税方法、資産運用方法などについて学んでみましょう。 -

社会的信用が魅力!医師ならではの資産形成
医師は社会的信用が高い職業です。したがって、金融機関から融資を受けやすいため、資産形成をしやすくなります。
この記事では、医師が融資を受けやすい理由や融資を受けられる資産形成方法について解説します。
この記事を読むことで、医師が融資を受けるメリットを理解できるので、医師に向いている資産形成方法がわかるようになるでしょう。 -
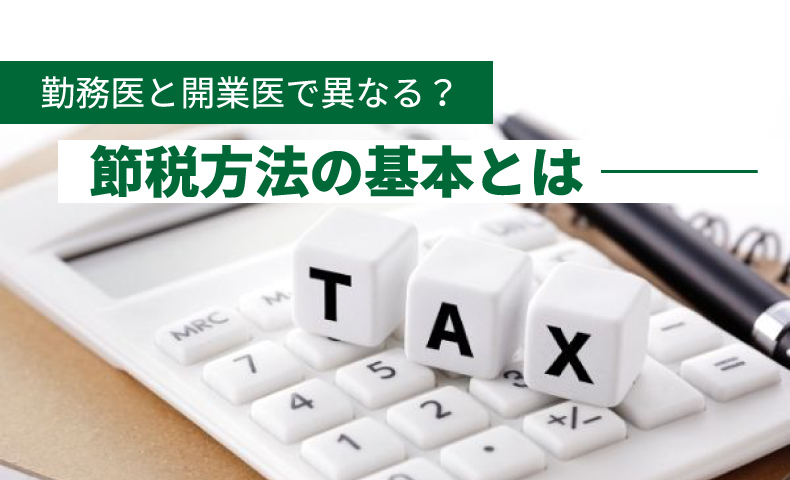
勤務医と開業医で異なる?節税方法の基本とは
現在の日本では、所得税や贈与税そして相続税において「累進課税制度」が採用されています。この累進課税制度とは、多くの収入を得ている人や相続する資産の多い人ほど、税率の高い所得税や相続税が加算される制度をいいます。医師として働いているうちに収入が増加していくと、節税を考える必要も出てくるでしょう。
-

地方勤務医による不動産投資実践① 区分マンション投資について―自分の経験から(地方都市の場合)
こんにちは、地方在住アラサー医師(勤務医)のt-nakaです。本業のかたわらでアパート2棟、貸家1戸の不動産投資をしております。
私の不動産投資は、戸建てを相続したところからスタートしました。その後、2016年5月および2018年9月に築古のアパートをそれぞれ購入し、現在は青色申告事業者として家賃収入はおよそ1,000万円/年、借入金は8,000万円です。2棟目のアパート購入が決まった際に『地方勤務医の不動産投資ブログ』というブログを書き始め、現在に至ります。
今回は区分マンション投資についての内容です。以前に区分マンションの購入を試みたこともありましたが、購入には至りませんでした。自分の経験と、もし自分が大都市圏に住んでいたらという2つの視点で書いていこうと思います。私も不動産投資に参入したばかりですので、自分の経験が「これから不動産投資を始めたい・始めたばかり」という医師の方にとって少しでも参考になればと思います。 -

勤務医のキャッシュフローを大公開!年収1000万超え富裕層の「資産形成術」
資産の運用について検討する機会はありますか。また、すでに資産運用に取り組まれている方は、現状の課題やその改善手段について、考え直す時間をお持ちですか。日々多忙な医療従事者にとって、そのような時間を捻出することは難しいかもしれません。しかし、堅実な医師ほど、忙しい合間を縫って貴重な資産の運用に励んでいます。1人乗り遅れてしまわないためには、うんうんと悩み続けるのではなく、まずはプロに相談するのも良いかもしれません。本記事では、そんな悩める医療従事者の資産運用スタイルについて、2つのケースを紹介します。
-

なぜ高収入の医師ほど退職後に「お金がなくなる」のか
病院によっては退職金制度が定まっていなかったり、そもそも制度自体がなかったりするところがあるなど、医師の“退職金事情”は安泰とはいえません。働いているときは所得が高く、社会的信用も高い医師だからこそ、若いうちから幅広い資産形成の方法を選べるメリットがあります。現役時代は所得が多く、医師という職業の社会的な信用の高さから融資が受けやすいため、医師は若いころから幅広い資産形成の方法を選ぶことができます。この特徴を上手に活かせば、自身の老後や子どもの将来のための資産を築くことが可能です。
-

【現役医師連載コラム】医師×不動産投資、個人所有で節税する方法
こんにちは、医師で不動産投資家の大石です。前回の記事<医師×不動産投資、法人設立で節税するって?>では、法人設立で節税する話を書きました。なんとなく「経費」っていう言葉の響きが、良いですよね(笑)
さて今回は
「法人設立せずに個人所有でも、不動産投資で節税ってできないのか?」
という声にお答えしたいと思います。 -

不動産投資において法人化する方法とそのメリット
節税効果が高いことから、不動産投資が軌道に乗り次第、法人化させることを目指すことが推奨されています。ただ、そのメリットが見いだせないとなかなか実践に移すことができないのも事実です。ここでは不動産投資を法人化させることのメリットや法人化移行へのタイミング、法人化する流れについてまとめました。
-
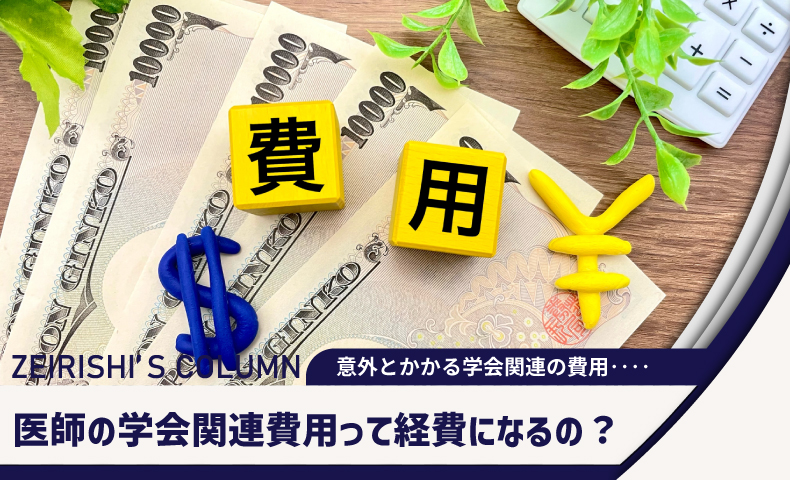
【税理士連載コラム】医師の学会参加費用・学会会場までの旅費交通費・医学書は経費になるのか?
医師が学会に参加するときは、参加費、会場までの交通費、日をまたぐなら宿泊費、食事代と、種々の費用がかかります。
それらを経費に計上できれば節税効果が期待できますね。
しかし、どこまでの範囲が経費にできるのか、「準備のために購入した医学書代も落とせるのか?」、「宿泊費は?」「ついでに観光した場合は?」と、さじ加減に悩んでしまうことも多いかと思います。
今回はそうした経費にできるもの・できないものの考え方をご紹介します。 -

不動産投資で絶対譲れない“立地”を徹底検証
購入前に必ず押さえたいポイントの筆頭にあるのが「立地」です。でも、実際に現地へ足を運び、自分で調べて決めることは多忙を極める医師には難しいもの……。
そこで今回は、どこを押さえるのがよいのか、気をつけるべきことは何か、立地に関して押さえたいポイントをまとめました。 -

医師のキャリアアップに必要な資質と注意すべきこととは
医師として順調にキャリアを重ねていけば、自然と「キャリアアップ」について考えるタイミングが訪れるでしょう。「もっと自分を評価してくれる職場で働きたい」「収入を増やしたい」「●●について学べる環境に身を置きたい」など、その動機はさまざまあると思います。しかし、キャリアアップには求められる資質や適切なタイミングがあり、闇雲にキャリアアップを図っても、うまくいくものではありません。
理想のキャリア形成を叶えるためにも、正しいキャリアアップ術を学びましょう。 -
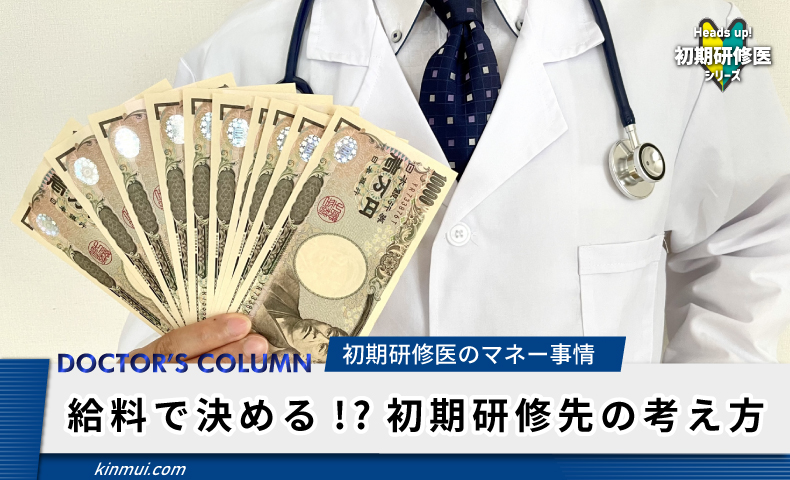
【現役医師連載コラム】初期研修先病院を給料で決めるのは正しいか?マネーで考える
最近、初期研修先の病院を「給料」で決める医学生さんが、多いように思います。
この現象は、概ね2015年くらいから観測されていますが、近年はその傾向がより顕著になっていると感じます。
確かにお金は重要なファクターの1つです。しかしながら、初期研修先の給料というのは長い人生で見れば微々たるものと言えば微々たるもの。
そもそもマネーにフォーカスして初期研修先を選ぶ=給料で選ぶ、という事であっているのでしょうか?
今回はそこを掘り下げていきます。 -
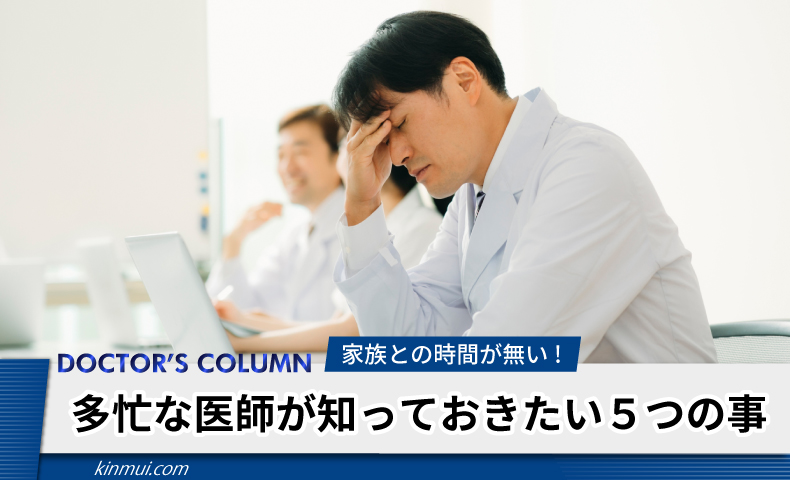
【現役医師連載コラム】家族との時間が無い…多忙な医師が知っておきたい5つの事
お医者さんは、忙しい職業です。
時にはプライベートを犠牲にしても、患者さんを助けなければいけない時があります。
なぜなら患者さんがいくら他人とはいえ、患者さんの命や健康、体の機能が損なわれようとしているのですから。自分のプライベートの時間と、他人の命や健康。天秤で重さを測る方が、おこがましいような気がしてしまいます。
そのような職業だからこそ、周囲や社会から尊敬され、日常的に「先生」と呼ばれる存在でもあるわけです。
しかしながら、実際は医師が「忙しさ」とバランス良く向き合うのは、難しい事のようです。 -
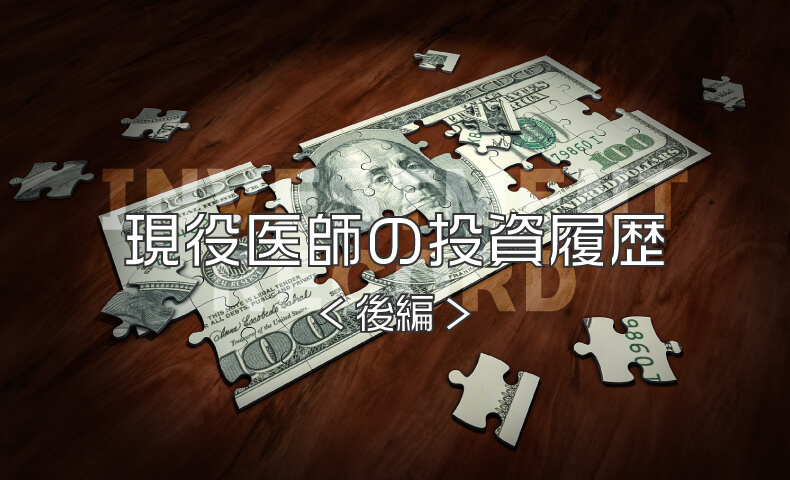
【現役医師の投資履歴】最初の物件購入~現在 ≪後編≫
こんにちは、現役医師で不動産投資家の、大石です。
前回の記事では、初期研修開始から、後期研修2年目の後半で不動産投資を考えて勉強し始めるくらいのところまでを書きました。
今回はそこから先、具体的に不動産投資をどうやって開始していったのかを、書いていきます。 -

不動産投資で税金対策|経費としてどこまで計上可能か
預貯金を不動産に替え、家賃収入を得る不動産事業を始める投資家が増えています。
この方法は低リスクであり、医師や企業経営者などの高所得者層に有効な投資法として紹介されています。
収入を得るばかりではなく、高所得者層には「節税効果も大きい」とされている不動産投資。
では節税を有効化するためには、どんな経費をどこまで計上すべきなのでしょうか。
ここでは不動産投資に掛ける経費について深く掘り下げていきましょう。 -

勤務医が節税するための方法
総合病院などで働く勤務医は年収も高く、源泉徴収票をみると多額の所得税・地方税を納めている事実に驚愕されている方もいらっしゃることでしょう。少しでも納める税金を少なくしたい、節税したいと考えることはとても自然な流れです。では、高所得者層の医師(勤務医)が節税のためにできることとはどういったことでしょうか。
-

不動産投資において一括払いにリスクはないのか?
不動産投資において、ローンと一括払いでどのような違いが生じるのでしょうか。一括払いにも、購入者によってはリスクが生じます。
ローン払いと一括払い、それぞれのメリットやリスクを見ていきましょう。 -

地震、火災…「災害」が起きた場合、投資した不動産はどうなる?
先日来襲した台風15号・19号は、日本列島の広範囲にわたり猛威を振るい、各地のインフラ機能、そして多くの家屋にダメージを与えました。過去に経験がないほどの強い暴風雨による被害が著しく、房総半島では未だにブルーシートを被った建物が多数…。もし、あなたの所有する投資物件が、災害によって何かしらの被害を受けたとしたら、まず何をしますか? 今回は、火災そして台風などの天災被害に備える「損害保険」の適用範囲と、補償金の考え方について解説します。
-

子どもの習い事はいつから始めて何を習わせればいい?
どんな習い事をさせるかを考える前に、まずは何歳から始めたら良いのかを考えてみましょう。スポーツ選手やピアニストなど、小さいころから習い事として始めていた人も多いですが、実際、子どもの習い事はいつ頃から始める人が多いのでしょうか?
イオレが習い事をしている子どもを持つ親を対象に行った「子どもの習い事に関するアンケート」によると、習い事を始めた年齢は、1位が「5歳(18.6%)」、2位が「4歳(17.2%)」、3位が「3歳(15.9%)」となっていて、なんと、小学生に上がるまでに、6割以上の子どもが習い事を始めています。
イオレ『子どもの習い事に関するアンケート』より -
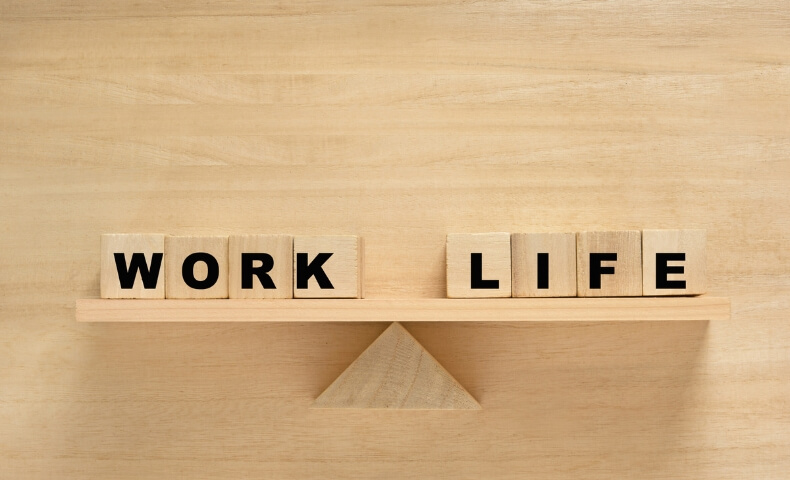
多忙を極める医師のワークライフバランスについて考える
「働き方改革」が提唱されている影響か、ワークライフバランスを重視する人が増えています。医師は高収入を得られる職種ですが、絶えず緊張しながらの長時間労働など、肉体的にも精神的にも負担が大きいというイメージもあります。働き続けるためには、患者のことはもちろん、自分の生活を確立させ、心身ともに健康であることが重要です。いま一度医師のワークバランスについて考えてみます。
-

副業をしている医師必見!給与所得以外の所得について学ぶ
医師が主に得ている収入の1つとして「給与所得」があります。給与所得はイメージがつきやすいものですが、じつはそれ以外にも「所得」はあります。そこで今回は全部で10種類ある所得の解説と、その中でも重要になる不動産所得を掘り下げて紹介します。
-

【現役医師連載コラム】家族に給料、親を扶養に…「個人を使い分け」節税する方法
医師の皆さんならきっとわかって下さると思いますが…税金って高いですよね。
税金を少しでも抑える方法、いわゆる節税という類の者の中に、実は「家族」を絡める方法がある、というのはご存知でしょうか?
意外と知らないという方も多いのでは無いかと思います。
今回は、家族など「税率の違う人」をうまく使い分ける事で、節税する方法についてです。少しでも節税するための参考になればと思います。 -

北海道リレーインタビュー VOL.5武田宏司先生(北海道大学大学院薬学研究院教授)
北海道で活躍されている医師の方にインタビューを行い、ご自身の取り組まれている医療分野やキャリア、資産・資金形成などについてお聞きする本企画。
第五回は、北海道大学大学院薬学研究院の教授であり、北海道大学病院栄養管理部長を兼務される武田宏司先生にお話を伺いました。消化器内科医として活躍しながら、薬学教育や漢方薬の研究にも熱心に取り組まれる武田先生が目指す医療や薬学教育のあり方、資産形成に対する考えなど、幅広くお話しいただきました。 -

【現役医師連載コラム】医師にとっての不動産投資の始め時は、いつ?
皆さんこんにちは。
僕は2019年に最初の物件を買って以来、以後毎年物件を購入し続けていますが、今振り返ってみて思う事があります。
それは
「あの時不動産投資を始めておいて、よかったな…」
という事です。
というのも、2021年現在、物件価格が高騰し続けており、一昔前と比べるとグッと高くなった印象で、下がってくるのを待っているのですが…正直一向に下がってきません。
こういう話を聞くと、一体いつ不動産投資の世界に足を踏み入れれば良いのか、わからなくなってしまいますよね。
今回はそんな、医師にとっての不動産投資の始め時はいつなのか?という事について考えます。 -

ギャンブル好きだった勤務医が「堅実な資産運用」に目覚めたワケ
病院に勤務する医師の平均年収は、1200万円~1400万円ほどといわれています。一般的なサラリーマンと比べたら高給であることは間違いありませんが、その一方で、長時間労働、医療ミスに伴う責任など、ストレスも多分にある職業です。特に勤務医の場合、「自分の資産を把握する余裕がまったくない」という方も多いのではないでしょうか? 多忙を極め、お金を使うアテもないから、気晴らしにギャンブルにはまってしまうという人すら耳にします。
-

節税方法としての確定拠出年金iDeCo
節税を考えたことがある方であれば、一度は「iDeCo(イデコ)」という言葉を聞いたことがあると思います。興味はあるけれど内容がよくわからないから手を出せない……そんな方も少なくないかもしれません。
そこで今回は、 “自分で作る年金”とも言われている「iDeCo」について、基本的な仕組みと、「節税」という点で利用できることについて詳しく解説します。 -
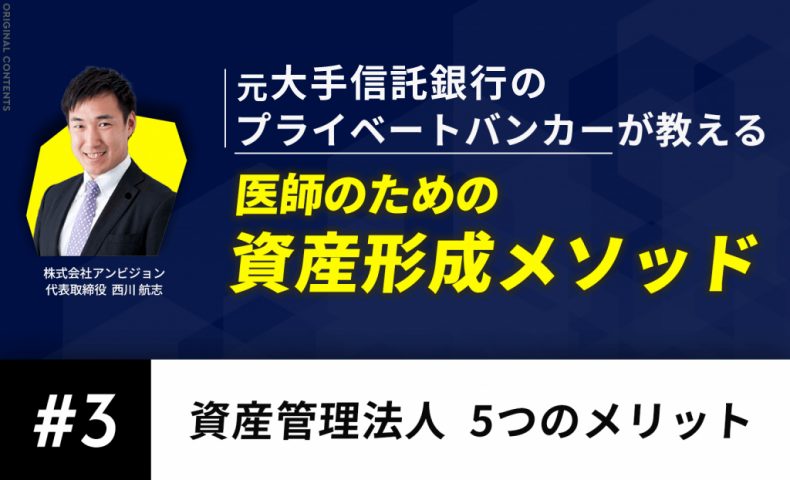
【元銀行員が教える】医師にできる 「資産管理会社」を使った節税対策とは?【後編】
本記事は過去に勤務医ドットコムで開催したセミナーの内容を記事にしています。
今回の記事では、資産管理法人設立のメリット・デメリットについて詳しく解説していきましょう。 -
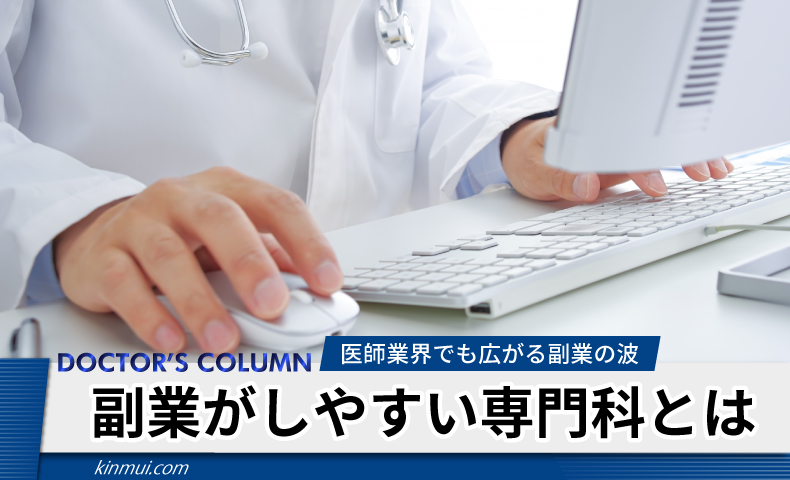
【現役医師連載コラム】副業がしやすい医師の専門科
こんにちは、医師で投資家の大石です。昨今、医師業界でも副業という言葉が少しずつ浸透してきています。
医師はただでさえ、医師免許という強力な参入障壁によって守られた「医業」という事業領域を持っていますから、副業なんてあんまり考えないのが普通です。
しかしながら昨今の副業ブームや、医療業界に対する漠然とした不安感、医療費削減の流れから、医師の中にも「医師免許に頼らない収入を作ろう」と考えている人が増えている、そんな印象を受けています。
さて、そんな医師の副業ですが、個人的には「ある程度副業のしやすい診療科は限られている」というのが、僕の感想です。
今回は、副業のしやすい診療科と、その詳細について、少しずつ考えていきたいと思います。 -

地域別医学部進学率の高い高校とその傾向とは?
「医学部に強い高校」というものがあります。これは文字通り卒業生の医学部への進学率が多い高校のことを指します。そこで今回は全国のランキングと、地域別医学部進学率の高い高校について各地域の上位3位までを紹介し、そこから読み取れる傾向を分析します。
まずは全国ランキングの一覧を紹介します。1位:東海高校(愛知/私立)、2位:洛南高校(京都/私立)、3位:開成高校(東京/私立)、4位:久留米大学附設高等学校(福岡/私立)、5位:ラ・サール高校(鹿児島/私立)、6位:桜蔭高校(東京/私立)、7位:愛光高校(愛媛/私立)、8位:灘高校(兵庫/私立)、9位:海城高校(東京/私立)、10位:豊島岡女子学園高校(東京/私立)、11位:南山高校(愛知/私立)、12位:四天王寺高校(大阪/私立)、13位:渋谷教育学園幕張高校(千葉/私立)、14位:滝高校(愛知/私立)、15位:白陵高校(兵庫/私立)、16位:聖光学院(神奈川/私立)、17位:麻布高校(東京/私立)、18位:熊本高校(熊本/私立)、19位:智辯学園若山高校(和歌山/私立)、20位:大阪星光学院(大阪/私立)。
有名私立高校の名前がずらりと並ぶ結果になっています。やはり有名進学校は強いですね。続いて、地域別のランキングを紹介します。 -

「高収入だけど、お金の悩みが尽きない…」開業医の不安をFPが解消!【前編】
今回は20年間メガバンクに勤務されたご経験をお持ちの洲濵拓志氏をお迎えして、開業を考えている勤務医に向けて「開業医の事業や資産に関する悩みについて」のスペシャルインタビューをお届けします。
「病院の経営」と「資産の形成」をキーワードに、金融業界と不動産業界の現場経験が豊富な洲濵氏のお話を伺いました。 -

【医師必見】30代から始める不動産投資でFIREする3つの方法
FIRE(Financial Independence Retire Early)を目指して30代の勤務医をはじめとする医師が不動産投資を始めようとしている人の中には、以下のような点に疑問を感じる人もいるのではないでしょうか。
■ FIREを達成するに必要な資産額(物件規模)■ FIREを達成するまでの具体的な方法■ FIREを達成できるタイミング
これらを明確にしないと目標とする物件規模や目標達成までの道のり、目標達成の概算時期が分からないため、やみくもに不動産投資を進めることになりかねません。本記事では、30代からの不動産投資でFIREを達成するまでの3つの方法とFIREを達成できる2つのタイミングについて解説します。 -

北海道リレーインタビュー VOL.2篠原信雄先生(北海道大学大学院 腎泌尿器外科 教授)
北海道で活躍されている医師の方にインタビューを行い、ご自身の取り組まれている医療分野やキャリア、資産形成などについてお聞きする本企画。
第二回は北海道大学大学院腎泌尿器外科教授の篠原信雄先生にお話を伺いました。医師として臨床研究の最前線に立ちながら、後進の指導も行われている篠原先生は、今の医学界や医師の働き方についてどのようにお考えなのでしょうか。 -

北海道リレーインタビュー VOL.3 井上哲先生(北海道大学大学院歯学研究院 教授)
北海道で活躍されている医師の方にインタビューを行い、ご自身の取り組まれている医療分野やキャリア、資産形成などについてお聞きする本企画。
第3回は北海道大学大学院歯学研究院教授の井上哲先生にお話をうかがいました。長年にわたり歯科保存分野での研究や治療に取り組みながら、臨床教育部において若手医師の育成に尽力される井上先生は、歯科医師を取り巻く現状や将来展望についてどのような考えをお持ちなのでしょうか。 -

【前編/地方在住20代医師インタビュー】常に学び続け自分に合う投資スタイルを見極めること
インターネットでどこにいてもあらゆる情報が手に入るこの時代。地方に暮らしながら利回りのいい都心のマンションのオーナーとなり資産運用を行う人が増えています。愛媛県松山市在住の田中先生もそんなオーナーの一人。現在、松山市から約670km離れた新宿と虎ノ門にそれぞれ区分マンションを所有しています。
28歳という若さでオーナーデビューをされた田中先生。年齢やマンションとの距離に関して不安はなかったのでしょうか。前編では、不動産投資に取り組もうと考えた背景や購入に向けてどう準備したかについてお話しいただきます。 -

仕事ばかりはNG! 家庭を顧みる時間を作ろう
ハードワークな医師のみなさんは、日々の業務に追われて、どうしても家庭をおろそかになってしまいがちです。そのため、家事や育児など家の仕事は全てパートナーの負担になり、気づけば家庭の空気が悪化してしまっていた……という話もよく聞きます。パートナーがいる医師にとっては、それが離婚の原因になることもあるようです。
-

【現役医師連載コラム】医師はいつマイホームを買うべきか?
医師にとってマイホームは、悩みのタネです。
マイホームをいつ買うか?
どこに買うか?
どれくらいの金額で買うか?
何年のローンを組むか?これらは医師以外でも、当然悩ましいわけですが、特に医師ならではのマイホームの悩みも、あります。
-

【後編/30代医師夫婦×担当営業対談】購入の決め手は還付金の多さ?確定申告で節税効果を実感
高額所得者の医師にとって不動産投資は節税メリットが大きい投資法です。しかし、金額が大きかったり、リスクに対する不安が拭い去れなかったりと、二の足を踏んでしまう方も少なくないかもしれません。
そこで、夫婦で不動産投資を実践されている、30代の松尾ご夫妻と営業担当の佐々木大地の対談を実施。不動産投資をはじめて2年あまりのお二人は、どのようなメリットやデメリットを感じているのでしょうか。後編では、不動産投資をはじめてから現在までの心境の変化や、不動産投資に対する印象の変化などについて語っていただきます。 -
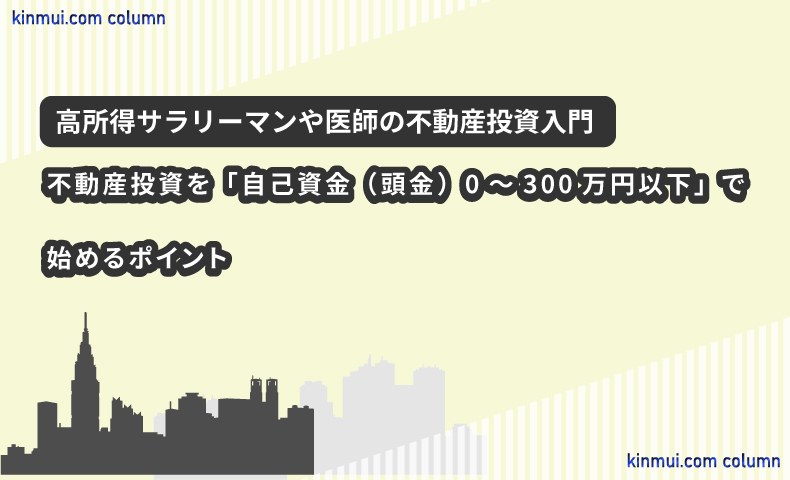
高所得サラリーマンや医師が不動産投資を「自己資金(頭金)0~300万円以下」で始めるポイント
医師や士業、高所得者サラリーマンの人は、社会的信用力がある特性を活かして不動産投資を「自己資金0~300万円以下」で始めることも可能です。少ない自己資金で不動産投資をスタートするには、金融機関からなるべく多くの融資額を引き出す必要があります。本稿では、そのためのポイントとなる「3つの信用力」について解説します。
-

独立・開業するために医師が知っておくべき不動産の知識
勤務医として働く医師にとって一つの夢である自身のクリニックの開業。ただ、開業を夢物語で終わらせずに成功するためにはさまざまな知識や努力が必要です。クリニックを開業する地域の特性など、不動産の知識も把握し、駆使することも成功への近道だといえるでしょう。
-

不動産投資の契約時の注意点
実際に不動産投資を行う場合、投資用の物件を購入する際の売買契約を行うところから始まります。この契約時に投資家が注意すべき点についてまとめました。
また、売買契約書作成から契約締結に至るまでのプロセス等も合わせて解説してまいります。 -
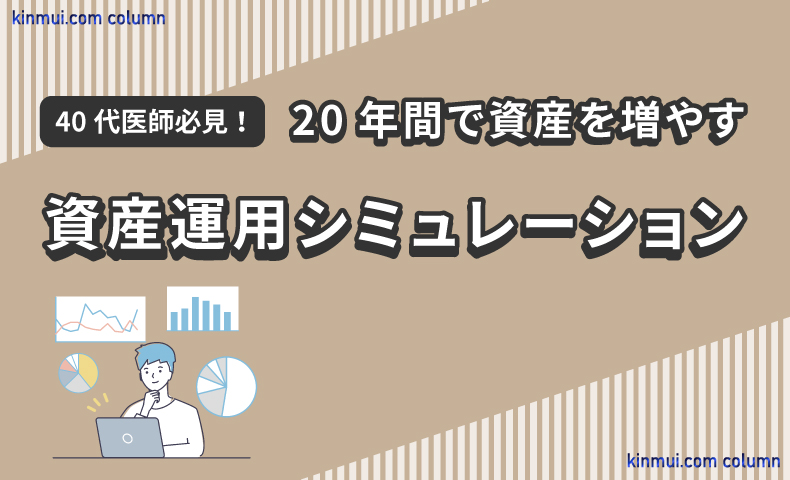
40代医師必見!20年間で資産を増やす資産運用シミュレーション
新型コロナウイルスの感染拡大以降、経済的に不安定な状況が続くなか、公的年金だけで老後を過ごすことに不安を覚える勤務医も多いでしょう。ある程度の資産を築いた40代から60代までの20年間で資産をどこまで増やせるかが老後生活の鍵を握ります。そこで、40代から資産運用を始めてどこまで資産が増えるか、主な投資方法と運用利回り別のシミュレーションを紹介します。
-
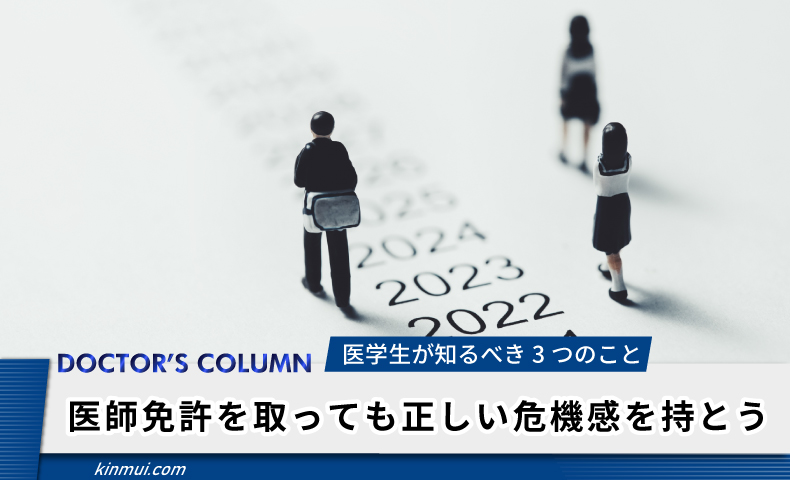
【現役医師連載コラム】「医師免許を取れば一生安泰」と思っている医学生が知るべき3つの事
医師免許を取れば、一生安泰だ。
そう周りには言われていましたし、僕も昔はそう思っていました。
それなりの生活をする事は常にできる、大した努力をしなくてもお金に余裕のある生活ができる。そう思っていました。
しかしながら時代が移り変わり、必ずしもそうとも言い切れない状態になりつつあります。
今回はそんな、医学生が知るべき「医師免許にまつわる不都合な真実」についてです。 -
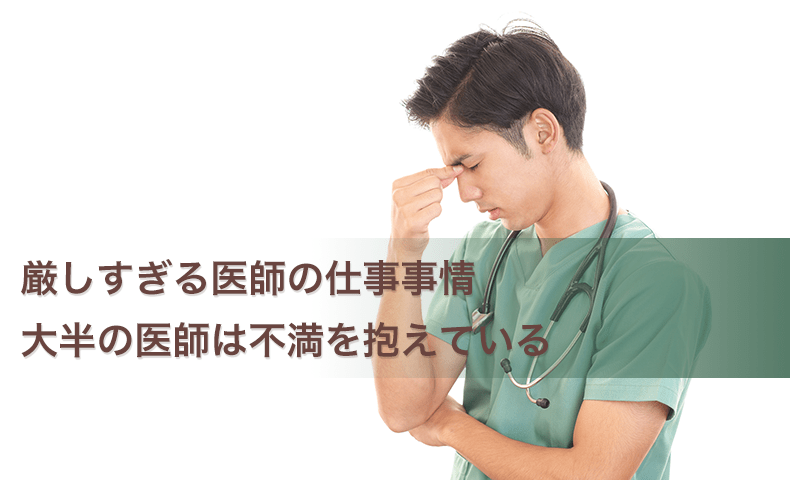
辛すぎる仕事漬けの日々……大半の医師は不満を抱えている
医師のなかで、仕事漬けの日々を送っていない人(あるいは送った経験がない人)はまずいないのではないでしょうか。当然、過酷な労働環境であれば、さまざまな不満も出てきます。ここでは厳しすぎる医師の仕事事情を紹介します。
-

不動産投資は副業とみなされるのか?
自身の本業を持ちながら不動産投資をすることが、「副業」にあたるのか不安に思われる方も少なくありません。事実「副業を禁ず」と社則に定めている企業もありますし、公務員の場合、公務員法という法律によって兼業や副業が禁じられています。
では、不動産投資は副業とみなされるのか、サラリーマンが不動産投資をすることはいけないことなのかについてまとめました。 -
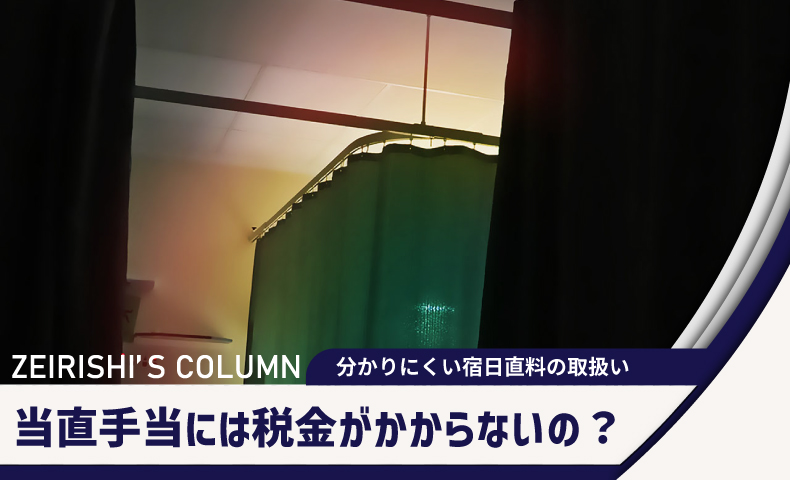
【税理士連載コラム】当直手当には税金がかからないの?
一般的に、「当直」とは所定労働時間外に通常労働とは異なる軽微な労働(基本的には待機労働)に従事することをいい、日中に行う当直は「日直」、夜間に宿泊を伴って行う当直は「宿直」と呼ばれています。
では、当直手当の中に、所得税が非課税となる部分があることはご存知でしょうか。本来、会社から従業員に対して支給される基本給・各種手当などは、そのほとんどに所得税が課せられます。にもかかわらず、なぜ当直手当は一部が非課税となる「税務上の特別な配慮」がなされているのでしょうか。 -

【現役医師連載コラム】大繁盛、開業2ヶ月…なぜあのクリニックは潰れたのか?
クリニックって、潰れる時はどうやって潰れるのか?
考えたことはありませんでしょうか。
今回は、僕が見聞きした中で、個人が特定できない範囲で、簡単に紹介しようと思います。
これから開業を考えている先生はもちろん、既に開業されている先生や、研修医の方も参考になると思います。
それではどうぞ。 -

「高収入なのに、お金が増えない…」勤務医の悩みをFPが解消!Part.1
今回は、20年間メガバンクに勤務されたご経験をお持ちの洲濵拓志氏をお迎えして、勤務医の「お金の悩み」についてのスペシャルインタビューをお届けします。
第1回目は、勤務医ならではの資産形成について、ファイナンシャルプランナーである洲濵氏にお話を伺いました。 -
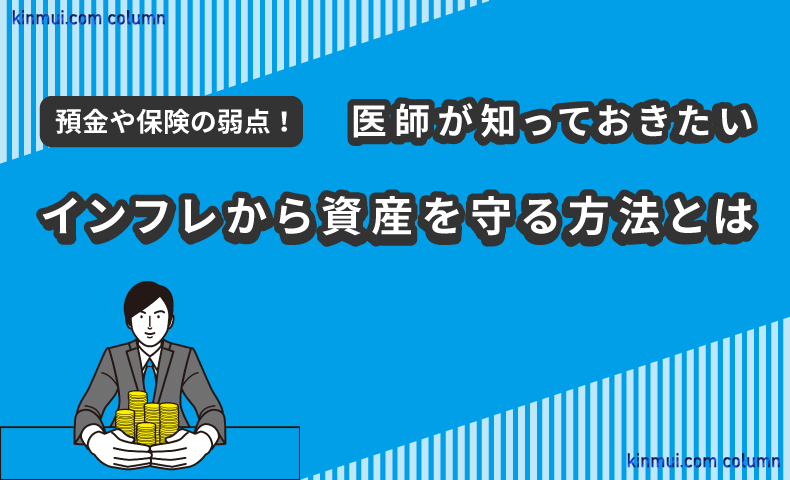
預金や保険の弱点!医師が知っておきたいインフレから資産を守る方法とは
投資は、元金が保証されているわけではないため、当然損をするリスクがあります。そのため「資産はできる限り安全な現金で保有したい」「銀行に預けて老後や万が一の場合に備えて保険に加入したい」といった資産形成を考えている人は多いのではないでしょうか。1985年ごろのバブル最盛期であれば銀行預金金利は、年率5.5%もありました。
そんな時代であれば現金を銀行に預けておくだけで資産が着実に増えていく状況が実現できたでしょう。しかし銀行預金金利が0.001%(2021年5月時点)の時代においては、預金の利息をあてにするのは得策とはいえません。預金と保険を中心に資産形成を考えるのであればインフレリスクと金利についてもしっかりと押さえておくことが必要です。
本記事では、預金と保険のみで資産形成をすることのリスクと低金利時代にインフレから資産防衛をするために有効な4つの資産について解説します。 -

勤務医は何故「いつまでもお金を貯められない」のか?
勤務医として働いている医師の平均年収は1200万円~1500万円といわれています。世間一般からすると高収入であることは間違いありませんが、実はこのあたりの年収が一番、税務の面で“損”をしているのです。そんな勤務医のみなさんが投資用不動産を購入することによって得られるメリットについて考えます。
-

【現役医師連載コラム】最近の若手医師の生態と、その理由
いきなりですが、皆さんの周りには研修医、もしくは研修医が終わった後くらいの若手医師は、いらっしゃいますか?
そして、その若手医師と一緒に仕事をしてみて、どう感じるでしょうか?
先に断っておきますと、今回は「最近の若いのはけしからん!」みたいな内容を書くつもりはありません。
少し話はそれますが、古代遺跡に残された文字列にも、どうやらそういった内容の文章があった、というようなニュースをどこかで見ました。おそらくこの「最近の若いのはけしからん!」というフレーズは、大昔から言われているのではないでしょうか。
その理由としては、やはり世の中は常に変化していて、その変化を鋭敏に察知して適応しようとする力が若者にはあるので、世代間で価値観の差や考え方の乖離が生まれるのは、ある意味当たり前なので、「最近の若いのはけしからん!」というフレーズが古代から存在するのも、当たり前なのかもしれません。
さて、今回は僕が感じた「最近の若い先生の傾向」と、その理由について、僕の主観で考察してみました。 -

医師でも車の購入を節税に生かすことができる!
賢い経営者は、車などをはじめとする個人的なもののように思える物品も、節税に利用しています。これは「経営者=事業主」のみが行える節税の手法ですが、医師でも「開業医」や「プライベートカンパニーを持っている勤務医」であれば、同様に車の購入を節税に生かすことが可能です。
なぜ車の購入が節税になるのか、車以外に節税になる買い物はあるのかなど、詳しく解説していきます。 -
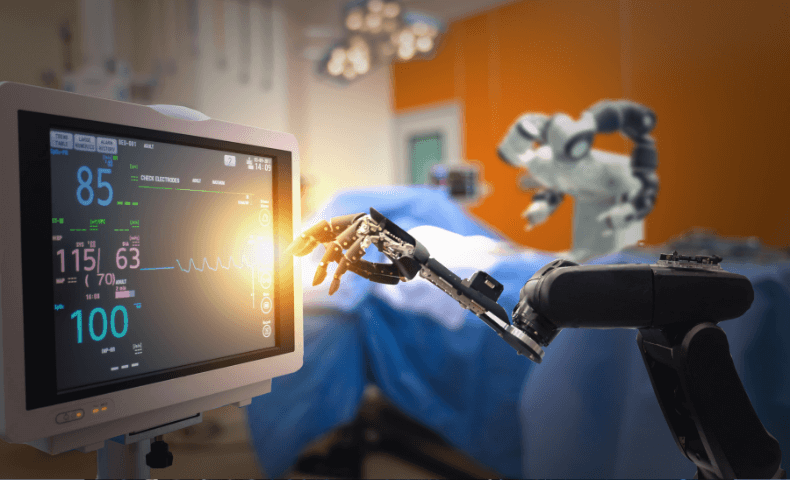
進化を続けるAIは医療現場にどのような影響を及ぼす?
アメリカでAI(人工知能)による臨床実験が進み、「将来は医師の仕事が減る」という試算が出ているのをご存じですか? 2013年に発表されたオックスフォード大学のマイケル・A・オズボーン准教授の論文「雇用の未来」により、今後10~20年でAIにより代替される可能性のある職業が日本でも大きな話題になりましたが、医師もその例外ではないかもしれません。AIの領域が拡大する未来に、人間の医師だからこそできることとは何でしょうか。
-

【後編/地方在住20代医師インタビュー】「この人なら頼れる」。営業マンとの出会いが購入の決め手に
都心部の投資用マンションを運用する地方在住オーナーにとっての不安要素は、運用するマンションと居住地が離れていること、土地勘を持っていないこと。安心を得るためには、管理会社や営業担当者との緊密なリレーションシップが欠かせません。
松山市ご出身・ご在住の田中先生は、そうした不安を営業担当者との密接なやりとりによって払しょくしました。後編では、WINXの営業担当である沖野氏との出会いや普段のやりとりについて、また今後の不動産投資やご自身のキャリアについてどのようにお考えなのかをお聞きします。 -

所得の多い医師に最適 個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)とは
税制優遇のある個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)をご存じでしょうか?
開業医の方は経営者であり、厚生年金や企業年金に加入する事が出来ませんので、将来の年金対策を手厚くしておく必要があります。
また勤務医の方も老後の資産形成として、老後2,000万円問題のニュース等で「公的年金以外の備えが必要」と感じる方もいらっしゃることでしょう。
所得の多い医師がiDeCoを利用することで、より多くの節税効果が期待できます。
この記事ではiDeCoの概要やメリット・デメリット、医師がiDeCoを始めたほうが良い理由についてお伝えしていきます。
節税しながら老後の資産形成を行いたいという方は、ぜひご覧ください。 -
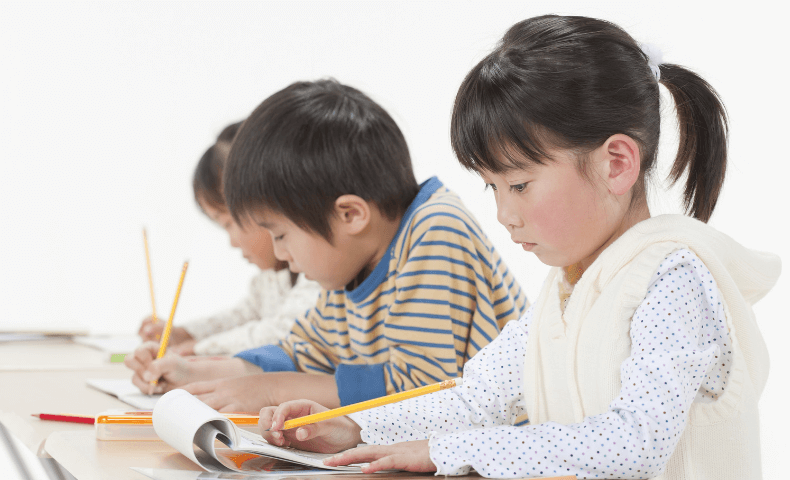
将来は医学部に? 今から始める子どものお受験
開業医が考えることの一つに「跡継ぎ問題」があります。ゆくゆくは自分の子どもに医師になって欲しい、そのためには子どもを医学部に入れたいと考えてはいるものの、何から始めたらよいのか悩んでしまうという方も少なくないでしょう。そこでこの機会に、小学校から中学、高校、大学とすべて私学に通った場合いくらかかるのかなど、子どもの教育に関する情報を押さえていきましょう。
-
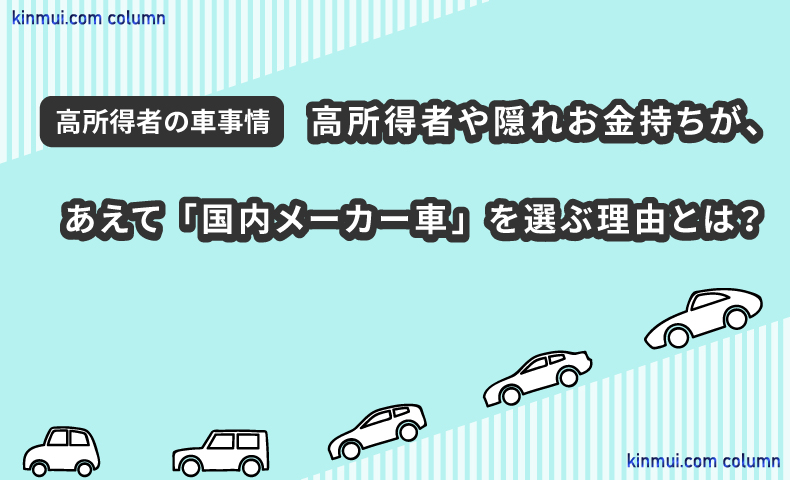
医師を含む高所得者や隠れお金持ちが、あえて「国内メーカー車」を選ぶ理由とは?
高所得者の愛車といえばメルセデス・ベンツやBMW、レクサスなどの高級ブランド車を想起する人も多いのではないでしょうか。しかし実際は収入が平均より多くても国内メーカー車を選んでいる人も相当数います。本記事では「高所得者のうちどれくらいの割合が国内メーカー車を選んでいるのか」「隠れお金持ちが国内メーカー車を選ぶ理由は何か」について考察します。
-

【FP連載コラム】人生3大支出のうちの1つの住宅費、マイホーム購入と一生賃貸のどちらがお得なのか?
初めまして、今回より勤務医ドットコムのコラムを執筆させていただくことになりましたファイナンシャルプランナーの長尾真裕美と申します。
ご相談者の住居・教育・老後資金等のライフプランニングのアドバイスをしております。
不定期ですがコラムを通して勤務医を中心とした医師の皆様に有益な情報を発信してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
さて早速、表題の「マイホーム購入派と賃貸派」、医師の皆様はどうお考えでしょうか。戸建派とマンション派と同様、ちまたでよくこれらの議論を見かけますよね!!
両者の意見をまとめると以下のような主張です。 -

高所得の医師向けふるさと納税攻略法(おすすめ返礼品5選あり)
何かと話題に事欠かないふるさと納税ですが、近年では人気の返礼品がある程度固まってきた感もあり、制度として定着してきた印象を受けます。この記事を読んでいる方の中にもすでにふるさと納税を経験した方は多いかもしれません。ふるさと納税の返礼品としては、和牛や果物などご当地の高級食材が目立つことから「こうした返礼品をもらうための制度」とイメージしている方もいるでしょう。
しかし実際にはそれ以外にも実に多彩な返礼品が用意されており、こうした高級食材はほんの一部にすぎません。そこで今回は、すでに制度として定着しつつあるふるさと納税について当メディアの読者層に多い年収1,000万円以上の医師(勤務医)におすすめの攻略法や返礼品を紹介します。高所得者には、高所得者ならではの楽しみ方があるのでぜひご参考にしてください。 -
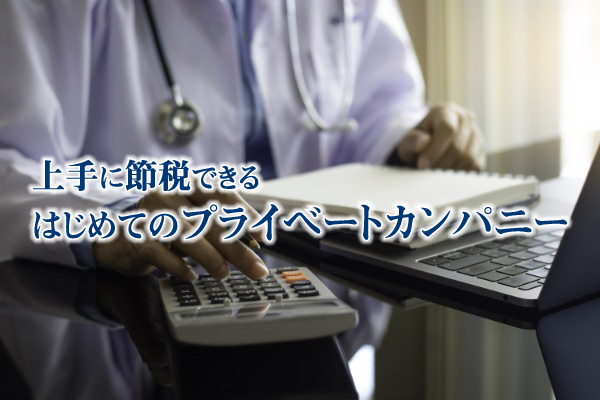
勤務医や高収入会社員が上手に節税できるはじめてのプライベートカンパニー(法人化)
勤務医を中心とした医師や高収入の会社員にとって、悩みの種はその高収入による税率の高さです。激務に耐えてお金を稼いでも、税金が高いため、思ったほど手元には残らず、資産形成も思うようにならないとお悩みでしょうか。
このような場合、プライベートカンパニーを設立して節税をすることが出来ます。本記事では、はじめてプライベートカンパニー設立を検討する医師(勤務医)・高収入の会社員が知っておくべきことをまとめました。 -

医師の妻に求められる資質と、医師自身がすべきこと
「高収入で社会的地位の高い医師の妻になりたい!」という女性は世の中にたくさんいます。しかし、一般的なサラリーマンとは仕事のサイクルが大きく異なる医師と結婚して、幸せな生活を送るのは、想像以上に大変なことです。
そこで今回は医師の妻に求められる資質や医師が努力すべきポイントをまとめてみます。これから結婚を考えている医師の方は、ぜひ参考にしてみてください。 -

医師(勤務医)の平均年金はいくらなのか?制度概要を解説
老後のことは考えずに毎日楽しく生きていきたいものですが、避けては通れないものに老後の生活を支えてくれる「年金」の問題があります。そこで今回は、医師を対象とする公的年金から民間の個人年金保険まで、“医師に関する年金”に関して解説します。
-

勤務医に向いているマイクロカンパニーで節税する方法
自分1人でも会社を興すことができる「マイクロカンパニー」が注目されています。高年収の勤務医にとっては「相性がよい」といわれていますがマイクロカンパニーを設立するとどのようなメリットがあるのでしょうか。本記事では、マイクロカンパニーの概要とマイクロカンパニーを使って節税する方法を紹介します。
-
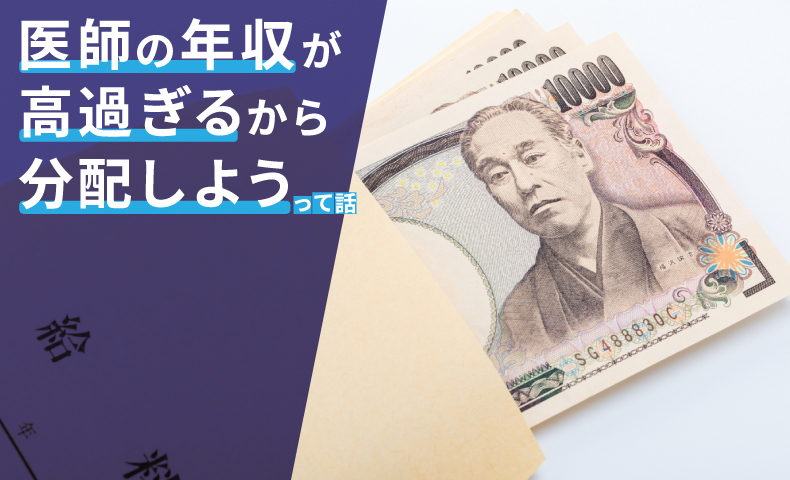
【現役医師連載コラム】医師の年収が高過ぎるから分配しようって話
皆さんこんにちは、いきなりですが、お医者さんの給料がニュースになりました。
-
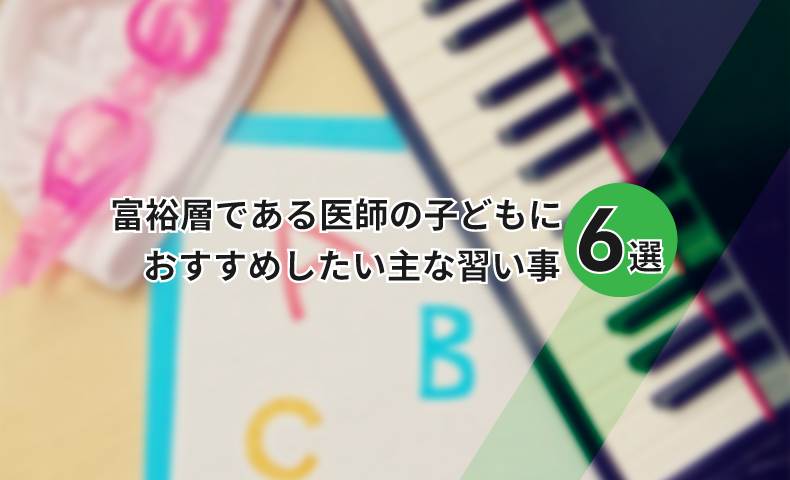
将来への投資?富裕層である医師が力を入れている子どもの習い事とは
親であれば誰もが「将来自分の子どもが社会で活躍してほしい」と願うことでしょう。特に富裕層である医師は、子どもに習い事をさせる親が多い傾向です。社交界や実業界にデビューする際に困らないようにするための将来への投資と考えることもできます。富裕層は、子どもにどのような習い事をさせているのでしょうか。
-
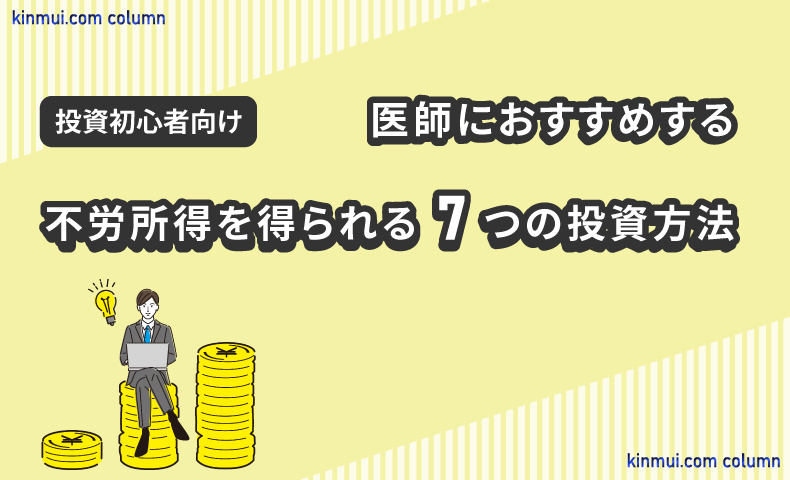
【投資初心者向け】医師におすすめする不労所得を得られる7つの投資方法
収入アップや老後の備えセミリタイアなどを目的に「不労所得を得たい」と思った医師の方も多いと思います。近年は、副業に取り組む勤務医を中心とした医師が増えていますが何から始めたらよいか分からない人も多いかもしれません。そこで本記事では、初心者医師向けに不労所得を得られる投資方法を7つ紹介します。
-

フリーランス医師の働き方と開業届による節税効果
医療業界における価値観や仕事観が変化する近年の日本では、「フリーランス」という働き方を選ぶ医師が増え始めています。
勤務医として働く医師の多くが抱く長時間労働や人間関係の悩みとは無縁ともいえるフリーランスは、ワーク・ライフ・バランスを重視する人には特におすすめのワークスタイルです。
また、結婚や妊娠、出産といったライフイベントにより、キャリアの継続に支障が出ることの多い女性医師の間でも、自分のペースで働くことのできるフリーランスは注目されています。
そこでここでは、フリーランス医師という働き方の魅力と収入アップ時に実践したい節税を分かりやすく解説します。 -
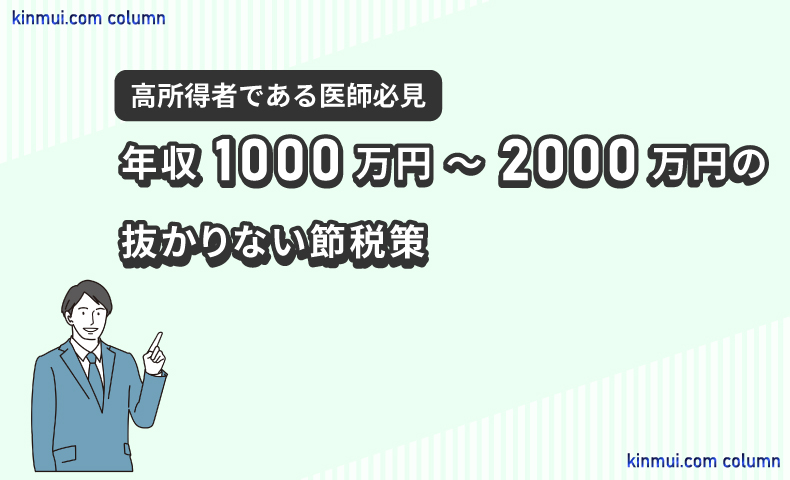
勤務医で年収1000万円~2000万円の抜かりない節税策
働き方改革の一環で「103万円の壁」といわれたパートで働く人の扶養控除の是正をはじめ、平均的な所得層向けの所得税の改訂が行われました。一方で1,000~2,000万円超の勤務医を中心とした医師にとっては大きな増税となっています。ここでは、その問題を学んでみましょう。
-
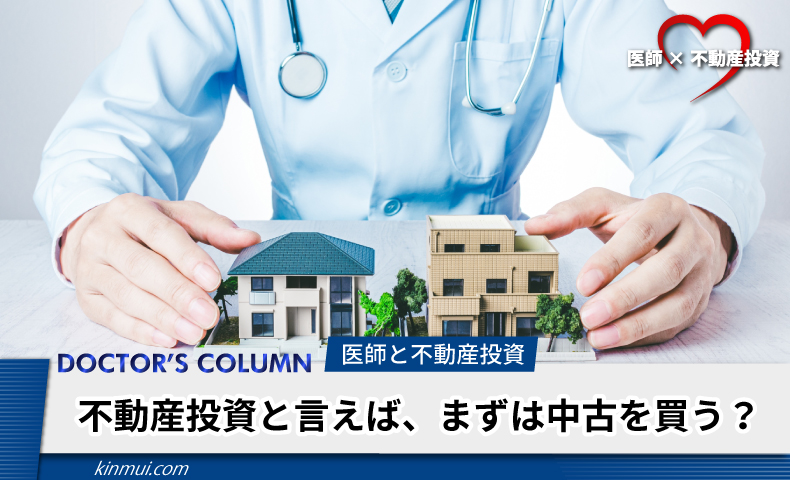
【現役医師連載コラム】医師の不動産投資は「新築」が良い理由
不動産投資と言えば、まずは中古を買う、というイメージがあると思います。この心理状態の裏にあるロジックは単純で
新築は建築業社の利益が乗っているから、美味しくない
というロジックです。これは一見すると正しそうに見えますが、一概にそうとは言えません。 -

【医師執筆】勤務医は激務?割に合わないと言われる理由を解説
現在医師人気が高く医師人口は増えてきております。また、国も医師の絶対数を増やすために新規の医学部を増設したりなどの制作をしている今日この頃です。
人気の理由としては医師という仕事は平均給与が高い職業であるというのがまずは大きいでしょう。
しかし、そんな中でも医師という職業は「大変そう」、「まったく寝ていなさそう」などというイメージがある方も多いと思います。では時給換算するとどうでしょうか?
おそらく、医師(勤務医)の方で激務の方は一度は考えたことがあるのではないでしょうか。医師という職業は年収はだいたい1,000~2,000万円くらいに収まっている方が多いと思います。
しかし、時給換算で見てみたら働き方によっては雲泥の差があると思います。
医師は勤務先によって時給が全く異なってくるので今回はこの「時給」という観点からコメントしていきたいと思います。
時給が高ければ少ない時間でも高収入になるので、それだけQOLが高くなるため非常に気にされる方も多いと思います。
今後医師になる方でこの記事を読んでくれる方にはその辺が参考になればと思います。 -
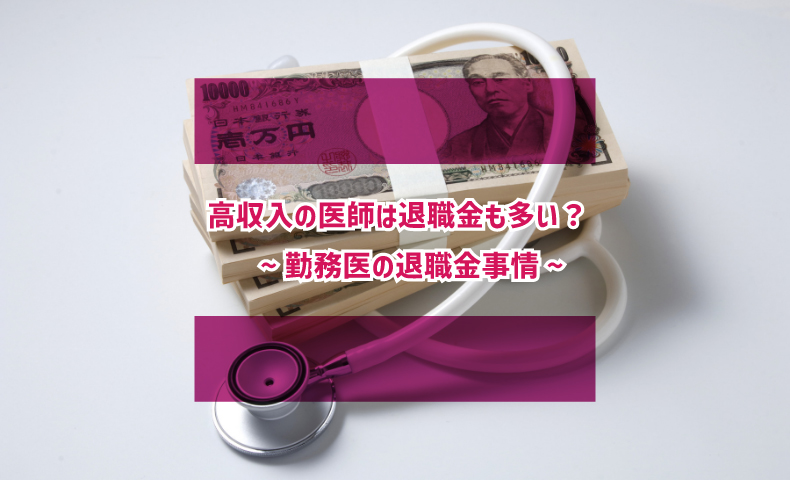
高収入の医師は退職金も多い? 勤務医の退職金事情
定年退職後の生活を考えるうえで重要な「退職金」。医師は高収入のため退職金も多くもらえるイメージがありますが、実際のところはどうなのでしょうか? 今回は医師の中で勤務医の退職金事情に着目します。
-
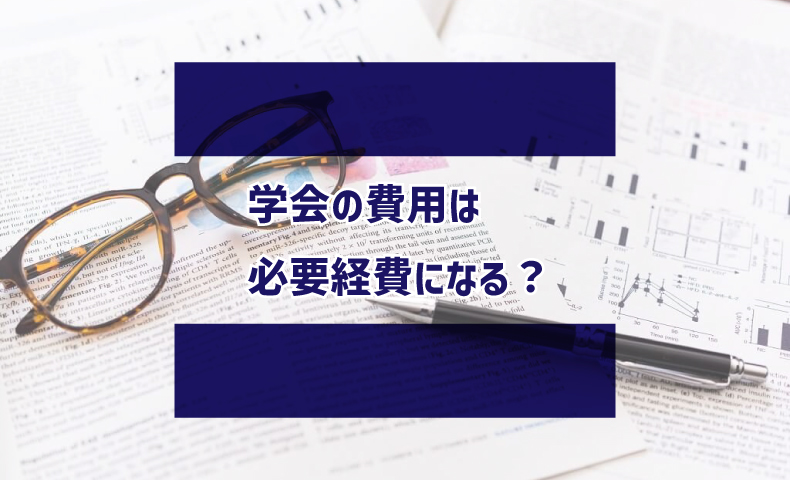
学会の費用は必要経費になる?
医師は勤務するクリニックで患者の診察をするだけでなく、学会に参加して最先端の医療技術を学ぶことも重要な仕事の一つです。
学会に参加する場合は、移動のための新幹線代や飛行機代、宿泊のためのホテル代など、さまざまな費用がかかるものです。これらは会計上、「経費」にすることができるのでしょうか? 実際、どこまでを経費として計上してよいのか、頭を抱えている医師の方も少なくないことでしょう。そこで今回は、学会費に関する経費計上について解説します。 -
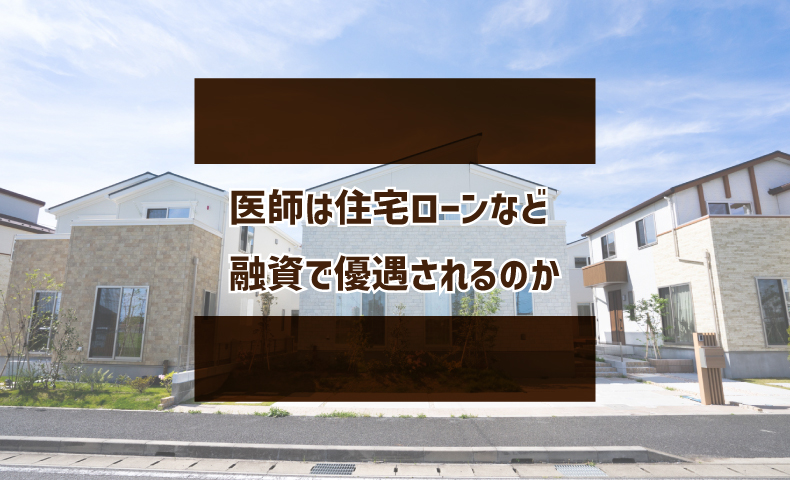
医師は住宅ローンなどの融資で優遇されるのか
一般的な会社員よりも収入が高いといわれている医師。住宅ローンを組む時もその収入が有利に働く部分はあるのでしょうか。
この記事では、医師が住宅ローンを組む際に、優遇があるのか、そして注意点についてもご紹介します。これから住宅を購入したい人はぜひ参考にしてください。 -

「投資の勧誘電話」をしてくる営業マンは、どこで連絡先を知ったのか?
不動産・証券などの投資会社から、資産運用を促す「迷惑電話」が来たことはないでしょうか。自宅だけでなく勤務先にまでかけてくるケースもあり、「どうしてここがわかったの?」となる方もいるはずです。こうした迷惑電話がなぜかかってくるのか、狙いはなんなのか、どう対応すればよいのかを解説します。
-
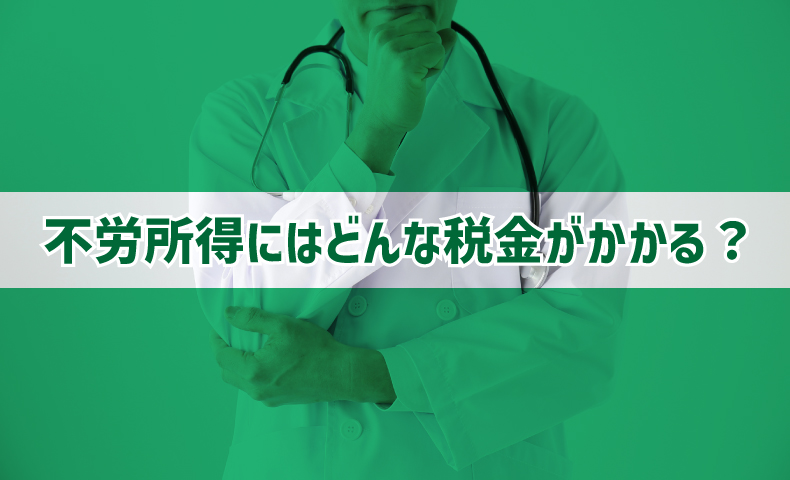
不労所得にはどんな税金がかかる?課税所得や税金の種類、確定申告が必要なケースを解説
将来のお金に対する不安から不労所得を目的に副業に取り組む会社員が増加傾向です。不労所得には、いくつかの種類があり分類される所得に応じて税金がかかります。そのため副業を始める前に不労所得の税金について理解しておくことが大切です。今回は、不労所得でかかる税金の種類や確定申告について詳しく解説します。
-
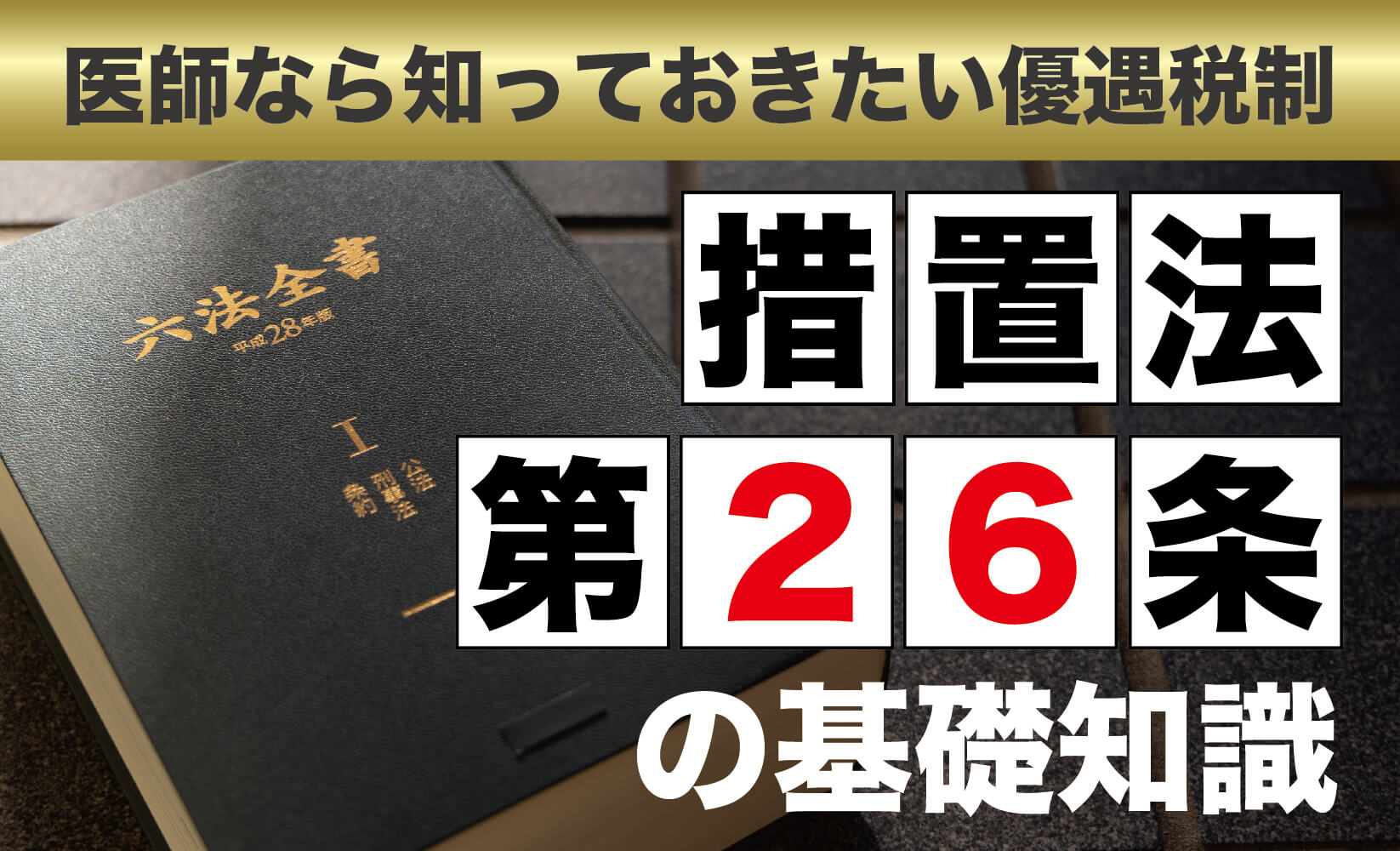
医師なら知っておきたい優遇税制~措置法第26条~の基礎知識
「租税特別措置法第26条」をご存知ですか? 開業医の経営安定と医療の安定供給を目的とする制度ですが、実は、医業従事者の所得に対し、高い節税効果が期待できると言われています。現在勤務医をされている方は、開業すれば収入がアップしますが、税金も増えるのが悩ましいところです。この優遇税制を正しく理解・適用すれば、かなりの節税が可能になります。
この記事では、租税特別措置法第26条の概略とメリットはもちろん、具体的な計算方法と注意点もまとめてみました。ぜひ今後の節税にお役立てください。