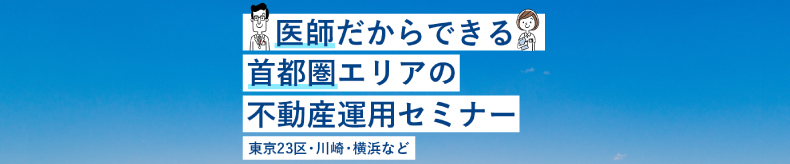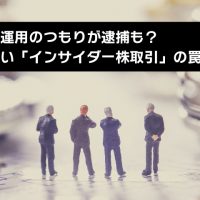勤務医として働いている医師の平均年収は1200万円~1500万円といわれています。世間一般からすると高収入であることは間違いありませんが、実はこのあたりの年収が一番、税務の面で“損”をしているのです。そんな勤務医のみなさんが投資用不動産を購入することによって得られるメリットについて考えます。
年収1000万円あたりの医師を苦しめる「累進課税制度」
「年収は普通のサラリーマンより多いはずなのに、なかなか手元にお金が残らない」
そう感じている勤務医の方は、意外に多いのではないでしょうか。
医師の中でも勤務医のみなさんは毎年、常勤先やアルバイト先などの病院から受け取った収入に対して所得税を支払っています。
所得税の税額は、収入の合計から必要経費や社会保険料などを差し引いた金額(これを「課税所得金額」といいます)に、一定の税率を掛けて計算します。
日本では、「累進課税制度」と呼ばれ、課税所得金額が多くなればなるほど、所得税率が上がる制度が採用されています。現在の所得税率は、最低5%から最高は45%までの7段階になっており、その差は40%にもなります。
これが、高収入である勤務医のみなさんにとって、「なかなか手元にお金が残らない」大きな原因のひとつです。
所得税の税額の速算表は、次のとおりになっています[図表1]。ここで注意したいのですが、たとえば課税所得金額が900万円から901万円になったら、適用される税率が23%から33%へ、一気に10%もアップするわけではありません。実は、累進課税制度はさらに「単純累進税率」と「超過累進税率」にわけられます。日本の所得税は「超過累進税率」を採用しています。
いまの例でいうと、課税所得が901万円の場合、900万円を超えた1万円の部分だけが税率33%になります。それ以下、900万円までの部分も、195万円までの部分の税率は5%、195万円超え330万円までの部分の税率が10%、330万円超え695万円までの部分の税率が20%、695万円超え900万円までの部分の税率が23%という具合に、段階を追ってアップするのです。
なお、いちいち税率の区分ごとに計算するのは面倒なので、一度にわかるように用意されているのが「速算表」です。この「速算表」を使うと、たとえば課税総所得が1500万円の場合の所得税は次のようになります。
1500万円 × 33% - 153万6000円 = 341万4000円
「超過累進税率」は「単純累進税率」に比べると、高収入の人にとって重税感はやや抑えられますが、それでも所得が増えるにつれて、適用税率が高くなっていくのは事実です。
特に、課税総所得900万円を超えると税率が10%もアップすることが、平均年収1200万円~1500万円ほどといわれる勤務医のみなさんに大きな影響を与えるのです。
【[図表1] 所得税の速算表(平成27年分以降)】
| 課税総所得額 | 税率 | 控除額 |
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1800万円を超え4000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
年々引き下げられる「給与所得控除」もネックに
先ほど、所得税の税額は、収入の合計から必要経費や社会保険料などを差し引いた「課税総所得」に一定の税率を掛けて計算すると述べました。
このなかでもうひとつ、医師(勤務医)のみなさんが「なかなか手元にお金が残らない」と感じる原因が、「必要経費」の扱いです。
必要経費というと、仕事に実際にかかった支出がすべて含まれると思いがちです。しかし、勤務医を含めて「給与」として収入を得ている人の場合、その扱いが少し変わっています。
このようなケースでは、必要経費を個別に計算するのではなく、給与の金額をベースに一定の式に当てはめて計算した「給与所得控除」を使うのです。給与所得を得ている人が、個別の経費をひとつひとつ計算するのは非常に煩雑で現実的ではないことから、給与の額に応じて一律に計算することになっているのです。
問題は、この「給与所得控除」が近年、どんどん引き下げられていることにあります。 [図表2]にもあるように、平成25年分から平成27年分で上限245万円(給与収入1500万円超)だったものが、平成29年分から平成31年分では220万円(給与収入1000万円超)になり、さらに平成32年分以降からは195万円(給与収入850万円超)になります。
これは、給与収入は変わらなくても、税金を差し引いて手元に残る金額は減っていることを意味します。
「なんだか手取りが少なくなっているな」と感じているとしたら、この「給与所得控除」の影響かもしれません。
[図表2] 給与所得控除額
<平成25年分から平成27年分>
| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除 |
| 180万円以下 | 収入金額 × 40% ※65万円に満たない場合は65万円 |
| 180万円を超え360万円以下 | 収入金額 × 30% + 18万円 |
| 360万円を超え660万円以下 | 収入金額 × 20% + 54万円 |
| 660万円を超え1000万円以下 | 収入金額 × 10% + 120万円 |
| 1000万円を超え1500万円以下 | 収入金額 × 5% + 170万円 |
| 1500万円超 | 245万円(上限) |
<平成28年分>
| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除 |
| 180万円以下 | 収入金額 × 40% ※65万円に満たない場合は65万円 |
| 180万円を超え360万円以下 | 収入金額 × 30% + 18万円 |
| 360万円を超え660万円以下 | 収入金額 × 20% + 54万円 |
| 660万円を超え1000万円以下 | 収入金額 × 10% + 120万円 |
| 1000万円を超え1200万円以下 | 収入金額 × 5% + 170万円 |
| 1200万円超 | 230万円(上限) |
<平成29年分から平成31年分>
| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除 |
| 180万円以下 | 収入金額 × 40% ※65万円に満たない場合は65万円 |
| 180万円を超え360万円以下 | 収入金額 × 30% + 18万円 |
| 360万円を超え660万円以下 | 収入金額 × 20% + 54万円 |
| 660万円を超え1000万円以下 | 収入金額 × 10% + 120万円 |
| 1000万円超 | 220万円(上限) |
<平成32年分以降>
| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除 |
| 162万5000円以下 | 55万円 |
| 162万5000円を超え180万円以下 | 収入金額 × 40% - 10万円 |
| 180万円を超え360万円以下 | 収入金額 × 30% + 8万円 |
| 360万円を超え660万円以下 | 収入金額 × 20% + 44万円 |
| 660万円を超え850万円以下 | 収入金額 × 10% + 110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
医師(勤務医)に不動産投資をお勧めできる3つの理由
このような影響を受け、一般的には高収入である医師(勤務医)のみなさんであっても、手元になかなかお金が残らないのです。
これをなんとか改善できないかということで、不動産投資に関心を持つ医師(勤務医)の方が増えています。
その理由はどこにあるのでしょうか。
第一にあげられるのは、医師としてのお仕事に支障をきたさないで、副収入を得られるということです。もうひとつの収入源があれば、手元に残るお金も増えるはずです。
不動産投資はそもそも、賃貸マンションやアパートなどの不動産を購入し、それを人に貸すことで毎月、賃料収入を得るのが主な目的です。物件を購入し、入居者が入るまで多少手間はかかりますが、いったん事業がスタートすれば、物件の管理や入居者とのやり取りは管理会社に任せておけばよく、ほとんどやることはありません。
第二にあげられるのは、同じ投資でも株式や外国為替(FX)のように、値動きに一喜一憂する必要がないということです。株式や外国為替(FX)では、短期間に投資資金が何倍にもなることがありますが、逆に相場の急落でゼロになる可能性だってあります。
それに比べ、不動産投資はミドルリスク・ミドルリターンといわれ、賃料や地価などの変動は緩やかであり、なにより投資資金がゼロになることはほぼ考えられません。
そして、第三にあげられるのが節税効果です。不動産投資を始めた当初は、各種費用が膨らみやすく、不動産所得は赤字になるのが一般的です。この赤字を、給与所得と損益通算することで、所得税の税額を抑えることができます。
しかも、不動産所得の赤字は計算上のもので、実際には建物などの減価償却費のように支出を伴わない経費が少なくありません。
所得税を減らしながら、安定したもう1つの収入源をつくるということが、医師(勤務医)のみなさんにとって大きなメリットといえるでしょう。
不動産運用セミナーTOPはこちら