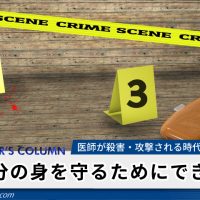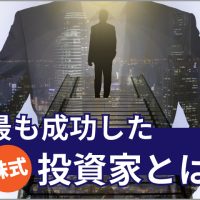医師は、一般の人よりも高収入であるため、当然ながら資産がたまりやすい傾向にあります。厚生労働省が公表しているデータによると、医師の平均年収は1,200万円を超え、生涯賃金は約6億円にも及びます。
日本の平均年収がおよそ500万円、平均生涯賃金が約2億5,000万円なので、いかに医師の報酬が高いかが分かります。
しかし、資産が多いということは、相続対策をしっかり行わないと、いざ相続というときに莫大な税金を支払うことになります。相続税の最高税率は55%にも及び、一般的に相続は三代続くと資産の大部分を失うといわれています。相続税は、誰しも逃れることができないものですが、時間をかけてしっかり対策を行うことは可能です。
今回は相続対策で有効な方法である暦年贈与について解説します。
あえて110万円を超える生前贈与が行われているのはなぜ?
歴年課税を活用した贈与は、数ある相続税対策のなかでも以前から用いられてきた、最もポピュラーな方法です。
贈与税の暦年課税には贈与を受ける人、1人あたり110万円の基礎控除があるため、110万円以下の贈与であれば課税されず、申告の必要もあません。そのため、110万円以下の現金贈与を長期間にわたって行い、無税で生前贈与を行う人が多いのです。シンプルかつ、効率的な節税対策として人気があるのはそれゆえです。
一方、贈与金額を「あえて」110万円超とし、贈与税を払ってでも生前贈与を行っている方が、ここ数年で急増しています。贈与税を支払った人は、2012年が29.2万人だったのに対し2017年は36.9万人と7万人以上増加しています。110万円以下であれば無税にも関わらず、税金を払ってまで贈与するメリットはズバリ相続税を減らすためです。贈与税で払う税金と相続税で払う金額を天秤にかけ、贈与税を払う選択をする人が増えてきているのです。
贈与の金額が310万円までであれば、贈与税の税率は最も低い10%で済みます(贈与税は200万円までは税率10%です)。そのうち110万円は基礎控除なので、310万円までの贈与は10%の税率になります。つまり、高い税率の相続税を支払うくらいなら、相続税よりも低い税率の贈与税を支払って財産を引き継いだ方が節税効果は高いということです。
生前贈与で知っておくべき3つのポイント
生前贈与は、もっともポピュラーな相続対策の一つですが、正しい方法で行わないと相続発生時に相続税を払わなければならなくなるケースも増えています。ここでは正しい生前贈与の仕方についてまとめていきたます。生前贈与のポイントは3つです。
①贈与契約書を作成する
生前贈与のポイントの1つ目は贈与契約書を作成することです。贈与が成立するためには贈与者と受贈者双方の認識が必要です。贈与したのかどうか不明瞭では、相続税の税務調査の際に問題になります。そこで客観的に証明できるように書面を残す配慮が必要です。
②基礎控除を超える贈与は、贈与税の申告・納税をする
2つ目は、贈与税の申告をしっかり行うことです。当たり前のことですが、国税庁によると平成29年度の贈与税の指摘事項は3565件ありました。そのうちのおよそ8割が無申告事案に対するものです。「申告不要と勘違いして」あるいは「贈与を隠そうとして故意に」贈与税の申告をしていない場合に税務調査を受けるケースが多いようです。
③受贈者が通帳・印鑑を管理し、自分で活用する(未成年の場合、一般的には成人するまで親権者が代理で管理)
財産の贈与を受けた場合には、当然その財産の管理処分権は受贈者に移転しているはずです。管理処分権とは、財産を自由に使用、処分することができる権利をいいます。この管理処分権が受贈者に移っていないのであれば、贈与は成立していなかったとみなされる恐れがあります。
以上の3点を守らないと節税目的の名義預金とみなされてしまう可能性が高くなります。名義預金とみなされると相続の際に、贈与税ではなく相続税の支払いをしなければならなくなります。
近年、税理士や会計士はもちろんですが、銀行や保険会社などの金融機関も積極的に贈与をすすめていることもあり、国税当局の見方はかなり厳しくなっています。名義預金とみなされないためにもしっかりルールを守って計画的に贈与していく必要があります。
生前贈与は保険と組み合わせるとより効果的な節税になる
生前贈与を行う際に、保険を組み合わせるとより効果的な贈与が行えることをご存知でしょうか。
先述のとおり、贈与税の非課税枠110万円の範囲内で親から子に贈与をして親の資産を減らしていくのが最も一般的な贈与の方法です。医師のような富裕層にとって、年間110万円は少ない金額に思われるかもしれませんが10年続ければ1,100万円、妻と子が2人いれば計3,300万円の資産を移転できるので効果は、大きいと思います。ここに平準払終身保険を組み合わせることにより、さらに効果的な節税効果が得られます。
【平準払終身保険の契約スキーム】
- 生前贈与の前提:贈与者(親)、受贈者(子)
- 保険の契約形態
- 契約者:子(受贈者)
- 被保険者:親(贈与者)
- 保険金受取人:子(受贈者)
- 払い込み期間:10年
以上のような契約形態で保険を組みます。子どもに多額のお金を贈与すると無駄遣いが心配になる親が多いようですが、保険料に充てるので無駄遣いがなくなるというメリットがあります。
また、親に万が一のことがあっても被保険者が親になっているので、保険金という形で納税資金の確保ができます。払い込み期間から数年経てば、たとえ解約しても払い込み保険料を下回ることがなくなるタイプの商品も多いので、子どもの将来のための資金として活用することもできます。
デメリットは払い込み期間を10年にすると、原則10年は贈与をし続けなければなくなることです。贈与者の経済事情が変わっていると払い込みが厳しくなることも考えられます(この場合も保険料を払い済みにしてしまえば、以後保険料を払わなくてもいいタイプが主流です)。
また、親の年齢が高いと保険に入れない可能性や、払い込み保険料より死亡保険金が少なくなってしまう可能性などが出てきます。極力、贈与者が若いときに検討する必要があるでしょう。
まとめ
相続に頭を悩ませる医師の方は多いのではないでしょうか。納税は国民の義務とはいえ、ただでさえ高額な税金を支払っている以上、少しでも多くの資産を次世代に残したいというのは当然のことです。
今回ご紹介した生前贈与を活用した節税以外にも、不動産投資によって相続税対策を行う方法など、さまざまな選択肢があります。ご興味がある方は、ぜひこちらのコラムもチェックしてみてください。