世界の先進国の中でも「群を抜いてファイナンシャルリテラシーが低い」と言われている日本人。
勤勉で真面目ではあるものの、お金の使い方と向き合っている人は少ないようです。でも、お金は生きていくうえで欠かせない大切なもの。そこで今回は、お金を守る、増やすにはどうしたらよいか、お金を上手に使うにはどうすればよいかを解説します。
ファイナンシャルリテラシーとは
ファイナンシャルリテラシーとは、一言でいえば「お金に関する知識」のことです。お金のことを正しく知り、使い、増やす――これらを適切に行うためには知識が必要で、その知識のことをファイナンシャルリテラシーと呼んでいます。
医師は高収入のため、お金を得る分野ではトップクラスですが、使う、増やすという部分では大きく個人差があるでしょう。得た収入を特に考えずに浪費してしまう医師、得た収入はそのまま貯金しているだけの医師、節税対策をしっかり行っている医師、投資をして資産形成を行っている医師もいます。
でも、多くの日本人は前者を批判することはできません。なぜなら、日本人の多くは「ファイナンシャルリテラシーが低い」と言われているからです。
アメリカのスタンダード&プアーズ社が2015年に世界各国のファイナンシャルリテラシーについて調査した資料「Financial Literacy Around the World」を見ると、「ファイナンシャルリテラシーがある」とジャッジされた日本人の割合は43%と過半数以下。他の先進国を見てみると、スウェーデン71%、ノルウェー71%、英国67%、オランダ66%、アメリカ57%、シンガポール59%など。日本人は決してリテラシーが高くはない現実がデータに現れています。
なぜ、このような状況が生まれているのでしょうか? その理由の1つは、子ども時代の教育にあります。日本では子どもにお金のことを話さない、話させないという家庭が多くありますが、海外では子どものときから積極的にお金に関する知識を学ばせる家庭が多いようです。実際、海外では投資のことを理解している10歳の子どもが当たり前にいますが、日本では理解している子ども(大人も)は少ないのが現実です。
お金を貯めるだけではなく、守り増やす意識
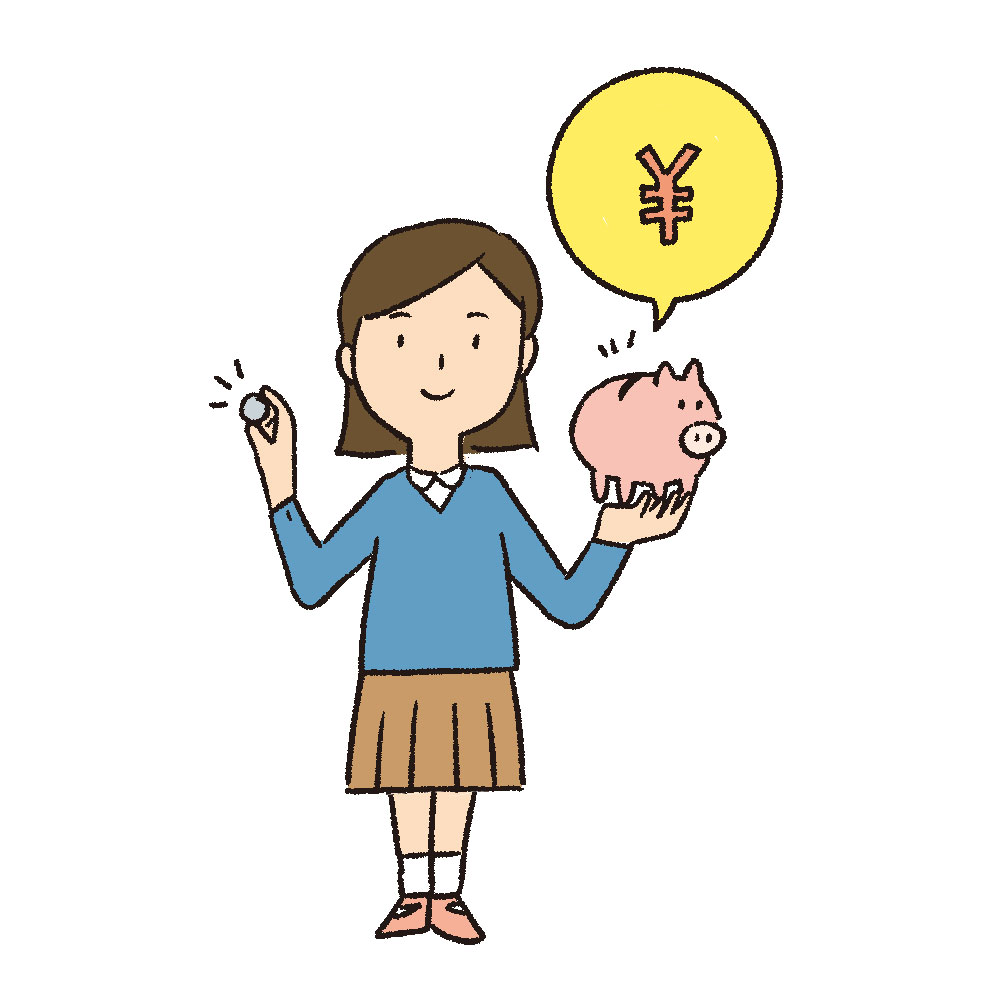 ファイナンシャルリテラシーが低いと「損をしている」かもしれません。医師は高収入であるがゆえに支払う税金も高額ですが、同じ収入を得ていても、ファイナンシャルリテラシーが高い人はしっかりと節税対策をして、支払う税金を抑え、資産形成をしています。
ファイナンシャルリテラシーが低いと「損をしている」かもしれません。医師は高収入であるがゆえに支払う税金も高額ですが、同じ収入を得ていても、ファイナンシャルリテラシーが高い人はしっかりと節税対策をして、支払う税金を抑え、資産形成をしています。
現在は銀行にお金を貯めておいても、金利が非常に低いため、昔と比べて増える額は本当に微少です。つまり、「預けている」だけの状態です。でも、そのお金を有効に活用して、節税したり、さらに銀行に預けるよりも増やすことができたらどうでしょうか?
たとえば、iDeco(個人型確定拠出年金)。掛金を5千円以上から自由に設定できて、60歳まで運用して、60歳以降に年金として受け取るという私的年金です。iDecoのメリットは、掛金が全額所得控除になる、運用利益が非課税、年金の受取も一定額まで非課税と、「節税」の面で大いに効果を発揮する点です。さらに、運用がうまくいけば、銀行に預けているよりもお金を増やすことができる可能性もあります。
iDecoはほんの一例ですが、ファイナンシャルリテラシーを高めていくと、「節税」や「資産形成」など、お金を守り、増やすためにはさまざまな方法があることに気付きます。
ファイナンシャルリテラシーを身につけるためには
医師がファイナンシャルリテラシーを身につけるためには、「損益計算書」と「貸借対照表」の2つの関係を理解する必要があります。言葉だけ見ると難しそうですが、実際はそんなことはありません。
収入と支出の2つからなる「損益計算書」は“お金の出入り”を表すもので、もらった給料は収入、買い物で使った金額は支出になります。一方、“持っているもの”を表すのが「貸借対照表」で、建物などの資産とローンなどの負債の2つで構成されます。「損益計算書」と「貸借対照表」は、「資産が収入を、負債が支出を生む」という関係性があります。
ファイナンシャルリテラシーを身につけるということは、この2つの関係性をよく理解することです。この2つの関係性を理解すると、金利が非常に低い銀行に資産(お金)を預けていても収入を生み出していない、つまりそれは「適していない」ということがわかります。
お金を上手に使う方法
 お金を上手に使うためには「資産が収入を、負債が支出を生む」ということを理解して行動することが肝心です。たとえば、高収入の医師は資産形成がしやすいと思いがちですが、節税などをして資産を守らなければ資産は目減りするので、生み出す収入も少なくなります。また、資産をもっていても、ただ銀行に預けるだけではなく、正しく収入を生み出すような投資、運用を行うこともポイントです。
お金を上手に使うためには「資産が収入を、負債が支出を生む」ということを理解して行動することが肝心です。たとえば、高収入の医師は資産形成がしやすいと思いがちですが、節税などをして資産を守らなければ資産は目減りするので、生み出す収入も少なくなります。また、資産をもっていても、ただ銀行に預けるだけではなく、正しく収入を生み出すような投資、運用を行うこともポイントです。
不動産投資、株式投資など、収入を生み出すための方法はたくさんあります。ただ、それを行うためには、「何も考えずに銀行に預けていただけ」と同じように「投資しただけ」では損をする可能性があるので、事前にしっかりと行う投資について学ぶようにしましょう。
欧米は日本と比べて預貯金率が低く、日本人よりも投資、運用をして「お金を活かしている」と言われています。ファイナンシャルリテラシーを身につけることで、お金の上手な使い方も併せて身につけたいですね。
まとめ
お金の知識をしっかりつければ、大切なお金を守りつつ増やすことができます。逆に、知識がないと損をすることがたくさんあります。ファイナンシャルリテラシーを身につけて、大切なお金を自分の手で管理、運用しましょう。















