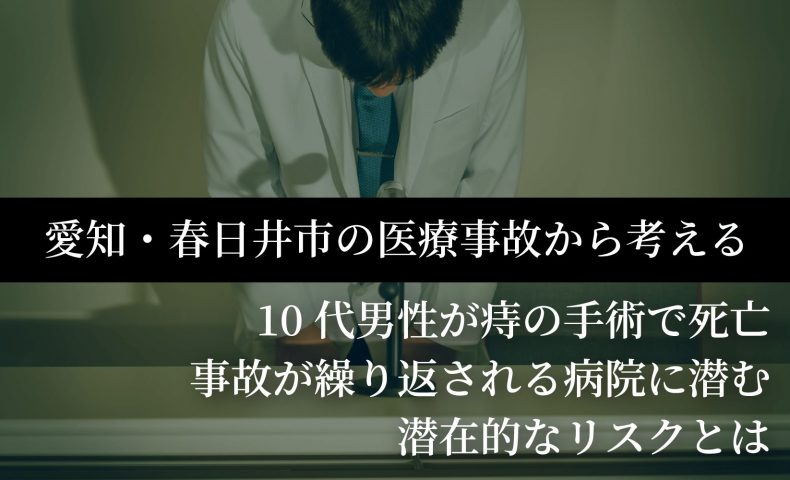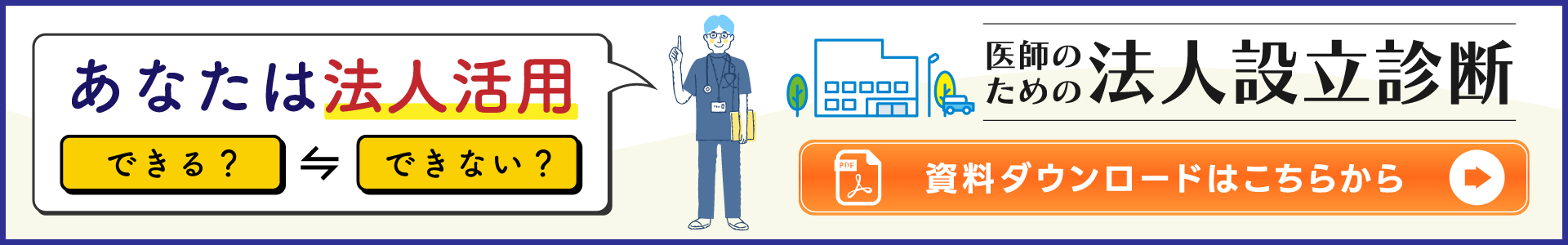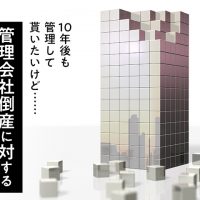2023年6月、愛知県立医療育総合センター中央病院(同県春日市)は、21年5月に重度の脳性麻痺で通院していた当時10代男性が、痔の手術後に出血性ショックで死亡する医療事故があったことを発表しました。同病院では2021年5月に別の男性患者(当時36)に、基準値の約15倍の下剤を処方し死亡する医療事故を起こしています。なぜ短期間に医療事故が繰り返されてしまったのでしょうか? 対策をしてもそれを妨げる、変え難い構造的な問題があったのでしょうか? 今回の事例をもとに、医療事故対策について考えていきます。
当時10代の男性は、自発呼吸できない重度心身障害者であり、21年5月17日に痔ろうのため入院し、翌18日に根治手術を行いました。手術は医師の想定よりも広範囲に及び、術後3〜5日後に脈拍が速くなるなどの症状を発し、術後6日目には手術創からの再出血を起こし、出血性ショックで死亡しました。
事故を受けて設置された事故調査委員会の発表によると、病院側は患者の脈拍が速くなった原因の究明を怠り経過観察と判断したことや、手術創から大量出血した際、輸血を行わなかったことが判明しました。また、心肺停止後血圧が測定できないほど症状が悪化したにもかかわらず、心配蘇生を始めず看護師が強心薬「ボスミン」と鎮静薬「ホリゾン」を間違えて医師に手渡し投薬するミスなど、病院側の処置が「適切ではなかった」と判断しました。
調査報告書では、同病院では日常的な患者ケアが必要な患者の入院が多いため、緊急時の対応が定着していなかった点を指摘し、急変に対応できる医療チームの再教育に努めるとしました。
医療現場に求められる医療事故防止策とは
こうした医療事故につながる不適切な医療行為は、どうしたら防げるのでしょうか?
日本医療安全調査機構によると、2022年1年間で報告された医療事故は300件となっています。医療事故は社会問題として大きく取り上げられており、どの病院にも事故のリスクは潜んでいます。医療現場に求められる対策は下記の通りです。
1、 常に潜在する事故に対して危機意識を持ち業務に取り組む
2、 業務量が適正を超える場合には、管理者に報告や相談を行う
3、 患者にとって最善の医療に従事する
4、
危険な医療行為には、確認・再確認を徹底する
5、 コミュニケーションと患者の同意に十分な配慮をする
6、 正確で丁寧な記録を時間的に適切に行う
7、 自身の健康管理と職場でのチームワークに努める
8、 患者相談窓口で問題に対応していく
2007年に医療法の一部改正が施行され、医療機関に対する医療安全対策が条文化され、義務化されました。更に医師法の改正により、医師に対する行政処分の類型が変更され、医業停止等の処分を受けた医師は、再教育を受けなければ医業に復帰することができなくなりました。医療従事者は地道な努力を積み重ね、医療事故の再発を予防し患者の信頼と安心を取り戻さなければなりません。
なぜ2度も医療事故が起こったのか? 医療の構造的問題とは
今回10代男性が死亡した医療事故の前に同病院では、難治性の便秘で受診した男性(当時36)が死亡しています。原因は、医師が処方した下剤が、通常の便秘治療に必要な量の10〜15倍であったことでした。この事故が発生した際、適切な調査や改善に繋げるための組織的な連帯不足が、2度目の医療事故につながった可能性も考えられます。
また、救急対応の不備を指摘する声もあります。東海地方で勤務する救急経験豊富な麻酔科医師であるS先生は、
「本来であれば通常よりもハイリスクな患者層に当たるので、経験豊富なハイボリュームセンターで行うのが安全ですが、脳性麻痺というバックボーンを理由に断られてしまう可能性はあると思います。まずはそこを断られないように密に連絡を取り、受け入れ側にも配慮してトライするのが良いと思います。
それでも受け入れ不可であれば、自院でやる可能性はあり得ます。であるならば少なくとも急変の可能性を考慮し、対応できる環境を整えて行うべきですが、発表された資料を拝見するに、全体的に急変対応に慣れていない印象を受けました。急変対応に慣れた人材を育成する、不足している場合は外から一時的に呼ぶ事で、今回のような悲劇の確率を少しでも下げる事ができるかもしれません。」
と指摘しています。
▼医師にオススメの法人節税で資産形成【無料資料ダウンロード】
まとめ
医療事故を未然に防ぐ対策や、万が一発生してしまった際の適切な取り組みは言うまでもなく重要です。しかし個別の事象に対してのみの対策では不十分であり、救急対応を含めた病院全体の対策が不可欠であるといえます。