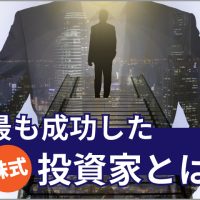令和4年に入り新聞をはじめインボイスという言葉が聞かれはじめました。
「うちにはインボイス制度って関係するんですか?」
「対応しないと何か損するんですか?」
という質問も最近(令和4年8月)になって多くなっています。
特に免税事業者の方からの質問が多いのが特徴です。
クリニックについては、その収入の大部分を保険診療が占めています。保険診療については、非課税取引という消費税を課さない取引となっているため、クリニックには免税事業者が多くなっています。今、クリニックこそインボイス制度への対応を検討する必要があります。
今回から数回に分けては、クリニックとインボイス制度について解説をしたいと思います。
クリニックこそ今検討が必要なインボイス制度とは
ここまで断りもなくインボイスという言葉を使ってきました。
ところで、皆さんはインボイスという言葉をご存じでしょうか。多くの方は「消費税について何かあるんだよね?」ということを知っているのみで、詳しく知らない方も多いと思います。
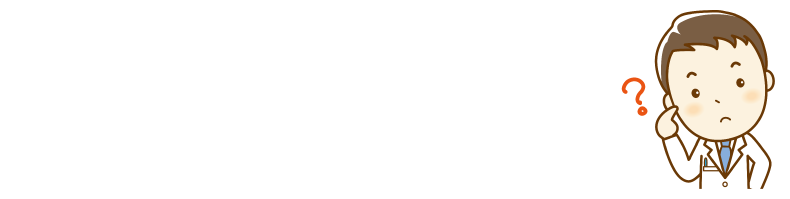
まずインボイス制度について簡単に解説をしたいと思います。下記の説明は、国税庁のホームページから引用しました。
インボイス制度の概要
インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。
• 適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
• インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
(国税庁HP引用)
ちなみに、仕入税額控除という言葉が分からない方がいらっしゃるかもしれません。消費税を計算するときには、「売上に係る預かった消費税」から「仕入に係る支払った消費税」を差し引くことで計算されます。この支払った消費税のうち、消費税の計算をする際に、差し引く消費税を仕入税額控除といいます。
ポイント
① インボイスは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの
② 売手は、要件を満たした請求書を発行する必要がある
③ 買手は、仕入税額控除をうけるためにインボイスの保存が必要
なぜインボイス制度が導入されたのかー益税という問題
なぜ、インボイス制度を導入するのか、根本の理由としては、益税の問題です。消費税は、間接税といい「負担する人」と「納める人」が異なっている税金です。消費税は、仕入税額控除の説明でも書いたとおり、「売上に係る預かった消費税」から「仕入に係る支払った消費税」を差し引くことで計算され納税をします。但し、事務処理の負担などを考慮し、課税売上が1,000万円以下で課税事業者を選択していなければ、消費税の納税が免除されます。
つまり、消費税を預かっているのに納税しないでよいという益税が生じているのです。
この益税を防止するには、
① 全員が課税事業者になる
② 課税事業者かどうかが判別できる仕組みをつくる
このいずれかの方法によるわけですが、課税事業者かどうかが判別できる仕組みとしてインボイス制度が導入されるわけです。
クリニックが「適格請求書発行事業者」になるには
登録事業者は、「適格請求書発行事業者」といいます。この適格請求書発行事業者になるには、税務署に申請手続をすることでなることができます。ただし、登録申請手続を行うには、課税事業者、つまり、消費税を納税する事業者であることが必要です。
現在、課税事業者か免税事業者かによって手続が異なるので分けて説明をします。
課税事業者のクリニックが対応すべきインボイス制度
では、課税事業者であるクリニックが適格請求書発行事業者となるには、どのような手続きが必要でしょうか。
「適格請求書発行事業者」となるには、税務署に登録申請書を提出する必要があります。そして、登録申請するには、課税事業者として登録を受ける必要がある点は先ほど記述しました。
制度そのものが開始するのは、2023年10月からですが、2023年10月1日から登録を受けるには原則、2023年3月31日までに登録申請を行う必要があります。
ポイント
現在、課税事業者で適格請求書発行事業者となる場合には、2023年3月31日までに登録をする。
免税事業者のクリニックが登録事業者になるには
現在、免税事業者の場合、クリニックが適格請求書発行事業者となるには、課税事業者となる必要があります。この場合に問題となるのが、いつから課税事業者になるかということです。
たとえば、個人事業主の方の事業年度は、暦の1月1日から12月31日ですから、事業年度の途中の10月1日で、インボイスの制度が始まるわけです。この場合の対応は、どうしたらよいのでしょうか。
消費税の課税事業者となるには、本来であれば事業年度が始まるまで(個人であれば事業年度が始まる前の12月末まで)に届けが必要です。仮に、2023年1月から課税事業者を選択するとした場合、本来なら10月1日から課税事業者になりたい場合でも、1月1日から9月30日までも消費税を納めることになってしまいます。
そのため、 2023年10月1日から「適格請求書発行事業者」になる場合は、それと同時に課税事業者になれるよう配慮がされています。 別途で手続きをする必要はありません。厳密に言うとこの経過措置は、6年間有効で「2023年10月1日から2029年9月30日が含まれる課税期間中」に適格請求書発行事業者の登録をうけると、それと同時に課税事業者になることができます。 但し、それ以降については、事業年度の初日の1ヶ月前までに税務署に対して申請を行う必要があり、今までの課税事業者選択の届出提出期限と異なる点に注意が必要となります。
ポイント
・免税事業者が仮に2023年10月1日から適格請求書発行事業者になりたい場合には、事業年度開始の日から課税事業者になる必要はなく、同時になれます。
・この経過措置は2029年9月30日が含まれる課税期間中まで
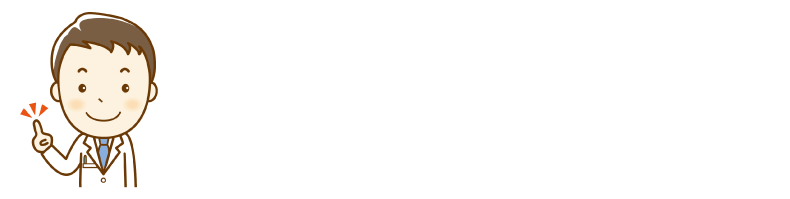
いかがでしたでしょうか。
インボイスの説明のところでも書いたとおり、大きく分けて、売手と買手それぞれの立場で影響があります。次回具体的に解説をしたいと思います。
▼著者
疋田税理士公認会計士事務所
税理士・公認会計士 疋田 通丈
税理士として、一般事業会社だけでなく、クリニック、NPO、社会福祉法人など幅広く税務・会計の支援を行うだけでなく、公認会計士として、医療法人、公益法人、学校法人の会計監査に携わっている。