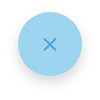-
 知っておきたい、開業医の確定申告と節税対策
知っておきたい、開業医の確定申告と節税対策勤務医で経験を積んだのちに晴れてクリニックを開業する医師は多いでしょう。そのとき気になるのが開業後の確定申告です。開業医と勤務医の確定申告にはどのような違いがあるのでしょうか。こんかいは、計上できる必要経費など開業医の確定申告の方法と所得控除を利用した節税方法について解説します。
-
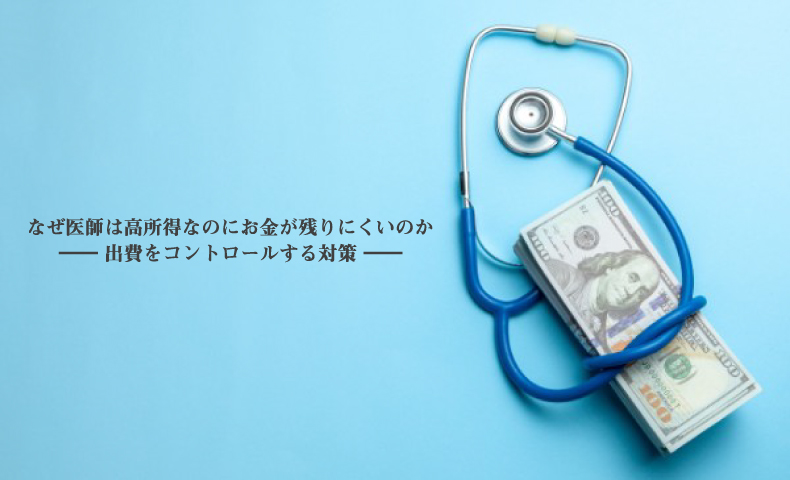 なぜ医師は高所得なのにお金が残りにくいのか 出費をコントロールする対策
なぜ医師は高所得なのにお金が残りにくいのか 出費をコントロールする対策医師といえば、高所得な職業の代表です。しかし、勤務医のなかには「それなりに収入はあるけれど、手元にキャッシュが残らない……」と感じている人も多いのではないでしょうか。この記事の前半では、医師の出費を整理し、後半では出費をコントロールするための対策を解説します。
-
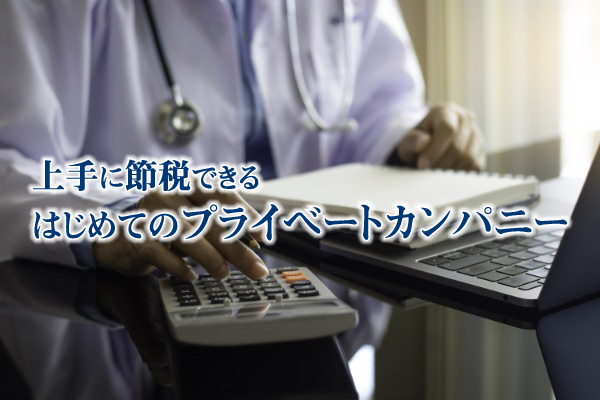 勤務医や高収入会社員が上手に節税できるはじめてのプライベートカンパニー(法人化)
勤務医や高収入会社員が上手に節税できるはじめてのプライベートカンパニー(法人化)勤務医を中心とした医師や高収入の会社員にとって、悩みの種はその高収入による税率の高さです。激務に耐えてお金を稼いでも、税金が高いため、思ったほど手元には残らず、資産形成も思うようにならないとお悩みでしょうか。
このような場合、プライベートカンパニーを設立して節税をすることが出来ます。本記事では、はじめてプライベートカンパニー設立を検討する医師(勤務医)・高収入の会社員が知っておくべきことをまとめました。 -
 期限ギリギリ…駆け込み申告で大失敗!確定申告でやりがちなミスとは?
期限ギリギリ…駆け込み申告で大失敗!確定申告でやりがちなミスとは?控除が適用されるにも関わらず、申告し忘れたり、経費のつけ方を間違えて税金を多く払い過ぎたりするなど、誰もが失敗しやすい「確定申告の落とし穴」。税金の支払いが少なければ税務署から指摘がありますが、払い過ぎた場合は何も指摘されず、スルーです。気づかないうちに「大失敗」しているかもしれません。
国税庁のホームページでは、確定申告でよくある間違いについて、Q&A形式で公開しています。多くの人がミスしやすい項目とはいったい何なのか? 国税庁が掲げる「確定申告で失敗しやすい12のケース」について解説します。 -
 「私はコレでキャッシュを残しました」不動産投資で大幅節税に成功した医師の事例
「私はコレでキャッシュを残しました」不動産投資で大幅節税に成功した医師の事例医師(勤務医)にとって、年収2000万円達成はひとつの目標であることでしょう。複数の職場を兼務し、その数字を実際に見た時の喜びはひとしおです。でも、そこでおかしなことが起こります。確定申告後、その所得の3割以上もの金額を「所得税」として税務署へ支払わなければいけないのです。しかし、これはあくまで「税金対策」をしていない場合です。しっかりと対策をすれば、天国から地獄への転落は免れます。株などの金融投資をはじめ、資産形成の手段は様々ありますが、今回は、医師の中でも日々忙しい勤務医に最適な「不動産投資での節税」について、2つのケースを例に説明します。
-
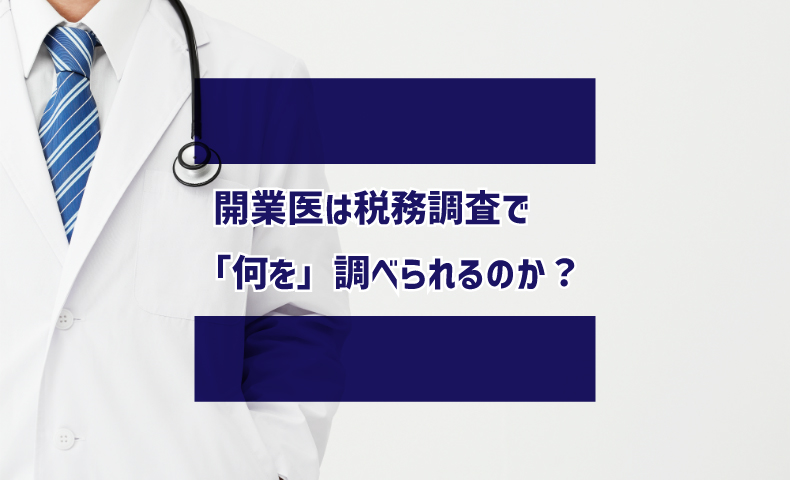 重い税負担も…開業医は税務調査で「何を」調べられるのか?
重い税負担も…開業医は税務調査で「何を」調べられるのか?高額所得者である医師にとって、確定申告は1年間の税務を確認できるチャンスです。手元により多くのキャッシュを残すため、上手に節税することも重要ですが、一部にはそれを取り違え、「脱税」に走ってしまうケースもあります。そんな悪質な医師たちがどんな落とし穴に堕ちるのか。一方、日頃まじめに業務に従事している医師が脱税の疑いをかけられたら、どう対処すればよいのか。突然の「税務調査」への対策や、ちょっとしたミスで課せられる税ペナルティについて解説します。
-
 「確定申告は税理士に丸投げ」で大丈夫? 意外と知らない税理士の実態
「確定申告は税理士に丸投げ」で大丈夫? 意外と知らない税理士の実態日々診療などで多忙な医師のみなさんは、勤務医であれ開業医であれ、確定申告などの「税務」について、税理士に任せっきりになっているケースが多いようです。しかし、「確定申告は税理士に丸投げ」は思わぬリスクもはらんでいます。具体的にどのような危険性があるのでしょうか。それに対して、どのように対応すればいいのでしょうか。
-
 「青色申告」で大幅節税!? 開業医なら知るべき確定申告の基礎知識
「青色申告」で大幅節税!? 開業医なら知るべき確定申告の基礎知識医師の中でも勤務医の将来は大きく2つにわかれます。大学病院で働いている場合、勤続して教授の道を目指す人もいることでしょう。一方で、多くの勤務医として働いている医師が望んでいるのは「開業」という道です。自身でスケジュールを管理でき、収入も増えることから、そのメリットは大きいといえます。開業後の利益を最大化するためにも、まずは「確定申告」の基礎知識を知っておきましょう。今回は、医療法人を設立しないパターンでご説明します。
-
 北海道リレーインタビュー VOL.3 井上哲先生(北海道大学大学院歯学研究院 教授)
北海道リレーインタビュー VOL.3 井上哲先生(北海道大学大学院歯学研究院 教授)北海道で活躍されている医師の方にインタビューを行い、ご自身の取り組まれている医療分野やキャリア、資産形成などについてお聞きする本企画。
第3回は北海道大学大学院歯学研究院教授の井上哲先生にお話をうかがいました。長年にわたり歯科保存分野での研究や治療に取り組みながら、臨床教育部において若手医師の育成に尽力される井上先生は、歯科医師を取り巻く現状や将来展望についてどのような考えをお持ちなのでしょうか。
勤務医ドットコムトップ
タグ一覧